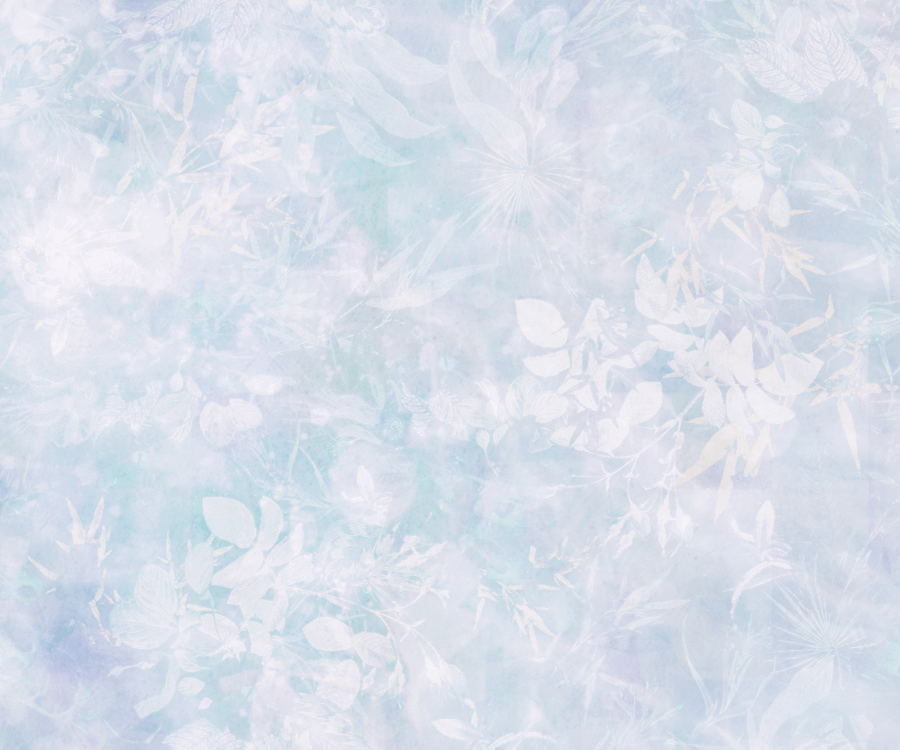純真はひずめばひずむほどに甘い
ぼうっと、ただただ窓から見える空を見つめていた。綺麗だな、天気が良いな、だなんて思える頃には意識がはっきりとしてきていて、少し前の自分の行動を恥じた。
あれが、運命。自分の理性では止めることの出来ない、非情で出来たそれ。私はあの夢のように抗えないままいつか彼を求め、そして番になるのだろうか。
「やだな……」
ぽたぽたとカーペットに水滴が染み込んでいく。夢の中のような、あんな怖い思いはしたくない。特に好きな人がいるわけでもないし、自分の未来が必ず明るく幸せになるとだなんて思っちゃいないが、あの夢ように、自分の意志とは関係なくずるずると運命に引き摺られ、心と体が別々になったような感覚は二度と味わいたくない。
夢の中の私はヒートになればあの人を求め、そしてヒートが終われば絶望の淵に立っていた。毎度後悔して、そしてまた繰り返す。ただあの人はどんな時でも私を求めていた。そして拒絶し逃げれば、冷たい視線に射抜かれ、私の居場所は少しずつ無くなっていった。
「注意をしていないと、正夢のようになりますよ」
少し前に夢の中で六道骸に言われた言葉を思い出す。彼はこうなることを分かっていたんだ。
◇◇◇
「なまえ、最近ぼうっとしてること多くない?なんかあった?」
休み時間中、友人に声を掛けられ、また自分が上の空でいたことに気付く。あの人に会ってからこんな日々が続いていた。
「ごめんごめん、ちょっと進路に悩んでて」
「意外。なまえはもうとっくに決めてると思ってたけど……。そんなに難しいところいくの?」
「そういう訳じゃないけど……」
自分の嘘の下手さに凹みそうになる。これ以上踏み込まれたらなんて答えよう。
だが私の心配を余所に、話は思わぬ方向へと転んでいった。
「本当はあれじゃないの?好きな人出来たとか」
「えーー!なまえが?!」
所謂恋バナが好きなお年頃の友人達は私を囲むようにして椅子を寄せる。前も左右も固められ、私の逃げ場は無くなってしまった。
「そういえば今まで聞いたこと無かったけど、なまえって好きな人いたことないの?」
「だよね!気になる」
「基本的に自分のこと全然話さないからな〜」
それはなるべくそういう話を避けていたからだ。いつかバレてしまうかもという不安と、自分がオメガであることを痛感してしまうことに嫌気が差して。
「好きな人は出来たことない」
嘘だ。もう随分昔の話になるが居たのだ、好きな人が。その人はベータだった。
「いいや嘘だね」
心を見透かされたのかと私は内心どきりと焦る。嘘と言った友人を恐る恐る見上げてみれば、彼女はしたり顔で私の頬をつまんだ。
「いひゃい」
「本当は今、好きな人いるんでしょ」
的外れな彼女の指摘に私はほっとした。
「いないって」
「でも最近ずっと考え込んでいるのって同じことでしょ?」
その言葉に私は数瞬動きが止まる。これでは、はいそうです、と言っているようなものだ。
「ほらね」
「へえ〜なまえがねぇ」
「だから好きな訳では!」
「やっぱり進路のことなんかじゃないじゃん」
「あ……」
もう、私の馬鹿。
「どんな人なの?」
目の前に座る友人が尋ねる。私は答えることが出来ない。なんて答えるべきか分からないのだ。
視線を下げる私に友人達は困惑している。早くこの話題を終わりにしたい。私をそんなに見ないで欲しい。よく見てしまえば私が彼女達にずっと偽りながら過ごしていることを知られてしまうような気がして。
「なまえ」
予想に反して掛けられた声は優しく、私は顔を上げる。
「困ったらいつでも相談のるから」
「え……」
「無理に話す必要はないよ」
本当に?本当にそう思っているの?だなんて思ってしまう私はなんて最低なんだろう。自分のエゴで彼女達を偽っているのに、彼女達の言葉すら信じないなんて。
「ごめん」
「そこはありがとうじゃない?」
「ありがとう」
いつか本当のことを話す時が来るのだろうか。
◇◇◇
「あいつに会いたいか?」
目の前いる赤ん坊が告げた。
私は今、ツナくんにお呼ばれして彼の家にお邪魔している。ツナくんのお母さんはとても優しく朗らかな人で、ご近所なのもあり、何かとお世話になることも多かった。家にお邪魔したのは十年ぶりくらいで、近頃は道端で会うことも少なかったからか、とても歓迎してくれた。
私が持ってきた手土産のお菓子と、ツナくんが入れてくれた麦茶を持って彼の部屋へと入り、何を言われるかとそわそわしていれば、口を開いたのは彼ではなく隣にいたリボーンくんであった。
「あいつって」
「分かってんだろ?」
膝の上に置いた手をぎゅう、と強く握る。会いたいか会いたくないかで言えばそんなもの、会いたくないに決まっている。
「会いたい」
隣にいたツナくんは驚いたように私を見た。私もまた、自分で言ったことに驚いていた。
「あんなに辛い目にあったのに……?」
「あ、いや今のは」
「お前、結構拗らせてるんだな」
リボーンくんのその発言にカチンと来てしまった私はなんて大人気ないのだろう。だが私はそれを隠す余裕も無かった。
「私だって、好きでこうなった訳じゃない……!アルファには分からないでしょうけどっ……」
言い終えた後に失言に気付く。こんなことを言うつもりでは無かったのに。
ツナくんは苦しそうに眉尻を下げた。私は何てことを……。
「ご、ごめんなさい……」
「なまえさん……」
「あんまり難しく考えんな」
怒る様子もなく、リボーンくんは諭すように告げた。まるで答えを知っているようだ。彼の発言は確実に赤ん坊とは言えない。だが見た目とは違う大人びた彼の発言は私の中にすっと入り込んだ。
以前の私であればリボーンくんの存在自体受け入れられなかっただろう。だがあの夢を見てしまえば、夢の中のあの人に出会ってしまえば、私が知る世界はあまりにもちっぽけだったと理解することが出来た。
「分からないけど、会いたいの……」
勿論あの夢の中のような未来は御免だ。だけどあの日、私の家に来た時に彼は、ただ私に会いに来たと言った。未来の時は知ることが出来なかったあの人のことを私は知りたい。
「んじゃ、行ってみるか」
リボーンくんはまるで私の答えを分かっていたかのようにニヤリと不敵な笑みを浮かべた。
「行くって何処へ……?」
「丁度今あいつ心臓を失って病院で寝てるんだ」
「え……?」
今なんて?と、聞き返した私は何も悪くないと思う。説明欲しさに思わず隣にいるツナくんに視線を向けた。
「ちょっと色々あって怪我してるんだ……はは……」
「生きてるの?」
「幻術で出来た心臓でなんとか」
あの夢を見ても理解出来ないことは沢山あるらしい。幻術で出来た心臓?何なのかさっぱり分からない。こんな言葉で片付けてしまっていいのか疑問ではあるが、マフィア絡みで色々とあったらしい。心臓を失ってしまう程の戦い。そしてそんな世界にあの人やツナくんはいるのだ。
「よく分からないけどツナくん達が生きてて良かった」
「なまえさん……」
「そうと決まればさっさと行くぞ」
「リボーン!本当になまえさんを連れて行く気か?!」
「当たり前だぞ」
ぴょん、と椅子から飛び降りたリボーンくんは早々と部屋から出てしまう。私とツナくんは急いで彼の後を追った。