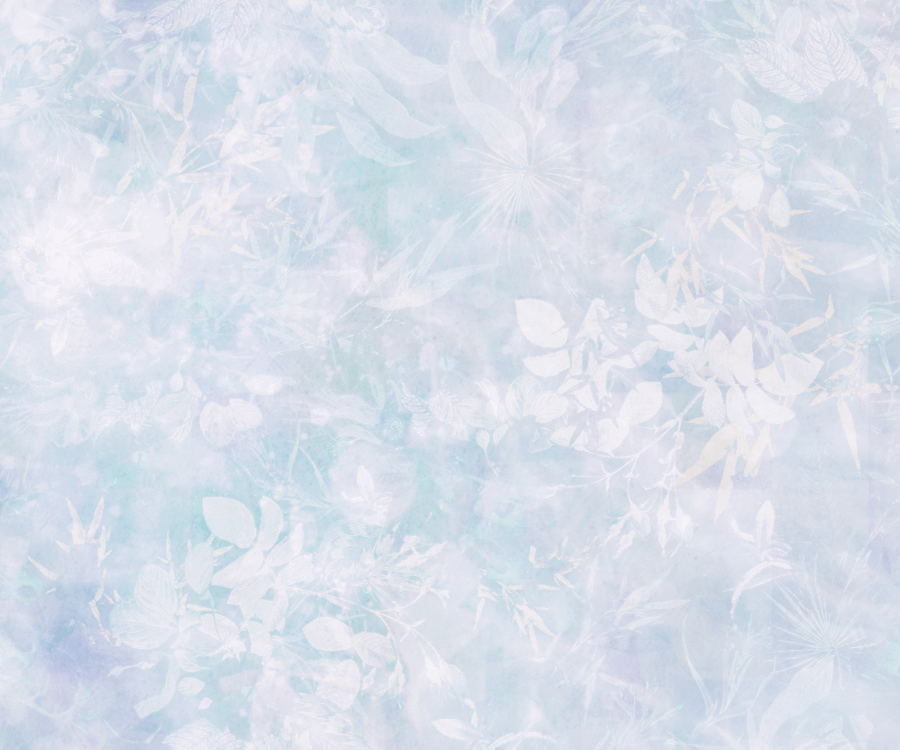瓶底のジェム
連れてこられた病院のエレベーターに乗り、ある階に着いた瞬間、私は足を止めた。
「ねえ、ここって」
きょろきょろと辺りを見渡す。微かだがアルファの香り。それも普段感じる数よりもかなり多い。
「この間の戦いで怪我した人みんな此処にいるんですけど……その、アルファが多くて」
その言葉に私は眩暈がした。運命のあの人に加え、こんなに沢山のアルファがいる所に来たことなど今まで一度もない。目の前にいるツナくんだってアルファなのだ。もし何かあったらと、考えるだけでぞっとする。
「ただのオメガに理性飛ばすほど、アイツらは軟弱じゃねえ。運命は別かも知れないけどな」
だから力を抜け。
そう言われて無意識に自分の腕を強く掴んでいたことに気付く。
「ヒートは終わってるんだろ?」
「うん……」
リボーンくんは赤ん坊だからか特に何も感じることはないが、きっとアルファになるのではないかと直感が働く。実際のところアルコバレーノになった時点でバース性から外れており、リボーンは間違いなくアルファなのだが、私がそれを知ることになるのはずっと先の話。
リボーンくんの後ろに着いて行くと、徐々に感じたのは多数のアルファの香り。その中でもとびきり甘い香りがあることに気付く。この匂いはあの人のものだ。
段々と濃くなっていくその香りに、あの人の元へ一歩ずつ近付いていることが分かる。リボーンくんとツナくんが左へ曲がり、部屋へと入っていくが、私は怖くて曲がる寸前で足を止めてしまう。すると、部屋の中からあの人の声が聞こえた。
「どういうつもり?」
やはり此処へ来ることは不味かったのだろう。このまま帰るべきなのかもしれないと、一歩後ろへと下がる。
「おいなまえ、何時まで突っ立ってんだ」
いつまでも部屋に入ってこない私に待ちくたびれたのか、リボーンくんは廊下まで戻って来て私を急かした。
「お、お邪魔します……」
部屋に一歩踏み入れれば、あの人の匂いはより強く香り、私に纏わりつく。
「んじゃ暫くしたら戻るからな」
「え?!」
ツナくんも驚いたように声を上げた。
「リボーン!いくら何でもそれは……!」
「怪我したばっかで流石にあいつもそこまで暴れられないだろ」
口角を上げてはいるが、リボーンくんの目は一切笑っていない。まるで忠告しているかのように、視線だけは強くあの人を見つめていた。
「大丈夫だよ綱吉クン」
目の前にいるあの人の表情や声は、私がこの時代で見てきた中で一番落ち着いているように見える。ツナくんもそれを感じたようで「何かあったら呼んでください」と告げてから部屋を出て、扉を閉めた。
「こっちにおいで」
あの人に言われ、近くにあるスツールに腰掛ける。何を話せばいいのか分からず、私はただ自分の握った拳を見つめていた。
「どうして来てくれたの?」
まるで子供に話しかけるかのように優しく、でも何処か戸惑っているようにも聞こえて、私はゆっくりと視線を上げて彼のラベンダー色の瞳を見つめた。
「貴方のこと、知りたくて」
「……怖くないの?」
「怖いけど、それでも知りたい」
伸ばされた手に一瞬驚き、思わずびくりと肩を揺らす。無意識に手を伸ばしていたのか、私の様子を見て彼は慌てて伸ばした手を引いた。
「ごめん」
再び沈黙が訪れる。窓際のテーブルには彼によく似合う白い花と、夢の中でも食べていた白くてふわふわなあれ。
「マシュマロ……」
「ん……?ああ、ここって退屈だから持ってきてもらったんだ」
「夢の中でもよく食べて……」
夢の中での出来事を思い出しながら呟く私はよくない事まで思い出してしまい言葉が詰まる。
あれはそう、夢の中で彼が手元にあるマシュマロをただ食べるのではつまらないからと言って始まったゲーム。私の唇で挟んだマシュマロを彼の口元まで持っていき、それを啄むようにして食べて、また繰り返す。続けていくうちに舌が絡み合い、どろどろに溶けていった酷く甘い夢。
「なまえチャン?」
「へっ?!」
「顔、真っ赤だけど」
何想像したの?と、ニヤニヤしながらこちらを窺う表情が、夢の中の彼と重なる。私はきっと耳まで赤くなっているだろう。
「な、何でもないっ……」
「ふうん。ねえなまえチャン」
夢の中の彼と重なっても、私に掛ける言葉が同じでも、声音は全く違った。夢の中で私を呼ぶ彼の声はもっと余裕が無くて、冷たくて、怖くて、呼ばれる度に私は肩を揺らしていた筈だ。
「触ってもいい?」
またあの時のように、箍が外れて目の前の彼に夢中になってしまうのではないかと恐怖する。でも触れられたいと思っている自分もいた。
「この間よりは落ち着いてるから、大丈夫だよ」
まるで自分が二人いるようだ。迷う私の心を見透かして、誘惑する彼の言葉にぐらぐらと気持ちが揺れる。彼を信じてみてもいいのだろうか。
「……うん」
小さく頷いた私に、彼はほっとした表情を見せると、優しく彼の腕の中に迎え入れられる。やはり体は正直で、彼の匂いを近くで感じられることに歓喜している。少しでも彼を感じたくて、無意識に目一杯空気を吸い込むと、花のような甘い香りが体中を巡った。
彼が今どんな顔をしているかは分からない。けれど、頭を優しく撫でられ、キスを送られている今の状況はまるで愛でられているようだ。
腕の中に収まり暫く経った頃、目の前の彼はとても小さな声で私に囁くように呟いた。
「また来てくれる?」
「……うん」
まただ。夢で見た彼はもっと我儘で、私の気持ちなんて汲もうともしなかった筈だ。だが実際会ってみればどうだろう、落ち着いて話してみれば私の様子を窺うように一つ一つ確認して、距離感に戸惑っていて、重なる部分はあれど夢の中のあの人とは違う。
「3日後、会いに来て」
その言葉に私は素直に頷いた。
◇◇◇
好きか嫌いかでいえば分からない。それがあの人に対する私の答え。それでもあの人のことを知りたい、近くに居たいと思っているのは本当で、あの人と約束をしてからの数日間は待ち遠しく感じていた。
早く、会いたい。
「なまえー、今日も行くでしょ?」
「ごめん、今日は約束がある」
珍しく友人達の誘いを断ったことに、彼女達も驚いたのか目を瞬かせる。
「珍しい」
「もしかして、気になってる人?」
「ち、違うよ」
「ふーん、じゃあまた今度ね」
自分でも浮かれているなと分かっている。これではまるで恋する乙女のようだ。
彼女達はそんな浮ついた私を長居させない為か、あっさり身を引いて教室を出ていく。彼女達の後を追いかけ、校門の前で別れると、私は意を決して病院まで向かう。あの人に会えるまでもう少し。
エレベーター内には自分しか乗っておらず、そわそわとしながら徐々に増えていく階数を眺める。
少しでも綺麗に見られたいと思ってしまうのは決して好きだからとかでは無く、誰かと会うなら当然のことだと自分の中で言い聞かせ、スクールバッグの中から手鏡を取り出して身だしなみを確認する。前回まで感じていた恐怖は、息を潜めてどこかへ行ってしまった。
お目当ての階数に着くと、感じるのはやはり多数のアルファの匂い。迷うことなく部屋へ向かっていくと微かに甘い香りが漂い始め、同時に聞こえてきたのはあの人の声と女性の声が二人。
「にゅにゅ〜!なんでユニまで……」
「皆さんでこれ食べませんか?」
この二人の声を私は知っている。幸いあの人はまだ気付いていないが、ここから一歩踏み出してしまえばきっとあの人も私の匂いに気が付く筈だ。なのに、その一歩が踏み出せない。
夢の中で聞いたことのある声の主達とあの人は楽しそうに、和やかに会話を続けている。未来のことや戦いのこと。私が知らない世界をあの人達は共有していて、分かりあっている。それを私が踏み込んではいけないような気がした。こんな、綺麗なんかじゃない運命だけで繋がっているような私なんかが。
足は自然と後ろに一歩下がっていた。踵を返し、無我夢中でエレベーターへと戻る。途中、別の夢で会ったあの男の姿を見たような気がした。