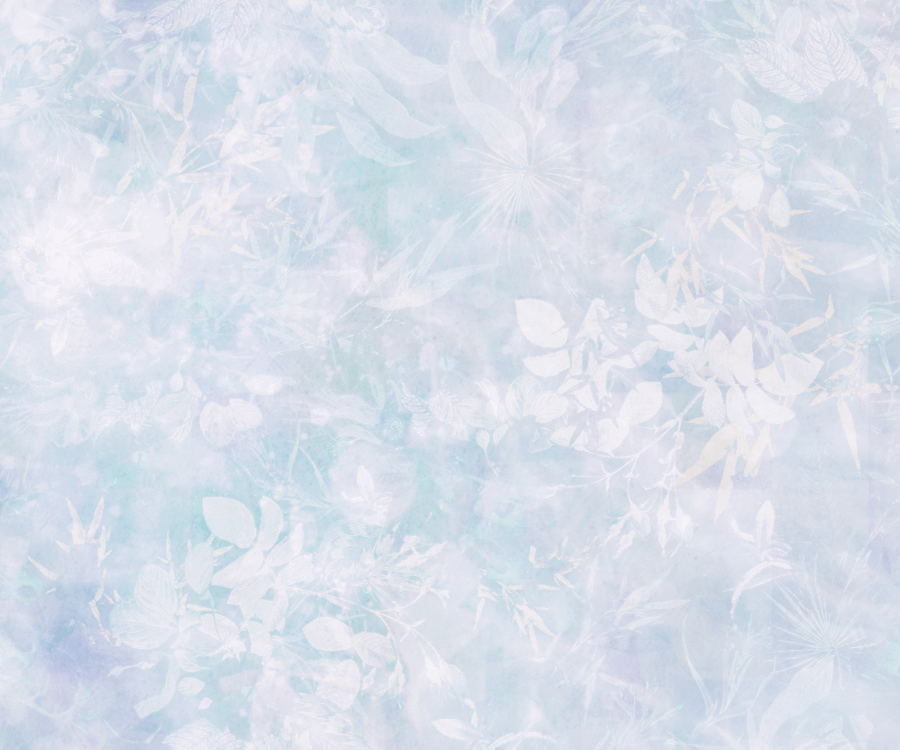泳いで虹のはじまりまで
夢を見ていた。最初の日から一度も見ることが無かった未来のあの人との夢。
海の中で溺れているような、苦しくて辛い日々の中で、たまに訪れる砂糖みたいな甘い時間。それは特に互いがヒートの時が多かったけれど、ヒートが終わりそうな頃、あの人に抱きしめられて白いベッドで眠る瞬間は、意識も戻りつつある中で唯一私が好きな時間だった。
会話はいつも無かった。それでも優しく頭を撫でてくれたり、私の髪にキスをしてくれたりすることが心地良く、向かい合って寝ている時はいつも寝たふりをして、瞼を持ち上げることが出来なかった。見てしまったら、もう後には戻れないような気がして。
もしかしたこの時の私も、今と同じ気持ちを少しは抱えていたのかも知れない。今の私には分からないことだけれど。
◇◇◇
終わってしまえばあっという間で、卒業式を終えた私達は教室で卒業アルバムを開きながらクラスメイトにメッセージを書いてもらったり、写真を撮ったり、思い出話をしたり、それぞれが別れを惜しむように教室に残っていた。
「来週みんなで旅行行くし、そこまで寂しくないね」
「何言ってるの、制服着られるの今日で最後なんだよ?!」
友人達はいつものように一つの席を囲んで、くだらない話をして笑い合っている。明日からもうこれが無くなるのかと思うと、やはり少しだけ寂しかった。
「あのね」
卒業旅行の話で盛り上がっていた友人達を遮って、私は意を決して切り出した。言うならば、今日までじゃないといけない気がして。このまま帰ってしまえば、この3年間ずっと偽り続けたまま高校生活を終えることになる。
友人達は様子の違う私に戸惑いを見せる。言ってしまえば、この関係は崩れてしまうかもしれない。卒業旅行にも行けなくなってしまうかもしれない。けどそれでも。夢の中のあの人と、白蘭が私の背中を押してくれたような気がした。
「私、本当は、オメガで……嘘ついてた、ごめん」
その言葉に目の前の友人達だけで無く、未だ教室に残っていた他のクラスメイトも驚いたようで、教室内は一瞬静まり返った。顔を上げることが出来なくて、私は下を向いたまま握った拳を見つめていた。
「そうだろうなあ、って思ってたよ」
一人の友人が呟いた。その言葉に私ははっとして顔を上げる。残りの二人の友人も、困ったような顔をして私を見つめていた。
「言ってくれるの待ってた」
「そんなの気にしないのに」
変わらない様子で私を囲む友人達に、思わず涙が零れた。目の前に座る友人は優しい瞳で私を見つめている。
「なまえがオメガだって知ったって、何も変わらないよ」
いつだったか、縛り付けているのは自分自身だと六道骸は言った。本当にその通りだったのかもしれない。周りはこんなにも私のことを受け入れようとしていたのに、一線を引き続けていたのはずっと私だけだった。
「うん……ありがとう……」
ふと、同じオメガのクラスメイトと目が合った。彼は嬉しそうな表情で私にガッツポーズを送る。もっと早くに言えば良かっただなんて、少しだけ思ってしまったけれど、きっと私一人じゃ無理だった。
「さ!帰ろ!」
「旅行の詳細決めなくちゃね」
卒業アルバムを仕舞い教室を出れば、廊下にも沢山の生徒がまだ残っていた。私達はもう歩くことの無い最後の廊下を歩いて、下駄箱を抜け、校門に向かって歩き出す。すると、後ろから駆け出してくる足音と、私を呼ぶ声がした。
「あれってクラスメイトの……」
振り返れば、そこにはクラスメイトの男の子がいた。ただならぬ雰囲気に、友人達は何かを察したようで私の肩を叩いた。
「なまえ、私達先に行ってるね」
「いつもの所にいるから」
「分かった」
暫くして、後ろから友人達の黄色い声が聞こえたような気もするが、理由は後で聞くとしよう。
目の前のクラスメイトに向き直れば、彼は何度か視線を彷徨わせると、真っ直ぐ力強い視線を私に向けた。
「俺ずっとみょうじのことが好きだったんだ。さっき教室で聞いちゃったけど、俺、オメガとかそういうの気にしないし……みょうじがもし良かったら……俺と、付き合ってくれませんか」
その言葉に、私は胸に暖かいものが広がった気がした。そう言って貰える日が来るなんて思いもしなかったのだ。世界は少しだけ私にも優しくて、でもそれは自分から歩み寄らなければ気付かなかった。
「ありがとう。……でもごめん、私好きな人がいるの」
「そっか……、ありがとう」
「ううん、嬉しかった。またね」
踵を返した瞬間に強い風が吹く。背後にいたクラスメイトは驚いたように声を漏らしたような気がするが、私は振り向かずに校門を抜け、友人達を目指した。
「って、あれ……」
「ちょっとなまえ!この人、誰?!」
校門を抜けたすぐ、先に向かっていた筈の友人達がいて、そしてその中心には何故か自分の番がいた。
「え……何で……」
「なまえ、誰このイケメン」
先程の黄色い声の原因はこれだったのかと今になって気付く。白蘭は私の手を引くと、友人達に見せつけるように肩を抱き寄せた。
「話してないの?」
「これから話そうと……」
目の前の友人達は驚きと、期待の目で私を見つめている。旅行中にでも話そうと思っていたのに、こんなに早く紹介する日が来るだなんて思いもしなかった。
「あの実は、番もいて……この人が、そうなの」
友人達は驚愕の声を上げた。一方隣の白蘭は心底楽しそうな表情をしていて、ああ彼女達の反応が面白いのだろうな、なんて予想出来るくらいにはご機嫌で、その光景に私も彼と同じように笑った。
いつか友人達にもう一度、私の話をしよう。オメガのこと、白蘭のこと、運命の番のこと。長くなってしまうけれど、私はもう話せる勇気を手に入れたから。
「なまえチャン、借りてもいい?」
白蘭の言葉に友人達は無言で何度も頷く。手を引かれるように彼に連れられ、黒い車に乗せられたかと思えば、行き先も告げずに走り出す。
一体何処へ向かっているのかと、隣にいる彼に視線を向けても、静かに微笑まれるだけで、何も答えてはくれなかった。
◇◇◇
「わぁ……」
目の前に広がっているのは青い大空と海の境界線。何処までも続く景色に思わず声が漏れた。
「どうしてここに?」
振り返りながら問えば、白蘭は前を向いたまま「何となく」と、答えた。
瞳に映る海は、光も届かないような暗い海の中では無い。明るく澄んだターコイズブルーではないけれど、何処か力強さも感じられるサファイアブルーは優しく不安を吸収するかのように静かに砂浜に波打つ。
結局あの未来の夢と同じ結末になってしまったかもしれない。けれど、私はこの結末を自ら望んで選んだ。もう後悔も、悲観も、することは無い。
「白蘭、ありがとう」
私の声はとても小さかったけれど、彼にはしっかり届いたようで、後ろから優しく抱き込まれる。まだ不安は残っているけれど、これからゆっくり進んでいこう。まだまだ時間はある。
もう私達は番なのだから。