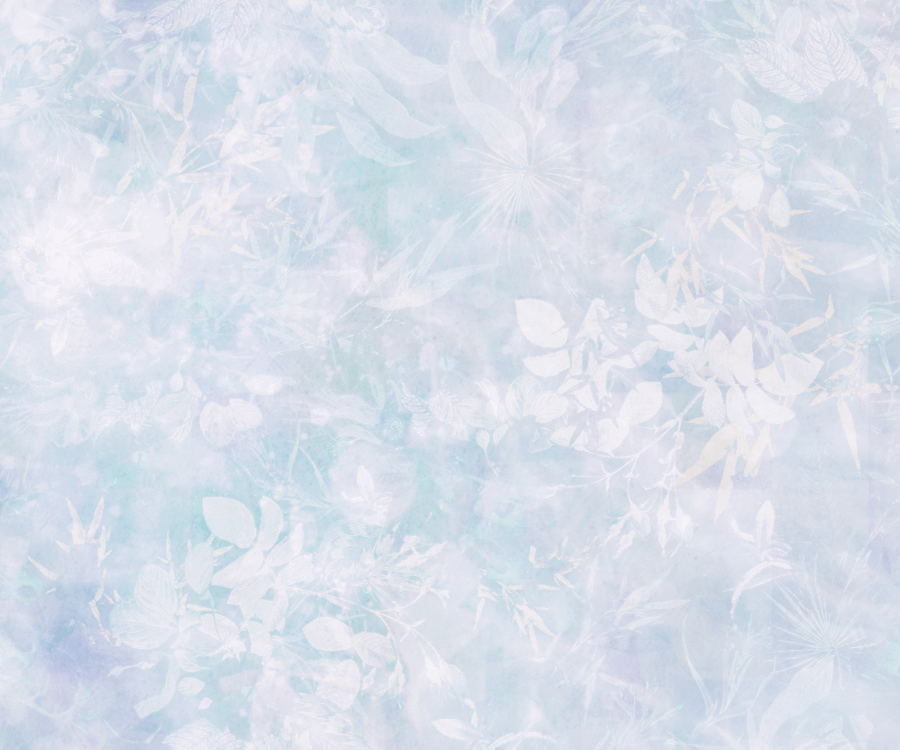その歪みを恋と名づけて
安心する暖かさに包まれながら、私はゆっくりと意識が浮上していくのを感じた。そっと瞼を開けてみれば、抱え込まれるようにあの人に抱き締められている。それが無性に嬉しくて、私はあの人の胸元に額を擦り寄せた。
目で見える何かが生まれた訳じゃない。けれど確かに私の中で、目の前にいるあの人が自分の番なのだと確信することが出来て、今まで感じていた甘い香りの中に何処か安心することも出来て、不思議な気持ちになった。
あの夢の中の私には感じ得なかった、安心するあの人の温もりと匂い。
「素直に甘えることも出来るんだ」
突然頭上から降ってきたあの人の声に、私は体が硬直した。てっきり寝ているものだと思っていたのに、あの人の声は寝起きとは言えない程はっきりとしている。恐る恐る視線を上げると、あの人は清々しい程の笑みを浮かべて私のことを見下ろしていた。
「いつから……」
「なまえチャンが起きるずっと前から」
その笑顔は夢の中のあの人と変わらない、悪戯が成功した時の子供のような顔をしていて、こういう部分は変わらないのだな、と、何となく私はあの夢のことをぼんやりと思い返した。
未来ではただただ恐怖に怯え過ごしていたから分からなかったことも、今なら分かることが出来るような気がした。まさか、この笑みに愛しいという感情が芽生えるだなんて、あの夢の中の私は思いもしなかっただろう。
◇◇◇
あの人──白蘭がさよならだと告げたあの日から少しして、彼の手術は無事成功したらしい。暫くはイタリアの病院に入院していたらしく、漸くまともに動けるようになった所で再び日本に来ていたのだとか。
元より私は彼と運命にあることからボンゴレの護衛が付いていて、意識を失っていたたため知らなかったが、連れ去られた時に敵との乱闘があったらしい。それでも敵のマフィアに私を奪われてしまったことから、すぐにツナくん達や丁度日本に来ていた白蘭にも連絡がいったそうだ。
「なまえチャンが大学を卒業するまでは日本にいるよ」
両親は初めは勿論戸惑っていたが、私を助けた恩人だということ、ベータである両親には分からない運命の番という繋がり、そして私の気持ちを尊重して、彼と共にいることを許してもらえた。
彼の素性については、ツナくんのお父さんの同僚という位置付けになっているらしい。勿論本当のことを話すことは出来ないが、両親を騙しているような気がして罪悪感が拭い切れないのは事実だ。
「え、でもそれって大丈夫なの……?色々と……」
「大丈夫。ユニにもお願いしたし」
正直マフィア事情を私は全く知らないため、深く聞くことをやめた。やめたと言うより聞くことを恐れてしまったのだ。それに私は一つ蟠りを残したまま番になってしまったと、彼女の名前を聞いてから思い出す。
「心配?」
「え?」
「今後のこと」
心配かと聞かれれば勿論心配である。番にはなったが、私達はお互いのことを知らなすぎるのだ。あの夢の中──未来でも番ではあったようだが、あの未来は私が歩んだ内の一つでしかない。
いつだったか、ツナくんからパラレルワールドの話を聞いたことがある。どれほどの世界で私達が番であったのか、私が知り得ることは出来ないが、今の私達はあの時の私達じゃない。同じ白蘭であれど、未来の記憶の彼をそのまま当て嵌めていいものでは無いと、私は思っている。そう考えれば私は彼のことを何も知らないのだ。
「私、白蘭のこと何も知らない」
俯くと、彼の指が私の頬に触れる。そのまま輪郭をなぞり、顎を掬うように上を向かせられると、彼はとても優しい表情をしていた。
「ゆっくり知っていけばいいじゃない」
これからずっと一緒なんだから。と、甘い言葉を囁かれれば、本当に大丈夫な気がしてくるのだから不思議なものである。それほど私がいつの間にか彼のことを信頼していたということであろう。
◇◇◇
私は部屋でゆっくりと寛いでいる筈であった。しかし、突如視界が暗くなったかと思えば辺り一面は一度見たことのある廃虚のような所。
突然移り変わった景色に驚いて、思わず持っていた本を手放し飛び上がる。何が起きたのだときょろきょろと周りを見渡せば、見知った男が一人。
「おや?」
「どうして……」
ボロボロのソファに座り、私の姿を捉えると僅かに目を見開いたのは六道骸だった。
「……白昼夢、ですかね」
「これは現実なの?」
彼は私の質問に答えること無く笑みを浮かべるだけだった。
「全く嬉しくないですけど、僕と君は相性が良いようで」
まあそのお陰で未来も助かったのですけどね。と六道骸は呟いたが、夢でしか未来のことを知らない私には何のことだかさっぱりわからない。
私は自室にいた筈なのに、どうしてこんな所にいるのだろうか。だがそれよりも、私は彼に会ったら言おうと思っていたことがあったのだ。
「……あの、私、あの人と番になったの」
その言葉に六道骸は大して驚いた様子も無く、私の方に視線を向けてから大きく溜息をついた。
「知っていますよ」
どの言葉をかけるのが正解なのだろうか、考えてもどれも不正解な気がするが、私は今一番伝えたい言葉を告げた。
「その……ありがとう」
驚いてから段々と顔を顰めていくのが分かる。やはり不正解だっただろうかと、少しだけ体を強ばらせて返ってくる答えを待つ。
案の定、彼は先程よりも低いトーンで、呆れたように呟いた。
「別に感謝されるようなしていませんし、貴女がどうなろうと知ったこっちゃない。それに、こうなる未来は予想出来ましたから」
「え……」
「はあ……そういう所が嫌いなんですよ」
気持ちに鈍感というのは本当に面倒ですね。と、彼は呟く。
しかし、思ったよりも彼の答えが冷たくなかったことに私は少しだけ安堵していた。本当はもっと否定されるかと思っていたからだ。
「まあ、初めから逃げられなかったと思いますけどね」
六道骸は小さな声で呟いたので、私は首を傾げた。
「いえ、何でもありません。……そろそろ時間では無いですか?」
彼の言葉と殆ど同じタイミングで、意識が薄れていくのが分かる。視界が段々と暗くなり、意識が途絶えそうなところで「随分と厄介な男に好かれたものだ」と彼が呟いたような気がしたが、聞き返す間もなく私は意識を手放した。