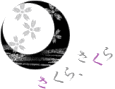「やはり、そなたはここに来なさったか」
ふいに声をかけられた方に顔を向けると、池のほとりに静かに佇む神官がいた。
「私がここへ来ることが分かっていたのですか?」
神官は答えずに柔らかな微笑みを向けてくる。さくらはゆっくりと立ち上がり、神官が佇む池のほとりへと移動した。
「ここへは翔流が連れて来てくれるって言ってたんです。私にこの桜を見せたいって。神官様、私、この桜を知っているような気がします。それに…、」
ここへ来た時、たくさんの翔流の幻が見えた。子どもの頃から最近までの、泣いたり笑ったり頑張ったり悲しんでいたりする、何気ない日々の翔流の幻が。
「なぜそれが見えるのか、そなたの深い場所はもうその理由を知っていなさる」
「………神官様、やっぱり私と楓姫の魂は同じではありません」
さくらが神官の目をしっかりと見つめて言うと、神官は小さく頷いた。
「いかにも。そなたの魂はかの姫様とは無関係。ですが、そなたは楓という姫様をよく知っていなさった」
「………翔流が楓姫のことをいつも話して聞かせてくれたから…」
「そうですな。翔流殿は幼い頃からかの姫様のことを日常的にそなたに語ってこられた。そなたは翔流殿が語る楓の姫様をそなたの中に吸収しなさっていた」
この場所に来た時からなんとなく分かっていた。記憶があるわけではないが、感じるのだ。この桜の木と自分が、“同じ”ということを。
「私は、この桜の木なんですね…」
「正しくは、桜の精気…種が人に転身したのがそなたであるのでしょう」
「神官様は、最初から知っていたのですか?私が楓姫の生まれ変わりではないと」
「確信したのは今…。そなたがここへ来なさって分かりました」
だが、さくらが翔流に連れられて初めて城に来た時に、違和感はあった、と神官は言う。
「吾は“種”そのもの。森羅万象、摂理と一体となっている身。その吾にそなたの奥深くに存在している“種”が響いた、といえばいいですかの」
「私の奥深くの種が…」
今、さくらが記憶ではないものを自分の中に感じているこれが、神官の言う種なのだろうか。
「疾風殿に与えた召喚の術は吾の種。種が時を渡りそなたにたどり着いたのはそなたの奥深くにも吾に似た“種”があったからかもしれぬ。だとすれば、そなたがあの時あの森に降りなさったのはそなた自身――そなたの種の意志」
「桜は、翔流の魂を救いたかった…」
今、さくらの口からその言葉が自然に零れた。桜の木に宿る命――種に人と同じ感情があるかは分からない。だが、種が人のさくらになったのだとしたら、さくらだっら思う。翔流が桜の木や花に癒されていたように、桜の木も翔流に癒されていたのだろうと。翔流がこの場所に来て語りかけてくれる時が至福だったのだろうと。人と同じ愛があったかどうかは分からないが、似たものはきっとあったのだ。
幼いころから桜の木を慕い語りかけてきた翔流の定めは、あの森の中で命を落とす横死だった。その時の翔流には救いも何もなかった。
『しばらくお前にも会いに来られないだろう。いや、もう生きてお前の前には来られないかもしれない…』
『お前はいつまでも変わらずに優しい花を咲かせてくれ。そして兄上を見守ってくれ――』
あんな悲しい言葉を最後にして去った翔流を、心に深い疵を持ったまま死を迎えてしまった翔流の魂を、桜は救いたかった。翔流の定めに歪みを起こしてでも、あの場で死んでしまう翔流の運命を変えたかった。だから、疾風に召喚された時、桜は自ら望んであの時のあの森に降りたのだ。
さくらにはよく分かる。
なぜなら、誰よりも翔流を愛しているから。
「そなたの種は、滅びの時に人に変わり、転生を繰り返しながら時をずっと待っていたのでありましょうな」
翔流に、翔流だった魂に人として出逢える時を。人に転じて再び出逢いたいと願うほど、桜の木は翔流を愛していたのだ。
「だが、偶然にもそなたは疾風殿に召喚され、この時代に生きる翔流殿に出逢ってしまった」
『歪みがすべて忌むものとは限らない。俺はこの歪みに感謝する。さくらと暮らせたひだまりの日々が心から愛しい…』
そう言ってくれた翔流。
翔流の魂は安らかに種に還れただろうか。
だとすれば、翔流との出逢いは必然。翔流の魂を救いたいと願ったこの桜の木の祈りが、摂理、森羅万象、天…それらに通じ叶えられた必然だったのだと思う。
疾風の召喚術を使って――。
「この桜…、滅ぶのですね」
「滅びがあって、桜の精気、種がそなたとなったのでしょうからな…」
「この国は…、どうなりますか?」
疾風の捧げによって豊かさを保っている松風だが、その疾風の消耗は激しい。そればかりでなく、他国の脅威にもさらされている。さくらがいた未来の松風は、珠羽村の中に地名が残るだけとなっている。村の歴史には詳しくないが、松風という独立した国はないから――、
「神官様…!」
「……これからの松風にとっては辛い方向へ定めは流れるでありましょうな」
「……っ」
国のため、民のためにすべてを犠牲にした孤独な領主は。
命懸けで愛する人、ただひとりの楓姫を求めた咎負の術士は。
「疾風はどうなるの…!?」
神官はじっと瞑目した。
「疾風殿の定めによります」
「疾風の……」
「捧げの行使による疾風殿の定めは、すべてを捧げることにほかならない。即ち、願うこと叶わぬ定め。それは、禁忌の術の行使もしかり」
「そんな…!じゃあ、最初から疾風の願いは、楓姫には届かない定めだったの…!?」
神官は小さく頷いた。
「召喚の術にそなたが応えたことは翔流殿にとっては救いとなり、疾風殿にとってはそのまま報いとなりました。疾風殿の命数はまもなく尽き魂は消滅します」
「消滅…!?」
「魂とは繋がっていくもの。だが疾風殿のそれは先への繋がりを断たれる。すなわち、転生叶わぬということ」
「そんな…、どうして疾風だけそんな悲しい定めなの?捧げは民のため、召喚の術は愛のためでしょ…?」
疾風にはひどいことをされた。
でも――。
「それじゃあまりにも…、疾風が可哀想…!」
はらりはらりとさくらの瞳から涙がこぼれた。
「疾風が召喚したかったのは楓姫なのに…、それさえも叶わず私が召喚されてしまって…、それでも疾風は咎を負い、報いを受けなきゃならないなんて…!」
「それが疾風殿の定め。捧げの術はすべてを捧げてこその効果ゆえ…」
「そんな――っ」
願うことなにひとつ叶わない。
全霊を懸けた召喚さえも、初めから叶うはずのないものだった。
「疾風…」
さくらから大切なものをすべて奪った疾風だが、今はもう憎めない。
捧げ、咎の報いはどれだけ重いのだろう。疾風はどうしてそこまでして、すべてを捧げ咎を背負ったのだろうか。
「吾の先見ではもう幾月もしないうちにこの国は他国に攻め入られ亡びることとなりましょう。今なら吾はそなたを先の世に還すことができる」
――え?
さくらは思いがけない神官の言葉に耳を疑った。
「還れる…の?」
元の世界に。
蒼空がいる世界に。
「もともと、国の定めは先の世から参ったそなたは無関係。そなたはここで還らねばならない」
さくらの心がぐらりと揺れる。
もうこの世界に翔流はいない。
ここで生きていく理由は何もない。
――でも…!
「………いいえ。私は還りません」
「なんですと…?」
神官の目が、おそらく初めて心底動揺したように見開かれた。
「なぜですかな?そなたは元の世界に還りたくはないと?」
「還りたい。今すぐにでも還りたいです。でも、疾風をこのまま放っておくなんてできない」
「………」
激しくて脆くて孤独な領主をこのままにして還ることなどできない。
「疾風の悲鳴が聞こえる気がするんです…。あの人は必死に救いを求めて手を伸ばしている。だから、私、疾風を探しに行きます。滅びるのが定めなら、せめて最後は……っ」
「……さくらの姫様…」
神官はふっと微笑んだ。
「ようやく、この輪廻から抜け出せますな…」
「どういうことですか?」
「いや。こちらの話…。疾風殿は地下の『魔法使いの部屋』におられます」
さくらはうん、と頷いて踵を返した。
「………種を繋げたいと願うは生のあるもの万人に共通する本能的な欲望…」
神官は歩き去るさくらの後姿を見つめながらつぶやいた。
「桜の姫よ…。そなたは気づくはずもないでしょう…」
何度もここから還り、そしてまた召喚されてこの同じ時を迎え、神官の手によってここから還り、また疾風に召喚される輪廻の中にあったことを。
「吾を最後に滅びる定めにある古代種…。吾には子孫を繋ぐ種だけはない。吾の無意識は少しでも存在を保ちたいと願っていたのでありましょう…」
疾風に召喚されこの時代へとやってきたさくらは、この場所この時に神官の手によって未来へ送り帰されるが、疾風の術によってまた召喚され同じことを初めからたどって、この時この場所へとやってくる。
何度、同じことを繰り返したかは分からない。
だが、さくらは必ず半年前の森の中に降り賊に襲われるところを翔流に助けられる。
そして翔流と恋に落ち、だが疾風に囚われ身を奪われる日々を過ごし、翔流が死に、この時に桜の木に逢いに来るのだ。
古代種である老人はさくらが塔の部屋から地下に下り、初めて言葉を交わし傷を癒した時に、さくらの魂に刻まれているそれに気が付いた。
さくらを元の世界に還す時、あえて召喚の術が発動している場所へと還し、さくらはまたやってくるというこの輪廻を続けていたのはほかならぬ神官自身だったのだ。
「輪廻の中では永遠…。吾は滅びずにすみますからの…」
あさましいことだ、と神官はうなだれた。
何度も同じことを繰り返すうちに、知らずうちに同じことが魂に刻まれ業になる。業とはそのものの振る舞いによって刻まれるもの。その業が別のことを引き起こし、同じことの繰り返しの中で少しずつ何かが変わっていく。
それが、今だ。
いつものさくらはここで還るが、このさくらは還らなかった。ここから、何かがまた変わる。
「やっと、忌まわしい輪廻が断ち切られますな」
吾も滅びの時を迎える――そうつぶやいた神官の顔はどこか晴れ晴れとしていた。
ふいに声をかけられた方に顔を向けると、池のほとりに静かに佇む神官がいた。
「私がここへ来ることが分かっていたのですか?」
神官は答えずに柔らかな微笑みを向けてくる。さくらはゆっくりと立ち上がり、神官が佇む池のほとりへと移動した。
「ここへは翔流が連れて来てくれるって言ってたんです。私にこの桜を見せたいって。神官様、私、この桜を知っているような気がします。それに…、」
ここへ来た時、たくさんの翔流の幻が見えた。子どもの頃から最近までの、泣いたり笑ったり頑張ったり悲しんでいたりする、何気ない日々の翔流の幻が。
「なぜそれが見えるのか、そなたの深い場所はもうその理由を知っていなさる」
「………神官様、やっぱり私と楓姫の魂は同じではありません」
さくらが神官の目をしっかりと見つめて言うと、神官は小さく頷いた。
「いかにも。そなたの魂はかの姫様とは無関係。ですが、そなたは楓という姫様をよく知っていなさった」
「………翔流が楓姫のことをいつも話して聞かせてくれたから…」
「そうですな。翔流殿は幼い頃からかの姫様のことを日常的にそなたに語ってこられた。そなたは翔流殿が語る楓の姫様をそなたの中に吸収しなさっていた」
この場所に来た時からなんとなく分かっていた。記憶があるわけではないが、感じるのだ。この桜の木と自分が、“同じ”ということを。
「私は、この桜の木なんですね…」
「正しくは、桜の精気…種が人に転身したのがそなたであるのでしょう」
「神官様は、最初から知っていたのですか?私が楓姫の生まれ変わりではないと」
「確信したのは今…。そなたがここへ来なさって分かりました」
だが、さくらが翔流に連れられて初めて城に来た時に、違和感はあった、と神官は言う。
「吾は“種”そのもの。森羅万象、摂理と一体となっている身。その吾にそなたの奥深くに存在している“種”が響いた、といえばいいですかの」
「私の奥深くの種が…」
今、さくらが記憶ではないものを自分の中に感じているこれが、神官の言う種なのだろうか。
「疾風殿に与えた召喚の術は吾の種。種が時を渡りそなたにたどり着いたのはそなたの奥深くにも吾に似た“種”があったからかもしれぬ。だとすれば、そなたがあの時あの森に降りなさったのはそなた自身――そなたの種の意志」
「桜は、翔流の魂を救いたかった…」
今、さくらの口からその言葉が自然に零れた。桜の木に宿る命――種に人と同じ感情があるかは分からない。だが、種が人のさくらになったのだとしたら、さくらだっら思う。翔流が桜の木や花に癒されていたように、桜の木も翔流に癒されていたのだろうと。翔流がこの場所に来て語りかけてくれる時が至福だったのだろうと。人と同じ愛があったかどうかは分からないが、似たものはきっとあったのだ。
幼いころから桜の木を慕い語りかけてきた翔流の定めは、あの森の中で命を落とす横死だった。その時の翔流には救いも何もなかった。
『しばらくお前にも会いに来られないだろう。いや、もう生きてお前の前には来られないかもしれない…』
『お前はいつまでも変わらずに優しい花を咲かせてくれ。そして兄上を見守ってくれ――』
あんな悲しい言葉を最後にして去った翔流を、心に深い疵を持ったまま死を迎えてしまった翔流の魂を、桜は救いたかった。翔流の定めに歪みを起こしてでも、あの場で死んでしまう翔流の運命を変えたかった。だから、疾風に召喚された時、桜は自ら望んであの時のあの森に降りたのだ。
さくらにはよく分かる。
なぜなら、誰よりも翔流を愛しているから。
「そなたの種は、滅びの時に人に変わり、転生を繰り返しながら時をずっと待っていたのでありましょうな」
翔流に、翔流だった魂に人として出逢える時を。人に転じて再び出逢いたいと願うほど、桜の木は翔流を愛していたのだ。
「だが、偶然にもそなたは疾風殿に召喚され、この時代に生きる翔流殿に出逢ってしまった」
『歪みがすべて忌むものとは限らない。俺はこの歪みに感謝する。さくらと暮らせたひだまりの日々が心から愛しい…』
そう言ってくれた翔流。
翔流の魂は安らかに種に還れただろうか。
だとすれば、翔流との出逢いは必然。翔流の魂を救いたいと願ったこの桜の木の祈りが、摂理、森羅万象、天…それらに通じ叶えられた必然だったのだと思う。
疾風の召喚術を使って――。
「この桜…、滅ぶのですね」
「滅びがあって、桜の精気、種がそなたとなったのでしょうからな…」
「この国は…、どうなりますか?」
疾風の捧げによって豊かさを保っている松風だが、その疾風の消耗は激しい。そればかりでなく、他国の脅威にもさらされている。さくらがいた未来の松風は、珠羽村の中に地名が残るだけとなっている。村の歴史には詳しくないが、松風という独立した国はないから――、
「神官様…!」
「……これからの松風にとっては辛い方向へ定めは流れるでありましょうな」
「……っ」
国のため、民のためにすべてを犠牲にした孤独な領主は。
命懸けで愛する人、ただひとりの楓姫を求めた咎負の術士は。
「疾風はどうなるの…!?」
神官はじっと瞑目した。
「疾風殿の定めによります」
「疾風の……」
「捧げの行使による疾風殿の定めは、すべてを捧げることにほかならない。即ち、願うこと叶わぬ定め。それは、禁忌の術の行使もしかり」
「そんな…!じゃあ、最初から疾風の願いは、楓姫には届かない定めだったの…!?」
神官は小さく頷いた。
「召喚の術にそなたが応えたことは翔流殿にとっては救いとなり、疾風殿にとってはそのまま報いとなりました。疾風殿の命数はまもなく尽き魂は消滅します」
「消滅…!?」
「魂とは繋がっていくもの。だが疾風殿のそれは先への繋がりを断たれる。すなわち、転生叶わぬということ」
「そんな…、どうして疾風だけそんな悲しい定めなの?捧げは民のため、召喚の術は愛のためでしょ…?」
疾風にはひどいことをされた。
でも――。
「それじゃあまりにも…、疾風が可哀想…!」
はらりはらりとさくらの瞳から涙がこぼれた。
「疾風が召喚したかったのは楓姫なのに…、それさえも叶わず私が召喚されてしまって…、それでも疾風は咎を負い、報いを受けなきゃならないなんて…!」
「それが疾風殿の定め。捧げの術はすべてを捧げてこその効果ゆえ…」
「そんな――っ」
願うことなにひとつ叶わない。
全霊を懸けた召喚さえも、初めから叶うはずのないものだった。
「疾風…」
さくらから大切なものをすべて奪った疾風だが、今はもう憎めない。
捧げ、咎の報いはどれだけ重いのだろう。疾風はどうしてそこまでして、すべてを捧げ咎を背負ったのだろうか。
「吾の先見ではもう幾月もしないうちにこの国は他国に攻め入られ亡びることとなりましょう。今なら吾はそなたを先の世に還すことができる」
――え?
さくらは思いがけない神官の言葉に耳を疑った。
「還れる…の?」
元の世界に。
蒼空がいる世界に。
「もともと、国の定めは先の世から参ったそなたは無関係。そなたはここで還らねばならない」
さくらの心がぐらりと揺れる。
もうこの世界に翔流はいない。
ここで生きていく理由は何もない。
――でも…!
「………いいえ。私は還りません」
「なんですと…?」
神官の目が、おそらく初めて心底動揺したように見開かれた。
「なぜですかな?そなたは元の世界に還りたくはないと?」
「還りたい。今すぐにでも還りたいです。でも、疾風をこのまま放っておくなんてできない」
「………」
激しくて脆くて孤独な領主をこのままにして還ることなどできない。
「疾風の悲鳴が聞こえる気がするんです…。あの人は必死に救いを求めて手を伸ばしている。だから、私、疾風を探しに行きます。滅びるのが定めなら、せめて最後は……っ」
「……さくらの姫様…」
神官はふっと微笑んだ。
「ようやく、この輪廻から抜け出せますな…」
「どういうことですか?」
「いや。こちらの話…。疾風殿は地下の『魔法使いの部屋』におられます」
さくらはうん、と頷いて踵を返した。
「………種を繋げたいと願うは生のあるもの万人に共通する本能的な欲望…」
神官は歩き去るさくらの後姿を見つめながらつぶやいた。
「桜の姫よ…。そなたは気づくはずもないでしょう…」
何度もここから還り、そしてまた召喚されてこの同じ時を迎え、神官の手によってここから還り、また疾風に召喚される輪廻の中にあったことを。
「吾を最後に滅びる定めにある古代種…。吾には子孫を繋ぐ種だけはない。吾の無意識は少しでも存在を保ちたいと願っていたのでありましょう…」
疾風に召喚されこの時代へとやってきたさくらは、この場所この時に神官の手によって未来へ送り帰されるが、疾風の術によってまた召喚され同じことを初めからたどって、この時この場所へとやってくる。
何度、同じことを繰り返したかは分からない。
だが、さくらは必ず半年前の森の中に降り賊に襲われるところを翔流に助けられる。
そして翔流と恋に落ち、だが疾風に囚われ身を奪われる日々を過ごし、翔流が死に、この時に桜の木に逢いに来るのだ。
古代種である老人はさくらが塔の部屋から地下に下り、初めて言葉を交わし傷を癒した時に、さくらの魂に刻まれているそれに気が付いた。
さくらを元の世界に還す時、あえて召喚の術が発動している場所へと還し、さくらはまたやってくるというこの輪廻を続けていたのはほかならぬ神官自身だったのだ。
「輪廻の中では永遠…。吾は滅びずにすみますからの…」
あさましいことだ、と神官はうなだれた。
何度も同じことを繰り返すうちに、知らずうちに同じことが魂に刻まれ業になる。業とはそのものの振る舞いによって刻まれるもの。その業が別のことを引き起こし、同じことの繰り返しの中で少しずつ何かが変わっていく。
それが、今だ。
いつものさくらはここで還るが、このさくらは還らなかった。ここから、何かがまた変わる。
「やっと、忌まわしい輪廻が断ち切られますな」
吾も滅びの時を迎える――そうつぶやいた神官の顔はどこか晴れ晴れとしていた。