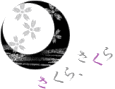おばさんたちが主催する祝言はとりあえず中止にしてもらった。だが、村の者たちみんなが翔流とさくらを祝福する空気が漂っている、そんな秋深まったその日の朝、翔流の小屋にふたりの兵士が訪ねてきた。
兵たちとともに任に向かう翔流を、さくらはいつもと同じように送り出した。
そして、夕方になって小屋へ帰宅した翔流に、さくらは「おかえりなさい」と笑顔を向けた。
「ただいま。さくら?この暗い中で何をしているんだ?」
薄暗い部屋の中でさくらは一心に手元を動かしている。
「この前失敗して縫い合わせちゃった翔流の衣を繕い直そうと思って糸をほどいているの」
「こらさくら。無理をするなと言っているだろう。暗い手元では針が指を痛めるし目にも悪い」
「ごめんなさい。でも、どうしても今日これがやりたかったの…」
「なぜだ…?」
「分からないけど、なんだかどうしても…」
「そうか…」
何かの啓示なのだろうか。
さくらは知るはずもないことなのに――。
今朝の兵士たち――城からの使者の訪れがなくとも、いずれ決意しなければならないことは分かっていた。
だが、今があまりにも満たされているから。
まるで凪いだ海のように、こんなにも穏やかな気持ちでいるのは生まれて初めてだ。
さくらの存在が自分を満たし、癒している。さくらは翔流にとって明るい灯と同じ。さくらがいるから生きよう、生きていたいと思える。
だから、任についてのことは極力言わないでいたのだ。言ってしまえば己が置かれている立場や状況に縛られてしまうから。ひだまりのような日々の終焉が近くなってしまうから。告げなければならないことを明日、明日と先延ばしにしても、ここに在る、ここにしかないさくらとの時間を手放したくはないと思っていたから。
「翔流、どうしたの?なんだか、つらそう…。まさか!どこか怪我でもしたの!?」
「…いや怪我などしていない。さくらに話さなければならないことがあるのだ」
「なに?」
翔流はさくらの手から繕いかけの衣を取り、寝台に腰掛けさせて自分も隣に座った。
「今朝来た兵たちは城からの使いだ」
「うん…」
「領内の視察を終えここの賊も殲滅した今、もう俺は城に戻らなければならない」
「……!」
さくらは絶句した。
翔流は松風領の武将でここには賊を討伐するために逗留しているだけ。だから、いつかは城に帰ってしまうこんな日が来ると知っていたはずなのに、いつまでも翔流と一緒にいられるような気になってしまっていた。
これまでには一度もなかった兵士たちの訪れによって、今までとは違う何かが起こってしまうような不安と予感を胸のどこかで感じていた。不安に囚われてそれが現実になるのが怖かったから、普段と変わらない態度に努めたのに。
「戦が始まる」
「……戦…?」
「一週間ほど前、北の領地に隣国が攻め入った。今、北国境では攻防戦が繰り広げられている。俺は城に帰って兄上の指示に従い、場合によっては軍を率いなくてはならない。今朝の兵たちはそれを伝えに来た」
「戦に…、行くの?」
「それはまだ分からん。今、北には別の軍が出ているからな。だが俺は兄上の援けとなり国の為に身命を捧げるのが使命」
「翔流の、使命…」
「………だからさくら。ここでの暮らしは今夜が最後。明日、城へ発つ」
「…明日!?」
「急ですまない」
「翔流…っ」
翔流は武将。軍を率いて戦うのは武将の使命。だから泣いてはだめ、と自分に言い聞かせても、あまりにも突然に告げられた別れにさくらの涙腺は耐えられそうにない。だから唇をぎゅっと噛みしめてさくらはうつむいた。
「だが、城に戻ることはさくらにとってはよいかもしれない。もっと早くそうしなければならなかったのだと思う」
――………え?
「兄上は術士だ。薬師では治せぬ傷も術士の兄上ならあるいは癒せるかもしれん。それが分かっていて、俺は城に帰る日を先延ばしにしていた…」
ふたりの、穏やかな時間を手放したくない思いの方を優先させてしまっていたから、と翔流はつぶやく。
「すまない。こんなのは俺の身勝手だ…。だが城に戻ればこれまでのように共にいる時間はなくなる。だから言えなかった。さくらを見た兄上もきっと動揺する。俺は、さくらを兄上には…、」
「ま、待って翔流」
翔流の言葉をちゃんと理解しようと一生懸命聞いていたさくらだが、とうとうひとりでは解決できなくなってしまった。
「術士のお兄さんなら私の傷を癒せるって…、私をお城に連れて行ってくれるということなの?ここでお別れするのではないの?」
さくらの問いに翔流は目を丸くして、半ば唖然としたように答えた。
「あたりまえだ。さくらをひとりここに残して行くわけがないだろう」
「翔流…っ」
別れを覚悟して堪えていた涙だったが、今、別の意味に変わってさくらの瞳から一気に溢れた。
「さ、さくら…、なぜ泣く…」
「ごめ…っ、私、てっきり翔流とさよならしなきゃならないのかと思って…っ!ここで…、お別れなのかと……っ、ごめ…んな…、」
感情的な涙が後から後から溢れてくるさくらは、それを指で払いながら何とか笑顔に戻ろうとするが上手くいかなくて、とうとう顔をくしゃくしゃにして泣き出した。
「こんなに泣いて、ごめん…なさい。でも…っ」
そんな綺麗なさくらの涙に、翔流の胸には狂おしいほどの想いが突き上げる。
さくらを城に連れ帰っても、自分が戦に出れば共にはいられなくなる。だから、いつも傍にいられなくなるのは同じ。
だが、意味は全く違う。
さくらは城へ連れて行き、そして――。
「さくら…!」
翔流の両手が自然とさくらの体を抱き寄せ、まるで胸の中に閉じ込めるかのように抱きしめていた。
「そなたが…、さくらが愛しい。愛しくてたまらない」
「かけ…る…っ」
「さくらを、どこにも手放したくない」
「やっと……、」
さくらが愛しいと、そう言ってくれた。
心のどこかでずっと待っていた翔流の言葉を聞いて、さくらの胸は嬉しいような切ないような、温かな想いでいっぱいになった。
だから、翔流の胸に顔を押し付けて背中に回した腕にぎゅっと力をこめる。男らしくたくましい翔流の匂いが好きだと思いながら。
「さくら…」
「翔流…」
互いの命を刻む音がとくんとくんと、静かな空間に響いて重なり少しずつ大きくなっていく。翔流は腕に抱いたさくらの顔をそっと上に向かせ、涙の乾いていない瞳を見つめて囁いた。
「そなたを、抱きたい…」
「翔流…っ」
翔流の唇がさくらの唇に重なった。
「ずっと思っていた。さくらに触れ、ひとつになりたいと…」
眠れぬ夜を、幾夜も過ごしながら。
さくらの心臓が早鐘を打つ。
その音があまりにも大きくて翔流に聞こえてしまいそうだ。
「翔流が、好き…」
囁いた言葉の上に翔流の唇が触れた。だがすぐに離れてしまう。それが寂しくて目を開けると、翔流が驚いた瞳で見つめていた。
「翔流…?」
「さくらは今、俺が好きだと言ったのか?」
「言ったわ……」
「俺の聞き間違いではないのだな…?」
「聞き間違えてなんかいない…。翔流が好き…。大好きよ…。翔流に…触れて欲しい。触れて。私の、ぜんぶに…」
「…ああ、さくら…!」
再び重なった唇は先よりも強くさくらの感触を求めた。何度も何度も角度を変えながら重なり合うくちづけを交わしながら、ふたりの体は自然と寝台へ横たわっていった。
「さくら」
「翔流…」
世界で一番愛しい名を呼びあい、唇を求め合う。唇が離れ、代わりに指がそこを滑る。またどちらからともなく唇の感触を求めて重なる。
「ん…っ」
触れ合うだけでは足りなくなった翔流が、舌を深く侵入させてさくらの舌を絡めとった。初めは驚いて逃げようとした舌を上手に捕まえ、逃がすまいと深く深くくちづける。
「ん…っ!」
「逃げるな、さくら…」
翔流の甘く掠れた声にさくらは一瞬で縛られ、求めるられるまま応えていく。
唇どうしの触れ合いは吐息も声も呑みこむ深く激しい求め合いに変わり、ただそれだけでさくらの全身が痺れていった。
くちづけが熱くなればなるだけ、翔流の昂ぶる想いは自然とさくらの素肌をも求めていく。本能が猛るままに唇は首筋へとさがり、手が衣の上から胸の膨らみに触れた。
「…っ」
微かにさくらの体が強張るが夢中になっている翔流にそれは伝わらない。だが、翔流の手が襟を割って素の膨らみに進んだ時。
「…っ!!」
さくらの体は激しい拒絶の反応を表すように痙攣し手の進入を阻んだ。
「さくら…、怖いのか」
「…っ。――平気…よ」
震える心を押し込めてさくらはきゅっと目を閉じた。
さくらの襟元を大きく開いた翔流の手が、首筋から肩、そして乳房へと優しく触れながら下がってくる。
触れているのは大好きな翔流の手だと分かっているのに、その感触はさくらからあのおぞましい男たちの手の記憶を無情に引っ張り出してくるのだ。その嫌悪感はさくらの柔肌を硬い鎧に変えてしまう。
「さくら…」
手が触れるたびに強張り粟が立っていくさくらの素肌。
さくらの顔を見れば、今にも泣きだしそうに歪められ、悪夢にうなされる時のさくらが思い起こされる。さくらの躰に刻まれている恐怖が、翔流が触れる手に拒絶の反応をしているのだ。
「さくら…」
さくらの躰に残された無惨な痕が今でも生々しく翔流の脳裏にある。心も体も傷ついて毎晩のように悪夢にうなされているさくらを知っている。
賊が蹂躙したこの躰すべてに己の唇、舌、指で触れ、見えない疵痕を消し去ってやりたいと心の底から思う。
だが、翔流の理性はさくらに触れている手を引き戻した。
「翔流…!いいの…!私にちゃんと触れて…!」
「無理をするな、さくら」
翔流はそう言ってくちづけた。
「ごめ…んなさいっ」
さくらの瞳からせつない涙が溢れた。
拒絶してしまう体が疎ましい。
翔流に触れて欲しいのに、こんなにも心は翔流を求めて疼いているのに。
翔流とひとつに繋がりたいと、思っているのに……!
「俺はさくらが何よりも大切だ…。そなたの心も躰も壊したくはない…」
翔流はその涙を優しく指で拭う。
さくらが未だ生娘だからこそ、急がずに全ての傷が癒えるまで大切にしたいと思った。
「だが…、せめて…」
さくらの首筋に翔流の唇が触れ、それから少し強く吸い上げ、ほんの微かな痛みをさくらに与えた。
「あ…」
さくらの白い首筋に翔流の花が鮮やかに咲いた。
「その痛みはさくらが俺のものだという、せめてもの印…」
この痛みをもっとさくらの躰に教えさせてほしい…、と翔流は勃ちあがる桜色の頂をそっと口に含んでから、乳房に朱い所有印を刻んだ。
「あ…っ」
「もっと…」
もう片方の乳房にも。
「ん…っ」
「もっと…」
鎖骨の上、襟足、そして胸の真ん中。
ビリっとした痛みを伴ってさくらの白い肌に翔流の朱い所有印が刻まれていく。
「愛してる、さくら…」
「翔流…!」
翔流の想いが熱くさくらを縛る。
この躰も心も翔流だけのもの――。
それが嬉しくて切なくて、さくらは翔流の頭をかき抱いてくちづけた。
唇をぶつける勢いで激しく激しく翔流の唇を求めれば、翔流もさくらを求めて舌を絡める。
「さ…くらっ」
抱きしめて。
くちづけて。
くちづけて。
抱きしめる。
交わるのは躰でなくてもいい。
さくらを愛しいと思う心をこの唇に込めて、深く深くどこまでも深く交われば。
「んんっ」
「はぁ…っ」
足りなくなった酸素を求めて喘ぎ、そしてまた唇は重なる。何度も何度も、心を貪るように。
「翔流…!好き、大好き……っ」
「さくら…、愛してる…、さくら…!」
ただただ、互いの存在が愛しい。
翔流はさくらの名を、さくらは翔流の名を何度も何度も呼びながら、愛しい存在を強く強く抱きしめた。この小屋でふたりで暮らす最後の夜だと思えば、唇も抱き合う手も放すことなどできなくて。
こんなにも愛しているその想いを伝え合いたくて。
放れてもまたどちらからともなく触れて、求めてしまう。
くちづけて抱きしめあうだけの行為だが、それだけで翔流とさくらは高く高く上りつめていく。
愛してる。愛してる。愛してる。
伝え合う言葉が止まらない。
止めることなどできない触れ合いは、夜の闇が濃くなっても、空が白ずんできても終わることはなかったのだ。
兵たちとともに任に向かう翔流を、さくらはいつもと同じように送り出した。
そして、夕方になって小屋へ帰宅した翔流に、さくらは「おかえりなさい」と笑顔を向けた。
「ただいま。さくら?この暗い中で何をしているんだ?」
薄暗い部屋の中でさくらは一心に手元を動かしている。
「この前失敗して縫い合わせちゃった翔流の衣を繕い直そうと思って糸をほどいているの」
「こらさくら。無理をするなと言っているだろう。暗い手元では針が指を痛めるし目にも悪い」
「ごめんなさい。でも、どうしても今日これがやりたかったの…」
「なぜだ…?」
「分からないけど、なんだかどうしても…」
「そうか…」
何かの啓示なのだろうか。
さくらは知るはずもないことなのに――。
今朝の兵士たち――城からの使者の訪れがなくとも、いずれ決意しなければならないことは分かっていた。
だが、今があまりにも満たされているから。
まるで凪いだ海のように、こんなにも穏やかな気持ちでいるのは生まれて初めてだ。
さくらの存在が自分を満たし、癒している。さくらは翔流にとって明るい灯と同じ。さくらがいるから生きよう、生きていたいと思える。
だから、任についてのことは極力言わないでいたのだ。言ってしまえば己が置かれている立場や状況に縛られてしまうから。ひだまりのような日々の終焉が近くなってしまうから。告げなければならないことを明日、明日と先延ばしにしても、ここに在る、ここにしかないさくらとの時間を手放したくはないと思っていたから。
「翔流、どうしたの?なんだか、つらそう…。まさか!どこか怪我でもしたの!?」
「…いや怪我などしていない。さくらに話さなければならないことがあるのだ」
「なに?」
翔流はさくらの手から繕いかけの衣を取り、寝台に腰掛けさせて自分も隣に座った。
「今朝来た兵たちは城からの使いだ」
「うん…」
「領内の視察を終えここの賊も殲滅した今、もう俺は城に戻らなければならない」
「……!」
さくらは絶句した。
翔流は松風領の武将でここには賊を討伐するために逗留しているだけ。だから、いつかは城に帰ってしまうこんな日が来ると知っていたはずなのに、いつまでも翔流と一緒にいられるような気になってしまっていた。
これまでには一度もなかった兵士たちの訪れによって、今までとは違う何かが起こってしまうような不安と予感を胸のどこかで感じていた。不安に囚われてそれが現実になるのが怖かったから、普段と変わらない態度に努めたのに。
「戦が始まる」
「……戦…?」
「一週間ほど前、北の領地に隣国が攻め入った。今、北国境では攻防戦が繰り広げられている。俺は城に帰って兄上の指示に従い、場合によっては軍を率いなくてはならない。今朝の兵たちはそれを伝えに来た」
「戦に…、行くの?」
「それはまだ分からん。今、北には別の軍が出ているからな。だが俺は兄上の援けとなり国の為に身命を捧げるのが使命」
「翔流の、使命…」
「………だからさくら。ここでの暮らしは今夜が最後。明日、城へ発つ」
「…明日!?」
「急ですまない」
「翔流…っ」
翔流は武将。軍を率いて戦うのは武将の使命。だから泣いてはだめ、と自分に言い聞かせても、あまりにも突然に告げられた別れにさくらの涙腺は耐えられそうにない。だから唇をぎゅっと噛みしめてさくらはうつむいた。
「だが、城に戻ることはさくらにとってはよいかもしれない。もっと早くそうしなければならなかったのだと思う」
――………え?
「兄上は術士だ。薬師では治せぬ傷も術士の兄上ならあるいは癒せるかもしれん。それが分かっていて、俺は城に帰る日を先延ばしにしていた…」
ふたりの、穏やかな時間を手放したくない思いの方を優先させてしまっていたから、と翔流はつぶやく。
「すまない。こんなのは俺の身勝手だ…。だが城に戻ればこれまでのように共にいる時間はなくなる。だから言えなかった。さくらを見た兄上もきっと動揺する。俺は、さくらを兄上には…、」
「ま、待って翔流」
翔流の言葉をちゃんと理解しようと一生懸命聞いていたさくらだが、とうとうひとりでは解決できなくなってしまった。
「術士のお兄さんなら私の傷を癒せるって…、私をお城に連れて行ってくれるということなの?ここでお別れするのではないの?」
さくらの問いに翔流は目を丸くして、半ば唖然としたように答えた。
「あたりまえだ。さくらをひとりここに残して行くわけがないだろう」
「翔流…っ」
別れを覚悟して堪えていた涙だったが、今、別の意味に変わってさくらの瞳から一気に溢れた。
「さ、さくら…、なぜ泣く…」
「ごめ…っ、私、てっきり翔流とさよならしなきゃならないのかと思って…っ!ここで…、お別れなのかと……っ、ごめ…んな…、」
感情的な涙が後から後から溢れてくるさくらは、それを指で払いながら何とか笑顔に戻ろうとするが上手くいかなくて、とうとう顔をくしゃくしゃにして泣き出した。
「こんなに泣いて、ごめん…なさい。でも…っ」
そんな綺麗なさくらの涙に、翔流の胸には狂おしいほどの想いが突き上げる。
さくらを城に連れ帰っても、自分が戦に出れば共にはいられなくなる。だから、いつも傍にいられなくなるのは同じ。
だが、意味は全く違う。
さくらは城へ連れて行き、そして――。
「さくら…!」
翔流の両手が自然とさくらの体を抱き寄せ、まるで胸の中に閉じ込めるかのように抱きしめていた。
「そなたが…、さくらが愛しい。愛しくてたまらない」
「かけ…る…っ」
「さくらを、どこにも手放したくない」
「やっと……、」
さくらが愛しいと、そう言ってくれた。
心のどこかでずっと待っていた翔流の言葉を聞いて、さくらの胸は嬉しいような切ないような、温かな想いでいっぱいになった。
だから、翔流の胸に顔を押し付けて背中に回した腕にぎゅっと力をこめる。男らしくたくましい翔流の匂いが好きだと思いながら。
「さくら…」
「翔流…」
互いの命を刻む音がとくんとくんと、静かな空間に響いて重なり少しずつ大きくなっていく。翔流は腕に抱いたさくらの顔をそっと上に向かせ、涙の乾いていない瞳を見つめて囁いた。
「そなたを、抱きたい…」
「翔流…っ」
翔流の唇がさくらの唇に重なった。
「ずっと思っていた。さくらに触れ、ひとつになりたいと…」
眠れぬ夜を、幾夜も過ごしながら。
さくらの心臓が早鐘を打つ。
その音があまりにも大きくて翔流に聞こえてしまいそうだ。
「翔流が、好き…」
囁いた言葉の上に翔流の唇が触れた。だがすぐに離れてしまう。それが寂しくて目を開けると、翔流が驚いた瞳で見つめていた。
「翔流…?」
「さくらは今、俺が好きだと言ったのか?」
「言ったわ……」
「俺の聞き間違いではないのだな…?」
「聞き間違えてなんかいない…。翔流が好き…。大好きよ…。翔流に…触れて欲しい。触れて。私の、ぜんぶに…」
「…ああ、さくら…!」
再び重なった唇は先よりも強くさくらの感触を求めた。何度も何度も角度を変えながら重なり合うくちづけを交わしながら、ふたりの体は自然と寝台へ横たわっていった。
「さくら」
「翔流…」
世界で一番愛しい名を呼びあい、唇を求め合う。唇が離れ、代わりに指がそこを滑る。またどちらからともなく唇の感触を求めて重なる。
「ん…っ」
触れ合うだけでは足りなくなった翔流が、舌を深く侵入させてさくらの舌を絡めとった。初めは驚いて逃げようとした舌を上手に捕まえ、逃がすまいと深く深くくちづける。
「ん…っ!」
「逃げるな、さくら…」
翔流の甘く掠れた声にさくらは一瞬で縛られ、求めるられるまま応えていく。
唇どうしの触れ合いは吐息も声も呑みこむ深く激しい求め合いに変わり、ただそれだけでさくらの全身が痺れていった。
くちづけが熱くなればなるだけ、翔流の昂ぶる想いは自然とさくらの素肌をも求めていく。本能が猛るままに唇は首筋へとさがり、手が衣の上から胸の膨らみに触れた。
「…っ」
微かにさくらの体が強張るが夢中になっている翔流にそれは伝わらない。だが、翔流の手が襟を割って素の膨らみに進んだ時。
「…っ!!」
さくらの体は激しい拒絶の反応を表すように痙攣し手の進入を阻んだ。
「さくら…、怖いのか」
「…っ。――平気…よ」
震える心を押し込めてさくらはきゅっと目を閉じた。
さくらの襟元を大きく開いた翔流の手が、首筋から肩、そして乳房へと優しく触れながら下がってくる。
触れているのは大好きな翔流の手だと分かっているのに、その感触はさくらからあのおぞましい男たちの手の記憶を無情に引っ張り出してくるのだ。その嫌悪感はさくらの柔肌を硬い鎧に変えてしまう。
「さくら…」
手が触れるたびに強張り粟が立っていくさくらの素肌。
さくらの顔を見れば、今にも泣きだしそうに歪められ、悪夢にうなされる時のさくらが思い起こされる。さくらの躰に刻まれている恐怖が、翔流が触れる手に拒絶の反応をしているのだ。
「さくら…」
さくらの躰に残された無惨な痕が今でも生々しく翔流の脳裏にある。心も体も傷ついて毎晩のように悪夢にうなされているさくらを知っている。
賊が蹂躙したこの躰すべてに己の唇、舌、指で触れ、見えない疵痕を消し去ってやりたいと心の底から思う。
だが、翔流の理性はさくらに触れている手を引き戻した。
「翔流…!いいの…!私にちゃんと触れて…!」
「無理をするな、さくら」
翔流はそう言ってくちづけた。
「ごめ…んなさいっ」
さくらの瞳からせつない涙が溢れた。
拒絶してしまう体が疎ましい。
翔流に触れて欲しいのに、こんなにも心は翔流を求めて疼いているのに。
翔流とひとつに繋がりたいと、思っているのに……!
「俺はさくらが何よりも大切だ…。そなたの心も躰も壊したくはない…」
翔流はその涙を優しく指で拭う。
さくらが未だ生娘だからこそ、急がずに全ての傷が癒えるまで大切にしたいと思った。
「だが…、せめて…」
さくらの首筋に翔流の唇が触れ、それから少し強く吸い上げ、ほんの微かな痛みをさくらに与えた。
「あ…」
さくらの白い首筋に翔流の花が鮮やかに咲いた。
「その痛みはさくらが俺のものだという、せめてもの印…」
この痛みをもっとさくらの躰に教えさせてほしい…、と翔流は勃ちあがる桜色の頂をそっと口に含んでから、乳房に朱い所有印を刻んだ。
「あ…っ」
「もっと…」
もう片方の乳房にも。
「ん…っ」
「もっと…」
鎖骨の上、襟足、そして胸の真ん中。
ビリっとした痛みを伴ってさくらの白い肌に翔流の朱い所有印が刻まれていく。
「愛してる、さくら…」
「翔流…!」
翔流の想いが熱くさくらを縛る。
この躰も心も翔流だけのもの――。
それが嬉しくて切なくて、さくらは翔流の頭をかき抱いてくちづけた。
唇をぶつける勢いで激しく激しく翔流の唇を求めれば、翔流もさくらを求めて舌を絡める。
「さ…くらっ」
抱きしめて。
くちづけて。
くちづけて。
抱きしめる。
交わるのは躰でなくてもいい。
さくらを愛しいと思う心をこの唇に込めて、深く深くどこまでも深く交われば。
「んんっ」
「はぁ…っ」
足りなくなった酸素を求めて喘ぎ、そしてまた唇は重なる。何度も何度も、心を貪るように。
「翔流…!好き、大好き……っ」
「さくら…、愛してる…、さくら…!」
ただただ、互いの存在が愛しい。
翔流はさくらの名を、さくらは翔流の名を何度も何度も呼びながら、愛しい存在を強く強く抱きしめた。この小屋でふたりで暮らす最後の夜だと思えば、唇も抱き合う手も放すことなどできなくて。
こんなにも愛しているその想いを伝え合いたくて。
放れてもまたどちらからともなく触れて、求めてしまう。
くちづけて抱きしめあうだけの行為だが、それだけで翔流とさくらは高く高く上りつめていく。
愛してる。愛してる。愛してる。
伝え合う言葉が止まらない。
止めることなどできない触れ合いは、夜の闇が濃くなっても、空が白ずんできても終わることはなかったのだ。