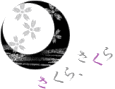蝋燭の灯がともる石造りの仄暗い部屋。
奥には祭壇、床には魔法陣、その上に佇む影がふたつ。
ひとりは身の丈よりも長い杖を手にし法衣を纏う老いた神官。
もうひとりは、稲妻色の長髪と闇夜のような漆黒の瞳を持つ若い術士。
「死人を蘇らせることは神とて不可能。だが、魂を同じとする者を遙かな時の向こうから喚ぶことは可能。吾はその禁忌の種を所有している」
「神官殿。その秘術の種、俺に授けてくれまいか」
「別の時を生きる者を喚ぶは理を犯すこと。本来、あってはならない異の物が今に混ざることによって定めに必ずや歪みが生じる」
「歪み?」
「時は先に向かって流れるが摂理。その道筋は世界、国、個に至るまで例外なく未来永劫まで定められている。理を犯し先世の者を召喚すれば、その者に関わった全ての定められた流れが一時変えられる。だが定めは必ずや元の流れに戻ろうとする、そのせいで起こる歪みだ。その報いは必ずや術を用いた者、そなたの身に還る。それでもその者を召喚すると望むか」
「望む」
「魂を喚ぶは魂を使う。その消耗は激しく今世の命数は確実に削られ、後には魂そのものが消滅し転生叶わぬ」
「それでも、望む」
「喚んだとて、そなたの望みが叶うとは限らぬ。そなたはただ咎を背負う者となるだけやもしれぬ」
「それでもだ…!」
「……ならば、吾はそなたに術を拓くのみ…」
石の空間に術士が唱える呪文がめぐり、魔法陣から天へ放出された稲妻のような光。
(楓よ。愛しき者よ。我が元へと還れ…!)
魔法陣から放つ閃光が空間を突き抜け時の波の中に溶けていく。
光を失わない魔法陣。
術士は意識を一点に集めて秘術の呪文を唱え続け長い時が過ぎていった。
(俺の声を聴け…!我が喚びかけに応えろ、楓よ!)
(私を呼ぶのは誰なの!?)
「応えた…。とうとう、見つけた…!」
「……」
術士は喚ぶ声を聞き応えた者を、全霊を懸けて召喚をかける。
「く…っ」
魂が強い力に吸い取られる衝撃に全身を貫かれ端正な顔が苦痛に歪むが、術士は呪文行使を続行する。
「ぐあぁ!」
あまりの苦痛に術士の絶叫が渡り、紅い飛沫が飛び散った。
「はぁ…、はぁ…っ」
術士は自分の胸を押さえつけながら荒い息を繰り返し、それでも術の行使を続ける。
やがて――。
術士の精神力が限界を迎えた時、魔法陣の光がすぅーと消えて行った。だが、ここには何も召喚されない。
「何故、降りぬ…!」
「いや…。還っておる」
「だが、俺の元には…!」
「報いはもうそなたの上に堕ち、歪みもまた生まれているのだ…」
重々しい神官の声を遠く聞きながら疲弊した術士はがくりと膝をついた。
◇ ◆ ◇
西の外れ。
海原を望む高台に建つ松風城は絶壁の縁に高い塔がそびえ、低い城を挟んでもう反対側にも同じ高さの塔を持つ大きな城だ。この城門を翔流がくぐるのは四年ぶりだった。
広間に通された翔流とさくらはそこで領主が現れるのを待つ。
翔流に横抱きにされているさくらは警備の兵士たちから向けられる好奇の視線にいたたまれなくなり、下ろして欲しいと耳打ちするが、翔流は気にするなと囁き、さくらを抱く腕に力を込めた。
やがて、老人を従えた領主が足音を響かせながら広間に入ってきた。
翔流はさくらをしっかりと抱いたまま膝をつき頭を垂れる。さくらも翔流にならい、頭を深く下げた。
「帰ったか、翔流!」
低く強い響きを持った声が広間を走った。
「は!ただいま戻りましてございます!」
「まずはこれまでの報告を聞こう」
「城を出ましてより北東南の国境とその集落を視察して参りました。境向こう、それぞれ兵が配置され攻め入られた北はもとより、東にも不穏な動きが見られ我が領内の攪乱を企でている様子。集落を襲った賊の討伐に手間取りましたが先ほどこれを殲滅しました。珠羽には今のところ注視する動きはありません」
「そうか。……して、そなたの疵は癒えたのか?」
翔流の肩がびくりと震えた。領主には翔流が城を出た理由が全てお見通しだったということか。
だが。
「長らくの勝手、真に申し訳ありませんでした」
「よい。長きに渡る視察、苦労であった。もうかしこまる必要はない。楽にしろ」
「痛み入ります…」
翔流はすっと顔を上げ、領主を見上げた。
「四年ぶりだな、翔流」
「兄上も息災でなにより」
「あ、兄上?!」
それまでおとなしくしていたさくらだったが、翔流の言葉につい声をあげてしまった。
「翔流のお兄さんって、領主様だったの?」
「言ってなかったか?」
「領主だなんて聞いてないわ。ということは、翔流はこの国の皇子様なの?」
「皇子って柄ではないが、一応な」
さくらは目を丸くして翔流を見つめ、翔流はどこかバツが悪そうに笑う。
そんなふたりの様子を眺めていた領主は――。
「その娘は?」
冷静に言葉を投げかけた。
「これはさくらという娘。半年前、東の集落で賊を討伐していた折に森において賊に襲われ傷を負ったさくらを救出保護しました。未だ遺症に苛まれてますゆえ、ここに連れ帰った次第」
「さ、さくらといいます…!翔流にはじゃなくて翔流様…には、助けてもらっただけじゃなくずっとお世話になって…、いえ、お世話していただいて…、そして…っ」
領主の放つ神々しいまでの威圧感に恐れをなし、俯いたままあわあわ話をするさくらに、領主はふ、と笑った。
「よい。さくらとやら、顔をあげて普通に話せ」
「は、はい。ありがとうございます…!」
領主様に挨拶なんてどうしたらいいのかと慌てたさくらだったが、思いの他、優しい言葉をもらってほっとした。
さくらはおずおずと顔を上げて、翔流の兄、松風領主の顔を見たのだ。
「………っ!!」
初めて互いの顔を見、目と目を合わせたさくらと領主。
さくらの顔を見て領主は空気が震えるほどに息を呑みこんだ。
「…領主…様?」
ほとんど驚愕した目で見つめられさくらは委縮した。銀髪を背の下まで流し端正な顔の中に夜闇のような漆黒の瞳。まるで神がそのまま現世に降りてきたような威厳と凍てつくほどの美しさを併せ持つ松風の領主は、大らかな翔流とはずいぶん違う雰囲気を持っている。
「兄上…」
翔流は、兄がさくらを見ればこのような反応をするだろうことは予想していた。
だから、たとえ兄の術がさくらの足を癒すことができようと、翔流の本心は兄にさくらを会わせたくはなかった。翔流がそうであったように兄もまた、癒えることのない疵を抱えている。
「そなたは…」
だが、領主がこれほどに息を呑んだ真の理由を知っているのは領主本人と傍にいる老人だけだ。
「……やっと……、しかし半年前だと…?」
老人がちらりと領主を見る。
ごくごく小さくつぶやいた領主の声は老人のみに届き、すぐに掻き消えた。
「このたびは、突然お城にお邪魔してしまってすみません。こんな格好でのご挨拶もすみません。アキレ…、脚の腱を切ってしまったので歩けなくて、翔流様に助けてもらっています」
領主はさくらの脚に鋭い視線を向けた。
「腱を切った、だと…?」
「はい」
賊の仕業か、と領主は翔流に問う。
「はい…」
ならず者が女の腱を切るということはそういう意味。
領主は顔をきつく引き締めて、もういちど翔流に訊いた。
「他に、疵は?」
「……ありません」
「真にか」
「はい。ありません」
「そうか……」
領主は安堵したように息を吐いて瞑目し、それから再び翔流とさくらに目を向けた。
「ふたりとも疲れているであろう。晩餐が整うまで部屋でゆっくりするがよい。さくら殿、そなたにも部屋をひとつ与えよう。この城で傷を癒すといい」
「ありがとうございます、領主様…」
「疾風(はやて)だ」
え?と首を傾げるさくらに、兄上の名だ、と翔流が教えた。
「疾風さま…」
その名を口にした時、さくらの胸が奥深いところで、どくん、と鳴った。
あまりにも微かに、だが間違いなく。
「疾風でいい。そなたは翔流のこともそう呼んでいるのだろう」
「はい」
「なら俺のことも疾風と呼んでかまわない。そなたはこの城に滞在する“客人”。堅苦しくなる必要はない」
「そのことで兄上に頼みがございます」
「なんだ、言ってみろ」
「ここではちょっと…。後ほど、さくらと共に兄上の部屋を訪ねてもよろしいですか」
「かまわない」
領主は一言で答えると広間を後にして行った。後に続く老人が振り向きざまにさくらと翔流を見つめ、何かを言いたげに、だが何も言わずに出ていく。
ふたりの姿が広間から消えた途端に、さくらはふーと深い息を吐いて強張らせていた肩の力を抜いた。
「緊張した…」
「はは。俺もだ」
「翔流も?だってお兄さんでしょ?」
「………兄上には…」
昔から敵わないのだ、と翔流は苦笑した。
「あの大きな杖を持った老人は誰?」
「この国の神事を全て司り、術の種を所有する神官殿だ」
「術の種?」
「術は才の在る者にしか扱えず、元となる種をその身に受け入れて使うもの。幼い頃に術の才を見いだされた兄上は、神官殿より種を授けられ術の行使が叶う、稀な術士なのだ」
「……?」
術とか種とかさくらにはイメージがまったく湧かないが、疾風がさくらの足を治してくれるかもしれない術士だということだけは分かった。
「でも、翔流のお兄さん、私を見てずいぶん驚いていたみたいだわ」
「それは…、」
翔流にその理由は分かっていたがさくらには言わず、自分の胸にのみしまったのだ。
奥には祭壇、床には魔法陣、その上に佇む影がふたつ。
ひとりは身の丈よりも長い杖を手にし法衣を纏う老いた神官。
もうひとりは、稲妻色の長髪と闇夜のような漆黒の瞳を持つ若い術士。
「死人を蘇らせることは神とて不可能。だが、魂を同じとする者を遙かな時の向こうから喚ぶことは可能。吾はその禁忌の種を所有している」
「神官殿。その秘術の種、俺に授けてくれまいか」
「別の時を生きる者を喚ぶは理を犯すこと。本来、あってはならない異の物が今に混ざることによって定めに必ずや歪みが生じる」
「歪み?」
「時は先に向かって流れるが摂理。その道筋は世界、国、個に至るまで例外なく未来永劫まで定められている。理を犯し先世の者を召喚すれば、その者に関わった全ての定められた流れが一時変えられる。だが定めは必ずや元の流れに戻ろうとする、そのせいで起こる歪みだ。その報いは必ずや術を用いた者、そなたの身に還る。それでもその者を召喚すると望むか」
「望む」
「魂を喚ぶは魂を使う。その消耗は激しく今世の命数は確実に削られ、後には魂そのものが消滅し転生叶わぬ」
「それでも、望む」
「喚んだとて、そなたの望みが叶うとは限らぬ。そなたはただ咎を背負う者となるだけやもしれぬ」
「それでもだ…!」
「……ならば、吾はそなたに術を拓くのみ…」
石の空間に術士が唱える呪文がめぐり、魔法陣から天へ放出された稲妻のような光。
(楓よ。愛しき者よ。我が元へと還れ…!)
魔法陣から放つ閃光が空間を突き抜け時の波の中に溶けていく。
光を失わない魔法陣。
術士は意識を一点に集めて秘術の呪文を唱え続け長い時が過ぎていった。
(俺の声を聴け…!我が喚びかけに応えろ、楓よ!)
(私を呼ぶのは誰なの!?)
「応えた…。とうとう、見つけた…!」
「……」
術士は喚ぶ声を聞き応えた者を、全霊を懸けて召喚をかける。
「く…っ」
魂が強い力に吸い取られる衝撃に全身を貫かれ端正な顔が苦痛に歪むが、術士は呪文行使を続行する。
「ぐあぁ!」
あまりの苦痛に術士の絶叫が渡り、紅い飛沫が飛び散った。
「はぁ…、はぁ…っ」
術士は自分の胸を押さえつけながら荒い息を繰り返し、それでも術の行使を続ける。
やがて――。
術士の精神力が限界を迎えた時、魔法陣の光がすぅーと消えて行った。だが、ここには何も召喚されない。
「何故、降りぬ…!」
「いや…。還っておる」
「だが、俺の元には…!」
「報いはもうそなたの上に堕ち、歪みもまた生まれているのだ…」
重々しい神官の声を遠く聞きながら疲弊した術士はがくりと膝をついた。
◇ ◆ ◇
西の外れ。
海原を望む高台に建つ松風城は絶壁の縁に高い塔がそびえ、低い城を挟んでもう反対側にも同じ高さの塔を持つ大きな城だ。この城門を翔流がくぐるのは四年ぶりだった。
広間に通された翔流とさくらはそこで領主が現れるのを待つ。
翔流に横抱きにされているさくらは警備の兵士たちから向けられる好奇の視線にいたたまれなくなり、下ろして欲しいと耳打ちするが、翔流は気にするなと囁き、さくらを抱く腕に力を込めた。
やがて、老人を従えた領主が足音を響かせながら広間に入ってきた。
翔流はさくらをしっかりと抱いたまま膝をつき頭を垂れる。さくらも翔流にならい、頭を深く下げた。
「帰ったか、翔流!」
低く強い響きを持った声が広間を走った。
「は!ただいま戻りましてございます!」
「まずはこれまでの報告を聞こう」
「城を出ましてより北東南の国境とその集落を視察して参りました。境向こう、それぞれ兵が配置され攻め入られた北はもとより、東にも不穏な動きが見られ我が領内の攪乱を企でている様子。集落を襲った賊の討伐に手間取りましたが先ほどこれを殲滅しました。珠羽には今のところ注視する動きはありません」
「そうか。……して、そなたの疵は癒えたのか?」
翔流の肩がびくりと震えた。領主には翔流が城を出た理由が全てお見通しだったということか。
だが。
「長らくの勝手、真に申し訳ありませんでした」
「よい。長きに渡る視察、苦労であった。もうかしこまる必要はない。楽にしろ」
「痛み入ります…」
翔流はすっと顔を上げ、領主を見上げた。
「四年ぶりだな、翔流」
「兄上も息災でなにより」
「あ、兄上?!」
それまでおとなしくしていたさくらだったが、翔流の言葉につい声をあげてしまった。
「翔流のお兄さんって、領主様だったの?」
「言ってなかったか?」
「領主だなんて聞いてないわ。ということは、翔流はこの国の皇子様なの?」
「皇子って柄ではないが、一応な」
さくらは目を丸くして翔流を見つめ、翔流はどこかバツが悪そうに笑う。
そんなふたりの様子を眺めていた領主は――。
「その娘は?」
冷静に言葉を投げかけた。
「これはさくらという娘。半年前、東の集落で賊を討伐していた折に森において賊に襲われ傷を負ったさくらを救出保護しました。未だ遺症に苛まれてますゆえ、ここに連れ帰った次第」
「さ、さくらといいます…!翔流にはじゃなくて翔流様…には、助けてもらっただけじゃなくずっとお世話になって…、いえ、お世話していただいて…、そして…っ」
領主の放つ神々しいまでの威圧感に恐れをなし、俯いたままあわあわ話をするさくらに、領主はふ、と笑った。
「よい。さくらとやら、顔をあげて普通に話せ」
「は、はい。ありがとうございます…!」
領主様に挨拶なんてどうしたらいいのかと慌てたさくらだったが、思いの他、優しい言葉をもらってほっとした。
さくらはおずおずと顔を上げて、翔流の兄、松風領主の顔を見たのだ。
「………っ!!」
初めて互いの顔を見、目と目を合わせたさくらと領主。
さくらの顔を見て領主は空気が震えるほどに息を呑みこんだ。
「…領主…様?」
ほとんど驚愕した目で見つめられさくらは委縮した。銀髪を背の下まで流し端正な顔の中に夜闇のような漆黒の瞳。まるで神がそのまま現世に降りてきたような威厳と凍てつくほどの美しさを併せ持つ松風の領主は、大らかな翔流とはずいぶん違う雰囲気を持っている。
「兄上…」
翔流は、兄がさくらを見ればこのような反応をするだろうことは予想していた。
だから、たとえ兄の術がさくらの足を癒すことができようと、翔流の本心は兄にさくらを会わせたくはなかった。翔流がそうであったように兄もまた、癒えることのない疵を抱えている。
「そなたは…」
だが、領主がこれほどに息を呑んだ真の理由を知っているのは領主本人と傍にいる老人だけだ。
「……やっと……、しかし半年前だと…?」
老人がちらりと領主を見る。
ごくごく小さくつぶやいた領主の声は老人のみに届き、すぐに掻き消えた。
「このたびは、突然お城にお邪魔してしまってすみません。こんな格好でのご挨拶もすみません。アキレ…、脚の腱を切ってしまったので歩けなくて、翔流様に助けてもらっています」
領主はさくらの脚に鋭い視線を向けた。
「腱を切った、だと…?」
「はい」
賊の仕業か、と領主は翔流に問う。
「はい…」
ならず者が女の腱を切るということはそういう意味。
領主は顔をきつく引き締めて、もういちど翔流に訊いた。
「他に、疵は?」
「……ありません」
「真にか」
「はい。ありません」
「そうか……」
領主は安堵したように息を吐いて瞑目し、それから再び翔流とさくらに目を向けた。
「ふたりとも疲れているであろう。晩餐が整うまで部屋でゆっくりするがよい。さくら殿、そなたにも部屋をひとつ与えよう。この城で傷を癒すといい」
「ありがとうございます、領主様…」
「疾風(はやて)だ」
え?と首を傾げるさくらに、兄上の名だ、と翔流が教えた。
「疾風さま…」
その名を口にした時、さくらの胸が奥深いところで、どくん、と鳴った。
あまりにも微かに、だが間違いなく。
「疾風でいい。そなたは翔流のこともそう呼んでいるのだろう」
「はい」
「なら俺のことも疾風と呼んでかまわない。そなたはこの城に滞在する“客人”。堅苦しくなる必要はない」
「そのことで兄上に頼みがございます」
「なんだ、言ってみろ」
「ここではちょっと…。後ほど、さくらと共に兄上の部屋を訪ねてもよろしいですか」
「かまわない」
領主は一言で答えると広間を後にして行った。後に続く老人が振り向きざまにさくらと翔流を見つめ、何かを言いたげに、だが何も言わずに出ていく。
ふたりの姿が広間から消えた途端に、さくらはふーと深い息を吐いて強張らせていた肩の力を抜いた。
「緊張した…」
「はは。俺もだ」
「翔流も?だってお兄さんでしょ?」
「………兄上には…」
昔から敵わないのだ、と翔流は苦笑した。
「あの大きな杖を持った老人は誰?」
「この国の神事を全て司り、術の種を所有する神官殿だ」
「術の種?」
「術は才の在る者にしか扱えず、元となる種をその身に受け入れて使うもの。幼い頃に術の才を見いだされた兄上は、神官殿より種を授けられ術の行使が叶う、稀な術士なのだ」
「……?」
術とか種とかさくらにはイメージがまったく湧かないが、疾風がさくらの足を治してくれるかもしれない術士だということだけは分かった。
「でも、翔流のお兄さん、私を見てずいぶん驚いていたみたいだわ」
「それは…、」
翔流にその理由は分かっていたがさくらには言わず、自分の胸にのみしまったのだ。