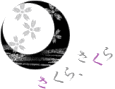「さくらちゃん、今日は芋の煮転がし持ってきたよー」
「ありがとうおばさん。そこに置いておいて」
煮物の器を抱えてきたのは右隣のおばさん。
「嬢ちゃん、豆はいるかい?」
「うん!いつも助かるわ、ありがとう!」
左隣のおじさんはたくさんの豆が入ったザルを卓の上に置いてくれる。翔流が住民たちの信頼を得ているからか、近所の人たちはさくらに対してとても親切だ。こうして、毎日のように食材や日用品を持ってきてくれる。
さくらは、そんな優しい近所の人たちに手伝ってもらいながら、食事の支度をしたり出来る限りの掃除や洗濯をしたりしている。
さくらの傷が癒え松葉杖の使い方も上達したころから翔流は自分の任を再開し始めた。
ここ、東の集落周辺には賊が頻繁に現れ、人々の生活を脅かしている。翔流がこの小屋に逗留しているのはもともと賊討伐のためだ。日中、翔流が不在になる時は近所の人たちが入れ代わり立ち代わりさくらの様子を見に来てくれるのだ。
「翔流様が来てからは賊もすっかりおとなしくなったよ」
翔流がこの地に来るまで賊の被害はかなり深刻で、盗み、拐し、殺戮に至るまで、賊たちはやりたい放題に暴れていたらしい。だが、さくらがここに来てからは集落が賊に襲われたことはない。
「それでも、賊がいなくなったわけじゃないからね。村にはやってこないが、森の近くではまだ人が襲われたりしてるから」
翔流は森周辺に出没する賊の討伐、集落周辺の見回りや情報の聞き込み、栖の探索等をやっているらしい。
賊の話を聞くとさくらの体に悪寒が走る。だから、本当はあまり聞きたくない。だが、翔流が賊の討伐を仕事にしているなら無関心ではいられない。
「翔流はずっとここで賊と戦っているの?」
「ずっとじゃないよ。まだ雪が残ってた頃だったかねぇ、翔流様はふらりとこの集落にやってきたんだよ」
「そうだったな。その頃は賊どもがしょっちゅう暴れててね。たまたま翔流様が来た時も賊がさんざん村を荒らしていて、それを翔流様はひとりで成敗しちまったんだ」
「ひとりで?」
「きっと偉い武人さんなんだろうと思うけど、それから翔流様はここに留まって賊の討伐をしてくれるようになったんだよ」
翔流に成敗された賊が仕返しにやってくる、それを翔流が追撃する、また賊が来る、翔流が追撃する――と、さくらが来る少し前までそんないたちごっこが翔流と賊の間で繰り返されていたらしい。
「翔流様は強い。賊の数は確実に減ってるよ」
「けど、強いからこそ、あたしは心配してたんだよ。翔流様はひとりで無茶ばかりしてたからね」
「そうだな。賊を討伐してくれるのはありがたかったが、追撃するのもどこか自棄になっているようで見ていて冷や冷やしたよ」
自棄?とさくらは聞き返した。
さくらが知っている翔流はいつも穏やかで優しい。自棄になっている翔流などさくらには想像もできない。
「ちょうど嬢ちゃんがここへ来た日の晩もひとりであの森に行ってなぁ」
「そうなんだよ。危ないからひとりで行くのはやめてくれって言ったのにきかなくてねぇ…」
あの日、翔流の留守中に集落に賊が現れ、さんざん暴れた後に森の中へと去って行った。あまりにも見え透いた所業に、翔流をおびき寄せる罠だと誰もが思った。だが、翔流は村の者が止めるのも聞かずにひとり馬を走らせて行ってしまったらしい。
「……あ」
さくらはハッと思い出した。
自分を襲ったあの賊たち、敵を待ち伏せていると言っていた。敵とは、翔流のことだったのかもしれない。
「あたしらの為に行ってくれたんだけど、せめて砦に駐屯している兵を連れて行って欲しいって、あたしらみんなで頼んだんだよ」
東の砦には松風軍の兵士が駐屯して隣国との境を監視している。この村から砦はさほど遠くはない。なのに、翔流はいつも単独で賊と戦っていた。
「なんでひとりであんな無茶をするんだってあたしらみんな心配してたんだよ」
「翔流、どうして…」
狙う賊が伏せている暗い森に翔流がひとりで来ていたらどうなっていたのだろう。翔流がどれほど強くても、さくらの脚を一太刀で斬ったあの賊たちもまともに戦えば決して弱くはなかったはずだ。
それに、賊はあの四人だけじゃなく、もっと仲間がいるらしいことを言っていた。もしも、あの賊たちがさくらを見つけるよりも先に翔流に遭っていたら。翔流がその賊たちに囲まれていたら。
そう思った時、さくらの肌がぞわりと粟立った。
「死を恐れてないっていうか、むしろ…」
「なんとなく、死にたがってるみたいにも思えて」
「え!?」
さくらがひどく動揺すると、いやいや、とおばさんは手を振った。
「さくらちゃんが来てからはそんなことないよ?翔流様はずいぶんと変わられたよ」
今はちゃーんと砦の兵士たちと行動しているからね、とおばさん。
「そうだな。翔流様が無茶しなくなったのは嬢ちゃんのおかげだな」
「私のおかげなんかじゃ…」
あの時、翔流が賊を追って来てくれていなかったら、今、自分は間違いなくここにはいない。賊に捕まって、きっとあれ以上の辱めを――。
さくらはきゅっと両目を瞑り、自分で自分を抱きしめるようにして首を激しく振った。未だ、生々しいあの汚らわしい感触。
「……っ」
「さくらちゃん。翔流様のこと頼むね。あたしらみんな、あの人には感謝してるんだ」
「ああ。半ば諦めかけていた儂らに希望をくれた人だからな」
「翔流が希望を…」
そうだよ、とおばさんはニコニコ笑う。
「翔流様に頼るばかりじゃなく、あたしら村の者は自分等でできる限り生活や身を守る。みんなで協力し合ってね。そういう前向きな希望をくれたのは翔流様なんだ」
「儂らはあの人にも無茶してほしくないし、死んでほしくない。だから嬢ちゃん翔流様を頼むよ」
「頼むって…そんな。私は翔流のおかげでここで生きていられるの…」
翔流はなぜ、そんな無謀を繰り返していたのだろう。たったひとりで、それこそ、死にたがっているとしか思えないほどの無茶苦茶な戦い方をして。
「翔流…」
ショックだ。
桜の季節にここに来て今は夏だからここで暮らし始めてもう三ヶ月ぐらいが過ぎただろうか。
最初のひと月は床から出られないさくらを献身的に看病してくれた。次のひと月は松葉杖を作ってくれたり、練習に付き合ってくれたり、時々小屋の外に連れて行ってくれたりした。そして今はこの小屋を拠点にして賊の討伐と近辺集落の視察を行いながら、夕方にはちゃんと小屋に帰ってきてさくらの傍にいてくれる。
翔流が死にたいと思っているなんて少しも感じなかった。おじさんとおばさんが言うように、本当に翔流は変わったのだろうか。死にたいなんて、もう思っていないだろうか。優しい翔流が死を願うほどの疵を心に負っているかと思うと、胸がぎゅっと締め付けられた。
「翔流、無事に帰って来て…!」
心配するさくらの様子に、おじさんとおばさんは顔を見合わせて言った。
「あたしら、余計なこと言っちゃったかね」
「ごめんよ、嬢ちゃん。そんな心配することはないって。あんたがいるんだ。翔流様はもう二度と無茶なんかしないよ」
「そうだよ、さくらちゃん。だからそんな顔しないでおくれよ」
うん、とさくらは頷いた。
それでも、不安はぬぐいきれない。
日が暮れる頃になって翔流が帰ってくると、さくらは半分泣きそうな顔でおかえりなさい、と叫び、いきなり翔流の胸にしがみついてしまった。
「さくら…、いったいどうしたというのだ?なにかあったのか?」
こんなこと今までのさくらにはなかったから翔流は戸惑いを隠せない。
さくらはふるふると首を振りながら、それでもしがみついた翔流の衣から手が放せなかった。今、握りしめている毛皮のような衣の肩口から袖にかけてかっぱりと裂けてしまっているのが、ますます不安を連れてくるから。
「翔流の衣…」
ああこれか…、と翔流は破けた衣の穴に触れた。
追っていた賊と斬り合いになり、賊の刀がこれを裂いた。もちろんその後、その賊は滅っした。
さくらは衣の裂け目から翔流の腕を覗き、傷の有無を確かめる。その様子があまりにも切羽詰ったものだから、翔流はやや困惑しながら無傷の腕をさくらに見せた。
「剣が衣を掠っただけだ。俺に傷はひとつもない」
「よかった…」
やっとさくらは安心して息をついた。
「だが、どうしたのだ?今日のさくらは様子が変だぞ?」
「何でもないの…。ただ、翔流のことが心配だっただけ」
「俺のこと?何故だ?」
「だって…」
おばさんたちに聞いた話は胸の中に留めた。だが、無茶をするしないに関わらず、翔流の仕事が命を危険にさらすものであることは変わりない。さくらの知らないところで翔流は毎日命懸けの仕事をしているのだということを、さくらは今日、初めて実感し、一度分かってしまうと身がすくむ。
「さくら?」
死を恐れず無謀を繰り返していたという翔流だが、少なくとも、今、傍にいる翔流は自棄を起こした人の目はしていない。
だから、
「翔流、無茶はしないでね。毎日無事にここに帰って来てね」
それだけを伝えて微笑んだ。翔流の過去や心の疵はとても気になるが、それに触れてはいけないような気がするから。
「………さくら」
さくらの微笑みは翔流に懐かしく柔らかな空気を運んできた。ふいに頭に浮かんだのは翔流の好きな花――桜だ。
「今、目の前に故郷の桜が見えた気がした」
「故郷の?」
「ああ…」
子どもの頃からその桜は翔流にとっての癒しだった。父に叱られた時、兄と喧嘩した時、ひとりではどうにも対処できない感情に呑まれた時に、庭の池のほとりに立つ桜の元に行くと不思議と落ち着いた。花を満開に咲かせている時も、散り際でも、葉だけになっていても、故郷の桜はどんな時でも翔流の心に安穏をくれた。
その桜と同じ空気が今、目の前のさくらの微笑みに見えた気がしたのだ。
「桜は翔流の好きな花よね」
前に翔流はさくらの名前を好きな花と同じいい名前だ、と言ってくれた。
「ああ。俺は花を愛でたりするよりも剣を振っている方が性分には合っているのだが、桜だけは俺にとって特別な花なんだ。物心ついた時から一番近くにあった花だからな」
「よかった…」
翔流の過去が死にたいと思うような疵ばかりではなくて。桜の花のような、明るい色の思い出がちゃんとあって。
「よかった…とは?」
さくらの真意に気付くはずもない翔流はきょとんとする。だが、さくらはただ、ふわりと笑うだけだった。
「ありがとうおばさん。そこに置いておいて」
煮物の器を抱えてきたのは右隣のおばさん。
「嬢ちゃん、豆はいるかい?」
「うん!いつも助かるわ、ありがとう!」
左隣のおじさんはたくさんの豆が入ったザルを卓の上に置いてくれる。翔流が住民たちの信頼を得ているからか、近所の人たちはさくらに対してとても親切だ。こうして、毎日のように食材や日用品を持ってきてくれる。
さくらは、そんな優しい近所の人たちに手伝ってもらいながら、食事の支度をしたり出来る限りの掃除や洗濯をしたりしている。
さくらの傷が癒え松葉杖の使い方も上達したころから翔流は自分の任を再開し始めた。
ここ、東の集落周辺には賊が頻繁に現れ、人々の生活を脅かしている。翔流がこの小屋に逗留しているのはもともと賊討伐のためだ。日中、翔流が不在になる時は近所の人たちが入れ代わり立ち代わりさくらの様子を見に来てくれるのだ。
「翔流様が来てからは賊もすっかりおとなしくなったよ」
翔流がこの地に来るまで賊の被害はかなり深刻で、盗み、拐し、殺戮に至るまで、賊たちはやりたい放題に暴れていたらしい。だが、さくらがここに来てからは集落が賊に襲われたことはない。
「それでも、賊がいなくなったわけじゃないからね。村にはやってこないが、森の近くではまだ人が襲われたりしてるから」
翔流は森周辺に出没する賊の討伐、集落周辺の見回りや情報の聞き込み、栖の探索等をやっているらしい。
賊の話を聞くとさくらの体に悪寒が走る。だから、本当はあまり聞きたくない。だが、翔流が賊の討伐を仕事にしているなら無関心ではいられない。
「翔流はずっとここで賊と戦っているの?」
「ずっとじゃないよ。まだ雪が残ってた頃だったかねぇ、翔流様はふらりとこの集落にやってきたんだよ」
「そうだったな。その頃は賊どもがしょっちゅう暴れててね。たまたま翔流様が来た時も賊がさんざん村を荒らしていて、それを翔流様はひとりで成敗しちまったんだ」
「ひとりで?」
「きっと偉い武人さんなんだろうと思うけど、それから翔流様はここに留まって賊の討伐をしてくれるようになったんだよ」
翔流に成敗された賊が仕返しにやってくる、それを翔流が追撃する、また賊が来る、翔流が追撃する――と、さくらが来る少し前までそんないたちごっこが翔流と賊の間で繰り返されていたらしい。
「翔流様は強い。賊の数は確実に減ってるよ」
「けど、強いからこそ、あたしは心配してたんだよ。翔流様はひとりで無茶ばかりしてたからね」
「そうだな。賊を討伐してくれるのはありがたかったが、追撃するのもどこか自棄になっているようで見ていて冷や冷やしたよ」
自棄?とさくらは聞き返した。
さくらが知っている翔流はいつも穏やかで優しい。自棄になっている翔流などさくらには想像もできない。
「ちょうど嬢ちゃんがここへ来た日の晩もひとりであの森に行ってなぁ」
「そうなんだよ。危ないからひとりで行くのはやめてくれって言ったのにきかなくてねぇ…」
あの日、翔流の留守中に集落に賊が現れ、さんざん暴れた後に森の中へと去って行った。あまりにも見え透いた所業に、翔流をおびき寄せる罠だと誰もが思った。だが、翔流は村の者が止めるのも聞かずにひとり馬を走らせて行ってしまったらしい。
「……あ」
さくらはハッと思い出した。
自分を襲ったあの賊たち、敵を待ち伏せていると言っていた。敵とは、翔流のことだったのかもしれない。
「あたしらの為に行ってくれたんだけど、せめて砦に駐屯している兵を連れて行って欲しいって、あたしらみんなで頼んだんだよ」
東の砦には松風軍の兵士が駐屯して隣国との境を監視している。この村から砦はさほど遠くはない。なのに、翔流はいつも単独で賊と戦っていた。
「なんでひとりであんな無茶をするんだってあたしらみんな心配してたんだよ」
「翔流、どうして…」
狙う賊が伏せている暗い森に翔流がひとりで来ていたらどうなっていたのだろう。翔流がどれほど強くても、さくらの脚を一太刀で斬ったあの賊たちもまともに戦えば決して弱くはなかったはずだ。
それに、賊はあの四人だけじゃなく、もっと仲間がいるらしいことを言っていた。もしも、あの賊たちがさくらを見つけるよりも先に翔流に遭っていたら。翔流がその賊たちに囲まれていたら。
そう思った時、さくらの肌がぞわりと粟立った。
「死を恐れてないっていうか、むしろ…」
「なんとなく、死にたがってるみたいにも思えて」
「え!?」
さくらがひどく動揺すると、いやいや、とおばさんは手を振った。
「さくらちゃんが来てからはそんなことないよ?翔流様はずいぶんと変わられたよ」
今はちゃーんと砦の兵士たちと行動しているからね、とおばさん。
「そうだな。翔流様が無茶しなくなったのは嬢ちゃんのおかげだな」
「私のおかげなんかじゃ…」
あの時、翔流が賊を追って来てくれていなかったら、今、自分は間違いなくここにはいない。賊に捕まって、きっとあれ以上の辱めを――。
さくらはきゅっと両目を瞑り、自分で自分を抱きしめるようにして首を激しく振った。未だ、生々しいあの汚らわしい感触。
「……っ」
「さくらちゃん。翔流様のこと頼むね。あたしらみんな、あの人には感謝してるんだ」
「ああ。半ば諦めかけていた儂らに希望をくれた人だからな」
「翔流が希望を…」
そうだよ、とおばさんはニコニコ笑う。
「翔流様に頼るばかりじゃなく、あたしら村の者は自分等でできる限り生活や身を守る。みんなで協力し合ってね。そういう前向きな希望をくれたのは翔流様なんだ」
「儂らはあの人にも無茶してほしくないし、死んでほしくない。だから嬢ちゃん翔流様を頼むよ」
「頼むって…そんな。私は翔流のおかげでここで生きていられるの…」
翔流はなぜ、そんな無謀を繰り返していたのだろう。たったひとりで、それこそ、死にたがっているとしか思えないほどの無茶苦茶な戦い方をして。
「翔流…」
ショックだ。
桜の季節にここに来て今は夏だからここで暮らし始めてもう三ヶ月ぐらいが過ぎただろうか。
最初のひと月は床から出られないさくらを献身的に看病してくれた。次のひと月は松葉杖を作ってくれたり、練習に付き合ってくれたり、時々小屋の外に連れて行ってくれたりした。そして今はこの小屋を拠点にして賊の討伐と近辺集落の視察を行いながら、夕方にはちゃんと小屋に帰ってきてさくらの傍にいてくれる。
翔流が死にたいと思っているなんて少しも感じなかった。おじさんとおばさんが言うように、本当に翔流は変わったのだろうか。死にたいなんて、もう思っていないだろうか。優しい翔流が死を願うほどの疵を心に負っているかと思うと、胸がぎゅっと締め付けられた。
「翔流、無事に帰って来て…!」
心配するさくらの様子に、おじさんとおばさんは顔を見合わせて言った。
「あたしら、余計なこと言っちゃったかね」
「ごめんよ、嬢ちゃん。そんな心配することはないって。あんたがいるんだ。翔流様はもう二度と無茶なんかしないよ」
「そうだよ、さくらちゃん。だからそんな顔しないでおくれよ」
うん、とさくらは頷いた。
それでも、不安はぬぐいきれない。
日が暮れる頃になって翔流が帰ってくると、さくらは半分泣きそうな顔でおかえりなさい、と叫び、いきなり翔流の胸にしがみついてしまった。
「さくら…、いったいどうしたというのだ?なにかあったのか?」
こんなこと今までのさくらにはなかったから翔流は戸惑いを隠せない。
さくらはふるふると首を振りながら、それでもしがみついた翔流の衣から手が放せなかった。今、握りしめている毛皮のような衣の肩口から袖にかけてかっぱりと裂けてしまっているのが、ますます不安を連れてくるから。
「翔流の衣…」
ああこれか…、と翔流は破けた衣の穴に触れた。
追っていた賊と斬り合いになり、賊の刀がこれを裂いた。もちろんその後、その賊は滅っした。
さくらは衣の裂け目から翔流の腕を覗き、傷の有無を確かめる。その様子があまりにも切羽詰ったものだから、翔流はやや困惑しながら無傷の腕をさくらに見せた。
「剣が衣を掠っただけだ。俺に傷はひとつもない」
「よかった…」
やっとさくらは安心して息をついた。
「だが、どうしたのだ?今日のさくらは様子が変だぞ?」
「何でもないの…。ただ、翔流のことが心配だっただけ」
「俺のこと?何故だ?」
「だって…」
おばさんたちに聞いた話は胸の中に留めた。だが、無茶をするしないに関わらず、翔流の仕事が命を危険にさらすものであることは変わりない。さくらの知らないところで翔流は毎日命懸けの仕事をしているのだということを、さくらは今日、初めて実感し、一度分かってしまうと身がすくむ。
「さくら?」
死を恐れず無謀を繰り返していたという翔流だが、少なくとも、今、傍にいる翔流は自棄を起こした人の目はしていない。
だから、
「翔流、無茶はしないでね。毎日無事にここに帰って来てね」
それだけを伝えて微笑んだ。翔流の過去や心の疵はとても気になるが、それに触れてはいけないような気がするから。
「………さくら」
さくらの微笑みは翔流に懐かしく柔らかな空気を運んできた。ふいに頭に浮かんだのは翔流の好きな花――桜だ。
「今、目の前に故郷の桜が見えた気がした」
「故郷の?」
「ああ…」
子どもの頃からその桜は翔流にとっての癒しだった。父に叱られた時、兄と喧嘩した時、ひとりではどうにも対処できない感情に呑まれた時に、庭の池のほとりに立つ桜の元に行くと不思議と落ち着いた。花を満開に咲かせている時も、散り際でも、葉だけになっていても、故郷の桜はどんな時でも翔流の心に安穏をくれた。
その桜と同じ空気が今、目の前のさくらの微笑みに見えた気がしたのだ。
「桜は翔流の好きな花よね」
前に翔流はさくらの名前を好きな花と同じいい名前だ、と言ってくれた。
「ああ。俺は花を愛でたりするよりも剣を振っている方が性分には合っているのだが、桜だけは俺にとって特別な花なんだ。物心ついた時から一番近くにあった花だからな」
「よかった…」
翔流の過去が死にたいと思うような疵ばかりではなくて。桜の花のような、明るい色の思い出がちゃんとあって。
「よかった…とは?」
さくらの真意に気付くはずもない翔流はきょとんとする。だが、さくらはただ、ふわりと笑うだけだった。