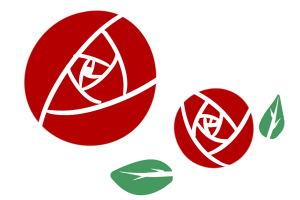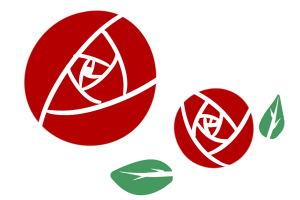
2話【別視点・廻る男】
『…死んでるな』
『お腹に赤ん坊がいたみたいだね……ひどい暮らししていたんだろうね…』
大学に行く途中、いつも通り過ぎる道で人が行き倒れていた。介抱しようとした男性が脈を測っていたが、もう既に命の鼓動は尽きていたようである。
『ひどい格好だ、どうせうだつの上がらない旦那に苦労させられた挙げ句、暴力を振られて事切れたところを捨てられたんだろ』
周りにいた人は口々に好き勝手なことを言ってひとり、またひとりと立ち去っていった。
倒れていたのはまだ年若い女の子だった。ハギレで合わせたような粗末な服に身を包んだ彼女はお腹を庇った体勢で息絶えていた。その表情は苦悶に満ちており、死の直前まで苦しんでいたことが見て取れた。
人の死を見たのは何もはじめてじゃない。
今までにも浮浪者が事切れているのを目撃することもあったし、近親者が闘病の末、壮絶な最期を迎えた瞬間を間近で目にしたこともある。
……なのに、名前も知らない彼女の苦しそうで、泣きそうなその死に顔は僕の記憶に焼き付いて離れなかった。
それから数十年後に僕は死んだはずだった。大学卒業後は家の事業を継ぎ、親の決めた女性と結婚し、子どもをもうけ、平凡な幸せを手に入れた。そして寿命を全うしてその生命を終えた。
なのに、僕は再び斎藤芳雄として生まれた。
どういうことなのか理解できなかった。
理解できないけど、時は無常にも過ぎていく。
仕方がないので、もう一度同じ人生を歩むことにした。
自分の人生に後悔はなかった。また同じような人生を歩むのだと思って呑気に過ごしていたのだが、そんな僕の前に彼女が現れたのだ。
彼女は生きていた。
あの哀れな亡骸ではない、生きた姿のまま、図書館で読書しているのだ。顔見知りの司書にこっそり話を聞いてみたら、幼少期からの常連だと聞いた。
僕はてっきり、あの彼女は浮浪者、もしくは場末の娼婦なのではと思っていたのだが、ここで見た彼女はそれなりに恵まれた家の育ちだとわかった。
上品で整った顔立ちをしていた。野に咲く花のように凛とした女性だった。仕立てのいい着物を着た彼女は本に夢中で、僕の視線には全く気づかない。勉強するためにいつも立ち寄る図書館なのだが、彼女の姿がないかを探すのが僕の日課となってしまった。
どこの家の娘さんなのだろう。
なぜ前の生ではあんな壮絶な最期を迎えたのだろう。
…お腹の子どもは誰の子だったのだろうか。
気にはなるが、女性に軽々しく声をかけるのは憚れて、僕はいつも遠くから見守るだけだった。
だから知り合ったのもたまたま偶然だったんだ。高いところにある本を自分で取ろうと着物姿でハシゴに乗ろうとする彼女を止めて、代わりに本をとってあげたことから、僕らの交流は始まった。
彼女は静子さんというそうだ。話し方や立ち振舞を見ていたら、やっぱりそこそこ裕福なお宅の娘さんのようだった。
話していると、きちんと淑女教育を受けた娘さんといった感じではあったが、彼女は何より好奇心が旺盛なひとだった。女学校には行かせてもらえずに、家庭教師に学ぶ毎日で行動を制限されているので知らないことが多すぎるから自分から外へ学びに来ているのだそうだ。
図書館に行くこと、外を出歩くことを親御さんはいい顔しないそうだが、彼女は自分のしたいようにすると笑っていた。親に逆らっても平気なのかと心配にはなったが、どうも彼女は家族とはあまりうまく行っていないようであった。家族の前でいい子に振る舞っていても無駄だからと笑っていた。
彼女は笑っているけど、僕には泣いているように思えた。悲しいのにそれを無理やり抑え込んで笑う。
その姿が痛々しくて、前世で見た彼女の亡骸のあの表情を思い出してしまって僕まで泣きそうになってしまった。
知り合ってから3ヶ月経った頃、彼女が気になることを漏らした。
婚約者がいること、しかしその相手は妹さんに夢中であること。
婚約破棄になったら別の相手に嫁がねばならないこと。
「これからきっと斎藤さんとも会えなくなります。せっかく良くしてくださったのに寂しくなるわ」
彼女はまた無理やり笑顔を作っていた。
「お元気でね」
その言葉はまるで「助けて」と言っているように聞こえた。
■□■
「静子…ですか? 失礼ですがあなたは…」
応対してくれた中年の女性から怪訝な目を向けられてしまった。婚約者でもなんでもない男が尋ねてきたらそりゃあ不審な目で見られるに決まっている。
だけど僕だって訳もなく訪ねたわけじゃないんだ。
「斎藤芳雄と申します。静子さんとは図書館で知り合って…」
「いやぁぁああああああ!!」
僕が自己紹介をしているその途中で、つんざくような悲鳴が飛んできた。
玄関先まで届く声。ただ事ではないその悲鳴に僕はギクリとした。
「千代子!?」
彼女の母親らしき女性が誰かの名前を呼ぶと、小走りで奥へと走っていく。非礼だとはわかっていたが、僕は勝手にお宅へとお邪魔させてもらった。
「なっ…これは一体どういうことなの!」
「お、お姉さまに婚約破棄のお願いをしたら、好き勝手にはさせないって……」
頭から血を浴びた少女がガクガク震えながら中年の女性に縋りついていた。
ドクンドクンと心臓がやけに大きく鳴り響いた。
──奥から異様な空気が流れている。嫌な予感と、それを気のせいだと思いたい気持ちで僕の心はざわめいていた。
こんなの悪夢じゃないか。
彼女は血の海の上で倒れていた。その手元には小刀が転がっていて……
ほんの数時間前までお話していたはずなのに。
そんな、また君は壮絶な最期をむかえてしまったのか。
「どうしましょうどうしましょう! 明後日にはあちらに静子を嫁がせる予定だったのに!」
その言葉に僕は呆然とした。
娘が血溜まりを作って息絶えているんだぞ?
何を言っているんだこのひとは。
「お母さま、私と正男さんの結婚はどうなるの? 嫌だわ、喪が開けてからになるじゃないの」
おかしいのは母親だけじゃない。妹もだ。
姉が死んだというのに、姉から奪った婚約者との結婚時期を気にしているだと? 人が死んでるんだぞ。目の前で姉が死んでいく姿を見ていたはずなのに、結婚のことを心配するのか?
僕は震えそうな足を動かして、躯となってしまった彼女に近づく。事切れている彼女を抱き起こすとまだ暖かい…。
「…静子さん、君はこれで良かったのかい?」
彼女の表情はあの苦悶の表情ではなかった。
うっすら目が開いており、どこかうつろな表情で亡くなっていた。その姿は哀れで悲しげに映った。
そっとまぶたを閉じてあげる。
「…君は誰だ」
静子さんを横たえ、胸の前で手を組ませてあげていると、横から声を掛けられた。硬い表情をした同年代くらいの男だ。
恐らく、静子さんの婚約者だろう。僕をジロジロ値踏みするように観察してくる。
「図書館で知り合った知人ですよ…嫌な予感がしたから訪問したんですが、遅かったですね」
「……なんだ、静子は不貞していたのか…なんだ、俺だけじゃなかったのか…」
ハハハッと嘲笑う男。僕は耳を疑う。この男は何を言っているんだと呆然としてしまった。
……この男もか。静子さんの周りにはまともな人間は存在しないのか…! 死して尚、彼女の名誉を傷つけようとするのか…!
僕は目の前の男を殴りつけたい衝動に駆られたが、それは僕の身勝手な行動になる。なんとか抑えた。
「違いますよ、あなた方とは違う。…静子さんを侮辱するな」
本当なら、彼女をこれ以上この人達のそばに置いておきたくないが、他人である僕には彼女を葬る権限はない。……もう静子さんの魂はここにはない。この世を嫌って遠くへと旅立ってしまったのだ……
静子さんの血がついた手のひらをぐっと握りしめると、その場を後にする。
僕には何もできない。
彼女を救うことすらできなかった。
あの時、彼女を引き止めていたら何かが変わったのだろうか。
それとも、何も変えられなかった…?
静子さんはこんな最期を望んでいたのだろうか。
彼女がいない今、その問いに答えてくれる相手はどこにもいない。
×