ライオンと距離を縮める
温室を出て、寮へ戻る道中で必死に誤魔化す方法を考える。
だが、考えても考えても何も思い浮かばないし、そもそも優秀な魔法士で頭のいい彼を誤魔化すことなどどう考えても無理な話だ。
それにしても…キングスカラー先輩は何を考えているのだろう。
魔法薬で匂いを誤魔化しているのに気が付いたわけでもなかったらしい。
だとしたらどういう理由で私に声をかけてきたのだろうか。
何か問題を起こしたわけでもなく、面白い性格をしているわけではない。
部活だって一緒ではないし、授業も一緒になったことはない。
ライオンはネコ科の獣人。私もそうだが、気まぐれなのが多い。
ということはキングスカラー先輩の気まぐれという可能性だって否定できない。
…もう考えていても仕方がない。
サバンナのような環境になっている寮へ戻り、砂を踏みしめながらいつもより重い足取りで自分の部屋へと戻る。
この学園へやってきて初めて明日が来るのが怖くなった。
部屋に戻ると同室のブッチ君に半年ぶりと言ってもいいぐらい、久しぶりに声をかけることになる。
同室なのに会話も何もしなかったのは寮長の側近でもあるし、人懐っこいブッチ君の性格についボロを出してしまうのが怖かったからだ。
部屋に帰るのは寝る前とかシャワーの時だけでほとんどが談話室の端で本と読んだり、勉強をして過ごしていたから、こうして部屋でちゃんと会話をするのは初めてかもしれない。
部屋へ入るといつものように自分のベッドへ腰を降ろす。
いつもだと無言で課題をして、無言でマジカメを見たり…シャワーを浴びるときぐらいしか声をかけていないのに、今回はキングスカラー先輩のことを話さなくては。
ドキドキとしながら恐る恐る声をかけた。
「ブッチ君」
「シャワーなら先どーぞ」
「…いや、シャワーじゃないんだ」
もともと大きい目をしているブッチ君が驚いたように目を見開いて私を見る。
半年間も碌に会話をしていなかったのだからこういう反応は想像していたが、これからは嫌でも関わる事になるのだからしっかり話しておいた方がいいだろう。
ブッチ君はベッドの上で寝転がりながら雑誌を読んでいたが、起き上がって私の方に向かい合いながら私と同じようにベッドに腰を下ろした。
どうやらマジフトの雑誌を読んでいたらしく、邪魔したことをとりあえず謝っておく。
「ごめんね、急に」
「ナマエから声かけて来るなんて珍しいっすね」
「キングスカラー先輩のことについて聞きたいんだけど」
「レオナさん?」
その名前を聞いただけで耳をピンと立てて反応してくる様はさすがと言うべきか。
私が女だということは伏せたまま、温室でキングスカラー先輩に突然朝起こしに来いと指名されたことを伝えればブッチ君はまたもや驚いた。
「レオナさんが指名?これまた何で?」
「うーん…トラの獣人なのに私みたいな貧弱そうなのが珍しいんじゃないか?」
「ふぅーん」
この寮にも私以外のトラの獣人も居るらしいが、同じ学年には居ないし会ったことも顔を見たこともない。
ブッチ君は私の方をじっくりと見てきて、怪訝な顔をした。
無理もない。私もあの寮長が私に目をかけるなんて思いもしなかったのだから。
女という理由が無ければ声もかけられなかっただろうし…ということはもしかして見張るためなのか?
自分の寮に女が居るという問題の種を大きくしないために、敢えて自分の監視下に置く。それならあり得そうだ。
「明日から私が起こしに行くよ」
「あれ?ナマエって部活やってなかったっけ?」
「朝練はないことが多いから」
私はバスケ部に所属している。
理由はサバナクローは運動部に所属しているのが大半だし、私も体を動かすのが好きでバスケは小さい時にやっていた経験があったからだ。
男の中でやるのは大変だが、バスケ部の殆どが獣人ではなく人間。そのため、獣人の男よりはカモフラージュできてこちらも好都合だから助かっている。
「なにやってんだっけ?」
「バスケ部。ブッチ君は?」
「レオナさんと一緒、マジフト。あと、いい加減名前で呼んでくれないっすかー?何か壁作られてるようで気になるんすけど」
今度は私が目を丸くした。
そういえば、名前で呼んだことはない。というか、ここまで話しかけたこともなかったからでもあるが。
私は頷いて「ラギー」と呼び直した。
照れたように笑うラギーにつられて私も吹き出す。
なんだか寮長に女と知られたのに身を置いてもらえる状況が、私の張り詰めた緊張を緩和させてくれたのか、ラギーとこんなに話せる。
それから私たちは遅くまで今まで話せなかった分を取り戻すかのように互いのことや授業のことを話した。
先程までどうしたらいいのかグルグルと悩んでいたのが嘘みたいに気が楽だ。
バレてしまったのは心配だが、ここにきてルームメイトと仲良くなれたのは他でもなく、キングスカラー先輩がきっかけを与えてくれた。そう考えれば感謝すべきなのかもしれない。
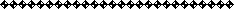
いつもより早い目覚め。
朝が苦手なのはこちらも同じというのに、今日からはラギーと交代で我が寮の寮長を起こしに行くこととなる。
まだぐっすり眠っているラギーを起こさないようにベッドから出て、浴室でしっかりとサラシを巻きなおして制服に着替える。
寝る時だけこのサラシを外してはいるが、パジャマは厚手でゆったりしたものを着ているし、今のところラギーには勘付かれていないと思う。
…尚更、キングスカラー先輩はなぜ気が付いたのか疑問ではあるが、考えたって仕方のないことは昨日で充分分かった。
静かに部屋を後にすると寮長だけが過ごせる一人部屋へ直行する。
この部屋に入るのは初めてだが、ラギーに事前に渡された合鍵で静かに入室した。
部屋の中は当たり前だがキングスカラー先輩の匂いがしてきて、ここが本当に彼の縄張りなのだと実感し、体に緊張が走る。
何しろ、彼自身の威圧感もすごいが、種族柄でも彼には逆らい難い。
狩りをするかのように気配を消して音を立てないようゆっくりと部屋の奥へと入るが…まあ、驚くぐらい散らかっている。
「…ラギーが言ってたのはこれか…」
レオナさんの部屋に入ったら起こす前に先に部屋の片づけ。
恐らく制服とかも脱ぎ散らかしてると思う。
全くその通りだった。
溜息を一つ零して脱ぎ散らかしてある服を腕にかけて仕分ける作業から始める。
新しいシャツの場所も事前に聞いておいてよかった。
王族というのもあるからなのか収納家具が多くて探すのに一苦労しそうだ。
新しいシャツと、制服の準備を終えると今度は最終目的であった起こすことに取り掛かることにした。
寝起きの機嫌も悪いし、起こすのにだいぶ苦労すると言っていたため部屋に入った時と同様に緊張する。
ベッドに身を乗り上げて恐る恐る手を伸ばして、眠れる獅子を起こし始めた。
「キングスカラー先輩。朝ですよ」
「…」
耳がピクッと動いて、綺麗眉間に皺が寄った。
尻尾も少し動いたし、意識は多少浮上しているだろう。
「キングスカラー先輩、起きてください」
「…グルル…」
「唸ってもダメです、起きてください」
威嚇するように先輩の喉が鳴りはじめて思わず私の尻尾の毛が逆立ってしまった。
この人の唸り声は心臓に悪い。
だが、怯んでいても時間は無情にも過ぎてしまうのだから私の心にも焦りが出てしまう。
次からはもっと早く来なくてはいけないと学んだ。
私は焦るようにキングスカラー先輩の胸に片手を乗せて体を揺さぶり始めた。
「起きてくださいって。朝練に間に合わなくなりますよ」
「うっせぇ…まだ寝かせろ」
「寝かせま…うわっ」
胸に置かれた手を掴まれたと思ったら勢いよく引っ張られて簡単に腕の中に閉じ込められた。
色んな意味で心臓が煩いくらいに鼓動を速めて、慌てて体を離そうと先輩の胸に両手を置く。
びくともしないのに加えて、キングスカラー先輩の尻尾が私の尻尾に絡み付いてきて、ゾクゾクと腰がくすぐったい様に感じにさせられる。
「や、やめてくださいっ!尻尾!」
「喚くな」
「喚きますよ!」
自分の尻尾に絡み付いてくるライオンの尻尾を振りほどこうとしているのに、尻尾ですら力の差で振りほどくことができない。
というか、先ほどから普通に会話をしていることから絶対に起きているというのにやめてくれない。
絶対にからかわれているのだとしたら、面白い反応はしないようにしようと抵抗をやめて体を固めた。
「…おい、チビトラ」
「私は石です」
「石…なら、しっかり石になってろよ」
「えっ」
私の腰と後頭部にあった手が徐々に下へ下がってきた。
背筋をなぞる様にゆっくりと下がり、お尻まで来たところで今度はこちらの喉が威嚇するように唸り、身を固める。
そこでやっと閉じられていたキングスカラー先輩の鮮やかな緑色の瞳が見えた。
「雌のくせに威嚇は立派に出来んじゃねェか」
「前も聞きました。それとそれ、他の人の前で絶対に言わないでください」
「言わねぇよ。こんな面白いオモチャは手放したくねぇからな」
「おもちゃ…」
やはり想像通りだ。
私をからかって遊んでいる。先輩からしたら暇な学園生活に都合よくやってきたオモチャに過ぎない。
「朝練ちゃんと行かないとダメですよ。参加率悪いってラギーから聞きました」
「…お前は部活入らねぇのか」
「すでにバスケ部に入ってます」
密着したまま答えるが、さすがに同じ年頃の男性とこんな密着することもなく生きてきたのでどうしていいか分からない。そんなことを考え出したら再び体に緊張が走り、尻尾がピンと立ってしまう。その尻尾に先輩の尻尾が離さないと言わんばかりに絡まっている。
「せ、先輩」
「あ?」
「尻尾、やめてください」
顔を上げて睨むように言ったのだが、当たり前かもしれないが全く怯まない。
それどころか口角を上げて私の耳をパクッと咥えはじめた。
「なっ!やめてくださいって!!」
今度こそ渾身の力を入れて両手を突っぱねると私の体は離れてそのままベッドから落ちた。
起き上がってベッドの上の先輩を見れば、肘を立てて自分の手の上に頭を乗せながらニヤニヤとこちらを見ている。
「っ!からかわないでください!朝練行きますよ!」
「あー、怠い」
「二度寝しないでください!」
声を荒げればやっと大きな欠伸の後に体を起こしてくれた。
「明日から毎日来いよ」
「毎日?!ラギーと交代ですよ!」
「なら行かねぇ」
「駄々っ子ですか!!」
毎朝起こすことを条件になんとか着替えてもらって朝練へ向かわせることに成功したが、これは予想以上に大変だと、今後の行く末が不安にしかならなかった。
この話しの感想あれば