それ以上、近づかないで
私の日課ともいえるほど、キングスカラー先輩の世話係は続いた。
朝だけでなく日中サボる先輩をラギーと手分けして探して、寝ている先輩を起こしていく。
ただそれだけの仕事であったが先輩は約束通り、女だということは目をつぶってくれているらしい
学園長から呼び出されることもないし、学園の中で噂されたり問題になったりもしていない。
そして私は朝起きたら先輩を起こしに行くというのが日常になっているが、そのたびに困っているのが先輩のスキンシップの多さだ。
「わわっ!また!先輩やめてくださいっ!」
声をかけても起きない先輩に近づいた瞬間に羽交い締めにされて、そのまま耳を舐められる。
こんな毛繕いなど、幼少期に母にされたっきりであったというのに。
猫科特有のざらついた舌が、私の耳の毛を整え、さらに困るのが先輩の尻尾。
ライオンの長い尻尾が私のトラ特有ともいえる黄色と黒の尻尾に絡み付くように動き出す。
女とわかっているのにこの仕打ちだ。男性との距離感が分からなくて私には戸惑いしか生まれない
「も、いい、ですって!」
「俺がグルーミングしてやってるってのに、テメェは礼も言えねぇのか」
「え、あ、すいません。ありがとうございます…いやいやいやいや、頼んでませんし!それより早く朝練いってください!」
「はぁ…だりぃ…」
マジフト部は結構厳しいと聞いていたが、トップがこんな怠そうにしていていいのだろうか。
いや、トップで実力もあるからこそ、このスタンスなのかもしれない。
こんな怠そうにしていても魔法と頭はピカイチだ
ただ本人に全くやる気がないだけで。
結局、しっかりと私の耳をグルーミングした後にキングスカラー先輩は朝練へと向かった。
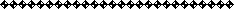
「最近、疲れてるな」
「あ、ジャミル。やっぱりそう思う?」
「それとため息が多い」
体育館にボールが弾む音を響かせ、生徒たちの掛け声が絶え間無く聞こえて来る。
今は本日の授業も全て終わって、放課後の部活中だ。
サバナクローでは運動部に入るのがほとんどで、一年生は全員何かしらの部活に入っている。
マジフト部に所属するのが大半であるが、獣人男子に混じって運動できるほどの身体能力はない。
幸いバスケは経験があるし、バスケットボール部は人間の多い部活であるため、雌であるとはいえ身体能力の高い獣人ということで上手いこと紛れることが出来たと思う。
練習試合の合間の休憩中に話し掛けてきたのは、他寮の同級生であるスカラビアのジャミル。
部活とは違う意味での私の深いため息にいち早く気がついたらしい。
額から流れる汗をタオルで拭い取りながらジャミルは私の横に座り込んだ。
「また授業でわかんないとこでもあったのか?」
「いや、そうじゃないんだ。それだったらとっくにジャミルに相談してるよ」
「なら何なんだ。動きが鈍くなってるし、さっきだって珍しくパスミスしてただろ」
「ご、ごめん」
先ほどの練習試合での失敗を指摘されて、慌てて謝る。
確かに冷静になって考えてみれば、普段はあんな無茶なパスは出さない。
獣人の特徴でもある耳が反省を伝えるように下がると、ジャミルはため息をついていつものように悩みを聞く姿勢になった。
いつもだったらここで悩みを全て打ち明けているところだが、この悩みはいうに言えない。
説明するには自分が雌であることを言わなければならないし、何だか恥ずかしい内容でもある。
異性からグルーミングされるのは何故なんだろう、だなんて聞けるわけない。
「あー…いや…うーん…」
「…まあいい。お前が言えるようになるまで待ってやる」
「さっすがジャミル」
「だが、部活は集中しろ」
「うっ、気をつけます」
いつの日か、ジャミルには雌であることを打ち明けたらこの関係は崩れてしまうのだろうか。
それとも「それが何だ」と笑って友達で居てくれるのだろうか。
そんな不安もあって打ち明ける日は来ない気もする。
どちらにしろ本当にそろそろ集中しなくては、今度はフロイドに絡まれるかもしれない。
私のことをクマノミちゃんと呼び、気まぐれに絡んで来る彼は少し苦手だ。
何を考えているのか読めない上に、あの気まぐれに絡まれるのは勘弁してほしい。
「もう大丈夫。ジャミルありがとう」
気合いを入れるために自分の頬を軽き叩いて立ち上がった。
こうなったら本人に問いただすことにしよう。
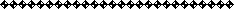
部活が終わり、汗をかいた体をさっぱりするために寮の部屋にあるシャワールームを目指す。
放課後の後のこの時間はマジフト部がその日の練習について話し合いをしている。
トップがあんなにやる気がないというのに部活動自体はものすごく真面目で、かなりキツイと同級生がぼやいていたのを耳にしたことがあるが、そんな同級生も揃いも揃ってキングスカラー先輩に憧れているのだからあの人の実力はすごいのだろう。
私自身はマジフトをしているところを見たことはないが。
談話室に入れば案の定、話し合いの真っ最中だ。
3年の先輩が中心で話し合っているようだが、キングスカラー先輩の姿が見えない。
思わずその場でキョロキョロと探したら、突然私の首元に逞しい腕が回された。
「よぉ、ちびトラ」
「何度も言ってますが、ちびトラという名前になった覚えはありません」
「体育着を着てどこ行ってたんだ?」
全く話しを聞いてくれない先輩にため息が零れる
全員が話し合いに集中しているからかこちらを見向きもしないが、こんな密着しているところはあまり見られたくはない。
首元にある腕を退かそうと掴んだが、驚くほどびくともしない。
「部活です。部活の後で汗くさいと思うので離れてください」
「部活?」
「バスケットボール部です。言いませんでしたっけ?」
私の部活について特に興味もないだろうと思っていたが、そんな反応をされるとは思わなかった。
キングスカラー先輩は私の首元に腕を巻き付けたまま、ズルズルと引き摺りみんなから離れていく
少し離れた物陰に隠れる様にして先輩が座り込むと、必然的に私も一緒に座り込む。
「何するんですか!」
「声デけぇよ。他の奴らに聞かれてもいいならおれは構わねぇけどな」
「うぐ…」
すぐに自分の口に手を置いて後ろを振り向いて、先輩を睨みつけた。
「何なんですか」
「そう威嚇すんなよ。何でマジフトに入らなかったんだ」
「何かと思えば部活ですか…」
先輩が何を考えているのかは分からないが、性別が知られているのだから隠すようなことではない
私は素直に理由を話すことにした。
「獣人と人間では身体能力が違うじゃないですか。マジフト部は獣人が多いので、同じ獣人とはいえ一緒に運動は難しいと思いまして」
「…成程な。確かに球遊びの部活にはうちの寮は少ないし、球遊びなら俊敏さで誤魔化しがきく。よく考えたじゃねぇか」
「ありがとうございます」
球遊びのところは否定したかったが、どんなに否定しようともこの人にとっては球遊びには変わりないだろう。
話しは終わりかと思い、いまだに私の首元に回っている腕を退かそうと両手で掴んだがビクともしない。
しばらく静かな攻防を繰り返したが、あまりに強すぎる力に息を切らせながら諦める。
後ろを振り返って先輩の顔を見てみれば、私の必死な姿を見て愉しんでいるかのようにニヤニヤと笑みを浮かべていた。
「もう終わりか?」
「もう、なんなんですか…」
グルルっと喉を鳴らして威嚇をすると、今度は私の方に向かってスンスンと鼻をくっつけてきた。
あまりの顔を近さに顔が熱くなって距離を取ろうと先輩の腕を再び引きはがそうと掴んだ。
「ちか、ちかい…」
「お前、スカラビア寮の匂いが微かにする」
「それは部活で仲がいい同級生が居ますから」
ジャミルの寮でもあるスカラビアは結構独特な匂いがする。
香辛料も多く取り扱っているらしいし、その匂いなのかもしれないが。
どちらにしろほのかな匂いなだけで、獣人がここまで至近距離にいてちゃんと嗅ごうとしなければ分からない匂いだ。
つまり、先輩は意図的に私の匂いを嗅いだという事。
「それがどうかしました?」
「気に食わねぇな」
「え?わわ、ちょ、いきなり、やめてくださいよっ」
キングスカラー先輩は私の耳を甘噛みした後、ペロペロとグルーミングをし始めた。
この行為は朝、先輩が寝ぼけてしてくるのだが今は朝でも寝ぼけているわけでもない。
まあ、朝してくるときも寝ぼけているにしてははっきりと受け答えをしているが、理由が見つからないので私の中では寝ぼけているということにしている。
ザリザリとざらつく舌で耳を何度も舐めて、しかも首元に巻かれている腕に力が入り、更に体が密着すると頭を擦り付ける様にスリスリとすり寄られた。
これでは自分の縄張りや自分のものに匂いをつけているマーキングそのものだ。
「先輩!マーキングやめてくださいって!」
「他所の寮の匂いを纏わせやがって」
「寮長だからって寮のものが全部先輩のものってわけじゃないんですよ!」
「…」
動きが止まり、静かになった先輩。
恐る恐る後ろを振り返ると、何やら私を見つめて考え出しているようだ。
首元の腕の力も抜けて、私はすぐに先輩から距離を取った。
もうすでに私の体からはキングスカラーの先輩がついている。
それが恥ずかしくて、すぐにでも部屋に戻るために考え込んでいる先輩に一度だけ頭を下げて逃げる様にして立ち去った。
部屋へ走って向い、部屋に入った瞬間にズルズルとその場に座り込む。
マーキング。
そうだ、朝のあの抱きついてくるのも、グルーミングをしてくるのもマーキングするための行動だ
ラギーや他の寮生にもしているのだろうか。
だとしたら、とんでもない寮長だ。
ただ…自分に纏った先輩の匂いが…何故だか全然嫌じゃなくて。
それどころか安心するのが分かって。
ふわりと先輩の匂いが再び私の鼻を掠めた時、先輩の近くなった顔を思い出し、一気に顔が熱くなって心臓が痛いくらい鼓動を速めた。
そんなもの自覚したくもないし、男として過ごすには必要のない感情なのに。
「私…先輩が好きなのか…」
これ以上先輩と居ると、私は女になってしまう。
それは絶対に避けなければ。
すぐに立ち上がって浴室へ駆け込み、体育着のまま冷水を浴びる。
私を包み込む様な錯覚を起こさせるこの匂いをかき消して、私は自分の想いもかき消した。
この話しの感想あれば