詩栄は空気が読めない。それを知ったのは中学2年の冬、全日本マーチングコンテスト直前の大事なチューニング中に「久しぶり〜」なんて声をかけてきたりとか、合同演奏会の練習の為に帝光に来た詩栄が練習で使うはずも無いクラスに入ってきて、私が告白されてる現場に遭遇してしまったりだとか。…まあ、何故私が突拍子もなくこんなことを言い出したかというと、誌栄が一緒に帰ろうとか待ち合わせしたこの場所…というか壁の向こう側で、女の子が例の赤司君に告白しているというとんでもないシーンに遭遇してしまったからだ。誌栄のバカ。
「全中の試合で赤司君のこと知って、好きになって…それで、ここまで追いかけてきたんです…!」
うっそマジか。女の子怖い。立ち聞きは趣味悪いとは思う。でも立ち退くタイミングがさっぱり分からないし、そもそも私が悪いわけではないから許して下さい!…と、叫んだ。心の中で。
「ありがとう」
「えっ……じゃ、じゃあ…!」
「すまないね。僕は僕が認めた女性としか付き合うつもりはないんだ。例えばそうだね…そういう人がいても、それは君じゃない」
「っ…そんな、分からないじゃ、ないですか…!だったら、友達から…!」
「物分かりの悪い女性は好きになれないんだ」
「……っ、う」
うわあ…。どこにも転がれない返答だなと、女の子が可哀想になった。まあでも、赤司君の気持ちはわかる気がする。好きになれそうにもない人に手を差し伸ばしてあげるようなことはしたくない。まあ、これは私が中学時代に一度だけ告白されるという体験をしたからこそ分かったことだ。ぱたぱたと、逆方向に走って行く音が聞こえてきたので、よかった全てが終わったと胸を撫で下ろす。このタイミングで誌栄が声をかけてこようものなら私は確実に死んでいただろう。色んな意味で。それよりも、まだ入学して1週間ですよ。高校生になるって怖い。
「入ってきても構わないよ」
「ヒ!!?」
ポン、と肩に重みがかかる。とても嫌な重みだ。後ろを振り向けないでいると、向こう側から誌栄が歩いてきているのが見えた。ほんと空気読めない子!でも助かった!
「覗くつもりはなかったんですごめん!」
「おっと」
それと同時に、勢いでその場から駆け出して赤司君を振り切った。ってかもう、高校生活始まったばっかなのに内容が濃い!濃いよ!!
「ごっめーんミイ、お待たせ…ってええ?なんでそんな顔青くしてんの?生理?」
「黙りなさいKY!!」
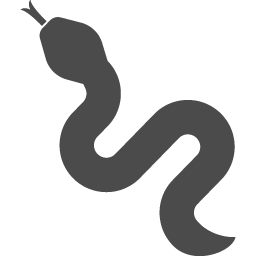
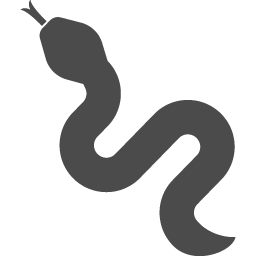
「赤司君が告白されてる現場に遭遇かあ。つくづく運が悪いなあミイは」
「誰のせい!?誰の!!」
コンビニ前でフランクフルトを頬張りながら、詩栄は事の顛末を聞いてケラケラと笑っている。こっちの身にもなってほしい。人の告白現場にいて通常心拍数でいられないっての、このオバカめ。
「まあでもさすが赤司君って感じだよねー。入学してたった1週間しか経ってないのに告白されるとか凄すぎ」
「さすが赤司君って何…そんな有名?イケメンだからという理由で?」
「はあ…中高バスケ部の友達がいたら1回は名前が出ると思うよ。帝光中の"キセキの世代"、赤司征十郎。しかも"キセキの世代"のキャプテンやってたんだから。加えて新入生代表だったってことは成績優秀ってことだし、あの顔面でしょ?モテないわけないし。なのに同中のアンタときたら…ミイってほんと音楽バカよねー知ってたけど」
‥え?何?キセキの世代?キセキって、奇跡?
「は…何々…?すごいネーミングセンス…」
「実は私友達の試合応援しに行った事あるんだけど、すごかったよー。158対23で帝光中の圧勝。遠い所から何故かシュートばんばん入るし、ぶん投げたらシュートばんばん入るし、ていうかボールが曲がったりするしなんかもう色々意味分かんなかったけど」
「へー。そうなんだ。……あ!そういえば明日から入部申し込みできるけど行く?」
「…人の話聞いてた?」
「え?うん、聞いてたけど…なんかピンと来なくて…明日から練習参加できるって思い出したらつい…」
「あーー……もういいわ、あんたに音楽の話以外するもんか…」
詩栄は呆れたように深ーく溜息を吐いて、私の持っていたガリガリ感白桃味にかぶりついた。
「あ、ちょっ…酷い誌栄!」
「どっちが酷いんだっての!折角悪いと思ってアイス奢ったのに!!」
2016.07.02
「全中の試合で赤司君のこと知って、好きになって…それで、ここまで追いかけてきたんです…!」
うっそマジか。女の子怖い。立ち聞きは趣味悪いとは思う。でも立ち退くタイミングがさっぱり分からないし、そもそも私が悪いわけではないから許して下さい!…と、叫んだ。心の中で。
「ありがとう」
「えっ……じゃ、じゃあ…!」
「すまないね。僕は僕が認めた女性としか付き合うつもりはないんだ。例えばそうだね…そういう人がいても、それは君じゃない」
「っ…そんな、分からないじゃ、ないですか…!だったら、友達から…!」
「物分かりの悪い女性は好きになれないんだ」
「……っ、う」
うわあ…。どこにも転がれない返答だなと、女の子が可哀想になった。まあでも、赤司君の気持ちはわかる気がする。好きになれそうにもない人に手を差し伸ばしてあげるようなことはしたくない。まあ、これは私が中学時代に一度だけ告白されるという体験をしたからこそ分かったことだ。ぱたぱたと、逆方向に走って行く音が聞こえてきたので、よかった全てが終わったと胸を撫で下ろす。このタイミングで誌栄が声をかけてこようものなら私は確実に死んでいただろう。色んな意味で。それよりも、まだ入学して1週間ですよ。高校生になるって怖い。
「入ってきても構わないよ」
「ヒ!!?」
ポン、と肩に重みがかかる。とても嫌な重みだ。後ろを振り向けないでいると、向こう側から誌栄が歩いてきているのが見えた。ほんと空気読めない子!でも助かった!
「覗くつもりはなかったんですごめん!」
「おっと」
それと同時に、勢いでその場から駆け出して赤司君を振り切った。ってかもう、高校生活始まったばっかなのに内容が濃い!濃いよ!!
「ごっめーんミイ、お待たせ…ってええ?なんでそんな顔青くしてんの?生理?」
「黙りなさいKY!!」
「赤司君が告白されてる現場に遭遇かあ。つくづく運が悪いなあミイは」
「誰のせい!?誰の!!」
コンビニ前でフランクフルトを頬張りながら、詩栄は事の顛末を聞いてケラケラと笑っている。こっちの身にもなってほしい。人の告白現場にいて通常心拍数でいられないっての、このオバカめ。
「まあでもさすが赤司君って感じだよねー。入学してたった1週間しか経ってないのに告白されるとか凄すぎ」
「さすが赤司君って何…そんな有名?イケメンだからという理由で?」
「はあ…中高バスケ部の友達がいたら1回は名前が出ると思うよ。帝光中の"キセキの世代"、赤司征十郎。しかも"キセキの世代"のキャプテンやってたんだから。加えて新入生代表だったってことは成績優秀ってことだし、あの顔面でしょ?モテないわけないし。なのに同中のアンタときたら…ミイってほんと音楽バカよねー知ってたけど」
‥え?何?キセキの世代?キセキって、奇跡?
「は…何々…?すごいネーミングセンス…」
「実は私友達の試合応援しに行った事あるんだけど、すごかったよー。158対23で帝光中の圧勝。遠い所から何故かシュートばんばん入るし、ぶん投げたらシュートばんばん入るし、ていうかボールが曲がったりするしなんかもう色々意味分かんなかったけど」
「へー。そうなんだ。……あ!そういえば明日から入部申し込みできるけど行く?」
「…人の話聞いてた?」
「え?うん、聞いてたけど…なんかピンと来なくて…明日から練習参加できるって思い出したらつい…」
「あーー……もういいわ、あんたに音楽の話以外するもんか…」
詩栄は呆れたように深ーく溜息を吐いて、私の持っていたガリガリ感白桃味にかぶりついた。
「あ、ちょっ…酷い誌栄!」
「どっちが酷いんだっての!折角悪いと思ってアイス奢ったのに!!」
2016.07.02