「あ、赤司君は私のこと知ってたんですね‥」
「もちろんだよ。ああ、気にしなくても大丈夫。君がクラスにあまり興味のないことは知っていたからね。僕のことも知らなくて至極当たり前だと思うよ」
「いや興味ないっていうか‥」
「あれ?でもおかしくない?ミイって地区から全国まで大会には出てたでしょ?地区なんか夏前くらいに開催してたじゃん」
なんでなんで?と興味津々に追求する詩栄に軽く溜息を吐いた。要約すると、説明が面倒くさい。
「そうねーー‥逆に後々面倒そうだから詩栄には話しとこっかなあ」
「どういう意味よ」
「まあまあ」
中学校1年の時に、ドラム・コープス・インターナショナル‥通称DCIというアメリカで行われる最大規模のマーチングイベントに参加する為、とある憧れの団体のスネアドラムオーディションを受けたことがきっかけである。当時の状況は、まさか日本人の中学に入学したばかりの女の子が逸早く合格し、ここまで上り詰めてくるとは‥という雰囲気が漂っていた。が、言わずもがな実力である。夜の睡眠より3度の飯より大好きなマーチングスネアドラムを始めてしまったら、ここまでくるのは最早自分の中では必然だった。合格と同時に分かったことだが、本番は冬、練習はもちろんアメリカで行われる。ただし日本の中学というものは義務教育であり、私はもちろん帝光中のマーチング部に入る為に入学したのだ。2つの内どちらかを選ぶなんて、私の頭の中では想像できなかった。
「じゃあテスト前と大会前の二週間だけこっち帰ってくるっていうのはダメですか?」
まさに、何も知らない子供だけが口にできる言葉だったと思う。もちろん担任の先生は口をぽかんと開けていたし先輩は唖然としてたし、それがまかり通るなんて誰もが思っていなかっただろう。しかしそれを快諾してしまうのが帝光の理事長だったりするのだ。
"勝つことが全て"
とどのつまり、私がいれば帝光中学校のマーチング部は安心だということだったらしい。そして理事長の思惑通りというか、私が在籍していた3年間のマーチング部の成績は、全国金賞、並びに明るみに触れない団体評価の細かい点数にまで満点が続く。同じくしてマーチングパーカッション部門に関しても同じくだった。もちろん私だけの力だけではない。私のいた3年間は、最強の駒が揃いすぎていたのである。
「そんなこと許されるの‥帝光中学校恐るべし‥アンタも物凄いこと口にしたもんだよ‥っていうか頭の方は大丈夫だったの?テストとか」
「向こうで日本人の家庭教師いたしね。予習復習バッチリだったよ」
「信じらんない住む世界違いすぎて寒気する」
「ま、そんなわけで私はあんまり学校は行ってなかったってわけ。だから別に興味なかったわけじゃなくて、単にドラムが大好きなだけで周りが見えてなかっただけなんですよ赤司君」
「そうか」
そう小さく呟いた赤司君の目は、半分笑っていて、半分笑っていなかった。
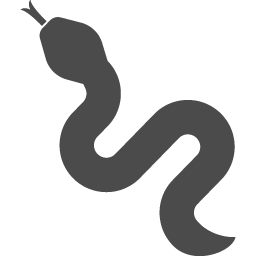
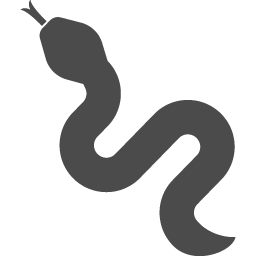
京都の洛山高校に入学し、当然かの如く新入生代表挨拶に抜擢された僕の視界に入ったのは、大勢の新入生から見えた1人の少女だった。
「(‥‥‥彼女は確か‥)」
ここ洛山に入ってくる者の中の約半数が、何かに特化してレベルが高いと言う噂がある。それを考えれば、彼女が何故東京の帝光から京都の洛山を受験したのかは直ぐに見当がついた。そもそも受験すらしていない、手厚い待遇の特待生だったのかもしれない。それは僕も一緒だ。
類稀なる才能に恵まれ、磨きあげた結果の光。ただ僕と違ったのは、彼女は良い意味でも悪い意味でも自由だった。それを証拠に、この入学式の最中での欠伸が目立つ。
「(恥がないのか、女性として)」
呆れを通り越して、逆に尊敬すらしてしまう。そんな僕の視線に気付いたのか、一瞬だけ彼女の目は僕に向けられた。
「‥‥新入生代表、赤司征十郎」
最後に自分の名前で締め終わると、沸き起こる拍手に背を向ける。端の方では男性教員がじろりと彼女を薄く睨みつけていた。
「‥」
最後に彼女と目を合わせた時より、瞳の色はより濃くなっていた。それは、確かな自信と誇りがあるからだろう。
「‥‥自由、か」
小さく呟いた僕の声は、何故か心の奥底で重く響いていた。
2016.06.11
「もちろんだよ。ああ、気にしなくても大丈夫。君がクラスにあまり興味のないことは知っていたからね。僕のことも知らなくて至極当たり前だと思うよ」
「いや興味ないっていうか‥」
「あれ?でもおかしくない?ミイって地区から全国まで大会には出てたでしょ?地区なんか夏前くらいに開催してたじゃん」
なんでなんで?と興味津々に追求する詩栄に軽く溜息を吐いた。要約すると、説明が面倒くさい。
「そうねーー‥逆に後々面倒そうだから詩栄には話しとこっかなあ」
「どういう意味よ」
「まあまあ」
中学校1年の時に、ドラム・コープス・インターナショナル‥通称DCIというアメリカで行われる最大規模のマーチングイベントに参加する為、とある憧れの団体のスネアドラムオーディションを受けたことがきっかけである。当時の状況は、まさか日本人の中学に入学したばかりの女の子が逸早く合格し、ここまで上り詰めてくるとは‥という雰囲気が漂っていた。が、言わずもがな実力である。夜の睡眠より3度の飯より大好きなマーチングスネアドラムを始めてしまったら、ここまでくるのは最早自分の中では必然だった。合格と同時に分かったことだが、本番は冬、練習はもちろんアメリカで行われる。ただし日本の中学というものは義務教育であり、私はもちろん帝光中のマーチング部に入る為に入学したのだ。2つの内どちらかを選ぶなんて、私の頭の中では想像できなかった。
「じゃあテスト前と大会前の二週間だけこっち帰ってくるっていうのはダメですか?」
まさに、何も知らない子供だけが口にできる言葉だったと思う。もちろん担任の先生は口をぽかんと開けていたし先輩は唖然としてたし、それがまかり通るなんて誰もが思っていなかっただろう。しかしそれを快諾してしまうのが帝光の理事長だったりするのだ。
"勝つことが全て"
とどのつまり、私がいれば帝光中学校のマーチング部は安心だということだったらしい。そして理事長の思惑通りというか、私が在籍していた3年間のマーチング部の成績は、全国金賞、並びに明るみに触れない団体評価の細かい点数にまで満点が続く。同じくしてマーチングパーカッション部門に関しても同じくだった。もちろん私だけの力だけではない。私のいた3年間は、最強の駒が揃いすぎていたのである。
「そんなこと許されるの‥帝光中学校恐るべし‥アンタも物凄いこと口にしたもんだよ‥っていうか頭の方は大丈夫だったの?テストとか」
「向こうで日本人の家庭教師いたしね。予習復習バッチリだったよ」
「信じらんない住む世界違いすぎて寒気する」
「ま、そんなわけで私はあんまり学校は行ってなかったってわけ。だから別に興味なかったわけじゃなくて、単にドラムが大好きなだけで周りが見えてなかっただけなんですよ赤司君」
「そうか」
そう小さく呟いた赤司君の目は、半分笑っていて、半分笑っていなかった。
京都の洛山高校に入学し、当然かの如く新入生代表挨拶に抜擢された僕の視界に入ったのは、大勢の新入生から見えた1人の少女だった。
「(‥‥‥彼女は確か‥)」
ここ洛山に入ってくる者の中の約半数が、何かに特化してレベルが高いと言う噂がある。それを考えれば、彼女が何故東京の帝光から京都の洛山を受験したのかは直ぐに見当がついた。そもそも受験すらしていない、手厚い待遇の特待生だったのかもしれない。それは僕も一緒だ。
類稀なる才能に恵まれ、磨きあげた結果の光。ただ僕と違ったのは、彼女は良い意味でも悪い意味でも自由だった。それを証拠に、この入学式の最中での欠伸が目立つ。
「(恥がないのか、女性として)」
呆れを通り越して、逆に尊敬すらしてしまう。そんな僕の視線に気付いたのか、一瞬だけ彼女の目は僕に向けられた。
「‥‥新入生代表、赤司征十郎」
最後に自分の名前で締め終わると、沸き起こる拍手に背を向ける。端の方では男性教員がじろりと彼女を薄く睨みつけていた。
「‥」
最後に彼女と目を合わせた時より、瞳の色はより濃くなっていた。それは、確かな自信と誇りがあるからだろう。
「‥‥自由、か」
小さく呟いた僕の声は、何故か心の奥底で重く響いていた。
2016.06.11