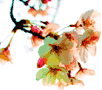
「小太郎・・・何方だったのですか?」
己を甲斐甲斐しく世話してくれる忍び―――風魔小太郎。
その小太郎と戦っている忍びに気付いたさくらは、寝ぼけ眼だったためか、それが佐助だとは分からなかった。
「・・・・」
小太郎は跪いた体勢から立ち上がり、さくらの手をとってその手のひらに文字を書いた。
盲目の彼女に対する、小太郎なりの優しさと意思表示。
“武田の忍び”
「武田・・・?どうしてそのような方が私に・・・」
自分の知り合いといえば、幸村と佐助、小太郎と自分を引き取ってくれた見たこともない親戚だけ。
ここが甲斐で武田信玄の治める地だとは知っていたが、移り住んでからというもの屋敷の外へ出たことは一度もない。
外れにあるだけ会って近所に家はないのだから、当然お隣さんが訪ねてくるなんてないに等しい。
「出て行け、ということなのでしょうか・・・」
つきん、と胸の奥が痛んで、着物が崩れるのも構わず、胸元を握りしめた。
住み始めたころの私はまだ幼くて、何故ここにつれてこられたのかさっぱり分からなかった。そもそも土地の基礎知識もなく、誰がどこを治めている、という難しい話を右から左へと流すような齢のころ。一人では何もできない、幼子の時代。
身の回りの世話をしてくれていた女性は夜になる前に帰ってしまい、無駄に広いこの屋敷に一人残された。
寂しくて、辛くて、悲しくて、苦しくて、最初は泣いてばかりいた。
静かな屋敷で過ごす夜が怖くて、このまま死んでしまおうかとも考えた。
それでも、そうしなかったのは、
「ああ、この花達ともお別れしなきゃならないんですね」
小太郎が教えてくれた、庭に咲く花々。
昔―――まだ目が見えていたとき、両親が生きていたとき、今もかすかに記憶に残っている花。
桜の木。
両親と、その木の下で食べた団子の味。
「幸村さん、」
彼とも、ここで会った。
桜の木の下で。
“幸村?”
「あ、そうですね、小太郎は知りませんか・・・私の、大切な人です」
小太郎がいない間、桜が心配になって幹に触れていると、どこから入ったのか幸村と名乗る青年がいきなり腕を掴んできたのだ。
驚いて悲鳴をあげてしまったが、彼のあまりの慌てっぷりについ怯えたのも忘れて笑ってしまった。
彼がここに来て、話すようになったのはその日から。
昨日のことのように鮮明に覚えている。
「彼との出会いは、奇妙なものでした」
「・・・」
「話したことは全て覚えています。ふふ、“桜の精でござるか?”って、一番に言われたんですよ。よりによって何でその言葉だったのか、私には分かりませんが」
「(・・・コク)」
「桜の精・・・そうであれば、どれだけ良かったでしょうか」
その目に映るのは今目の前にいる己ではなく、真田幸村。
小太郎は、切なげに歪められた端正な美貌を持つ、桜の精といっても過言ではないほどに美しい主を見る。儚くて、今にも消えてしまいそうな薄い笑みを浮かべていた。
可哀そうな少女。盲目なばかりに箱庭に閉じ込められ、自由を奪われた鳥籠の雛。外界から隔たれたこの場所は、戦国のこの時代、安息の地であったが彼女にはそれが分からない。己がいるから大丈夫、という本来の主の命の元、「箱庭で生活できる必要最低限の教養と教育」しかしていないのだから、知らないのだ。必要がない。つまり彼女が外に出ることは、今後もないということだった。
小太郎は、未だ握られている手に力を込め、寂しげに花の散った桜の木を見上げるさくらを引き寄せた。
「小太郎?」
身長差からか、胸元から聞こえてくる声はどこか遠い。
それでも、この腕の中には彼女がいる。
体が言うことをきかなかった―――否。
本能のままに、動いてしまったのかもしれない。
大切な人、と思い出を語る少女があまりにも苦しそうで、綺麗に笑っているはずなのに、それがどこか虚勢をはった偽りのように見えて。
さくらが抵抗しないのをいいことに、小太郎は抱きしめる力を強めた。
(なんて温かい。優しい。この子はこんなにも一生懸命なのに、どうして)
彼女は、確かに生きている。
「私・・・ずっと、ここにいられたらいいのにって、思ってた。でも、今は」
ぽつ、と呟かれたのは、きっと本心。
住み慣れた地を離れるのは嫌なのだろう。
それよりも小太郎の心を占めているのは、守り抜いてきた己にさえ弱音をはいてくれないという悔しさ。
(歯痒い)
彼女に伝えられたら、どれだけ救われるだろう。
盲目だから?
両親が死んだから?
女子だから?
弱いから?
戦えないから?
世界を知らないから?
そんなもの、関係あるか。
家の恥になるのなら、わざわざ外に出して目の届かない場所に置くものか(さっさと嫁に出すなりして追い出し、利用すればいいことだ。目が見えないことなんていくらでも取り繕える。赤子を孕むことさえできれば、なんの問題もない)
遠ければ遠いほど、人目につく可能性が高いのだから。
結果、武田に仕える真田幸村や猿飛佐助という厄介な者に遭遇してしまった。不幸中の幸いと言えるのは、彼女が“武田信玄”の名前しか知らなかったということだ。
それに、監視や状況報告の為だけに、要となる風魔小太郎を使っているのだ。
(主は・・・)
庭に美しい花や木々を植えたのは、外へ出られない彼女の退屈を紛らわすよう。
隙間なく塀を建てることで、野犬や流れ武士が入ってこないよう。
枯山水も、外部の者にただの石捨て場のように見せるためのもの。
第一、忌み子に世話係などつけるはずがない。
「ここから出たい。でも、その術が分かりません」
会いたい、とは決して言わない彼女。
そういうと、小太郎の腕からするりと逃れ、裸足のまま庭へ降りた。
砂はあるが、足を傷付けるような石は一つもない地面を、桜の木に向かってゆっくりと歩き出す。盲目ゆえに、他の四感が研かれ、気配が分かるようになったという。信じられない話であるが、ものの形も、少しは分かるとか。
「・・・・・」
「幸村さんも、佐助さんも、小太郎も・・・おじいさまも」
額を幹につけて、木の鼓動を聞くかのように、自分に問いかけるかのように。
ずきり、胸が痛んだ。
「みんな、私から離れていってしまう」
父も母も。
悲しくて悲しくて
でも、この桜が見守ってくれているようで、何度も勇気づけられた。
冬が終わって、満開になった花の香りが運んできてくれた声。
忘れかけていたものを、思い出させてくれた。
「私も、そろそろ、お別れなのかしら」
小太郎とさくらが初めて会ったのは、冬のある日だった。
主の命で火事が起きたという屋敷に向かい―――焼け落ちてただの炭となった家屋の前に、血と灰にまみれてうずくまっている少女を見つけた。
ちょうど雪が降っていた。
必死で逃げたのだろう、少女の服はぼろぼろで、体のいたるところに傷が見えた。
小さな結晶が触れるたび、白から赤に変わる。
光の映らない目で屋敷があった跡を呆然と見つめる彼女の姿は、まるで親に置いていかれた子供のように、寂しげだった。
その時、確かに彼女がいった、声にならない声で。
玉の緒よ 絶えなば絶えねながらへば 忍ぶることのよわりもぞする
(我が命よ、絶えてしまうのなら絶えてしまえ。このまま生き長らえていると、堪え忍ぶ心が弱ってしまうと困るから)