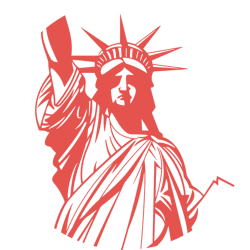
そちらの王座の居心地はどう
なまえのおかげで癒えた寂しさもあった。例えば、若くして川を渡ってしまった彼ら。逝ってしまった奴らの想いや信念は、まだ大地に踏みとどまっている人間の肩に襷のように託されるわけだが、ついに残されたのが自分一人となった今、それらぜんぶが唯一未来へと行ける僕へと収束する。
受け取った襷を負荷とは思わない。けれどさすがにこの量は勝手じゃないかとも思う。
初恋の女性。
その長女であった幼馴染。
数えてみれば現在の友人の数を喪った人々の数は優に上回る。
なまえとの関係は、決して溝を埋めるためだけの代替品などではなく。心安らかに眠るためだけの入眠剤でもなく。他の何にも変えがたい、僕の愛そのもの。
傷とも思っていなかった傷が、痛みとも思っていなかった痛みが、彼女を抱き締めたり、キスをしたり、手を繋いだりする時間の中で癒えていく。
けれども人生とは罅の入った花瓶のように注いでも注いでも取りこぼし続けて一向に満たされない。なまえと会えない日々の蓄積に比例して恋しさが募るお陰で、結局僕はいつも乾いているのだった。
ネクタイは首輪だ。最も、望んでつけられたもので、僕の感覚としては国に尽くす者としての勲章にも近いものだが。
首元のノットを緩めるとせり上がってくる開放感が、今日の務めが終わったことをリアリティを伴って脳を撃つ。しゅるりと襟元から引き抜いたネクタイと、袖から腕を抜いたグレースーツのジャケットをクローゼットの中にかけると、足元から僕に熱い眼差しを送ってくれていたハロを撫でる。
「おまたせ。ご飯にしようか」
アンッ! と響く良いお返事に口元が緩んだ。
夜の暗がりに沈んでいたキッチンにあかりを灯し、ドッグフードをクッキングスケールにかける。現在の彼にとっての適量きっかりを皿に盛りつけて床に置き、お約束の“まて”と“よし”を行ってから食べさせる。
皿に鼻先を埋めてはぐはぐとフードを頬張るハロの姿は毎日朝夕計の2回見ているはずだが、その愛らしさに飽きはこない。
しゃがんだ僕は膝の上で頬杖をつき、にこやかにハロの食事を見守る。
「うまいか?」
アンッ! とハロ。
「僕もお腹空いたよ。早いところ何か腹に入れないとな」
ごちそうさまでした、と手を合わせて一息ついたとき、僕は寂しさの奇襲を受けた。
室の至るところに孤独感が転がっていて、今までは目にも止まらなかったそれらがある日を境に鮮烈に存在を主張し始めたのだ。
僕が借りているメゾンの一室は決して広くはない。そのはずが、持て余すような広さに思えるし、室温も温度計が示す数値よりも数度低く感じられる。伽藍堂で広くて寒い。
全てはなまえがいないからだ。
「まさか僕が一人の女性をここまで恋しがるとはな……。数ヶ月前までは考えもしなかった」
独白が消毒済みのテーブルの上を転がった。
キッチンのテーブルの向かい席が空席であることを特別にしたのはなまえだった。
広いベッドでは寝足りなさを覚えるにさせたのも。寝坊助を叩き起こす役目のない朝を物足りなく感じさせるのも。いないというだけで部屋をがらんとさせるのも、室温を下げるのも。どれも、これも――。
どうしたことだろう、いつのまにか彼女がいる家であってほしいと願うようになっていた。
「明日はなまえと会う時間があればいいが」
僕が口にした、なまえ、という響きにテーブルの影でハロがきらりと目を光らせた。
「君もすっかり彼女を気に入ったんだな、ハロ。名前を出しただけで嬉しそうな顔をするなんて」
妬けるな。
本気とも冗談ともつかないことをぼやきつつ、椅子から腰を遊離させる。
食器をシンクへ置いて、水道水で濯ぐ。軽い水洗いで固形の汚れを流したあと、洗剤を含ませたスポンジを当てた。白い泡を纏う箸や茶碗を眺めてふっと息吹く。
目まぐるしい毎日の中にあっても彼女のいない夜は永遠よりも長い。
しっかりと捲ったはずのワイシャツに泡が跳ねて、染みが出来上がったものだから、やってしまったと肩を竦めた。
洗い物もひと段落し、ベッドに腰を下そうとした折のこと。
しまい忘れていたらしいギターのピックが部屋の隅に淋しく転がっているのを発見する。失くしたと思っていたらこんなところにあったのか、と僕はそれを拾い、引き出しの小物入れの中に大切に入れた。
そのとき、眼界の端の方に鈍色の光を知覚する。眼界の中心に据えたその鈍色の正体はこの部屋の合鍵で、まさしく僕を導いてくれる光といっても過言ではない。
「なるほど。そういう手もあるか」
僕は迷わず掴み取る。
2021/02/06