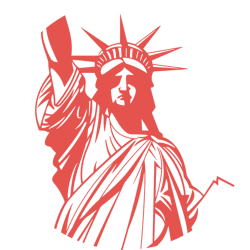
おばけと女の子の違い
二人でハロの散歩に出ることが日課と化したのは、例えちょっとした時間であってもなるべく一緒に過ごしたいという僕の思いからだ。多忙が服を着て歩いているとも揶揄される僕は、こういった日々の中に点在する、砂粒のような僅かな時間を大切に愛でていくしかない。
リードは僕が引いて、空いた片手は彼女と繋いで、二人と一匹で並んで歩く。
前述の通り多忙なおかげで散歩は夜帯になりがちなのだが、こうして人目を憚らずに手を繋いだり、無人の歩道を僕らだけで占領して、我が物顔で広がって歩いたりできるのは、いいものだ。
立ち寄ったコンビニエンスストアでノンアルコールの缶ビールを2本購入した。お互いいつ召集がかかるともしれない身――いつこの日常の時間が終わってもいいようにだ。警察官は酔えない夜が多い。不満はないけれど。
「帰ったら何かつまみでも作ろうか。なまえは何食いたい?」
「零君が好きなおつまみ」
なまえからはお決まりの、遠慮の滲むリクエストを頂戴する。
「君は本当にそればっかりだな」
僕もまた、お決まりの苦々しい笑みで答えた。なかなか手に入らない彼女のわがまま。まさかここまで手こずることになるとは。
冷蔵庫の内容物に思いを馳せて顎に拳を添える。
不意に視線を下したとき、ハロの喜びの宿るきらきらとした瞳とかち合って破顔した。
静かな夜道に靴音と仔犬の爪がコンクリートをつつく音が響いていた。
酔えない夜だったけれど、ぷかぷかと湖をたゆたっているかのように上機嫌。なまえの言葉を借りるのなら、“夢みたい”な。
「私グラス洗おうか」
「明日やるからいいよ。それより、こっちきてくれ」
綺麗好きの僕が空っぽの缶とグラスをローテーブルに放置することを許したせいか、なまえは少しだけ目を丸くしていた。
なまえを自分の脚に座らせて後ろから背中を抱き竦める。
「緊張しすぎだろ」
「で、でも」
生きたまま氷結したように固まり切った彼女の背中に笑を零す。
「俺に寄りかかって。くっつきたい」
言えば上肢を委ねてくれる彼女だけれど、こんな健気な行為も全て、部下としての意識のもとで行われているのだとしたら些か切ない。
なまえはローテーブルの上の自身のグラスに指を伸ばしかけて、すっかり飲み干していることに気づくと指先を引っ込めて拳の中に握り込んだ。そんなことも失念しているとは、相当動揺しているらしい。
僕の振る舞った料理を頬張り、落ちてしまいそうだと頬をおさえる。グラスを揺らして氷同士の擦れる音を奏でながら、零君と飲むとおいしいと目を細めて呟く。ちょっとしたハロの散歩中や日用品の買い物中、手を繋ぐだけではにかむ。僕はそんな彼女がかわいくて仕方がないのに。
夢みたい、と――困ったような声色とはにかみの滲む微笑みで、なまえはたびたび口にする。
小鳥のさえずりのようにささやかでかわいいことを言ってくれるものだと思っていたが、夢みたいとはつまりとても現実とは思えない――信じられないという意味だと悟った。
「零君はどうして私に優しいの?」
「僕がそうしたいから。それに君のことが好きだからだよ」
なまえのことがそれこそお姫様のように大切だからだ。
僕の息遣いやまばたきの一つ一つが彼女に対して好きだと訴えているのに、その何割も伝わらないとは歯痒い。
「零君はどうして私のこと好きになってくれたの?」
「赤ずきんちゃんみたいだな。……教えてもいいけど、果たして君が信じてくれるかどうか」
「……?」
「随分前になまえが一人で牛丼屋に入ったところを偶然見かけたことがあったんだ」
「ぎゅ、牛丼屋っ?」
「その頃からなまえと一緒に昼を食べることはあったけど、そういうときのなまえはかなり猫被りだったんだろうな……。人目から解放された君はすごくいい食べっぷりで、思わず笑ったよ」
「恥ずかしい……」
「それがすごくかわいくて」
「うっ、うっそぉ」
「本当さ」
「信じられないよ」
こんなふうに。
嬉しさや喜びが沸点を超えたとき、感情の昂りを表す語句として、人は「信じられない」という言葉を用いるが、なまえのそれはそういった表現法に則ったものではない。無論、言葉の綾でもない。恐らくは自己評価の低さに起因するのだろう。
そんな彼女にとって、「降谷零はみょうじなまえと仕事で付き合っている」と思い込むことは自己補完には最適だったに違いない。
しかしその拠り所にも等しかった補完は、僕は愛の言葉で真っ向から破壊した。
そうやって僕が彼女を丸めこむことで落ち着いた関係性だから、信用を勝ち取るための戦が長丁場になることも覚悟の上。
想いの丈を正確に伝えるのは難しい。他人の自己肯定感を高めることも難しい。大鍋をかき混ぜるように地道にアプローチを重ねていくつもりだ。
今のなまえはいっぱいいっぱになりながら、ひたすらに僕から好意を注がれている。
わけもわからないまま愛の鍋の中でぐつぐつ煮立てられて、のぼせている。
はやく「参った」と口にしてくれないだろうか。
――なぁ。
君はどうしたら信じてくれる?
縋り付くように彼女の背中をきつく抱き締めて、お互いの間に介在している距離や空白といったものを悉く滅ぼしてしまおうとする。密着度が極限まで高まったのはいいが、そうなると肌を隔てる服が邪魔になってきて、彼女のぬくもりも欲しくなってくる。
酔えない夜だけど、触れたくて溺れたくてたまらなくて、そんな思いで彼女と視線を結んだ。
2021/02/06