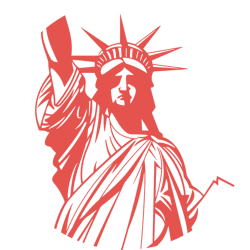
ぼくらはミネラル
「この後の予定は?」「特には」
「なら僕の家に来ないか? 話したいこともあるし……渡したいものもある」
話したいこと、と言われて真っ先に脳が弾き出した予測は説教だったけれど、そのあとに続いた渡したいものという言葉が引っ掛かり、私の中で謎を深めた。
降谷さんの純白のスポーツカーの窓から、流星のように前から後ろへと高速で流れていく深夜の街並みに眼差しを馳せて、ヘッドレストレイントに後頭部を任せながら、私は首を傾げる。
「ハロも君に会いたがってるからな」
と、降谷さんは、三日月のような綺麗な輪郭線を描く横顔に、私的なシーンでしか見せない柔らかな微笑みを湛えた。その横顔だけで、もう彼の肩からは本日分の荷は下りているとわかり、もう“零君”と呼んでいいのかな、と私は座席の下で両足をぶらりとさせた。
説教の可能性も、仕事に関わる資料の受け渡しの可能性も潰えた今、彼の要件を包む濃霧はより一層濃く厚くなる。
――「渡したいものって何?」って聞いていいのかな? でもわざわざ家でって仰ってるのにここで突っ込むのはよくないよね。空気読めないと思われたら嫌だし。
私はやきもきと膝の上で両手の指同士を絡めてはほどいたり、光の軌跡を描きながら後ろへ流れていく街灯の数を横目に数えたり、くちびるを弱く噛んだり。急な招集にも喜んで飛んでいく毎日だというのに、今日に限って心の準備をさせてもらえないことがこんなにも怖いなんて、妙だ。
「何か思いつめた顔をしてるな」
「そ、そういうわけじゃ……。渡すものってなんだろうと思って」
「それはまだ秘密だけど。悪い話じゃないよ」
赤信号に引っかかって、訪れた静寂。
零君は慈しみを乗せた指先でハンドルを撫で下ろす。
メゾンの駐車場に車を入れ、エンジンの静まっていく音を最後まで聞き届ける。
零君が私の腰かけていた助手席側のドアを開けて「どうぞ」と粋なことをしてくれたので、年甲斐もなく照れつつもそのエスコートを受けた。
そのとき、零君の携帯端末が震えた。
「すまん、電話だ」
「仕事かも。出て」
彼は通話を繋げたあと、「あぁ」や「わかった」などと相槌を何度か打つ。爪先で砂利を踏みながら待つ私の鼓膜には通話相手の声は届かないけれど、零君が放った「すぐにそちらへ向かう」の一言でこのあとの約束が壊れたことを悟ってしまった。
招集だろう。零君に向かって噛みついても仕方のないことだ。
「招集がかかった。すまない」
「気にしないで。頑張ってね」
今月だけで何度目だろうか、このやり取り。
零君はグレースーツのポケットに役目を終えた端末を滑り込ませたあと、何か小さなものを同じ場所から取り出した。
「すぐに片付けて帰るよ。君はこれで部屋に入って待っていてくれ」
言うと同時に零君がその何かをこちらへと投げ、そのまま駆け足気味にRX-7の運転席に乗り込んでしまった。
「えっ!? 零君!? ……わっ!?」
ぽーん、と放物線を描いて天高く踊った鈍色の光が、慌てて両掌で拵えた受け皿に見事収まった。落とさなくてよかったと心底安堵した私は、両手でその小さな鈍色を大切に握りこみ、胸に抱く。
恐る恐る結んでいた掌を開いてみると、私が手中に収めていたものが夜闇の中に晒された。
それは。
「か、鍵……?」
困惑の波に攫われそうになる私を現実へと引き戻したのは、ウィーン……という車の窓の開閉音。窓枠に肘を置いた零君が、車の中から身を乗り出して来る。
どういうことと唇を割るけれど先行は彼に奪われてしまった。
「その鍵なんだが、返さなくていい」
「え?」
「君の合鍵だよ。本当は家で落ち着いてから渡したかったんだが」
「えっ、えっ?」
「まったく……せめてサプライズくらいさせてほしかったな……」
髪をかき上げて、作戦失敗を自嘲する零君。彼の小麦色の指の隙間から落ちていく癖のないミルクブロンドが、夜風と踊る。
その次の瞬間、零君に真正面から見据えられ、私の拍動は大きく乱れた。
「いつでもきて」
「は、はい」
「いい返事。君が家で待っていてくれていると思うと頑張れそうだ。2秒で解決できるじゃないかな」
「2秒って……」
「冗談だけどそれくらいの気持ちだよ。サプライズを邪魔されたことにはわりと怒ってるしね」
零君が窓の開閉スイッチに指をかける。
「それじゃあまたあとで」
そんな挨拶を夜風に乗せて。
窓硝子が閉の上昇を始めるころには、もう彼はフロントガラス越しに前だけを見据えていた。
露払いをするように駐車場を照らし出すライトが夜道を導く。車が息吹いて、巻き上がった排気ガスが私の靴の先を舐めた。濁った風の中で遠のいていくスポーツカーを見送りながら、私は鈍色の鍵を握る。
――馬鹿だ、私。
それこそ降谷零さんに釣り合わないくらいの愚か者だ。
彼に想われておきながら、もったいないだの自信が持てないだの現実とは思えないだのとぐずくずべそをかいていたが、それらは本当に愚かな時間だった。
夢みたい。でも夢じゃない。現実。握り込んだ金属の質感が現実を歌っている。
特等席のチケットを手にしながらホームで立ち往生していた、自信なさげに眉を下げた女の子を卒業する季節が巡って来たのだ。
零君の車の排気ガスすらも消え失せて、ぽつんと私だけが佇む夜の駐車場。ハロに餌をあげなくちゃ、と私は合鍵を大切に掌で包んで、踵を鳴らした。
***
電話一つでサプライズが粉々に砕け散ったことは、さすがにしばらく根に持つだろう。
なにせ次に格好つけられる機会なんて、彼女の薬指に指輪を嵌める瞬間くらいしか残されていない。婚約指輪を駐車場でキャッチさせるのだけはまっぴらごめんだ。
などと、先ほどのアクシデントを反芻させながらメゾンの廊下に靴音を響かせる。夜闇に浮かぶかのような純白の廊下と、一定間隔で並ぶ各々の玄関。そのうちのひとつのドアを前に佇んだ僕は、その鍵穴に己の鍵を差し込み、ドアノブを回す――。
ドアの隙間から零れ落ちた明かりが僕の靴の先を照らし、空調の温かい人工風が僕の膝を撫でる。次いで、開けていく室内の景色。明かりの下で、揃えられて置かれた一足の靴。
パタパタと次第に近づいてくる足音。
――嗚呼。なんて、幸せなんだろう。
「おかえり。零君」
足音の主は玄関先で僕と向かい合って、花を咲かせるように笑った。ハロもずっと起きて待ってたんだよ、と抱きかかえた、眠さの伺える表情のハロと視線を合わせて。
「ただいま」
僕は徐に伸ばした腕で恋人と愛犬を包み込んだ。本当は彼女ときつく抱き合いたかったけれど、ハロを潰してしまわぬよう、そっとだ。
「ハロと君が帰りを待っていてくれるっていいな」
わが家が一番だ、なんて月並みな言葉だが、幸福を噛み締めるのに忙しい僕にはほかの表現を探している時間はないのだ。
2021/02/08
sweet home:愛の巣
home sweet home:我が家が最高だ!
ストラップ回でコナン君に車のキー投げて渡すの、信頼を感じます。