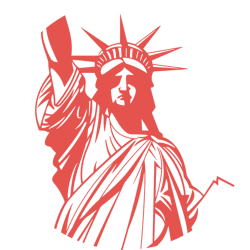
夜更かしする子の毛布を盗む
僕はなまえの浮かない顔ばかり見せられている気がする。否、気のせいではない。***
ゼロのエース。
彼の顔は限られた人間しか知らない。
警察学校を首席で卒業しただとか、あの大事件を快傑に導いたのも実は彼だとか。華やかな噂話ばかりが目立って、当の本人は決して表舞台には現れない。功績だけが宙ぶらりんになっていて、まるで幽霊だと遠い国のニュースのように思っていた。けれどそれも過去の話。
私が降谷さんと関わる権利を得たとき、彼が実在するということは確かめられた。降谷さんの背景を知ったことで、今まで月のように単独で宙に浮いていた彼の功績にも重みができ、リアライズされる。
反面、人間離れした偉業の数々に、物語の英雄が頁を突き破って出てきてしまったのでは、なんて空想を踊らせたりもした。そしてこれもまた過去の話。
降谷さんの顔を知る者は少ない。ましてや降谷さんに触れられる者となると更に減る。
そして。
驚くべきことに降谷さんに抱き締められたり、抱き締めたりできる者は、信じられないことに私だけらしい。
――降谷さんの腕枕という特等席を堪能しながら考えることではないけれど。
ミルク色の毛色に綿菓子の肌触り。彼の腕にぽふりと頭を預けて、柔らかに抱擁されながら、彼の愛犬を互いの体の間に挟んでまどろむ。はじめこそぴんと伸ばしていた意地っ張りな背筋も、寝息を立てる仔犬を撫でるのと同じ優しい手つきで髪を撫でられてしまえば、いやがおうにもくつろがせられる。
いつか私の頭からはバグが検出されるのではないか。顔におかしな表情を表示してしまったりして。
「零君、腕痺れない?」
「これくらいどうということはない。伊達に鍛えていないからな」
そう言ってまた私の涙袋のラインを指でなぞるように撫でた。
やっぱり彼は恋人に尽くすタイプなように思う。当人は無自覚だったようだけれど――或いははぐらかしていたようだけれど。
「朝は何にしようか。好きなもの作るよ、材料と時間の許す範囲で」
「零君が食べるものがいいな」
「いつもそれだなぁ」
「零君が何食べてるのか知りたくて」
「そんなに面白いものじゃないだろ」
「面白いよ」
私の胸中では、まだ“憧れの降谷さん”としての印象の方が勝ってしまう。
高嶺の花の上司に手料理をご馳走になったり、抱き締められたり、甘やかされたりしている日々は日常というより超常だ。安らぎよりときめきにあふれている。
たったひとりで死地を潜り抜け、凛と指揮を執る頼もしい上司が私と私的な時間を共にしているだなんて、顔も心も火照る。
まるで夢見心地。
2021/02/03