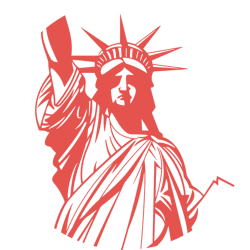
花冠の繋げ方もわからないまま
降谷さんと関係を結んで二週間ほどになる。恋人のようになっても、さすがは降谷さんといったところで、あの人は忙しい日々の合間を縫って私との時間をこしらえようと努めてくれていた。一緒に目を覚ました朝にはほかほかの白米をよそって食べさせてくれるし、お弁当を持たせてくれる。毎晩とはいかないけれど、都合がつけば迎えの車を出してくれるので、いつしかあのスポーツカーの助手席は私の特等席と化していた。
安室透として振る舞う時、私が隣にいやすいという利点もある。
理髪そうな眼鏡の小学生の男の子も、最初は突然湧いて出た「安室さんの彼女」なる不審な女にどことなく警戒心を漂わせていたけれど、恋人同士として路上や車内で――安室透としては迂闊すぎるほどの――見せつけるようなキスを繰り返しているうち、納得してくれたようだった。
私が降谷さんの恋人であるということは彼にとってもなかなか都合が良いのだろう。好青年の安室透としては、恋人の一人でもいた方がリアリティが増し、人物像に立体感が生まれる。バーボンとしては、万が一私との繋がりを組織連中に嗅ぎつけられても、公安の女をたぶらかして情報を引き出していたのだと弁解できる。疑われる余地もない、身体の関係はあるのだ。
「あれ……? これって……」
自分のデスクの上に身に覚えのない紙袋が乗っており、首を傾げる。中を覗いてみると見慣れたランチケースに昨夜降谷さんのメゾンで振る舞ってもらった品々が詰め込まれていて、登庁したあの人がわざわざお弁当を置いていってくれたのだと悟った。
降谷さんがまだ庁内にいらっしゃるのかどうかはわからない。会議室か、資料室か、はたまた既に別の場所へ移動してしまったのか。
読んでもらえることにはなから期待はしていないけれど、感謝の意のメッセージを送信しておく。
これは半ば儀式的なものだろう。誰に届けるでもなくいただきますやごちそうさまでしたを口にするような、儀式。
そして、待ちに待った昼休憩。
あたためてもいないお弁当なのに、というか膨れているのは腹なはずなのに、じんと胸が熱くなった。
***
――我ながら違和を覚えるのが遅すぎて、自分で自分に辟易してしまった。
彼女のこととなると自分でも驚くほどに夢見がちになり、論拠のない自信や期待を抱く青臭い己が頭を擡げる。そんな青年のようなメンタリティが許される時期はとうに過ぎているだろうに、情けない。
ようやくなまえを手に入れたはずが、付き合った途端時間の隔たりが都合よく消え去るはずもなく、思うように触れられない。
プライベートな時間が幸運にも噛み合うと、すぐにでもそれまでの距離と恋しさを埋めてしまいたいのに、僕の自宅までの移動時間すらもどかしくて、やきもきさせられる。
玄関のドアを閉めてすぐにブラウスに包まれた背中を潰す勢いで掻き抱いてしまいたかったが、出迎えてくれた愛犬のつぶらな瞳を見てびりびり火花の伝っていた神経が緩んだ。
ハロに餌を与えて、使い終えた犬用の皿を下げる。洗いますよ、と進んで蛇口を捻るなまえの手を掴んで制止した。
中途半端に捻り出された水道水の流れ続ける中、なまえの唇を奪う。舌を絡めて互いの熱をわかちあったところで、いよいよ水の音が鬱陶しくなり、後ろ手に蛇口を捻る。先ほどとは逆方向に。
焦燥感と、僕と彼女の汗が混じり合った獣じみた香りに眩暈のような、酩酊のような、そんな感覚に苛まれて。けれどずっと酔って、浸って、溺れていたくて。
キッチンの壁になまえを追いやる。壁と僕の間に体を挟まれて、息と唇はいいように奪われて、すっかり囚われの身だ。僕だけを捉える濡れた双眸に……それだけじゃない、なまえの顔を染める自分の影にさえ、ぞくぞくと総身を駆け上がるものがある。
「……したい。いいか?」
耳打ちで許可を乞いつつも、壁も自分の体も派手に使ってなまえを逃がすまいとしている現状が、
なまえの腿の間を割って、自分の膝を差し込む。
「零君、今日、その……」
生理、と雫の跳ねる音にかき消されてしまいそうなほどの声量でなまえが言った。
えっ、と拍子抜けしてしまいそうなところを押さえつけ、「そうだったのか」となまえの拘束を解いた。
「気づかなくてすまん。ひょっとしてずっと体調悪かったんじゃないか?」
「だ、大丈夫です」
流石に汚れるのは零君も困るだろうし。
彼女の口から続いた言葉に僕は唖然とした。
「今は僕が困るかどうかじゃなくて、なまえの身体の心配をしているんだが」
まるで厳しく誤りを指摘するかのような僕の声色に、なまえの顔つきが一瞬だけ部下としてのものになったのを見逃さなかった。すみませんと謝罪を紡ぐ彼女はやはり従う人間の色を帯びている。
これじゃあただの説教だな。僕もこんなことを望んでいるわけじゃないのに。
「なまえ、少し話そうか。こっちにきて?」
少し話そう、と極力柔らかな語調で。
そう言って、手を引いて、ベッドに二人で並んで腰を下す。
「辛くないか?」と問えば、今は大丈夫です、となまえは答える。今は、ということは先ほどまでは調子が優れなかったのやもしれない。知らず知らずのうちに押し付けてしまっていたかもしれないな、と己を戒める。
「少し待ってろ」
言い捨てて、キッチンに足を運ぶ。薬缶を火にかけて湯たんぽとカモミールティーをこしらえた。湯たんぽをなまえに抱えさせ、彼女の猫舌を困らせない程度に熱を帯びたティーカップを渡すと、本題に切り込んでいく。
「君にとっての僕はずっと上司だったし、慣れるまでは時間もかかるかもしれないけど――、プライベートでは君と対等な関係でありたいと思ってる」
なまえの瞳を真っ直ぐに見つめると、彼女もまた真っ直ぐに僕の瞳を見つめ返してくれた。
「仕事じゃないんだ。僕が君に触れたくて触れてる。キスもそう。でも押し付けるつもりはないし、嫌なときは拒んでくれ、お願いだから。繰り返しになるけど、これは仕事じゃない。嫌な時は嫌ってはっきり言ってくれ。君の望まないことなら、僕だって無理強いはしたくないんだ」
なまえのまばたきがぽろりと一つだけ零れた。
「――約束してくれるか?」
「ふ、降谷さん」
「うん?」
「ごめんなさい、私……」
「君が謝ることじゃない。むしろ悪いのは僕の方――」
「違うんです。私、付き合うのは降谷さんの仕事の一環だと思ってて……任務のための……」
「――は?」
らしくもない、心の底からの信じられないという気持ちを乗せた、僕の声。
判断が早いわけでもない、思い切りがいいわけでもない、豪快さも持ち合わせていない、そんななまえの二つ返事の理由を知る。恐らくはとても嫌な形で。
答えは単純明快。彼女はただ従順なだけだったのだ。
「なるほど。気付かぬうちにパワハラしていたとはな」
嗚呼と深く息吹いた後、睫毛にぶつかる邪魔臭い前髪をかきあげる。
「監視されてるからカモフラージュが必要なんだと思ってたんです。庁内や、あの降谷さんの家や車でまでそんなことがあるのかな、って不思議でしたけど……」
「言葉足らず、だったな。必要に追われて恋人を装うケースもゼロではない仕事だから、勘違いさせる材料はあったんだろう……。とはいえ、君も僅かな情報から邪推しすぎだ」
「ごっ、ごめんなさい」
邪推は推理にも通ずるものがあるし、僕も人のことをあまり言えた口ではなかったけれど。
仕事で偽りの関係を結ぶことも、想ってもいない女と体を繋げることも、確かに無いとは断言できない。人間関係を仕事に左右されているのは事実だ。なまえを叱責する権利はないように思える。
「率直に答えてくれ。君は僕のことは嫌いか?」
「好きに決まってます! 降谷さんを尊敬していない人なんていません!」
「その好意は僕と同種のものか?」
即答で尊敬の念を表したなまえも、質問を重ねればさすがに口籠もる。同情を誘う困り果てた表情で、視線を彷徨わせる。気の毒だ。
「君が望むなら僕は身を引く」
あと少し刺激を加えれば忽ち泣きだしそうだ。でも手加減はしてやらない。
「言っただろ。無理強いはしたくない、って。だから、君が選んでくれないか?」
みょうじなまえに、択を与える。
一度手に入れたものを失うことを恐れるのが人間の性である。手放すという行為には、必ず勇気が求められるのだ。だが、小心者のみょうじなまえにそんな勇気が備わっているとはとても思えない。
おまけに考える時間も満足に与えていないし、冷静な判断が可能な状態でもない。プレッシャーも充分にかけている。
この僕が直々に心に揺さぶりをかけて、冷静さを掻き乱してやっているのだ。恐らく彼女は、僕と、少なからず幸せだった僕との日々を、手放せない。
さらに今の僕は無敵に等しい。なにせ、もう純粋な恋の種から愛を育むことには拘っていない。
目論見通り、心理的な揺さぶりに絡め取られた哀れな彼女が、僕の元に残ってくれさえすれば万々歳。今の関係性を明日に持ち越せさえすれば、それでいい。
稀有なことだが、今の僕はその場しのぎなのだ。
裏を返せばそれだけ一人の女性に必死になっているということだが。
「わ、私も、降谷さんともっといたい、です」
失う恐怖の敗北者の振った白旗に、口角が上がりそうになってしまう。まるめこんだ、なんて人聞きの悪いことは言わないでくれ。
2021/01/26