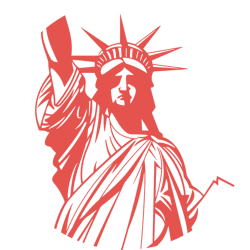
ユニコーンの庭
送っていくという当初の約束は守らなかった。苺の香りがする冷たい唇に触れたあとでは手放せなくなってしまったのだ。みょうじも僕の苦い舌に安っぽさを覚えたのだろうか。なんて、他愛もない考え事に脳を切り分けたうちの幾ばくかを割く。
彼女の躰や髪の香りに頭が蕩けてゆくのはまさに夢心地。僕を癒してくれるこの子をようやくこの手に納められたのだ。征服感が背筋をせりあがる。背骨が折れるのも厭わないくらいに抱き潰したい衝動に駆られつつも、そんな欲に栓をする。
汗の滲む鬢を指で梳くようにかき揚げて、包むものを剥ぎ取った胸を忙しなく上下させているみょうじにふっと目を細める。するとみょうじは赤い顔を逸らすので、仕返しとばかりに首筋に歯を立てた。
「あ……っ」
「僕の方見て、みょうじ」
唇同士がぴったりと重なり合っていない、丁寧ではないキスを積み上げて、少しでもみょうじの痛みを軽くしようと試みる。
ふるやさん――、と力なく縋り付いてくる彼女をあやすように抱き竦めて、大丈夫、とまじないみたいに呟いて。
舌を絡めるキスで彼女の神経を分散させるよう努めながら、脚の狭間の奥深くにまで押し入ってゆく。
みょうじの鎖骨を撫でていても、手を繋いでいても、闇の中に紛れていても、肌の色彩の差は歴然としており、彼女の白い肌に自分の褐色の肌が滑るとより双方の存在が鮮やかに感じられた。
僕は宝物を扱うように、彼女の髪を梳いて、細さを確かめて、余すところなく全てに口付けた。
時刻を見なくても朝が近づいていることはわかった。僕も彼女も深くは眠らずに、目だけを閉じて同じブランケットに包まっていた。相手のみじろぎひとつで完全に目覚めてしまうほど近しい距離だったので、案の定、上肢を起こしてベッドを抜け出そうとした彼女の気配で僕は瞼を開けた。何も纏っていないみょうじの肌が夜闇の中で月のようにぽっかりと浮かんでいる。
「もう少しそばにいてくれ。時間もあるだろ?」
僕自身はそそくさと服を纏うよりは、1秒でも長く互いの肌を触れ合わせてまどろむ時間を大切にしたい。彼女の手首をそっと掴んでそう望むと。
「寒くて……」
服を着たいのだとみょうじは小さな苦笑いを浮かべた。
「なら、貸して。着せてあげる」
みょうじが床から拾い上げたブラウスらしき白いものを奪うと、バフバフと軽く皺を伸ばしてからその肩に羽織らせた。
――でっかい。これ僕のだな。
袖も裾も余り放題で、チュニックかワンピースのように腿まで隠れている。けれどそんな無様さがとてつもなく愛らしかったので、僕は秘密主義らしくだんまりを貫き、このままこれを彼女に着せてしまうことにした。
ワイシャツの釦を止め終えると再び僕たちはベッドに沈み込む。
おとなしく僕に腕枕をされているみょうじをにこにこと眺める。
「降谷さんは寒くない?」
「寝る時は何も着ないんだ」
「裸族……?」
「そうとも言うね」
白魚の手が頬に伸びてきて、僕の前髪を耳の裏に流すように撫でた。僕の頬を指で撫でているその手に自らの手を重ね、捉える。
「なぁ、零って呼んでくれないか」
「零さん?」
「さんもいらないかな」
「れいくん」
「うん。ふふ、なまえ」
多幸感とは今を表す言葉に違いない。
「なまえは明日何食いたい?」
「イタリアン、とか」
またか? 本当に好きなんだな。なんて僕は笑うが結局はそれに応えようとしてしまうのだ。
「ならそれは夜だな。明日の昼、君の分も作ろうと思うんだけど何がいい?」
「零君いつも何のお弁当なの?」
「え? 特別なものではないけど。卵焼きと、野菜……セロリが多いな。あとは昨夜の残り」
「同じの食べたいです。降谷さんのお弁当はいつも美味しそうだっていろんな人が言ってて、気になってて」
「零」
「あっ、零君。……それで私、てっきり恋人いるんだろうって思ってたんですけど」
「国だけが恋人だったよ。まぁそれも数時間前までだが」
なまえの漏らす笑みにつられて僕まで笑ってしまう。
電光掲示板を泳ぐ文字のように悠々と言葉も話題は流れ流れて移ろいつづける。
「もしかして零君って付き合うと尽くすタイプ?」
「どうだろうな。自分ではわからないが」
「絶対そうだと思うけどなぁ。お弁当楽しみ。早く明日のお昼になってほしいな……」
「朝はいいのか?」
「作ってくれるの?」
「無理をさせてしまったしね。君はギリギリまで寝てていいよ」
瞼にキスを落とせば、なまえはそれを合図ととったのか、また浅い夢に転がり落ちていった。
2021/01/24