二人でみた幸せな夢
自分のより一回り小さなその手を、俺はいつまでも離せずにいた。目の前の彼女は、不思議そうな顔で俺を見上げている。出来ることならば、今すぐにでも拐っていきたい。この身体を抱き上げて連れ去ってしまいたい。でもそれでも衝動のままにそうしようとしないのは、少し俺の思考が大人になったからなのか、彼女の気持ちが分からないからなのか、それとも。
「…イタチ…?」
嗚呼、そうだ、彼女を孕ませておいて、何を迷う必要がある。ここから彼女をどうしても出したかったのは、他の誰でもない、この俺だ。
「…俺と共に来る覚悟はあるか?」
火芽にとってここを出ると言うのは人生を左右するほどのとても大きな選択なのに、なぜ俺はこんな浪漫のない聞き方しかしてやれないのだろうと恥じたのも束の間、彼女は満面の笑みを称えて俺の手をきゅっと握り返した。
「わっちを…連れ去っておくんなし、」
「本当に…良いんだな」
「あの初夜から、ずっと望んでいたことでありんす…どうぞお願いいたしんす。」
自然と重なる唇は、承諾の証。
いそいそと身支度を整える彼女を横目に、ふと机上を見ればあの時やった簪。ぼんやり眺めていると、横から伸びた白い腕がそれを手に取って髪に飾り付けた。まだ、使ってくれていたのかと笑みがこぼれる。
「…似合う?」
「あぁ、とても。」
嬉しそうに笑う彼女の、何て可愛らしいことか。着物もいつの間にか派手な打掛から真黒なものへと変わっていて、普段花魁が持っているはずもないその色に彼女の覚悟を垣間見る。待たせていたのは、やはり俺の方だったか。
暫くすると、彼女は大きな風呂敷包みを幾つか俺の前に置いて、正座をした。頭を深く下げて、あろうことか土下座をする。
「何のつもりだ」
「ふつつかものでは御座いますが、」
「いや、…俺が、先に言わねばならぬことなのに」
「どうぞ、よしなに…」
「あ、頭を上げろ、」
「…」
柄にもなく、ごくり唾を飲み込んだ。
「一緒に…来てほしい。」
「はい!」
長い長い年月を経てようやく手に入れたこの幸せに身を任せ、貪るように彼女の口内に舌を蠢かせる。度々漏れる声がなんとも厭らしく俺を煽った。でも、今は。焦ったように唇を離した俺を見て、彼女は申し訳なさそうに笑う。
これから先、時間は幾らでもある。そう自分に言い聞かせて身体を宥めた。
「暫くは…」
「気にするな、それより早く行こう。」
「はい。」
「それにしても…荷物が多くはないか」
「全て銭なのです、これから何かと要り用になるかと…」
まぁ確かに、これだけあればとりあえず角都に彼女を反対されることはなさそうだ。そう思いながら、見た目より何倍も重いそれらを手にして立ち上がる。
気付けば、空は大分白んできていた。
「わっちは…夢を見ているようでありんす」
「夢?」
「はい。とても…幸せな夢を。」
数年前、思い描いた夢が叶うなんて思ってもみなかった、そう言って微笑んだ彼女はまるで本当に夢の中だけに存在するもののような儚さを帯び、朝日のせいか若干神々しくもある。
「確かに…これは夢なのかもしれんな。」
「ふふ、可愛いお人。」
「なっ」
「では…ずっとわっちと、この夢を見ていておくんなし。」
「…死んでも、な」
そうして二人どちらからともなく、手を繋いだ。
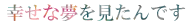
(20130715)
- 10 -
← →
←
自分のより一回り小さなその手を、俺はいつまでも離せずにいた。目の前の彼女は、不思議そうな顔で俺を見上げている。出来ることならば、今すぐにでも拐っていきたい。この身体を抱き上げて連れ去ってしまいたい。でもそれでも衝動のままにそうしようとしないのは、少し俺の思考が大人になったからなのか、彼女の気持ちが分からないからなのか、それとも。
「…イタチ…?」
嗚呼、そうだ、彼女を孕ませておいて、何を迷う必要がある。ここから彼女をどうしても出したかったのは、他の誰でもない、この俺だ。
「…俺と共に来る覚悟はあるか?」
火芽にとってここを出ると言うのは人生を左右するほどのとても大きな選択なのに、なぜ俺はこんな浪漫のない聞き方しかしてやれないのだろうと恥じたのも束の間、彼女は満面の笑みを称えて俺の手をきゅっと握り返した。
「わっちを…連れ去っておくんなし、」
「本当に…良いんだな」
「あの初夜から、ずっと望んでいたことでありんす…どうぞお願いいたしんす。」
自然と重なる唇は、承諾の証。
いそいそと身支度を整える彼女を横目に、ふと机上を見ればあの時やった簪。ぼんやり眺めていると、横から伸びた白い腕がそれを手に取って髪に飾り付けた。まだ、使ってくれていたのかと笑みがこぼれる。
「…似合う?」
「あぁ、とても。」
嬉しそうに笑う彼女の、何て可愛らしいことか。着物もいつの間にか派手な打掛から真黒なものへと変わっていて、普段花魁が持っているはずもないその色に彼女の覚悟を垣間見る。待たせていたのは、やはり俺の方だったか。
暫くすると、彼女は大きな風呂敷包みを幾つか俺の前に置いて、正座をした。頭を深く下げて、あろうことか土下座をする。
「何のつもりだ」
「ふつつかものでは御座いますが、」
「いや、…俺が、先に言わねばならぬことなのに」
「どうぞ、よしなに…」
「あ、頭を上げろ、」
「…」
柄にもなく、ごくり唾を飲み込んだ。
「一緒に…来てほしい。」
「はい!」
長い長い年月を経てようやく手に入れたこの幸せに身を任せ、貪るように彼女の口内に舌を蠢かせる。度々漏れる声がなんとも厭らしく俺を煽った。でも、今は。焦ったように唇を離した俺を見て、彼女は申し訳なさそうに笑う。
これから先、時間は幾らでもある。そう自分に言い聞かせて身体を宥めた。
「暫くは…」
「気にするな、それより早く行こう。」
「はい。」
「それにしても…荷物が多くはないか」
「全て銭なのです、これから何かと要り用になるかと…」
まぁ確かに、これだけあればとりあえず角都に彼女を反対されることはなさそうだ。そう思いながら、見た目より何倍も重いそれらを手にして立ち上がる。
気付けば、空は大分白んできていた。
「わっちは…夢を見ているようでありんす」
「夢?」
「はい。とても…幸せな夢を。」
数年前、思い描いた夢が叶うなんて思ってもみなかった、そう言って微笑んだ彼女はまるで本当に夢の中だけに存在するもののような儚さを帯び、朝日のせいか若干神々しくもある。
「確かに…これは夢なのかもしれんな。」
「ふふ、可愛いお人。」
「なっ」
「では…ずっとわっちと、この夢を見ていておくんなし。」
「…死んでも、な」
そうして二人どちらからともなく、手を繋いだ。
(20130715)
← →
←