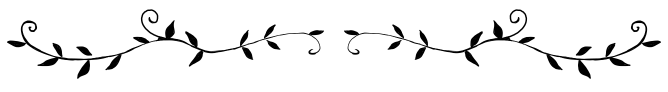うららかな、という形容がぴったりはまるような昼下がりのカフェ。対面の席でそうのたまった彼女──有希の口の端には、モンブランのクリームのかけら。
突拍子もない言葉に面食らう私に、彼女はなおも続ける。
「いや、幻覚ロスとも呼べるかも……?」
「……変な造語作らないでよ……」
返しながら、私も皿の上のフォークを進める。こちらはいちじくのタルトだ。ほの甘い果肉をのせたそれは、期待通りにとても美味しい。
魅惑の味に舌鼓を打ちつつも、胸の内で「やっぱりミスったかなあ」などと後悔し始めていた。かといって、この奇異ないきさつ──つまり、サボくんとの出会いに始まり消失するまでの話を、「頭がおかしい」などと一蹴せずに聞いてくれる友人など、そう多くもない。
そして、その数少ない存在が有希だった。相談した結果がさきほどの言葉へ繋がったことを考えると、適切な相手だったのか疑わしいところではあるが。
……あれから私は、サボくんを探しに探した。
遊園地では閉園時間ぎりぎりまで端から端へと駆け回り、部屋へ帰ればクローゼットの中からベッドの下まで覗き込んだ。
いつもの公園や本屋はもちろん、二人で出かけた場所や、サボくんが一人で行きそうな場所。それ以外も、とにかく思い当たるところはすべて当たった。
そして、彼はどこにもいなかった。
初めからいなかったのかもしれない。幾度となくそう考えたが、その都度、部屋の壁にピンで留められた地図がそうではないと私に教えてくれる。
くしゃくしゃだった紙面を伸ばして、四つに分かれた海を説明してくれた、幼い指。それは確かに存在していたはずなのだ。たとえ、私以外の人間には見えなくとも。
「ロスがどうとかはともかく」
有希の声だった。
私は口いっぱいのいちじくの風味を飲み下し、目を上げた。
「その幽霊?……は、話を聞いたかぎり、元の世界ってやつに戻ったように思えるけどね」
「やっぱりそう思う?」
「そりゃあ……それ以外ない流れかと」
コーヒーカップへ手を伸ばしながら、「確かにね」と首肯する。
「その通りなんだけど、なんだか急で……」
「祟られる前でよかったじゃん」
「……サボくんはそういうのじゃないし」
「はいはい」
呆れ顔の有希が腕時計に目をやり、席を立った。仕事へ戻る時間らしい。バッグを肩へかけながら私を見る。
「幽霊贔屓もほどほどにね。……お会計、本当に甘えちゃっていいの?」
「もちろん。急に呼び立ててごめん」
「いいよ、面白い話聞けたし。それじゃご馳走さま、今度はゆっくりご飯食べようね」
コートを翻し遠ざかる有希の背中を見送り、私は卓上の皿へ視線を落とした。食べかけのタルト。
(サボくん、甘いものも好きだったし、喜んで食べただろうなあ……)
そう考えると、胸がきゅっとした。ここ数週間何度も抱いた気持ちだ。
サボくんがいなくなって、とても寂しい。
すっかりしおれた心地のまま、タルトにフォークを突き刺して、口へ放り込む。口内に広がるバターの濃い香りが、心のすきまをより強調する気がした。
◇
スーパーのビニール袋を両手に下げ、マンションのドアを開いた。室内は暗い。
「ただいま……」
か細く言ってみたけれど、やはり何の返事もなかった。もうため息すら出ない。パンプスを脱ぎ取り、両手の袋を廊下へ放り投げると、沈む気持ちとともにずどんとベッドにダイブした。スプリングがぐわんぐわんと唸る。
誰もいない部屋。その端々にサボくんのいた名残りがある。
たとえば、壁に飾られた地図やいくつもの写真、テレビの脇に置かれたサボくん用の携帯ゲーム機。ベッド横のデッドスペースにあるトランプは、何度やってもサボくんの勝ちだったっけ。幼い彼はなかなか智略に富んでいて、いつも私を驚かせてくれた。
いたるところにある思い出。それに、今日もまた買ってしまった二人分の食料だって、サボくんがいた証のひとつだ。
(食材、どうしよう……冷蔵庫はもう作り置きでパンパンなのに……)
熱くなり始めたまなじりを抑えるように、両腕を目の上で交差させる。
遮った視界に反し鋭くなる聴覚が、外で行き交う車の音をつぶさに拾う。室内に満ちているのは、しんと佇む静寂と──…。
なにか、知らない音がする。
はっとして上体を起こした。薄暗い室内を見回しても、音が出るようなものはない。窓から射し入る街灯の光が、立ち並ぶ家具の輪郭を漠と浮かび上がらせるばかりで、目立ったものなどなにひとつ。
それでも、確かに音がする。……波の音だ。
もう一度、今度はゆっくりと室内を見渡す。観葉植物、テレビ、ドレッサー。それから写真の飾られた壁へと目を移して、「あっ」と声が漏れた。壁が光っている!
光っていたのはあの地図だった。
地図の中央、小指の先ほどの淡い光。耳をそばだてれば、そこから確かに潮騒の音がする。手で触れようとして、迷った。
漫画や小説によくある展開では、これに触れればなにかがおきる。たとえば、異世界へ飛ぶとか。その予感は、次第にけたたましくなる波音や、地図へと伸ばした指先からも、ひりひりと感じている。
それでいいのだろうか。
家族、友人、仕事。それらを捨てて飛び込むほどのものが、この光の先にあるのだろうか。……わからなかった。
地図上の眩い染みがとうとう紙面いっぱいを覆う。またたく閃光。
なんだか嫌な予感がする。そう思って、足元へ目をやれば、なんと私の体までびかびかと発光していた。そんな馬鹿な。
「え、うわ、ちょっと待って!まだ答え決まってないんだけど……!」
叫びはむなしく、光は私のつま先から髪の毛の一筋までを覆った。もはや何もかもが白い。
どさり、なにかが倒れ込む音を背に、私の全身は宙へと浮いた。
目を開ければ、そこは一面の海だった──。
……などと言えればロマンチックだが、現実は違った。
目の前には、いかつい顔をしたスキンヘッドの男。その背後にも男、男、これまた男。みな一様にカタギでなさそうな面相だ。
左右に目を走らせれば、ここが木壁で囲われた狭い一室だとわかる。部屋の両隅にはいくつもの木箱が積まれていた。
「なんだあ?お前」
目の前のスキンヘッド男が唸った。怖い。びくりと体を縮こまらせて、上目遣いに男を見る。
すると、男もまた怯えた顔で私を見ていた。
「何だって、おめェ、体が透けてんだよ!?」
「……えっ?」
かくして、新世界での生活が幕を開けた。