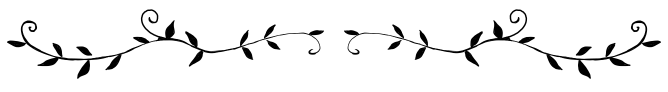いつも通りの休日。ふたり手を繋いで遊びに出て、隣ではサボくんがささいな出来事で喜んだり、驚いたりして。ひととおり堪能したあとは、家へ帰り、ご飯を食べ、同じ布団で眠る。そんな一日になるのだと思っていた。
私は彼と過ごすこの日々にすっかり慣れきっていた。だから忘れてしまっていたのだ。
突然現れた存在ならば、突然消えてしまう──という可能性だって、ひとしく存在してしかるべきだという事実を。
そのことを、今では強く後悔している。
「よっ!おはよ、ナマエ!今日はねぼすけなんだなァ」
ベッドの上。かけ布団にくるまって惰眠をむさぼる私を起こしたのは、サボくんだった。唯一の同居人だ。
彼は布団ごと私の上に腹ばいに乗ってきて、ニコニコといつもの笑顔で私の顔を覗き込んでいた。窓から射し込む太陽の光よりもずっと眩しい笑顔だ。
「……おはよう、サボくん。さっそくだけど、降りてくれないかなあ……」
「んあ?おれ、重てェか?」
「軽いけど。寝起きの顔を見られるのはちょっと、恥ずかしいというか」
これで私も女なのだ。子供に言うようなことでもないとは思いながらも、一応主張してみる。
「ふーん?おれは気になんねェけどな。いつものナマエだろ」
不思議がりつつも素直にしたがってくれるのが、サボくんのよいところだった。
突然起こされただけあって、正直まだ眠い。せっかくの休日なので、堕落的に過ごしたい欲求もある。……あるけれど、教育的理由でそれをするのははばかられる。
私は渋々洗面所で顔を洗い、パジャマから部屋着へ着替えた。
「ご飯、いつものでいい?」
「おう。ナマエのメシならなんでも。全部うめェからな」
ホットケーキにヨーグルトという簡素な食事は、サボくんの豪快な食べっぷりにより、すぐに終わった。
食後の紅茶を飲むサボくんが、「なあ、今日はどっか連れてってくれるんだろ?」と嬉しそうに切り出したので、私もそういえばと週半ばに交わした約束を思い出す。
「遊園地へ一緒に行く約束だったね」
「テレビで宣伝してたとこ?」
「そことは違うところだけど……でも、ジェットコースターとか乗り物もお化け屋敷もあるし、楽しめると思うよ」
「そっか!すっごく楽しみだ」
そう言って笑うサボくんはとっくに身支度を終えていた。私はといえば寝起きだったので、はしゃぐサボくんを横目に着替えをして、化粧をすべく鏡と向き合う。
化粧をする私をサボくんはいつも興味深げに眺めている。手を動かすたびに少しずつ変化するこの顔が彼には面白く映るのかもしれない。そう考えると、なんだか複雑な気分だ。
支度を終えたサボくんと私は、電車を乗り継いで目的の場所へ来た。
こじんまりとした遊園地だが、ここならばサボくんを見失うことはないだろう。それに、子供でも搭乗可能なアトラクションが比較的多いのも嬉しい。まだまだ背の低いサボくんであっても十分に楽しめるに違いない。
じっさい、かなり楽しめたようだった。
入園するなりあれもこれもと目移りするサボくんは、結局全制覇を決めたらしく、目に付いたアトラクションに片っ端から乗っていった。絶叫ものだろうが一切怖がらず、それどころか「すげェ面白かった!な、おれもっかい乗りたい!」などと瞳を輝かせ私の手を引くので、絶叫ものがあまり得意でない私は内心冷や汗ものだった。
そうしてひと通りのアトラクションを満喫したサボくんと、よれよれになりつつあった私は、園内のカフェでひと息つくことにした。
冬が迫っているとはいえ、天候がよい日などは汗ばむこともまだ多い。この日も気持ちのよい秋晴れだったので、私たちはテラス席に座った。たまに吹くそよ風が、汗のにじむ額に心地よい。
「遊園地ってすげェ楽しい!おれ、あのジェットコースター気に入ったよ」
「三回も乗ったものねえ……」
「あんな早く動くのりものがあるんだな。クルマってのもビックリしたけどさ」
「サボくんの世界にはこういう乗り物ないんだっけ?」
巨大ホットドッグにかぶりついていたサボくんが、こくりと頷く。頬にケチャップがついている。私は手を伸ばして彼の頬を拭った。
「ん、ありがと。……そうだなあ。おれの知る範囲だとなかったよ」
「そうなんだ。本当にこっちとはずいぶん違うんだね」
「ちょくせつ見せられたらいいんだけどな」
「そうだね。不思議なものがいっぱいあるみたいだから、確かに気になるかな」
サボくんが話してくれた「あちらの世界」は聞けば聞くほど漫画や小説の中の世界のようだった。不思議な実の存在や、想像もつかないような生き物の数々には興味をそそられる。けれど。
「でも海賊がたくさんいるんでしょ?ちょっと怖いな」
「ここは平和だもんな」
「戦争がないわけではないけどね。この国は特に平和だから」
「んー……」
大きな口を開けて、最後のひと口を頬張ったサボくんは、少しだけ考えるそぶりを見せたあと、ごくりと口の中のものを飲み下した。コーラの入った紙コップを持ち上げながら「それなら」と言う。
「ナマエがおれの世界に来ることがあったら、おれが守るよ」
「えっ、サボくんが?」
「うん。しょうじき今はそんなに強くないけどさ、これからうんときたえて強くなるつもりなんだ」
私は思わずサボくんをまじまじと見た。未成熟のちいさな体。とてもではないが強いサボくん、というのは想像がつかない。とはいえ気持ちは嬉しかった。
「頼りにしてるね」
「おう!任せとけ」
得意げに胸を張るサボくんになごんで、私も笑い返す。
通りすがりのカップルの会話が耳に飛び込んできたのは、ちょうどそのときだった。
「ねえ、あの席なんだか変じゃない?」
声のした先へ目をやると、学生だろうか、華やかに着飾った女の子が隣の同年代と思しき男の子へ、眉を潜めながら話しかけている。
「だって遊園地なのに一人でさ」
「友達とはぐれたとかじゃねえの」
「だとしても、さっきから一人でずーっとぶつぶつ喋ってるんだよ。絶対おかしい」
間違いなく私のことだった。
カップルは私の視線に気がつくと、そそくさと立ち去っていき、あとに残された私達のあいだには気まずい沈黙が落ちる。
言ってしまえば、いつものことだった。
サボくんと出会ってすぐの警察官に始まり、これまで散々浴びせられてきた類いのまなざし・言葉だ。そして、私はこれをとっくに受け入れている。
しょせん他人である。危害を加えているわけでもなし、遠巻きにあれこれ言われるのがせいぜいで、そんなていどのことでサボくんを部屋に閉じ込めてしまうのは嫌だなあ、と思ったのだ。
それなので、たった今のカップルのやり取りも、私にとってはどうでもよいものだったのだが。
サボくんはそうもいかないようだった。さきほどまでの明るい表情はどこへやら、すっかりしょげ返っている。
「やっぱりさ。おれと出かけるの、やめたほうがいいよ」
「私は気にしてないけどな」
「……おれは、おれのせいでナマエが悪く思われんのはいやだ」
「うーん……」
歳のわりに大人びた気遣いができるのが、サボくんという子だった。
私は空気を変えようとつとめて明るい声を出した。
「それより!おなかもいっぱいになったし、次はどこに行こうか?お化け屋敷はまだだったよね」
「……いや、いいよ。……もうすぐ日も暮れるだろ。そろそろ帰ろう」
確かに、秋の日暮れは早い。太陽はとうに中天から傾き、その色を濃くしながらゆっくりと西へ下っていた。
「……じゃあ、最後に観覧車に乗らない?ここの観覧車有名で乗ってみたかったんだよね」
「でも」
「一個くらい私が乗りたい乗り物に付き合ってほしいなあ」
少しだけ悩んでから、サボくんはこっくりと頷いた。
観覧車は順番待ちの行列ができていた。時間帯の関係もあるだろう。黄昏どきの景色はロマンチックなムードが漂う。じっさい、列に並ぶほとんどがカップルだった。
私達の順番が回ってきたのは、折りよくもその黄昏のさなかで、ゆっくりと上昇していくゴンドラから見える街並みは、一面オレンジ色に染まっていた。熟れきった太陽は遠くに見えるビル群のはざまへと沈んでゆく。
サボくんはイスに膝立ちになり、両手をガラスへつけたまま眼下の景色を眺めていた。その顔に浮かぶ笑顔にさきほどまでの暗さはなく、ほっとする。
「どんどん高くなるなァ」
「てっぺんはかなりの高さになるって。今よりずっと遠くまで見えるはずだよ」
「へえー!」
感心したような声のサボくんが、私達の先をゆくゴンドラを見上げる。途端、ぎょっとした顔になった。
「どうしたの?」
「あーっと、その……」
煮え切らない返事だ。なんだろうかと首をひねりながら視線を追って、すぐに得心した。頂上に達したゴンドラのなか、カップル達がキスをしている。
私は苦笑した。乗り物の選択を誤ったようだ。
「忘れてたけど、この観覧車にはジンクスがあってね。いちばん上にきたときキスをすると、永遠に結ばれるという……」
よくある類のものだ。しかしながら、説明するのはなにやら気まずい。
いたたまれずに目を逸らしていると、サボくんはいたって平静な様子で「ふうん」と納得した。
「ナマエもこういうの好きなのか?」
なんとも答えづらい質問だった。私が返事に詰まっているあいだに、ゴンドラは着実に上へ上へと昇っていく。
「……まあ、好きかどうかの前に、今は恋人がいないし」
言明を避けようとした結果、いらないことを言ってしまった。内心頭を抱えていると、サボくんは考え込むように顎先を指で撫でる。
ごうんごうん、と低い機械音をたてながら、ゴンドラはなおも昇っていく。ずいぶん見晴らしがいい。もう間もなく頂上に達しそうだ。
すっかり足元へ小さくなった遊園地を鳥瞰していると、
「ナマエ」
サボくんの声。すぐ側からだった。
振り向こうとした私の頬に、ふいにやわらかい感触が落ちる。視界を遮る影。それがゆっくりと離れていくのを、唖然としながら目で追う。……頬にキスをされた。
私に見つめられたサボくんは、茜色に染まる一面の空を背にして、照れたようにはにかんでいる。
「あのさ。おれが大きくなったらナマエのカレシになるよ」
「……彼氏って」
「カレシはカレシ。そんで、いちばん傍でナマエのこと守るんだ。……いい案だろ?」
思わず笑みがこぼれた。かわいらしい誓いだ。
「ありがと。それじゃあお願いしようかな」
「ほんとか?約束だぞ」
「約束、約束。サボくんかっこよくなりそうだもんね。楽しみにしてるよ」
「へへへ、ありがとな」
サボくんが大きくなるころ、私はとっくにおばさんだ。だからこの幼い約束が果たされることはないだろうけれど、サボくんがどんな青年になるのか、ひそかに楽しみだった。
今ですらこれだけかわいいのだ。将来はさぞかっこよくなるに違いない。……などと考えてしまうくらい、すっかり親馬鹿の心境だった。
ゴンドラが下り始めた。あれだけ鮮やかな光を放っていた夕陽も、今では地平線にか細くあるばかりで、あたりには夜の湿った気配がしのび始めている。
じりじりと近づくコンクリートの建物を眼下に、私は今晩の夕食のメニューへ思いを巡らせた。昨日、一昨日と洋食が続いたので、今日は和食にでもしようか。
「サボくん、今日のお夕飯なんだけどね」
言って、隣へ目をやる。けれど。
────誰もいない。
呆然とした。
あわててゴンドラ内を見回す。立ち上がると頭がぶつかるくらい、狭い密室だ。しかも今は空に浮かんでいる。隠れる場所などあるはずもない。
それなのに、あの小さな体が、イエローブロンドが、きらきらした瞳が、どこにもなかった。
「サボくん……!」
「ん?なんだ?」
返事があった。それもすぐ隣から。
けれど、声のしたほうを見ても、やはりサボくんの姿は影も形もない。
「サボくん、そこにいるの……?」
「そりゃあ。さっきからずっといるだろ」
なにもない場所から声がする。背筋がぞわりと粟立つ。
息を詰めて空間を凝視していると、驚いたことに、じわじわと人影が浮かび上がってきた。はかなげな輪郭は次第に表情を持ち、いかにも不安げに私を見上げる。サボくんだった。
滲むようにして姿を現したサボくんだが、その体ははっきりと透けている。本来なら見えるはずもない、ゴンドラの内壁の黄色が、彼の透けた体を通して分かってしまう。
「なあ、ほんとうにどうした?すっげェ顔してんぞ」
声が出ない。サボくんはますます怪訝そうな顔をした。
「……ナマエ?」
「……サボくん……体、透けてる……」
「は?」
きょとんとして自身を見下ろしたサボくんが、目を大きく見開く。
彼はその透明な両手をおそるおそる顔の高さまで上げ、確かめるように握って、また開き、それが間違いなく透けていることをしっかと見ると、色を失って唇を震わせた。
「これなんなんだ…?!おれ、いったい……」
「わからない……わからないけど」
混乱のまま無意識に腕を伸ばす。サボくんの肩に指先が触れようとして──通り抜けた。サボくんはいよいよ怯え切って「なんなんだよこれ」と、吐き出すように呟く。私はやはり返す言葉がなかった。
私たちの混乱が頂点に達したころ、彼の体に変化があった。透けているとはいえ、一応の色形を持っていたその身が、また薄くなっていくのだ。
「サボくん、」
もう一度手を伸ばす。サボくんが私を見る。
「ナマエ、おれ……」
彼の言葉はそこで途切れた。
私の手は何に触れることもなく空を掻き、そして、サボくんの姿は完全に消失した。
かすかな振動がして、ゴンドラのドアが開いた。
地上へ戻ってきたようだ。薄ぼんやりそう考えていると、場違いに明るい笑顔を貼り付けた係員が、ドア口から顔を覗かせる。射し込む蛍光灯の光が目に痛い。
「お客様、ご降車ください。続けての搭乗はできかねます。再搭乗をご希望の場合は、改めて列にお並びいただき……」
係員にうながされるまま立ち上がった。腰をかがめて数歩進み、コンクリートの固い地面を踏む。
ゲートへ歩む道すがら、振り返って見たゴンドラのなかには、やはり誰の姿もなかった。
他人の目から見ればなんら不思議な光景ではないだろう。私は一人で観覧車へ乗り、一人で降りた。はじめからそう見えていたはずだから。
それでも確かに私はサボくんと一緒にいたのだ。ついさきほどまでは。それが今はどこにもいない。
サボくんは消えてしまった。
私の目の前で、間違いなく、消えてしまった。