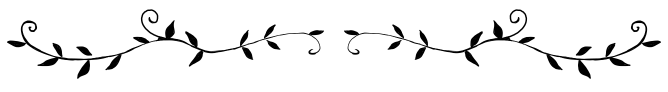そう吐き捨てた男に背中を押されて、私はつんのめるように冷たい地面に膝をついた。直後に響く、ガチャリという鉄扉の閉まる音。
振り返った先、鉄格子越しの男はやはりどこか怯えた目で、私を睨みつけている。
「気味の悪ィ女だ……体が透けてるなんてよォ。まったく、ゾッとするぜ……」
散々な言われようだけれど、もはや言い返す気力もない。無意識に触れた頬は、まだ殴られて間もなく、少しの腫れと熱を帯びている。
「まァ、てめェみてェな奴でも、欲しがる輩はいるだろうぜ。せいぜい、いい値段で売れるよう祈るんだな」
それで、言いたいことはすべて言い切ったらしい。
やがて立ち去った男の背中を見届けてから、私は改めて辺りを見回す。
ここはいわゆる地下牢だった。
十畳ほどの薄暗い空間は削り出された石壁で囲われ、明かりもない天井から突き出した鉄柵は、剥き出しの地面へ向かって長く伸びており、中に閉じ込めた者を逃すまいとする黒い檻そのものだった。
まるで映画の中にいるようだ。この場所も、ここに来るまでの経緯も、すべて現実味がない。
あの謎の光に包まれた直後、顔を合わせた男達は、ならずものの集団だった。彼らは突如として現れた女に、ご自慢の暴力を見せつけてくれた。
頬と鳩尾にパンチと蹴りを一発ずつ。あの巨体から繰り出される威力は生半なものではなく、抵抗する気など起こらなかった。
私は言われるままに男に従って、こうして自らの足で、地下牢へとやって来たのだ。
ここがどこなのか、なぜ体が透けているのかも、わからないままに。
(そりゃあ、そう簡単にはサボくんに会えないだろうとは、わかっていたけど……)
それにしたって、あんまりだと思う。
人から殴られる感触など、今日この日まで知らなかった。痛くて、惨めな気持ちだった。
地面に膝をついたままうなだれていると、ふいに背中を叩かれた。
「お姉ちゃん、だいじょうぶ……?」
女の子。七つぐらいだろうか。擦り切れたワンピースから覗く両手足は棒のように細く、顔はやつれている。
痛ましい見た目だったが、それよりもなお目を惹いたのは、頭に生えているうさぎのようなふかふかの耳だった。獣耳。
動物的な長耳を凝視していると、うさぎの少女は慌てたように私の背中をさする。
「大丈夫?あの人達、とっても乱暴だよねぇ……」
「あ、ええと、大丈夫だよ。ありがとう。……あの、その耳って」
聞いてから、しまったと思う。初対面で不躾だっただろうか。
伺い見た少女はけれど、きょとんとしたあと、「ああうん、これねぇ」と笑いながら耳をつまみ──なんと外してみせた。
「偽物なの」
「えっ!コスプレ……?」
「ううん?なんだかね、つけてろって」
スキンヘッド男は変態なのだろうか。
内心ざわついていると、「それより」と少女が首を傾げた。
「お姉ちゃんも捕まえられちゃったの?」
お姉ちゃんも、ということは、少女も同じなのだろう。
私は頷いた。
「そうみたい。……あなたはここがどこなのか分かる?」
「ううん……。島に着いてからすぐ、ここに閉じ込められたの……」
冬島のどこかだってことしか、分からないの。
そう言ってうなだれる少女は、街中で買い物をしている最中、両親とはぐれた隙をついて拐われてしまったのだと語った。そして先ほどの男達は、この海では悪名高い奴隷商人なのだと。
「少しでも隙を見せると女子供を捕まえて、天竜人やお金持ちの人に売るの。どれだけ抵抗しても、へっちゃらで、力づくで。それであたし……」
それきり、少女は涙ぐんで俯いた。
少女の右足には、奴隷の証として、重い鉄枷がはめられていた。そして私の右足にも、同じものがある。
◇
奴隷商の男が朝晩に運んでくる食事は笑えるほどに粗末で、その日はカビの生えたパン一切れと水だった。表面に浮くカビをちぎって地面に捨て、残ったパンに齧り付きながら、私は考える。
どうにかここから、逃げ出せないだろうか。
黒い鉄柵の隙間を抜け出し、見張りのいる階段を一目散に駆け上がり、この秘密基地めいた施設からの脱出……。
可能なのではないか、というのが、私の出した結論だった。
なぜなら今の私は、普通の人とは少しばかり違う。食事のせいでカビ臭くなった唾を無理やり飲み下すと、パンくずのついた手をかざすように、目線の高さまで上げて見た。
指先はほのかに透けていた。
「透けてるねぇ」
ちょこん、と体育座りの格好でパンを食べていた、うさぎのミリィちゃんが、横から私を覗き込みながら言った。
「そうなの」と、私は微笑んで返す。
「理由はわからないけど、なんだか、透けるようになっちゃって」
「すごぉい!悪魔の実の能力かなぁ?」
ミリィちゃんの瞳が好奇に輝く。劣悪な環境でもはしゃぐことを忘れない彼女は、存外、のんびり屋なのかもしれない。
それにしても、悪魔の実。名前そのものはサボくんから聞いたことがあるが、どうだろうか。そもそもこちらに来て何かを食べるより先に、体は透けていた。
「うーん。たぶん違うと思うけど……」
「ふうん……?」
首を傾げる少女の隣で、私はまた手に目をやる。
半透明のゼリーのように透けている指先だったが、肩へ向かうにつれてしっかりとした実体を持ち、触れてみれば肉感もある。足枷は外せそうにない。
観覧車でのサボくんのように触れられなくなるには、もっと透明になる必要があるのだろうか。
もしこれを自在に操れるようになれれば、あるいは──。
◇
今日も成果はなかった。
あれからずっと、腕をさすったり力を込めたり、逆に抜いてみたりとあれこれ試してみたけれど、肘から先以上はてこでも透ける気配がない。
そればかりか、事態は悪化していた。
ミリィちゃんに買い手がついてしまったのだ。
買い手が決まったのは昨日のこと。
スキンヘッドの男は突然、見るからに不健康そうな眼鏡男を伴って地下牢に現れ、両手を揉みしだきながらこうのたまった。
「これが先ほど言った半ミンク族です。どうです、可愛いもんでしょう」
らしくもなくへいこらしている。
眼鏡男は「ふうん」と鼻を鳴らしながら、スキンヘッドの指差したミリィちゃんをじろりと見た。
「話と違うな。随分と見すぼらしい」
「へえ。そいつはちょっと、寒さに弱いのかも知れやせん」
「品質管理がなってないんじゃないか」
「なあに、ちっとばかしいい餌を与えてやりゃあ、すぐに毛艶もよくなりますよ。……ほら、立て!」
スキンヘッドが牢屋に入って来て、ミリィちゃんの腕を引き上げる。言われるままによろよろと立ち上がるミリィちゃんの背中をバンと叩き、「おら、てめェ」スキンヘッドが低く唸る。
「てめェのお客様だ。自己紹介しろ」
「……ミリィです……」
「ふうん……名前は言えるようだな」
「へえ。ちィと緊張してるようで。ひと通りは喋れますぜ。文字も書けまさァ。獣と言っても使い方は幅広く、損はさせやせんぜ」
「ふむ……」
耳を塞ぎたくなる会話だった。ふつふつとした怒りが腹の底から湧き上がる。
第一、ミリィちゃんは半ミンク族ではない。人間だ。ミンク族というものは戦闘種族でとても強く、ごろつき崩れの奴隷商人などに捕まるはずがない。
それでも彼女がそう扱われているのは、スキンヘッドに無理やりつけられた、擬似獣耳のせいだった。
奴隷をより高く売るための悪知恵。胸糞悪い話だ。
もちろん、抵抗はした。
ミリィちゃんが半ミンク族だというのは嘘っぱちだと暴露したし、顧客とやらに罵詈雑言を浴びせてみたりもした。
けれど結局、ミリィちゃんは連れて行かれてしまった。
そうして私は今、牢に入れられたときと同じくらい、ボロボロの風体で剥き出しの地面に横たわっている。
ひやりとした冷気が、血で固まったばかりの傷口を舐める。投げ出した四肢は相変わらず透けているが、まったく無意味なものだった。
◇
朝、晩、そしてまた朝。
差し入れられるカビのついたパンで細々食いつなぎ、数日。
異変が起きた。
牢の向こうの階段の上、外のほうから騒がしい音がする。
もたれていた壁から背を離し、立ち上がる。鉄格子に鼻先を突っ込み、階段を覗き込むが、何が起きているのかさっぱり分からない。
ただ、囚われてから一度もなかった『何か』が起きたことは明白だった。
目を閉じて、耳を澄ませてみる。
複数の人間がせわしなく行き交う足音。遠くに響く悲鳴。怒号のようなものも聞こえる。それに独特の乾いた短く高い音──。
これは銃声ではないだろうか?
もしかして、ここは今、襲撃されているのでは。
だとしたらチャンスだった。この混乱に乗じてなんとしてでも逃げ出したい。
しかし牢屋の鍵は手近にはありそうになかった。大抵の場合、スキンヘッドの仲間の誰かが持っているのだが、この場には誰もいない。そうなると──。
私は自身の体を見下ろした。ゼリーのように半透明な指先や爪先。
やはりこれしかなさそうだ。
目を閉じて、サボくんが消えたときの光景を思い出す。
一面の夕焼け。突然に消えたサボくん。滲むように姿を現して、この指は彼の姿を通り抜けて、彼はまた溶けるように消えていった……。
ゆっくりと目蓋を開いた。
手のひらを上向けて、目線の高さまで上げ、透かすように眺めてみる。
……心なしか、先ほどより色が薄くなったような。
恐る恐る鉄枷のついた片足を動かしてみた。するりり。足首が黒い鉄を通り抜ける。
「やった……!」
これなら鉄柵も通り抜けられる!
牢を出てからは、ひたすらに走った。
鉄格子を抜け、階段を上がり、迷路のような廊下を右往左往しながらも、なんとか出口へと向かうべくひた走る。
恐ろしいことに、廊下には幾つもの伏した人の姿があった。生死はわからない。確認する勇気はなかった。人の背中をいくつも飛び越え、闇雲に駆け抜けた。
そうしてたどり着いた扉を押し開けば、久しぶりに見る陽光が両目を焼いた。
光に目を眩ませていると、ふいにこめかみに冷たい感触がした。それから喉元を背後からぐいと圧迫する腕。
どうにか目線だけを動かして、状況を悟った。
スキンヘッド男に羽交い締めにされ、なおかつ銃を突きつけられている。
男はかなり錯乱している様子だった。銃のセイフティは下ろされ、トリガーに指をかけている。人質を取りながらも、交渉もせずに殺すつもりらしい。
私の人生、ここまでなのか。
諦めのような虚脱に身を委ねて、私はそっと目を閉じた。撃たれると痛いのだろうか。どうせ死ぬならせめて穏やかに死にたい……そう願いながら。
銃声の乾いた音が辺りに響く。間もなく訪れるであろう激痛に身構えるものの、しかし結果として、銃弾はこの身を擦りもしなかった。
切り裂くような突風と、ふわりと全身が宙に浮く感覚。恐怖に丸めた背中を支える、あたたかい何か。
反射的に開いた視界にはもう、私の首を圧迫していた男の腕はなく、気がつけば私は誰かの腕の中にいた。
「もう大丈夫だ」
頭上から降ってきた力強い声を仰ぎ見る。
逆光を背負った見知らぬ顔が、間近にあった。
光を反射して輝くイエローブロンド。意志の強そうな瞳は透けるように青く、形のよい唇は余裕のある笑みを浮かべている。
と、吹き荒んだ突風が、彼の髪や襟元にゆるく巻かれた白いスカーフを揺らした。
「おっと……」
革手袋をはめた手が、黒いシルクハットの前鍔を掴む。殺気立ったこの戦場においては、場違いに優雅な仕草だった。
呆然とする私を腕に抱きかかえたまま、彼が口を開く。
「おれは革命軍だ。お前達を助けに来た!……少し立ち回るぞ、このまま捕まってろ」
革命軍とは? と聞き返すより早く、彼が動いた。
左右から放たれた小銃の弾丸をひらりと避け跳躍。あっという間に敵兵の背後に立つと、その背中に蹴りを落とす。
敵兵が倒れると同時に、すぐに他方からサブマシンガンの咆哮が聞こえたが、それすらもたやすく躱し一人、二人と沈めていった。
やがて彼は周囲に敵影がないことを確認すると、
「向こうにおれの仲間がいるから、そこに……」
腕の中の私に笑いかけ、それから驚いた様子で目を見開いた。
「……ナマエ……?」
聞き馴染みがあるどころではない、確かに私の名前を呟いたハスキーボイスに、今度はこちらが目を丸くする番だった。
青い目はなおも私を凝視している。
「まさか……。いや……だが、この顔は間違いねェ」
「あの……どうして私の名前を?」
思わず尋ねると、返ってきたのは満面の笑みだった。
「おれだよ、ナマエ。サボだ。……ずっと、会いたかった」