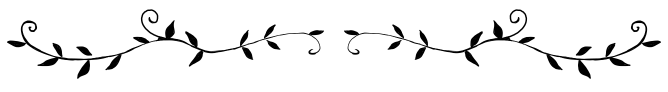たとえば、仕事帰りに寄るスーパー。二人分の食料を、それもバランスを考えて選ぶようになった。何がなんでも残業せずにすむよう仕事効率の見直しをしたし、それでも帰りが遅くなるようなら必ずサボくんに連絡した。
「ミョウジさん、彼氏でもできたの?」
なんて同僚にからかわれたりもしたが、まさか本当のことを言えるはずもなく、適当に笑うしかない。
やることは増えたが、それが負担かといえばそうでもない。どれだけ仕事でくたくたになって帰っても、マンションのドアを開くとサボくんの笑顔がある。
────おつかれ、ナマエ。うっわあ、ずいぶんくたびれた顔してんなァ! おれ風呂入れといたからさ、入って来いよ。うん、この間やりかた教えてくれたろ、ちゃんとできたよ……
そんなふうに労られて癒されないはずがなかった。
そのサボくんだが、適応能力においては彼のほうが私よりも数段上だった。見ず知らずの場所、そのうえ私以外の人間からは認知されない。そんな誰しもが不安になるような状況だというのに、すんなりとこの生活に馴染んでいる。
つらくないのかな、なんてさりげなく私が訊ねたときなど、屈託なく笑ってこう言うのだった。
「だっておれはおれだろ。ここがどこだろうが、他の人からおれが見えなかろうが、それだけは確かだ」
驚く私にサボくんはまたひとつ笑って、更に続ける。
「それに、ナマエがいるから。おれ、ナマエと出会えてよかったよ。そうでなきゃひとりぼっちになるところだったもんな。……ありがとな、ナマエ」
彼はほんとうに良くできた子供なのだった。
……ともかく、私達は快適な二人生活を送っていた。サボくんはよく私を手伝ってくれたし、私もサボくんが日中暇しないようさまざまな娯楽を用意した。
なかでも彼がことさらに喜んだのは世界地図だった。手渡すなり彼はすぐに読み込んで、今は旅行者向けのガイドブックと照らし合わせて眺めている。
私はそんなサボくんの肩をポンと叩く。
「サボくん、ちょっといいかな」
サボくんは寝転んだまま本から顔を上げた。パチパチと目を瞬かせているのは、読書に集中しすぎたせいだろう。
「もちろんいいけど。どうかしたか?」
「渡したいものがあって。手を出してくれる?」
「ん?こうか?」
広げられたサボくんの小さな手に、しゃらり、音を立ててあるものを載せる。部屋の合鍵だ。おまけで錨をモチーフにしたキーホルダーもつけてある。
「鍵……?」
サボくんが首を傾げる。私はひとつ頷いて返した。
「そう、鍵。もちろんこの部屋のね。好きなときに出入りできるように」
「おれこの部屋からかってに出ていいのか?」
「……その言葉はなんだか、誘拐犯の気分になるな……」
「あ、悪ィ」
「いやサボくんは悪くないよ、こっちこそごめん」
私は咳払いして話を元に戻す。
「今までたまに私と一緒に出掛けるだけで、日中はずっとこもりきりだったでしょ。でもサボくんはしっかりしてるし、基本他の人に見えない、触れないし、少しだけなら一人で行動してもいい……と、私は思う。ただいくつか条件があって」
サボくんは居住まいを正して私の言葉に耳を傾けている。
「行っていいのはいつも一緒に行く公園と、すぐそこのコンビニと本屋さん。それより遠くは駄目。車にはよく気をつけて。あと、もしサボくんの姿が見える人がいたとしても、ついていかずにまずは私に話してね。それから……」
「……ぷっ」
つらつら話す私にサボくんが吹き出した。きょとんとする私にサボくんは「ごめん」と謝りながら、なおも声をたてて笑い続けている。
ひとしきり笑い終えたサボくんは、目尻に滲む涙を指先でぬぐいながら、もう一度「ほんとごめんな」と言って笑顔のまま眉尻を下げた。
「あのさ、おれ、ずいぶん大事にされてんだなと思って」
「……口うるさすぎるかな。ごめんね。今だってほとんど部屋に閉じ込めてるし……」
「いや」
サボくんが首を振る。
「いいよ、そのくらい。だっておれのこと心配してくれてるんだろ? ……そういうのあんま慣れてないけどさ。でもすげェ嬉しいよ」
そう言ってはにかむサボくんに、私はなんだか胸をつかれる思いがした。つい黙りこむと、サボくんが少し迷ったように口を開く。
「おれは家出したって、前に話したろ。それって親のせいでさ。……あの家じゃおれはおれとして見てもらえなかった。あれやれこれやれ、めいれいだけして、できなきゃ罵られて……」
目を伏せながら、静かに続ける。
「おれをつうじて得られるかもしれない権力しか、見えてないんだ……」
どう声をかければいいのか。悩む私にサボくんはへらりと笑ってみせ、「へんな話してごめんな。鍵、ありがと」指先でつまんだ鍵をシャラシャラと左右に揺らした。
私はそんな動作ごとサボくんを抱きしめた。短い声を上げて驚くサボくんを包み込むようにして、腕に力をこめる。小さな体だ。胸が熱くなった。
「私はサボくんが大事だよ」
「……うん」
「大事だし、心配だからね」
よく覚えておいて。
そう言ってからそっと身を離すと、サボくんは私をじっと見つめて、それから黙って頷いた。青い瞳がいつもよりきらきらと輝いている。
「……ええと。それじゃ、ご飯作ろっか……」
私は急に照れ臭くなり立ち上がった。サボくんはキッチンへ向かう私の腰にじゃれるように抱きつきながら、へへへ、と小さく笑っていた。
◇
「ナマエ、見てくれ!」
「うん?」
嬉しそうに私を呼ぶサボくんはカメラを持っている。私は屈み込んでカメラのディスプレイを覗き、そこに映る画像を見た。雨上がりの公園と、その空にうっすらとかかる虹。なかなかにロマンチックな景色だ。
「あ、すごい! よく撮れてるね」
「へへ、そうだろ。今日のベストショットだ」
そう胸を張るサボくんはすっかり一人の外出にも慣れ切って、私の言い付け通りの狭い範囲に限られながらも、散歩を楽しんでいるようだった。
私以外の人には見えないサボくんがカメラを持つと、周囲からどう見えるのか。結論から言えばカメラごと見えない。しかし原理はわからない。私は考えることをやめた。世の中は理解できない事象で溢れている。
サボくんはそうして日中出掛けるか、あるいは本を読んだりゲームをして過ごし、夜私が帰宅してからはその日の出来事を嬉しそうに話してくれた。
それから私達は一緒にご飯を食べ、一緒にお風呂に入り、同じ布団で眠る。そうした日々が当たり前になったころ、それはある日突然起きたのだった。
サボくんが消えた。