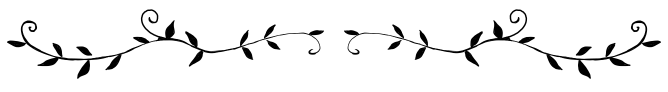行くあてもないままにトボトボ歩く私の横で、サボくんはだんまりと下を向いていた。話しかけたというよりは自問自答だったため、返事がなくても気にはならない。
「誰もいないなんて、そんなことは」
ないはずだった。
見下ろせば確かに、私の胸下ほどの高さに金色の髪がある。朝の陽射しを受けてきらきらと輝くさまは秋の稲穂のように美しく、見紛うはずもない。
しかしながら、いざ冷静になれば奇妙な点がいくつもあった。最たるものは先ほどの警察官の言動だが、それ以外の人々からの視線もおかしい。今だってそうだ。まさに今すれ違おうとする中年の女性は、サボくんと繋がれたままの私の左腕を、それは不思議そうに眺めている。
先刻、交番への道すがらにすれ違った男性も、子供連れの夫婦も、思い返せばみな一様に同じ反応をしていた。
そうして思索するうちに近所の公園へ辿り着いた。ひとまずベンチに座った私の横に、サボくんも座らせようとしたのだが、これが頑として従わない。どうかしたのかと顔を覗き込めば、プイッと逸らされてしまった。拗ねたようにひん曲がった口をようよう開いたサボくんが、恨みがましい顔で私を睨む。
「……帰りたくないって言ったはずだ」
うっ、と私は息を詰める。痛いところを突かれた。
「……そうだね」
「さっき帰そうとしただろ。おれ、いいって言ってねェのに」
「それは、うん。……ごめん」
約束を反故にされたんだから、そりゃあ怒るよなあ。
今更ながら思い出して、気まずさに目を泳がす。せめて彼が大人なら、私もこんな強行的な対応はしなかったのだけど。そんなことは言い訳だった。
サボくんの唇はいまや、彼にできる最大限でへの字に曲がっている。そんなサボくんの手を、私は両手でぎゅっと握った。
「約束守らなくてごめんね」
「……もうしねェか?」
「うん。次からはちゃんと、サボくんと話してから決めるようにする」
サボくんはしばらく私の目を探るように見て、それからニッと笑んでみせた。
「それならいいや。約束だな!」
そう言って歯を見せて笑うサボくんの顔を見ていると、とてもではないけれど、彼がこの場にいない存在だなんて思うことができなかった。
◇
私達はとにかくマンションへ帰った。昼食はパスタとサラダで簡単にすませて、食後のテーブルにはコーヒーと紅茶がひとつずつ。私はサボくんと差し向かってカーペット上に座り、居住まいを正してから、改めて彼の珍妙な話に耳を傾けた。
イースト・ブルーはゴア国。その高町。彼はそこで貴族として生まれた。
彼の知る世界というのは──実際にその目で見たのではなく、大半は書物で学んだ知識らしいが──海が四つに分かれていて、そこには海王類なる珍妙な生き物と、なによりたくさんの海賊が海という海に跋扈している。悪魔の実だとかいう、食べると特別な力を得られる果物がある。人魚がいる。巨人もいる。
そこまで聞いて、私は頭が痛くなった。
「それから──」
「サボくん、ストップ。一旦やめよう」
「どうかしたか?」
「どうかしたかって……。……確かにどうかしてるのかもしれない、私は」
なんたって透明人間、もしくは幽霊だか幻覚だか知らないが、そんな非現実的な存在とこうして話をしているのだから。
ぐるぐると煩悶する私を見て、サボくんが肩を落とす。
「……やっぱり信じられねェよな。おれだって正直わけがわからねェんだ。今だって夢でも見てるみたいでさ」
外はあっちもこっちも見たことないもんばっかだし。
ため息して話す姿に良心がちくちくと痛む。幼気な子供を落ち込ませてしまった。
「……サボくんが嘘を言ってるって思うわけじゃなくて、ただちょっと……現実味がないというか……」
それこそ彼の言う通り、夢でも見ているような。
気まずい沈黙が室内に落ちる。さほど厚くもない壁の向こうでお隣さんが掃除機をかける音。窓ガラスの向こうでは大型トラックが走り抜けていく。ぼんやりそれらの音に耳を傾けていると、
「あっ」
正面からの声。サボくんだ。見ればコートのポケットをごそごそと探っている。
「どうしたの?」
「いや、ポケットに入れといた地図がなくって……どこやっちまったかな……」
「あ、それね。そこにあるよ。洗濯するときにぐちゃぐちゃになっちゃうから抜いておいて……」
本当は検分がメインです。とはさすがに言わず、ドレッサー上に置き放したままの紙切れと硬貨を手渡す。サボくんはニッと笑うと「サンキュ」とそれを受け取り、とりわけ紙切れのほうを大事そうに眺めた。
「それがサボくんの世界の地図?」
「ああ。家出する前に本からここだけ破いてきたんだ」
「へえ……見てもいい?」
頷いて返すサボくんの手のなかで広げられた紙切れ──もとい地図へ目を向ける。
昨晩見たときには、奇妙な地図だ、としか思わなかったが、サボくんの話をきちんと聞いた今となっては、なるほどと思わせるものがあった。この地図は海が四つに分かれている。
「ほら、ここ。ここがイーストブルーで、ゴア国はこのへん」
と、小さな指が地図上を示す。指はつつつと紙面を滑っていき、ときおり動きを止めては、その都度サボくんの説明が入った。その語り口がまた驚くほど上手く、淀みなく話す幼い声には妙な説得力がある。
「……ほんとはもっと詳しい地図とかあればいいんだろうけどさ。でも、ま、こんなもんかな」
ひと通りの説明が終わったらしい。そう言って私を見上げたサボくんの瞳は、いかにも楽しげにきらきらと輝いていた。
「詳しいね。地図、好きなの?」
「ああ、好きだ。地図もそうだし本も。この世界はとにかく広くって、いろんなもんがあって……それになにより、そこには自由があるんだ!すげェよなあ……」
「自由……」
貴族に生まれた人間の気持ちは私にはよくわからない。映画や小説で得た知識がせいぜいで、それすらも階級社会での付き合いは大変そうだなあとか、ノブレス・オブリージュとかいう大層なものを彼らは背負っているのだなあとか、その程度の感想だった。
それでもこうして彼を見ていると、サボくんにとって「自由」がどれだけ大切なのかは、少しだけ理解できるような気がした。
しみじみ考えに耽る私をよそに、サボくんは世界に散らばるありとあらゆる不思議を嬉しそうに語り続けた。
結論から言えば、私は彼に絆された。だって彼は無害──今のところ私は祟られた気配を感じない──だし、聡明だし、なにより笑った顔がたいそう可愛らしい。可愛いは正義だと偉い誰かも言っていた。
サボくんと共同生活を営むにあたって、差し当たっては衣類と、最低限不便しないだけの知識を覚えて貰う必要がある。
衣服に関しては「着れるならなんでもいい」というので、ネットショップで彼らしい品の良く、けれどかしこまり過ぎないなものを。知識に関しては、文化や技術にいくばくの差異はあるものの、ただ部屋で過ごす程度ならなんら障りがないことがすぐに分かった。
そうしてひと通りを終え、夕食と入浴をすませたサボくんは、昨日買ってあげただぼだぼの服を着て、ベッドの上、更に言えば私の横で、布団を被って眠たげに目を瞬かせている。
「なあ」
電気を消した室内。控えめに響くサボくんの声に、私は微睡みから浮上した。暗闇のなか、薄ぼんやりと浮かぶサボくんの輪郭へ目をやって、私は「なあに?」と返した。
「おれさ、まだ名前聞いてない。なんて呼べばいいんだ?」
すっかり忘れていた。
「ごめん、名乗りそびれて。……私はミョウジナマエ。好きに呼んでくれて構わないよ」
「ミョウジナマエ……」
噛み締めるように復唱したサボくんは、それきり口を噤んだ。また微睡みの波が私を襲う。昨日といい今日といい、なかなかにハードな一日だったせいだろう。
「それじゃ、ナマエって呼ぶよ」
そう言ったサボくんの声はやはり囁くようで、私は返事をするかしないかの狭間で、ゆるやかな眠りへと落ちていった。