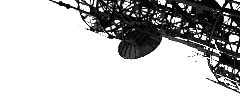
―野良猫の飼い方―
親指でツッとなぞれば、掌の下でびくりと細い首がはねた。
誰もいない屋上で本を広げてみたものの、隣に腰を下ろした男の視線が鬱陶しいせいで集中できず、それを注意しようとしたところ折原はニコニコと門田の両手でその首を器用に覆った、というのが現状を説明するに最も相応しいだろう。
この一連がいったい何を意味するのかを門田が問う前に折原は「官能的だろ?」と、カラカラと笑いだした。いったい何がそんなにおかしいのか、一向にその笑い声は止むことはない。ひとしきり折原に付き合った門田は、ふっと笑うのをやめたのを見届けるとどっと疲労した。
「本当、怖いやつだな、お前」
「そうかな」
「こんなに肝を冷やしたのは、久しぶりだ」
苦笑いする門田に、擽ったそうに微笑み返す折原の姿はどこか幼い。パッと離された両手がまるで自分のものではないかのように思えて、門田は掌をそっとこすり合わせる。自分の体温を確認しながら、先ほど触れたどくどくと脈打つ首筋の白さにゾクリと背筋を振るわせた。
「なに?寒いの?大丈夫?」
「ああ」
「あーあ、粟立ってるよ」
今度はその首に触れるべく伸ばされた指先を、門田の掌は勢いよく払いのける。ぽかんと驚いた顔をしてみせる折原の表情はおそらく作り物だろう。心的距離を測られている。そしてもしも可能であればまんまと利用する気でいるのが、なぜか門田には手に取るように分かった。
「あれ、どこでばれたんだろ。上手くいったと思ったんだけどな」
「俺は面倒ごとが嫌いなんだ」
「ふーん。そうか。残念だ。君はとても魅力的なんだけど。まぁ、仕方ないかな」
言いながら、そっと人一人分距離を開けて座りなおす折原は、さして残念がっているようには見えない。それにちくりと胸に何かが刺さったような痛みは、あまりにも不可思議な感覚である。少なからず傷ついているのか、とあまりにも打算的な相手の態度に門田は苦笑いを浮かべた。
「そんな、警戒しないでよ」
先ほどは毛ほどもないという顔していたくせに、打って変わって膝に顔をうずめながら、あーあとため息を吐く折原はどこか感傷的に見える。いったいどうしたというのだ、そう思いながらサラサラと靡く髪を梳くように頭を撫でてやれば擽ったそうに含み笑いが聞こえてきた。
「警戒してるのは、お前だろ」
「……」
「野良猫」
間をおいて、また、くふくふと猫が笑う。まるでごろごろと喉を鳴らしているかのようだ。
「餌が欲しいなぁ」
「俺に死ぬまで面倒見て欲しいって事か?」
「ナニソレ」
「野良猫に餌付けするときは、その猫が死ぬまで面倒見てやらなきゃいけないって知らないのか?」
「そうなの?」
「聞くな」
「そーか…。ドタチンに、一生ね…」
「…おい」
「うん、悪くない。悪くないよ、それ」
「冗談だ、馬鹿…」
「あはは!じゃあ俺、今日からドタチンの猫だから」
「お前それ死んでも人前で言うなよ」
「あははっははっあはははは!じゃあ静ちゃんに報告してくるよ!あいつ人間とは違うから!やばい!ちょううける!」
「バカヤロウ!それこそ一番めんどくせぇ奴じゃねぇか!」
先ほどまで手負いの小動物のように縮こまっていたというのに、ぴょんぴょんと飛び跳ねるように立ち上がった折原は十二分に機嫌が良さそうだ。何がそんなに嬉しいのか子供のようにはしゃいでいる。ふ、と門田は折原について今まで持っていたイメージは、勝手に噂で作り上げた折原像だったと思い立った。誰だ、折原イザヤが化け物だなんていった奴は。どう見たって普通の高校生じゃないか。などとボンヤリ頭の隅で考えていた、途端「じゃあ餌」といって唇を奪われ、瞬間的に、折原イザヤは化け物ではないが普通の高校生でもないと、考えを改めさせられるわけだが。
さて、とまた門田は考える。餌を与えてしまった以上、これから度々面倒ごとに巻き込まれるのだろう。意図しない口付けを思い出して、実際は自らが餌付けされたのではないかと頭を抱えながら染まった頬を隠すしかほかに、彼には術がなかった。
終わり