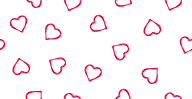
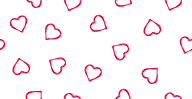
―ラブソング―
ソレは「生もの」扱いで折原の事務所に届けられ、自らを「サイケ」と名乗った。
折原イザヤは差出人が岸谷シンラであることとそれがアンドロイドであることを確認すると特になんの説明も要求せず安易に受け取り、そこで自己紹介と言う名の取り扱い説明のタイミングを逃してしまったサイケは、ただ主人が名前を読んでくれるのを待つ以外に術が無かった。しかし折原が例によって無関心を決め込んだため、その機会はいつまでたっても訪れない。彼にとってサイケの存在意義は、部屋のオブジェよりも希薄である。例えそれが自分と同じ容姿であり、奇跡と言っても過言ではないほど精巧に作られたアンドロイドだったとしてもだ。
そうであるにも関わらず、なんとも哀れなことにサイケには感情があった。さらには主人に対して、人間で言う三大欲求全てを注ぎ込むほどの愛情を持っている。だからこそ岸谷はソレを折原に送りつけた。痛烈な皮肉のつもりであったが生憎、サイケの使用目的すら知らない折原にはなんの興味対象でもなく、ただ「自分そっくりの悪趣味な人形が届いた」程度の認識しかない。ソレが可哀想だと感じるには、あまりにも認識が誤りすぎている。
だからといってサイケが折原からの接触を延々待っていたというわけではない。幾度か折原に手を伸ばそうとしたことは確かにあった。しかし何度話しかけても返答はなく、ようやっと口を開けば「あー、うるさい」「電源スイッチとかないわけ?」「介護施設に寄贈ってネットから出来たかな」そんな独り言を呟いて部屋から出て行ってしまう。彼は、サイケがただプログラムされた通りに音声を発しているのだと思っていたのだ。
サイケはそのつど、誰もいない部屋でボロボロと涙を零した。誰にも見てもらえないそれを流す意味を、人間ではないサイケはまだ理解していなかったが、勝手にあふれ出てくるものを止めることも出来ない。寒さを感じない体が、真っ暗闇の中でも昼間と変わらない視界が、ただひたすら憎かった。
「え?使ってないの?」
「使うって何?これセクサロイドだったりするの?」
それはちょっとあまりにも悪趣味じゃない?馬鹿にしたように笑う折原を前に、岸谷はただ「送りつけた」だけであったことをひどく後悔した。そろそろ打ち解けた頃合いだろうかと見計らって、折原宅を訪ねてきたものの、思っていた以上に事態は深刻なようだ。カップに口をつながら、ため息を吐くように「可哀想に」と呟いていた。それに聞き捨てなら無いのは勿論折原である。ため息を測れるほど、あきれ返られるいわれは無いとばかりに表情に不機嫌をあらわにする。
「へぇ、シンラは無機物にも同情することが出来るんだ?実に興味深いよ、ぜひそこらへん詳しく聞かせてくれないか。いったいあれのどこが可哀想だって?」
「…いや、今回は完全に僕が悪かった。謝るよ。この子には感情あるんだ」
「意味がよくわからないな」
「言ったままさ、この子には感情ある。そしてこの子はボッチの君を慰めるためにいるんだ」
「うわー。ごめんさすがにどん引いた、それ。何?じゃあ本当にこれを抱いて寝ろっていうの?あは!まーだ静ちゃん組み敷いたほうがましだね。あははは!想像したらゲロ吐きそう!」
「気持ちよくらりってるところ悪いけど、そうじゃない。僕がいいたいのはこの子は君が全てなんだってこと。ああ、そうだ使ってないなら丁度いい。この子の本来の使い方を教えてあげるよ」
そう、言われてしまえば折原にも断る理由は無い。寝室に追いやっていたサイケの腕を無言で引きながらリビングに戻ると、やっぱり岸谷は苦笑いで二人を見ていた。その、全てを見越しているといった顔つきが気に入らないので、よりいっそう折原は不機嫌になる。不機嫌と言っても平和島シズオを相手にしたときのような腹のそこから苛立つといった不機嫌さではなく、思い通りにならないことにぐずついた子供のすね方ではあるが。
しかしどうやらオロオロと不安げに岸谷を見るサイケには絶対的な効力があるようだ。好かれたい、愛されたいとその瞳は切々と物語っている。
「やあ、サイケこんにちは。じゃあ早速、何か歌ってごらんよ」
「…あ、うん。何が、良い…?」
「だって。イザヤ、何がいい?」
「いや、別になんだっていいけど。てかソレ歌うんだ?」
「うん…!サイケ、歌うの!イザヤ君のために、歌うために、いるの!」
「…ね?可哀想だろ?」
折原の返事を待たず、サイケはそっと歌い始めた。ただじっと折原を見つめながら、悲痛を訴えるかのように、歌詞に合わせてその表情を曇らせる。曲の歌詞は見当違いであるように感じられたが、自分に向けられていると思えばそうとしか聞こえてこない。
「わかるかい?イザヤ。この子はただ、君に愛されたいと歌っているんだよ。君に名前を呼んで欲しくて、君のそばを離れないんだ」
ダメ押しのように岸谷は折原に微笑んだ。なるほど、わざわざ彼が送ってきただけの事はある。精神的負荷で今にも心が折れてしまいそうだ。否、実際にはもう折れてしまっている。
歌い終わったサイケはぽつりそこに立っていた。感情をなくしたというより、何をしたらいいのかがわからないといった顔で岸谷と折原を見比べる。岸谷は来たとき同様ニコニコと笑っていたが、折原の方はといえば疲労困憊よろしく頭を抱えているではないか。とっさに謝ろうとしたサイケの声を遮ったのは、ほかでもない折原の呟きだった。
「……おいで」
「……」
「サイケ、おいで」
何かがサイケの背中を駆け抜けていった。
その言葉を、ずっと待っていた。たったその一言を、ずっと、ずっとだ。
「うぁあ…いざやく、あ、うう…!」
途端、サイケは涙が溢れてどうしようもなくなった。ぐずぐずと涙を拭いながら、折原の足元にぺたりと座り込む。本当なら抱きつきたいのだろう、顔に書いてあるといってしまえるほど分かりやすい表情で、サイケは折原のズボンの裾を遠慮がちに掴んだ。
「うん。そうか。そういうことか。どおりで君は温かいわけだ」
「いざやくん…、イザヤ君…」
「うん、ごめんねサイケ。俺が悪かったよ…ごめん」
よいしょ、とサイケを抱き上げた折原は、対面で膝に乗せるとそれをきつく抱きしめた。子供のような体温に、しゃくりあげる熱い息。ただ名前を呼ぶことしか出来ないサイケと謝りながら頭を撫でてやる折原に、岸谷は珍しいものを見たと口元を綻ばせた。
終わり
サイケに歌わせるラブソングが思いつかない件について。
サイケって何をうたうの?ぱひゅーむ?