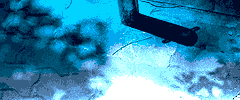
―救出劇―
「返してもらうよ」
単刀直入。岸谷シンラは平和島シズオに言い放った。
笑みを貼り付けたままではあってもその鋭い視線はどこまでも敵意を含み、平和島に対して苛立っていることを如実に現している。何度も何度も想定した事態を前に平和島はうっそりと微笑んだ。
「好きにしろよ」
用件はもう無いといった具合に平和島が後にしたソファーを、見つめる岸谷の視線の向こうには数日前の折原イザヤの影があった。彼は数日前、正確に言えば4日ほど前、この席に座り先ほどの平和島よろしく岸谷に微笑みかけていた。その折原がわざわざ岸谷家を訪れた用件は、なんとも単純明快である。
「死ぬかもしれないから、助けにきてくれないか」
自業自得だと、笑った自分がいる。それに対して彼は「わかってるさ」と笑顔で答えた。助けて欲しいけれど、助けに来なくても良いという意味を含んだ返答だ。そしてなんとも腹立たしいことに、岸谷が助けに来ることを知っていて、そう言う可愛くない物言いをしている。
「死因は?」
「さぁ、わからないな。でも犯人は人間じゃない」
「…それって、僕が助けに行ってもどうにもならないんじゃないかな。生きている確証がない」
「でもさ、あれは8年間も俺を殺すのに躊躇してきたんだ」
「だから殺されはしない?じゃあ、なんで僕に助けてなんていったのさ」
「…シンラ」
「……」
「大好き」
もう、何も言うことは無かった。
折原の依頼はただ助けにくること、たとえ死んでいたとしても助けに来ること。看取れというわけじゃない、けれど見捨てないで欲しい。例え、助けに来たことがわからない状態にあったとしても、だ。なんて理不尽なんだろうと、岸谷は苦虫を噛んだような顔をしたが、それを見た折原もひどく苦々しい顔をしていた。
「分かったよ。引き受ける」
「…ありがとう。さすが俺の友人だ」
「ただし、だ。君は絶対に生きていろ。僕は生ごみを友人だとは認めない」
「あは、ひどい言われようだな」
「僕は怒っているんだ」
分かるよ。
そう言って折原は岸谷の頬をそっと撫でた。勿論、嘘だ。折原にだってたった今岸谷が抱いているどこまでも禍々しい感情を計り知れるはずもないし、察することだって出来るはずがない。なぜなら折原が思うよりもずっと岸谷は折原を思っているからだ。それは友情と独占欲とセルティに対するものとは違った愛情が複雑に絡み合っている。
だからこそ、たった今、この現状に苛立って仕方が無い。
「生ごみの方が、いくらかましだね」
平和島のアパートの一室、ベッドの上にぐったりと横たわるそれは見るも無残な状態で発見された。辛うじて息はあるが、あのまま数日放置されていたならどうなっていたか分からない。漠然と、子供が戯れに虫かごに閉じ込めて死なせてしまうのとかわりないな、と思った。
「し…ら…」
「喋るな」
「しんら…」
「うるさい、だまれ、口を閉じろ」
「しんら、…泣くな、よ…」
どの口が言ってくれるんだ。振り下ろせもしないのに、硬く握り締めた拳を、眺めながら折原は深く、深く息を吐いた。それはまるで何かの儀式のように形式的な美しさを孕んでいる。
「でもうれしい…嬉しい…大好き、シンラ、大好きだ」
「本当、僕が殺してやりたいよ。今すぐに」
「うん、分かるよ」
岸谷の顔が歪んで見えるのは自分の視界がいかれているのか、実際に顔を歪めているのか判断は出来ないが、彼の頬に伝ったそれだけが何よりも折原を慰めた。そしてそれと同時に、この世の何よりも彼を苦しめる。
「もしも俺が死んだら、シンラは俺のことが嫌いになるのかな」
「…残念ながらなれないよ。僕はきっと、ずっと君が好きだ」
「そっか…」
「そうだよ」
「…良かった」
たったその一言で、この数日間の間に崩壊した折原の心は息を吹き返した。生理的に、瞳を潤すためだけに、溢れた涙をただ可哀想な自分たちのために流す。それだけで救われたような気持ちになってしまうのは、なぜだろう。
ぼろぼろの体で、岸谷の温もりを探していた。
何も言わなくとも、そっと抱き寄せてくれる彼の悲しみに報いたいと思う。それはきっとこの世でただ一人に向けるべき感情。愛おしくて、また涙が零れた。
「…約束してくれる?俺が死んでも嫌わないって」
「僕に嫌われるくらい、下らない死に方しなければね」
「…それは、また難しいな。まぁ頑張るよ」
終わり