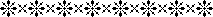 ベットの上に押し倒された形で転んだ私を上から見下ろして、イルミ様は言った。 長い黒髪が私の頬を擽る。 「どうして強くなりたいかって聞いたよね、リア」 私はただ声もなく、イルミ様を見上げる。頭の中は真っ白で何も考えられない。ただ唇にはイルミ様の熱が残っていて、それが身体中に広がっていくようだった。 自分の身体が自分のものではない熱に支配されて、動けない。それでも、肩に、腰に、私を押さえつけるイルミ様の重みを感じる。 「これが答えだよ。俺より強い女を押し倒すために、強くなりたかった。今のはかなりズルしたけど、見逃してね。じゃないと、俺はいつまで経っても嫁を迎えられないからさ」 「……誰が、嫁ぐのですか?」 かすれた声で問う。私が知らない間に、イルミ様の嫁が決まったのか? 混乱している頭はありもしない未来を勝手に描いて、慄く。 「俺がキスされた……いや、正確には俺がキスした女。リア、幾ら鈍いからって言ってもここまで言って、わからないってことある?」 「いや、あの……えっ?」 まだ理解が追いついて来なくて、間抜けな声しか返せない私にイルミ様は言う。 「王子様は一人の女をずっと待ち望んでたんだ、ただその女があまりにも鈍くてなかなかお城に来ないから無理矢理襲っちゃったけど」 「ですが……私は……」 執事という肩書はあるものの、家など持たない人間だ。伝説の殺し屋と言う異名を持つゾルディック家の大事な嫡男と釣り合いなどとれない身分だ。 だからこそ、諦めた。我慢した。 「リア、俺の結婚相手は最初から決まってたんだ。俺に触れるのは、俺より強い女――リア、お前だよ。それは母さんも父さんも承知してるし」 「……本当に?」 半信半疑で問う私に、イルミ様は唇を尖らせた。 「俺が嘘付く時なんてあった?」 何を考えているのかよくわからない性格ではあるが嘘をつく訳でも、人をからかって喜ぶ訳でもない。ただ正直すぎて、ときに高みからの発言に聞こえてしまうこともあるけれど、いつだって馬鹿正直に、挑戦してくる女たちの相手をしていた。 「リア、頼むから俺の言葉を信じてよ、考えてくれない?もうこれ以上無理。お前以外の女との結婚話をせっつかれるのも、リアの口から聞かされるのも耐えられない」 イルミ様の真剣な眼差しと赤く火照った頬を見やって、私はゆっくりと手を伸ばした。 指先が触れた肌が僅かに震える。見つめる瞳の奥にあるのは――期待と恐れが入り混じったような、初めて顔を合わせたときと同じ色。 「ねぇ、リア。俺はこの後どうすればいいわけ? ここでリアを襲っちゃってもいい?それとも俺はお前を諦めないといけないの…?」 そっと問いかけてくる声に私は微笑んだ。 「そうですね、私としてはこのまま続きをしたいところですが」 圧し掛かってくる重みと熱と、柔らかさをこのまま抱いていたい。けれど、さすがにそれは駄目だろうと理性が先立つ。 「……リア?」 そんな俺の言葉の真意を測りかねて、イルミ様の声は微かに不安が混じっていた。 ああ、と思う。 やっぱり私の坊ちゃんは、この手で守りたいほど愛おしく繊細だ。他の女になど、くれてやれるか。 「シルバ様にご報告に参りましょう。それから皆の前で勝負しましょうか。誰にも反論されないよう、私の強さを見せて差し上げます。そうしてイルミ様は私にすべてを預けて、守られなさい」 ゆっくりと身体を起こしながら、私はイルミ様の耳元で囁いた。 ――あなたを私のすべてでもって、守ります。 祝福のキスは血と錆の味 prev / next |