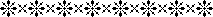 「それでリア、俺の好みを聞いて誰かしら俺の嫁に相応しい女は見つけられそう?」 イルミ様の問いかけに、私は言葉に詰まる。第一条件が一番の問題だ。 こうなったら、他の条件に合いそうな、イルミ様と身分が釣り合う姫か上流階級の貴族を探しだして、イルミ様より強く鍛え上げるしかないのではないか? 何で私がそこまでしなければならないんだ? という思いに囚われるが、これもシルバ様のため。イルミ様の幸せのためだと自分に言い聞かせる。 「…………申し訳ありません、しばしお時間を」 私の答えに、イルミ様はうんざりしたように天井を仰いだ。仰け反る首元に見える喉仏が男らしくて半端なく色っぽい……いやいや、今はそんなことを考えている場合ではなく。 「俺はいつまで強くなればいいの?」 イルミ様の唇から出たぼやきは、どうにも脈絡がないように思える。いや、この場合はこれ以上強くなられたら困るのだが。殺し屋としては立派な考えだが。 「あの、イルミ様は……どうして、そんなにまで強くなりたいのですか?」 単に家業のためかと思っていたが、今の声の調子は疑問を抱かされるものだった。 腕に覚えがあれば、強くなりたいと思うのは不思議ではなかった。当然だろう。だが、強くなることを嘆くような口調は、何かおかしい。 私の問いかけにイルミ様は少し間を置いて、口を開く。 真っ直ぐに私を見つめて、小首を傾げる。 「お前は? リア。もうゾルディック家一の執事って言われるほど強いのに、まだ精進を続けているのは、どうして?」 「それは執事として、イルミ様をお守りするのに抜かりがあってはなりませんから」 「俺を守るため? それは執事として、役目をおっての決意?」 「私はイルミ様の執事として生涯を通すつもりです。役目云々など、知りません」 仕事だと思われているのかと、反抗する気持ちで若干、声を尖らせた。 イルミ様を守る、そう心に誓ったのだ。あの日、シルバ様の陰に隠れるようにこちらを見つめ、やがてそっと、はにかむように微笑んだ姿を目にしたときから。 例え、想いが届かなくても。 「……リア、我儘を聞いて貰っていい?」 「何でございましょう?」 「疲れたから、歩くのが億劫なんだよね。俺をベットまで連れてって」 イルミ様の頼みに、私は驚いた。毎日、稽古をしているイルミ様の体力は私でも驚かされるものだ。今日の試合はそれほど大変なものではなかっただろうと思っていたが、他の仕事の量や陽射しの強さを思い出せば、納得しないでもない。 「はい。大丈夫ですか?」 揺り椅子に腰かけたイルミ様の横に回って、背中と肩に腕を通して、イルミ様の身体を支える。 イルミ様は身を寄せ私にもたれかかりゆっくりと歩き出す。 やはり男性であるからか、思ったよりも重い。 伝説の殺し屋や闇人形と周りから恐れられようと、私にはあの日と変わらない坊ちゃんだ。小さくて、か弱く、私が守りたいと思うその人。 胸の内に溢れてくる想いに意識が逸れたのか、不覚をとった。よく考えれば、もう一人の執事――同僚のゴトーがいないのだから、両腕の動きを封じてしまうようなことはしてはならなかったというのに。 鼻腔一杯に石鹸の香りが広がった瞬間、唇に柔らかな熱が触れた。その存在に気づいた私は膝から力が抜けて、尻餅をつく。ぐいっと肩を押されて、背中をベットに付けさせられた。 ピーターパンにさようなら prev / next |