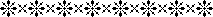 様々な思惑と期待をどっしり背負って、よろめきながらイルミ様の部屋の前に来た。ごくりと息を飲んで、扉をノックする。 「イルミ様、リアです、少しお時間をよろしいでしょうか」 「入っていいよ」 抑揚の無い声の応答に、私は扉を開けて室内に入る。 衝立が進行方向を邪魔しているのでそれを避けて歩みを進めた先で、硬直した。 脱ぎ散らかされた服が床に放りだされた部屋の中央にバスタブが持ち込まれ、湯が張られたその中にふわふわの泡と共に身を浸しているのは他ならない――。 「失礼しましたっ!」 私は踵を返して、部屋から出ようとした。 しかし、それより先に声が制する。 「何、要件も言わないで出て行くの?」 ぴしゃりと言いきるその声に、私の身体は凍った。まったく、か弱く見えたイルミ様は、いつから私を委縮させるほどの威厳を持ったのか。 幾ら、念を覚え、誰にも負けない自信がついたとはいえ、今のイルミ様はまったくの無防備であるはずなのにっ! 「……しかし、イルミ様」 私はイルミ様に背中を向けたまま、抗弁した。泡が邪魔をしていたとはいえ、今ちらりと肌が見えた。それを幾ら気心が知れている私相手とはいえ、見せていいのか? ――婿入り前の坊ちゃんがっ! というかいつからイルミ様の部屋の中央にバスタブが!? どうしてこんな所に… ご自分で運んだのだろうか?それともゴトーが? 如何にしても何でこんなことを! と、私は心の中で猛々しく叫ぶ。あくまで、心の中でだ。イルミ様を男として意識していると思われたら、軽蔑されるだろう。それは嫌だ。 「用があるんでしょ? リア」 湯を掻き混ぜたのか、微かに水音がする。それに合わせて室内に仄かに立ちあがる石鹸の香に、私は軽く眩暈を覚えた。いけない、一瞬、見ちゃいけないものを想像してしまった。身体の奥が本能から熱くなる。 たまに――思う。 私ならイルミ様に勝てる。あの条件に真正面から勝負して、イルミ様の嫁になれるのはある意味、私だけだろう。 ならば私がイルミ様の嫁に立候補してもいいのではないかと。 他の女に奪われるくらいなら、私がイルミ様を奪おうかと。 しかし、暴走する思考は冷静な頭の一部によって制される。 ――身分が違い過ぎるっ! それに一瞬のことなので、イルミ様とバスタブしか目に入らなかったが、恐らく室内には執事たちが控えているに違いない。だからイルミ様は女の私と二人きりになっても――正確には、二人じゃないだろうが――余裕なのだろう。いや、端から眼中にないのかもしれない。私という女はイルミ様にとって念の師匠で教育係、その程度だ。 だから私がイルミ様に対して無体なことをするなど、想像しやしない。 まあ、できるわけない。そんなことをしたら、私の将来は真っ暗だ。腕に覚えがあっても、世の中を渡っていくのはそれだけじゃ叶わない。 盗賊にでも身を落とす? いつか出会ったあの逆十字の男の側で働くか?血を浴び死と隣合わせで生きるか?そんな事をすればゾルディック家、世界中が敵に回るだろう。 どんなに私が強くても、誰よりもイルミ様を愛していても、世界を敵に回すなんて無理です。無理無理。 ぐっと拳のうちに爪を立てて、私は自分を律する。欲望に負けるな、私。執事としての身を弁えよ。シルバ様に拾って貰った恩を忘れるな。 それに私は、イルミ様の教育係に選ばれたときから、生涯、イルミ様のお傍にいると誓った。イルミ様もそう望んでくれた以上、胸の内にどんな想いが隠されていようと、お傍を離れることはできない。 例えイルミ様が私以外の女と結ばれようと……。 「ああ、稽古に誘いに来たの?」 イルミ様のどこか弾む様な声が背中に届いて、私の意識を引き戻す。 念を覚えてから、イルミ様は実に稽古熱心だ。強くなるのが、楽しくてしょうがないらしく、一日も稽古をさぼろうとしない。教える側としては良い生徒であるが、さすがにあそこまで無敵になられると…… どうなのか。 「いえ、汗を流してしまったのでしたら、今日は止めておきましょう」 私は衝立を睨んで言った。つまらない試合だったとはいえ、あの暑いさなかで掻いた汗は疲労を伴うはずだ。 「それよりそろそろ夕食のお時間です」 「今日はいらないや」 「よろしいので……?」 「母さんがきっとうるさいからね、それよりリア、何か用があったんじゃないの?」 「あ、はい。あのですね……イルミ様」 「待って、今そっち行く」 ざぶんっと水音が跳ねて、ひたりと水分を含んだ足音が大理石の床で鳴った。微かな衣擦れの音とともに石鹸の芳香が濃厚に漂う。 「それで話って?」 耳元で声が聞こえて、私は身体を跳ね上げた。振り返ると、ローブをまとったイルミ様が黒い髪から水を滴らせて、小首を傾げている。 髪からこぼれる雫がローブに染みて、水を吸った衣が既に男として完成された姿態に張り付いては身体のラインをあらわにしていた。稽古で鍛え抜かれたイルミ様の身体は引き締まり逞しくそれでいてしなやかである。 ――何と目のやり場に困ることをっ! 私は即座に視線を逸らした。しかし、目に焼きついた残像は直ぐには打ち消せない。胸の内側で心臓が高鳴っている。落ち着け、私。動揺を見せるな。ここは泰然と、師匠としての貫録を見せつけろ。 自らを叱咤激励し、しかし、視線は天井を見据えたまま告げた。 「その前に、髪を乾かし、服を着てくださいませ」 「これじゃ駄目なの」 着替えるのが面倒なのか、イルミ様の声はどこか無念そうに聞こえる。 「身体が冷えてしまいます。どうか、乾いた服にお着替えを」 「リアがそう言うなら」 「はい。風邪でも召されて、寝込まれては稽古もままならなくなります」 「そんな弱くないよ」 「ええ……知っております」 拷問や体術よりもっと、子供らしいことはないのかと思うも、死と隣り合わせで育った私と、その私をお傍に置いて殺し屋としての技能習得――要するに強くなることを趣味にしてしまったイルミ様の日常に、稽古以外のものなどなかった……。 こんな二人に、甘い感情など生まれるものか。 イルミ様を目にした瞬間、私の中に芽吹いた感情以外は……。 ペテン師は知らないふりをする prev / next |