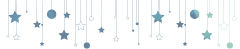4
夜もだいぶ更けた頃、沢口様がお帰りになった。
「一葉、今夜私の寝室に来なさい。」
テーブルの上を片付けている僕にそう命じると、政明様は2階にあるご自分のお部屋へと戻っていかれた。
書斎ではなく寝室へ。
これは今夜は政明様に抱かれる事を意味する、僕と政明様の暗黙の了解だった。
(はぁ…気が重い。)
政明様に抱かれるのは決して嫌ではない。
むしろ初めて抱かれた時は、羞恥心と共に喜びと幸福を感じた。
しかしそれが誰かの身代わりと知ってしまった今では、喜びよりもただただ空しいだけだ。
そう、身代わりだ。
僕が政明様を恋い慕うのと同じように、いや、それ以上に長い年月をかけて政明様はあるお方を想っていらっしゃる。
――僕とよく似た、あの方を。
だから叶う事のなかった恋心を埋めるように、こうしてたまに呼びだしては政明様は僕を抱く。
僕を抱きながら、僕じゃない誰かを見ている政明様。
それが切なくて悔しくて、ただ哀しかった。