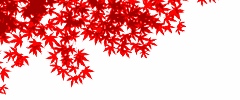 ‖新月にご注意 朱桜、という武門がある。 その屋敷が現在、この煉瓦街に建てられているのだ。どうやら本来は立派な武家屋敷を別に持っているらしいが、近代化に合わせ、煉瓦造りの洋風屋敷を作って一家が移り住んだそう。 そんなお屋敷だが、まだまだ御家の内情は江戸のままだ。屋敷で働くのはメイドや執事ではなく、女中や下男と呼ばれる下働きども。外向きの用事がない限りご主人も奥方もみな着物だ。 そして名前は、その朱桜の奥方に仕える女中として職を得ていた。良くも悪くも奥方は上流階級の人間で、決してこちらに踏み込みはしないものの、容赦なく人を使い倒す。 「もう真っ暗ねぇ」 今日の夜空には月がなく、星がまばらに散っているだけだった。 ガス灯はほの明るいが、すでにとっぷりと日は暮れているせいで、そうはいっても道は暗い。ここ最近、名前はずっと遅くに帰っている気がした。 煉瓦街の小さな借家が名前の家だ。表通りには店が立ち並んでいるので、自然、裏通りを歩かねばならない。裏通りには千秋の詰めている巡査派出所があるので、多少は安心だが。 「……あれ?」 裏通りの曲がり角が見えてきたところで、名前は目をこすった。 人が……倒れている。いや、壁に寄りかかっていると言った方が正しいか。 洋装の男だった。それこそ、朱桜のような由緒正しい家の青年なのだろうか、高級そうな黒の洋服を身にまとっている。が、ゆるく波打つ髪は半端に伸ばされているため、社交界とは縁遠い人間のようにも思われた。裏通りにはおよそ似合わない人間だったが、倒れている以上、無視する訳にもいかない。 「あの、大丈夫ですか」 「……んぅ……?」 近寄ると、その男が整った顔をしていることに気づいた。少々声をかけづらいほどの美形だったが、勇気を出して声をかけ、肩を揺する。 すると、気だるげな声で男が呻いた。ゆっくりとその目が開かれると、名前は少し肩を跳ねさせた。血のように紅い瞳をしていたからだ。 「ああ……すまぬな……、歩行の邪魔じゃったかのう……」 「あ、いえ……そういう問題じゃないと思いますけど……?」 「くっくっく……それもそうじゃな。いやすまん、我輩『昼間に』うっかり出かけてしまってのう、ぶっ倒れておった訳じゃ」 「はぁ」 昼間に出かけるのは、普通だと思うが。 しかし青年は口調とは裏腹に、まだ体に力がこもっていないように感じた。具合が悪いのだろうか。 「表通りまで案内しましょうか? 裏通りにお住まいなわけではなさそうですし」 「ふむ……そうじゃな。頼む」 「立てます?」 手を差し伸べると、青年は少し目を細めてその手を取った。立ち上がると、彼は背も高いのだとわかった。 表通りまで案内して、大きな橋のところまで二人連れだって歩く。雑談して、それとなくお互いの自己紹介も済ませた。彼の名は『朔間零』というらしく、思った通り洋風屋敷に住んでいるとのことだった。 「きっとお屋敷の方は心配なされてますよ」 「うーむ、そうだと良いんじゃがのう? 心配してくれる者がおらぬのでなぁ」 「……? 一人暮らしなんですか?」 「そうじゃよ。獣を3匹、飼っておるのじゃ……」 口調もそうだが、なんだかおじいちゃんみたいなことを言う人だ。独り立ちしてきた、という新鋭な感じがない。どう見ても、彼は二十そこらの若者だというのに……。 「っう……」 悠長に喋っていた朔間が、突然ふらりと名前の方に倒れこんでくる。慌てて彼女は、彼の長大な体を支えることになった。 「おわっ!? だ、大丈夫ですか、朔間さん!?」 「あ、ああ……すまぬ。やはり新月は良くない……」 「え、えっ? 新月?」 なんの関係があるのだ、と思いながら顔をあげた、 その時。 「なっ――」 空ではなく、朔間の背より遥か後方に。 なにかが、居た。ゆらゆらと揺れる陽炎のような、白い靄のような、けれど明らかに……交わってはならないモノが! どくどくと一気に心の臓が激しく脈打つ。朔間の背を支えた手に力がこもり、背中に嫌な汗が流れた。白い靄には、二つの目玉があった。……奇しくも朔間と同じ、血のような赤色の。 昼間、千秋の言っていた新聞の話が頭をよぎる。記者の言い逃れにすぎないと泉が笑っていたことも思い起こせる。嗚呼……まさか、これが新聞に出ていたモノなのだろうか? 「どうしたのじゃ、名字のお嬢さん」 「……っ……朔間さん……」 「我輩より顔が青いぞ? ……何を、見ておる?」 「あ、あやかしが……」 「――何?」 ギラリと朔間の赤い目が光った気がした。彼はゆっくりと振り返り、白い靄を見据えた。彼にも、見えているらしい。 「参ったのう……、目を付けられたか……」 「え……?」 「今宵は我輩、全然元気出ない……どころか体調不良なんじゃが……まずいのう……」 「さ、朔間さん……?」 先ほどからずっと彼はふらふらしている。このまま走って逃げることもままならないほど、具合が悪そうなのだ。名前一人だけ走り去ることもできなくはないが……そんなことをしたいとは、微塵も思えなかった。 白い靄はこちらの存在に気づいたのか、まるで四足歩行の獣のような重厚な動きをしながら、ゆっくりとこちらに向かってくる。異形の恐ろしさに、足が縫い付けられたように動かない。朔間は、靄が近づいてくるごとに辛そうな顔をし始めた。そしてついに、橋の上で膝をついてしまった。 「いかん……嬢ちゃん、早く逃げてくれ」 「な、でも朔間さんが」 「我輩は動けぬ。こんな凡百の鬼にすら、抑え込まれる有様じゃ……」 「え、お、鬼っ!?」 名前はすっかりパニックになったように叫んだ。けれど、彼女はそれでも逃げようとしない。朔間は困ったように眉を寄せた。 「第一嬢ちゃんも分かるじゃろう。『見鬼(けんき)』ならば、おぬしが一番危うい立場であることくらい……」 「け、けんき? なんですかそれっ」 「なんですか、とな? ……おぬし、あれが見えるのじゃろう? ……まさか、今宵が初めてか」 最悪だ、というように朔間が首を横に振った。 何が何だかさっぱりだったが、二人のやりとりを鬼が待ってくれるわけではない。すぐそこまで来ている鬼から朔間をかばうように、名前が彼の前に立つ。 獣の息遣いが聞こえる。獲物に舌なめずりするような音も聞こえた。近寄るにつれて、靄は晴れ、その全貌が明らかになった。鬼、というよりは虎のような生き物だった。 「嬢ちゃん!? 何をしておるのじゃ! はよう逃げんか!」 「逃げません……」 「逃げろというておるのじゃ!」 朔間の苛立ったような叫び声に、名前は振り返った。けれどまったく怯えた様子を見せず、負けじと言い返す。 「逃げない。だって見捨てて逃げたら、一生後悔する!」 「なっ――」 ついに目と鼻の先まで獣が迫った。その大ぶりな腕が、ゆっくりと月のない空へと振り上げられ―― 「え」 そして、空へと腕は『舞い上がった』。 「■■■■■■■――!!!!!」 獣が何事か叫び、なくなった腕をかばうようによろける。ごとっ、と橋の上で物体が落ちた音がする。獣の腕、だったものだ。 よく見ると、獣の肩口に何か白いものが貼り付けられていた。もはや足は恐怖で縫い付けられているのだ、だったらソレが何か判別してやろう――と名前が目を凝らした、その時だった。 「青龍・白虎・朱雀・玄武・勾陳・帝台・文王・三台・玉女」 涼やかな声。獣の後ろから、少年のような声がした。 すると同時に、ハッキリとした光の囲いが獣を覆う。がりがりと獣が橋へ爪を立てて抵抗するが、その囲いに従って、名前たちから無理矢理引き剥がされていく。 そして、その声の主が姿を現した。 「なぜこんなところに、鬼が自然発生したのかわかりませんが――お怪我はありませんか?」 赤い髪の少年だ。 こちらは、朔間とは逆で、上等な和服を着ていた。こんな時間に子供がなぜ出歩いているのだ、と大人であれば叱らねばなるまいが、もはやこの異空間では、その言葉に幾ばくの意味もないだろう。 平気、と名前がかすれた声で言えば、少年は安心したように微笑み、彼女と獣の前に立つ。すぅ、と薄い唇が息を吸った。 「――急急如律令呪符退魔!」 その言葉と共に、不思議な形を組んだ指が、まっすぐ獣を指した。 すると光の囲いは一斉に四散し、夜の橋を一瞬だけ明るく照らした。 霧のように、名前の周囲に降り注ぐ光。獣の姿は既になかった。茫然とそれを見ていると、少年は名前の方を振り返った。 「もう大丈夫ですよ。『見鬼』のご夫妻」 「い、いや、だからけんきって何……? あ、それとこの人は夫じゃないです、道で倒れてた人で」 「……どうやら、今度は橋の上で倒れられたみたいですね」 「えっ?」 名前が振り返る。すると、そこには完全に意識を失って、橋に寄りかかって眠っている朔間の姿があった。 「せ、せっかくここまで来たのに!」 「この方の家はご存じなのですか?」 「い、いや知らないんです……。ううん、こうなったらウチに泊めるしかないよね……」 「お家にご家族は?」 「自分、出稼ぎなものでして」 まるで巡査と話しているような感じになっている。少年は少し眉をひそめて、むむ……と腕を組んでいる。先ほどの大人びた雰囲気は薄れ、そこには年相応の感じがあった。 「一人暮らしの女性が、病人とはいえ男を……」 「いやぁ、仕方ないですよ。せっかくあやかしから庇ったのに、ここで死なれちゃ一生悔やみますし」 「うーん……そうですね。……なら、私もついて行きましょう」 「え?」 「この方は大柄ですし、もし何かの間違いがあったら大変です。この方が意識を取り戻すまで、貴女の護衛をいたしましょう。それに、これでも私は町の守護の端くれ。女性に無体はしないと誓います」 きりっとした顔でそう言われてしまえば、なんだか断りづらい。どちらにせよ、この男を運ぶのはさすがに名前一人では無理だった。少年の力を借りるほかない。 「じゃあ、お願いするね……?」 気が抜けたせいか、ルカにお手伝いしてもらうときの喋り方が出てしまった。 「はい! えっと……お姉さま」 怒るかなと不安に思ったが、彼は案外嬉しそうに笑った。 名前、あとで教えよう。と名前は自分をお姉さまと呼んだ彼に向かって、やさしく微笑んだ。 [*前] [次#] [戻] |