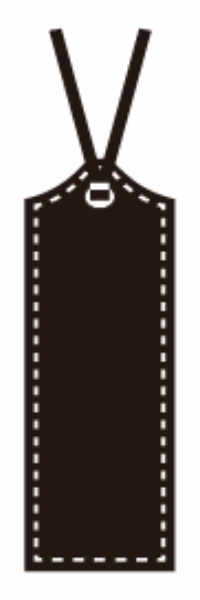3
無言電話
「でね?」
絶縁したわけではなく、男と女は、まだ連絡だけは取りあっていたらしい。彼の口調こそすでに感情も情緒もない無味乾燥としたものではあったが、だからこそ、連絡相手があの女であるということは容易に判断できた。
男が入浴に向かったのを見計らい、彼の携帯端末からコール。発信履歴が残ることまでは計算していなかった。ただ、自分の声を女に聞かせたいという一念からの行動。当てつけとか、侮蔑とか、そんな野暮な発想からではなく、繭という存在を音に換えて届けたかっただけ。同列のものか、それ以上のものかはわからないが、男の愛情を受けたことのある共通の女として、奇妙な友情を感じていたのだ。
友情──誰にも理解できないことだろう。
友情──しかし、汚れのない明瞭な感情。
女はとても驚いた様子だった。音量は微々たるものながら、息を飲んだとわかった。彼女に釣られ、繭も息を誤嚥するところだった。それから、しばらくの動揺の末、まるで取り繕うかのような近況報告。
もどかしい出だしだと思った。しかし、あまりにも女が噤みつづけるので、間が空くことを恐れ、繭は闇雲に喋りつづけた。
それでもなお、女は黙っている。嘆くでなく、憂えるでもなく。
「あんまり彼がムキになるもんだからさ」
聞きつづけるのだ。言語を封じたまま、吐息と咳嗽と洟の音声だけを几帳面に仄めかしつづける。
モールス信号の生存証明──まるで、自分で自分を責めているかのよう。
「あたしのほうから手を握ってやったわけ」
ふふふと笑う。繭の近況報告を、女は、息を殺しながらも笑ってくれている。しかし、含み笑いばかりで肝心の言語のほうが手に入らない。初めて電話した日から数えて数日間は聞こえていた「もしもし」という重たい言葉さえ、もうこの手には入らない。連日に渡る打電の習慣が、繭の切望する言葉をすべて略奪してしまった。
淋しい。
「前触れもなく、ぎゅって」
別に、男の二番目でもよかった。この女が一番でも淋しくはなかった。繭が淋しく思うのは、彼女の刹那的なあやまちによってこんなにも息苦しい無言が生まれてしまうという科学反応のこと。
でも、だからどうするつもりもない。自業自得だと責める気持ちはない。そんなくだらない一般論で自慰する気持ちはない。
淋しい──ただそれだけ。
侘が淋しい、寂が淋しい、後味という文学的な科学が淋しい──ただそれだけ。
| ≪ | 表紙に戻る | ≫ |