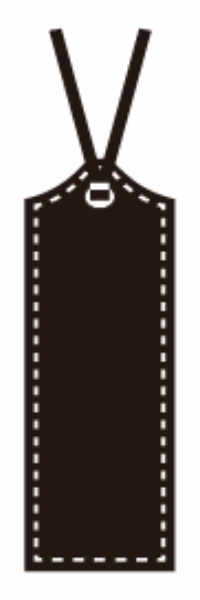4
無言電話
ただ一度、留守番電話の灯がともっていたことがある。二週間ほど前か、帰宅してすぐに気づいた。
夕闇だった。曇っていたからいつもよりもリビングは暗く、しんと静まり返り、まるで空き家のような廃れた空気が漂っている。トイレの換気扇の微かな羽音が唯一の生活音で、テレビも、ダウンライトも、漫画本もみな、息を止めて死んでいた。
男はまだ仕事に行ったきりで部屋は裳抜けの殻、そんな、ピンと張りつめた夕闇の中、留守番電話の青い光が規則正しく点滅している。
決して初めてのことではないが、なぜか繭の気にかかった。鞄をおろすと、跨いで越え、その向こうの床に座っている電話機へと近づく。手の届く距離で腰を落とし、正座になった。
しかし、気にかかるのに、留守録を再生する気が湧かない。
男の知り合いである可能性もある。例えば、仕事先の人間とか、友人とか、親とか。でも、だとしたら男の携帯端末のほうにコールしていてもおかしくはない。むしろ、そちらのほうが自然のような気もする。
もしやあの女からの電話なのではないかと繭は思った。でも、でも、男に用件があるのならば、やはり彼の携帯端末へと発信しているはず。
誰が、誰に──?
女が、繭に──?
『やめてよ』
発作的に、繭はぼそりとこぼしていた。鼻で笑うようなひとりごと。しかし、それが女に対しての憫笑なのか、あるいは自嘲なのか、繭自身にもわからない。
怖かった……のかも知れない。
もしも留守番電話の主が女だったら、もしも用件の相手が繭だったら、なにか大切なものが壊れてしまいそうで。仮に建設的な内容であったとしても、仮に幸福な内容であったとしても、この一方的な友情に比肩しうるものであるとはとうてい思えなかった。むしろ、繭の望まない余計な感情を押しつけられるように予感してならなかった。
息を殺し、固唾を飲む。
死んでしまったリビングの中、点滅する青い空。
フローリングに当たる脛が冷たい。
いや、死んでいるのは自分のほうかも知れない。
『届けるのはあたし。あなたではない』
ふたたび、ぼそりとつぶやく。
『やめて』
まるで、無言のように。
『そういうのは、やめて』
| ≪ | 表紙に戻る | ≫ |