 ブーゲンビリア ブーゲンビリア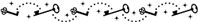 すったもんだあった末、私たちは無事、夏休みを迎えていた。 今回の件、親に内緒にしておいてあげるの条件で、期末試験を高得点を取るため、私たちはその後も、秋穂の部屋を借りて、勉強会を開く羽目になった。 そのお陰で何とか親にも恰好が付き、沖縄旅行も了承させることが出来た。 残るは私のダイエットのみ。 意地悪く笑ったヒッキ―は、ヨッちゃんと手を繋ぎ、座席二人分はきついでしょと付け加えた。 というか、いつの間に仲直りしてんだこいつら? 終業式を終え、渡り廊下を歩いていると呼び止められた私は、呆然とそんな二人を見ていた。 「横綱、好きな人が出来たんだって?」 ヨッちゃんがにやけ顔で聞いてきた。 ついこないまでは死にそうな顔をしていたくせに。フンと鼻を鳴らす私を見て、ヒッキ―が、横綱、鼻の孔、引き締めてと言いつつ、パシャリ。 携帯じゃ物足りなくなったヒッキ―は最近、秋穂に買ってもらったというデジカメを持参している。 以前よりアップの速度は遅くなったが、悪乗りしてきたヨーデルまでが、ノートパソコンを駆使してよりクリエーティブな仕上がりを求める様になり、音楽監修はヨッちゃんが担当をしている。コメントを考えるのはマッチの役目と、良い具合に役割分担されるようになり、本気でこんな部活があるんじゃないかと、錯覚してしまうほどだった。 最近、私の本気を認めた母親が、協力的にダイエット食を作るるようになり、父親までが参戦して来ていた。 「父さんも、最近腹が出て来て困るから」 一緒に朝、走るようになり、ヒッキ―が自転車で伴走を買って出る。ヒッキ―が調子が悪い日は、秋穂が変わりに来たり、マッチがわざわざ電車に乗ってやって来ることもある。ヨーデルも協力すると言ってくれるが、流石に乗りついでまで来させるわけにはいかない。そこで登場するのが私の弟、和馬だった。和馬は、秋穂の大ファンで、頼まれるとなんでもホイホイやってしまう。中三のマセガキは、受験勉強をそっちのけで私を撮ることに、異常までの執念を燃やし、5キロ減といういやらしい結果を出しやがった。 私の恋路そっちのけで、ダイエット計画は進められ、10キロ落とした私は二人分の座席を取ることもなく、沖縄へと飛び立った。 ヒッキ―とヨッちゃんは同じ部屋にチェックインし、私たちは顔を見合わせる。 「秋穂さん、知っているのよね」 マッチの質問に私は頷く。 「大丈夫なのかな?」 心配そうに言うヨーデルと目を合わせることが出来ず、言葉を濁らせた。 「大丈夫でしょ。あの二人もバカじゃないから」 「そうだよね。学年、ツウトップだもんね」 ヨーデルの言葉に、マッチが繋ぐ。 「本当、不思議だよね。あの二人が付き合うとは思わなかった。ヒッキ―ってどこか陰気くさいっていうか、あまり自分を表に出さないじゃない? ヨッちゃんにしたってさ、吹部で青白い顔して、挙動不審というか」 「分る。一年生の時、同じクラスだったけど、なんかみんなと馴染めないみたいでさ、ぽつんとしていること多かったし、喋りかけると、なんか言葉が縺れちゃって上手く話せないんだよね。そのくせ、楽器弄らせると豹変しちゃう感じ、ちょっと不気味だよね」 散々、盛り上がったところで。噂の二人が混じり、早速街へと繰り出す。 「泳ぐのは明日。まずは散策と行こうじゃないか諸君」 断然張り切ったヨッちゃんが言うと、私たちはそれに従った。 水族館やらなんやら散々歩き回って疲れたヒッキ―が、少しだるいと言いだし、私たちはホテルに戻る事を決めた。 私は、秋穂からヒッキ―の容態がおかしくなったら医者にこれを見せろと白い封筒を任されていた。 「相変わらず、体力ないね」 帰りのタクシーの中、マッチの言葉に、ヒッキ―は力なくごめんと謝る。 「勉強のし過ぎなんじゃない?」 ヨーデルが買ったばかりのサンゴの首飾りを付けながら言うと、ヒッキ―はヨッちゃんに肩を借りながら、そうかもと答える。 ヨッちゃんもあまりの衰弱しきったヒッキ―を見て、不安がる。 「芳郎、残念だけど、今夜は一人で寝ろ」 助手席に座った私は振り返り言う。 「何で、私、ヨッちゃんと泊まるよ」 少しだけ躰を浮かせたヒッキ―に言い返され、私は困惑で見返す。 「俺なら大丈夫。寝ないでヒッキ―の面倒見るから」 「面倒?」 マッチにいやらしい目で見られ、みるみる顔を赤くしたヨッちゃんが、いやらしこと想像してんじゃねーよ。と言い返す。 「別にしても良いよ」 「おいおい」 運転手が、明らかに顔を顰めるのが分かった。 「冗談はさておき、晩御飯、食べれないようだったら私の言うことを訊いて貰うからね」 凄んで言う私に、ヒッキ―は無言で見つめ返して来た。 秋穂から言われた最初の条件だ。ご飯が喉を通らないようだったら、相当に具合が悪い証拠。みんなにバラシテでも病院に連れて行くようにだった。 余程、皆と一緒に居たかったらしく、ヒッキ―は少量だけど食べ物を口にし、皆に隠れて薬を飲ませた。 「あたし、何歳まで生きれると思う?」 「100歳」 即答した私を見て、その心はと壁にもたれながらヒッキ―が尋ねる。 「憎まれっ子、世に憚る」 「確かに」 それは、ヒッキ―の秘密を知っている者は、誰でも思うことだった。 「帰りまでもちそう?」 「どうかな? 最悪、姉貴に来てもらわなくっちゃかもね」 ヒッキ―の目から、ぽろぽろと涙が零れ落ちた。 「思い出、沢山欲しいな」 「作ろうよ。それには条件がある」 小刻みに揺れるヒッキ―の肩を抱いて、私はみんなの元へと戻り、病院へ行くことを告げた。 「俺が連れて行く」 「ダメ」 「どうして?」 「好きな男に、弱っているところ、見せたくないんだって。今晩中には帰って来るから」 そう言う私の言葉を無視して、ヨッちゃんはロビーで待っているヒッキ―のもとへ走って行ってしまった。 「ヒッキ―、そんなに悪いの?」 「うん、ただの貧血だと思うんだけど、この暑さで参っちゃったらしいんだよね。前にもこういうことがあったから、その時も、点滴を打って貰ったらケロッとしちゃって、絶好調で遊べたから、その方が良いかなと思って」 自分で言っていても胡散臭いなと思うくらいだから、おそらく二人もそう思ったと思うけど、ツッコミが入らない内に、踵を返し私も、ヒッキ―の元へと急いだ。 頑として言うことを聞かなかったヨッちゃんと私は、静まり返ったロビーで、ヒッキ―の点滴が終わるのを待っていた。 「あいつ、どこが悪いの? ちょくちょく学校も休むようになって来ているし、俺とも何となく距離を置き出すっていうか、よく分かんないけど、何か怪しいんだよな」 顔を両手に埋めて言うヨッちゃんに、私は何て言ってあげていいのか分からなかった。 「私もよく分かんないんだ。昔っから躰が弱いとは知っているけど、何の病気なのかとか教えられていないし、さっき、先生も言っていたじゃない。貧血でしょうって。その言葉、信じるしかないよ」 救急車のサイレンが近づきて来る音がして、バタバタと人の足音がそれに続いて聞こえ、外国語を話す団体が入って来た。 どうやら、身内の誰かが運び込まれたようだった。 静けさが戻ったロビーで、私はふさぎ込んでいるヨッちゃんに話しかけた。 「私さ、昔凄くいじめられていて、死のうと思ったことがあったんだ。芳郎もその口でしょ?」 徐に顔を上げたヨッちゃんが、この上ない悲しみの色に染まった瞳のまま、小さく頷く。 「やっぱりな」 「何で?」 「ヒッキ―が惚れたから、そうかなって思ったんだ。あの子、小さいころから躰が弱かったから、何となく命のパワーみたいのが分かるんだって」 「なんだそれ?」 「気持ち悪いよね。私もそう思った。だけどそれには続きがあるんだ。その人の心が綺麗かそうじゃないかって言うのも、分かるって、だから私を最初に見た時、ピーンと来たって言っていた。この娘となら一生の友達になれるって。私、その頃、誰も口を利いてくれなかったから。そんな風に思っていてくれる娘が居たなんて思わなかった。でね、男子とか、もう打つわ蹴るわで、女子も口汚い言葉で罵って来ていたし、教科書なんてボロボロにされてね、教師は見て見ない振りすんだよね」 「最悪。そう言う奴に限って、普段はそんな節も見せない生徒だったから、気が付かなかったって言うんだよな」 鼻息荒く言うヨッちゃんを見て、私は小さく笑う。 「我慢できなかったな。もう人生止めちまおうって、フラフラと死に場所を探して、どうせなら学校で死んでやろうと思って行ったんだ。体育館の裏にある木にロープぶら下げてさ、エイってぶら下がったのは良いけど、ブツンとロープが切れちゃってさ、もう情けないのやらなんやれでいると、ゲラゲラと人の笑う声がして」 「ああ分かった。ヒッキ―だ」 「そう、広川夏妃がね腹を抱えて笑っているんだ。涙なんか流してさ。クラスとか一緒になったことないし、あんまり見覚えがない子でさ、最初、幽霊じゃないかと思っちゃったわよ」 「なんか想像つく。真っ暗だし、あいつ、いつも顔色悪いからな」 「散々笑った挙句に言うんだよね。死ぬほど辛いならもうちょっと痩せればって。きついよね。ドバっと涙が出て来て、うるせぇって思わず怒鳴っちゃったもん」 「本当にあいつは、地雷踏むからな」 「怒って、わんわん泣いている私に、ヒッキ―ったら、私広川夏妃。あなたと同じ学年だけど知っているなんて抜かしやがった。知る訳ないでしょって、言い返すと、ヒッキ―って呼んでねって握手を求めて来たんだよ。信じられる? その後、当たり前のように姉貴を呼ぶから待っててって言うと、あっという間に秋穂さんが現れ、私に事情聴取を始めたんだよね。それからの行動は早かったよ。私がいじめられている姿を、隠し撮りしていたって、学校相手に訴訟を起こし、いじめの主犯格の親も呼び出して、全てを話させられたわ。もう死ぬほど嫌だったけど、一度死んだんだから、お安い御用でしょって、ヒッキ―に言われて、もうブルブル震えて訴えたわよ。ウチの親も私の首のあざを見て、わんわん泣き出すしさ、私を学校に行かせないと言ったけど、どうしてですか? 登志子さんは全然悪くないですよ。むしろ、いじめにかかわった子達が一人一人、土下座をして謝るべきだと、思いますけど。ヒッキ―と秋穂さんが口を揃えて言ってくれて、クラス全員が私に土下座をして謝ったの」 「すっげーな」 「校長とか、担任とかも辞めさせちゃったしね。主犯格の子は保護観察扱い寸前まで追いつめて、転校させちゃったしね。そこまでする必要はないんじゃないって言ったらさ、あいつはダメ。性根が腐っている。ほとぼり冷めたら逆恨みで、あんたが殺されちゃうって、ヒッキ―が言い出してさ。そして最初の話に戻るけど、私には心が綺麗かそうでないかが分かるんだって言い張られて、それから腐れ縁になったんだ」 「だからか。俺がめちゃくちゃ落ち込んでいた時、タイミングよく話しかけられたんだ。吹部大変とか言われちゃって、一度も口を利いたことがなかった女子だったから、きょとんとしちゃってさ。それでもお構いなしで、話しかけて来るもんだから。何となくずるずる話すようになって、気が付いたらこういう関係になっていたんだよね」 「それはヒッキ―の作戦勝ちだわ」 「え?」 「ヒッキ―、入学式の時から、芳郎のこと、気にいってたみたいだから」 「そうなの?」 「例によって具合悪くなったヒッキ―がふらふらしだしたら、大丈夫って訊いたんだってさ。それで、近くにいた先生に言ってくれて、保健室に逃げ込めたって」 「全然覚えていない」 「そう言うものだよね」 「ヒッキ―!」 その声に驚いた私が、叫ぶように言うとヒッキ―が弱弱しく笑って見せた。 「大丈夫なの?」 「明日は、安静にしてろだってさ。帰ろう」 私たちはヒッキ―を支えるように、マッチとヨーデルが待つホテルへと帰って行った。 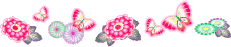 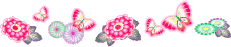 ブーゲンビリアの花言葉・・・情熱。あなたは魅力に満ちている。 戻る ×
|