酬い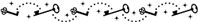 「ね、怖いでしょ」 加藤幸恵は見ず知らずの男に、今朝見た夢の話をしていた。 思いがけずに残業を命じられてしまった幸恵は、空腹に耐えかねて会社を出た足で、居酒屋に寄り、食事がてら酎ハイジョッキを3杯ほど空にしたあと、このホームにやって来たのだ。 ほろ酔い気分で、スマフォ片手にやって来たのは、理由があった。 幸恵は暗がりが大の苦手で、本来なら一人でこんな時間までいるなど、論外。考えられないことだった。7時まで残業して、一人で居酒屋などというより道は、あり得ない話。普段の幸恵なら絶対しない。でも、今日は違う。5年も付き合った彼と別れ、その彼を奪ったのが、これまたずっと可愛がってきた後輩の子だった。今日のように仕事が遅くなった二人は、やはり空腹に耐えかねて一緒に食事を摂ることにした。今日と違っていたのは、うちにおいでよと言う幸恵。良いんですかと、甘ったれるように上目使いで見る和実。 あの日、私の彼を紹介するよと連れて行ったのが間違いだった。 駅前のスーパーで食材を買い込み、三人で鍋を突っつく。 楽しいひと時が過ぎ、和実は一晩を我が家で過ごし帰って行った。 まさか二人がそんな関係になってしまうなんて思いもせず、傍らの彼と共に、むしろ自分の幸福を見せつけたことに、優越感さえ持っていた幸恵は、また遊びにおいでねと、和実に手を振り見送った。 アパートに帰っても、もう灯りはついていない。 人気がないホーム。ぼうっとベンチが明かりに照らされ、浮かび上がっているように見える。そのベンチに一人、中年の男性が蹲るように座っていた。幸恵は吸い寄せられるようにその男性の横に座りスマフォを弄りながら、気が付くと、今朝見た夢の話をしていた。 その男は穏やかな笑みで、それは怖いですねと言って頷く。 優しそうなその笑顔に癒され、我を忘れて幸恵は話を続ける。 「あり得ないですよね。死神なんて。超びっくり。鎌ですよ鎌。こんな大きな。タロットカードにも出てこないような。それにあれですよね。死神なら死神の風情って言う物がありますよね。もう顔なんか骸骨で、いかにも死神って感じの」 闇の中にぽうっと明かりが見え、その男がにこにこと、来ましたねと言って、ベンチを立ち上がる。 静かにホームに滑り込んできた電車のドアが開き、男が先に乗り込む。 「お嬢さん、あなたはラッキーだ。私に出会えた」 乗り際にそう言われ、幸恵は戸惑うように微笑む。 一旦電車に乗り込んだ幸恵は、ベンチにスマフォを忘れているのに気が付き、慌てて取りに戻り、そこでドアが閉まってしまう。 座席に座る男性の後頭部が、虚しく遠ざかって行くのを見送り、幸恵はため息をつく。 私も人のことを言えた義理じゃない。 妻から奪ったのだから。 しかも彼だけではなく、その妻の命さえも。 その話を聞いて一滴の涙も出なかった。むしろホッとしてしまった。もう自分たちを束縛しようとするものはない。そう思っただけで自然と笑いが出てしまった。 勝者の笑み。 私は勘違いしてしまっていた。 だから、こんな目に遭ってしまったんだろう。 幸恵は謝ってホームから転落。入って来た電車にはねられてしまった。 徐行していたため一命は取り留めたが、幸恵にはもう生きている価値のない躰しか残っていなかった。 死にたくても、もう手もない。足も動かない。意識だけがはっきりとしている。 あの男が残して行った言葉。 「私は全てを奪わない。最高のプレゼントをあなたにあげましょう」 やっとその言葉の意味が分かった幸恵には、もう涙を流す機能も残っていなかった。 戻る ×
|