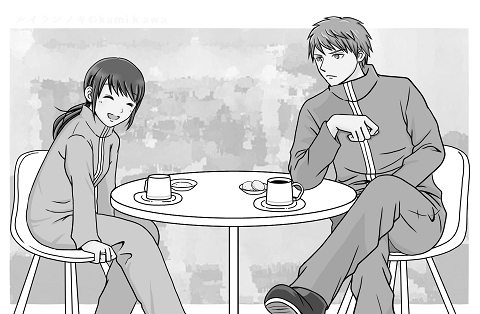voice of mind - by ルイランノキ |
因果の闇6…『優しい嘘』 ◆
午後9時過ぎ。
シドが宿に戻ると、フロントにあるカフェのようになっているフリースペースでアールがコーヒーを飲んでいた。
「あ、おかえり。遅かったね」
「なにやってんだよ」
と、シドはテーブルの向かい側に座った。
「この前ここでコーヒー頼んだら美味しいクッキーがおまけについてきたの。また食べたくなって」
「おまけのクッキー目当てかよ」
「シドもなにか飲み物頼んだら? あ、そうだ訊きたいことがあったんだ」
アールはシキンチャク袋を漁った。
シドはテーブルの上に置いてあった小さなメニュー表を手に取った。
「この人、見たことない?」
アールが取り出したのは、陽月とその恋人の似顔絵だった。
「誰だこれ」
メニューを置き、似顔絵を手に取った。
「陽月と、その恋人と思われる人。男の人の二の腕を見て」
「……属印?」
と、眉間にしわを寄せた。
「そうなの」
アールはシドが眠っている間にエイミーに会いに行って似顔絵を見せてもらったことを説明した。
「でね、憶測ばっかりだけど、やっぱり私がこっちの世界へ来る前に、組織の人間が私の世界に来ていたんじゃないかと思って。もしくは、私の世界の人がこっちの世界に来て組織に入ったとか」
「…………」
シドは似顔絵の男を眺めた。まったく見たことがない。
「どう思う?」
「どうって言われてもな」
「なんか飲む?」
「あ? あぁ、じゃあブラック」
「──すいませーん」
と、フロントの男性に声を掛け、ブラックコーヒーを注文した。
「もしその憶測が合ってたら、誰が別世界への扉を開けたの? ってことになるよね」
「まぁな。1人いるなら2人いても不思議じゃねぇが」
「黒魔術だよね?」
「組織にはそんなもの関係ないだろ。崇拝しているシュバルツ自身禁忌を犯して化け物化してんだから」
「そっか……シドは聞いたことない? 組織の中で別世界への扉を開けることが出来る人がいるとか」
「下っ端には上の情報はあまり入ってこないからな」
と、似顔絵を返した。
「そっか……。アサヒさんにも聞いてみよっと」
「…………」
シドはジトーッとした目でアールを見遣った。
「え、なに?」
「警戒心ねぇなと思ってな」
「してるよ警戒。ここ最近、自分は絡まれやすくてトラブルを引き起こしやすいって自覚したんだから」
「自覚すんのおせーよ」
──と、そこにブラックコーヒーが運ばれてきた。こちらも2枚のクッキー付きだ。
「なんか変な感じ。シドとお茶してるの」
「…………」
シドは無言でコーヒーを啜った。──特別美味くはない。
「ねぇ『俺は』ってなんて送ろうとしたの? カイに」
「あ? ……あぁあれか」
と、思い出す。「別に深い意味はねぇよ」
「そうなの?」
「やたらメール来てたからなんか返そうと思ったが特になにも言うこともなくやめただけだ」
「なんだ……てっきり『俺は戻らない』とかそういうメールを送ろうとしたのかと思った」
「んな文章送ってたら余計にお前ら騒ぎ立てるだろうが」
「それは否定できないけど」
と、アールもコーヒーを飲む。
「あ、もうひとつあったんだ」
アールはカップをテーブルに置いてまたシキンチャク袋を漁る。
「次はなんだよ」
「これなんだけど……じゃーん!」
と、仲間とお揃いのブラスレットを見せた。シドが捨てたものだ。
「……なんでお前が持ってんだ?」
「巡り巡って私の手に……。捨てたの?」
と、ブレスレットを眺めながら訊く。
「捨てた。」
「きっぱり言うかな普通!」
「嘘ついてどうすんだよ」
「優しい嘘くらいつきなよね!」
「ベンだったかワードだったか持ってったはずなんだけどな……忘れたな」
「新しいブレスレット買おうと思ってるんだけど」
「…………」
シドは無言で嫌な顔をした。
「そんなあからさまに嫌な顔しなくたっていいのに」
「はっきり言ってお揃いとかダサすぎねぇ?」
「…………」
アールは黙ったままブレスレットをポケットにしまった。
まぁ、ルイとカイはともかく、ヴァイスもあまりいい気分ではないんだろうなと思う。
「…………」
シドはコーヒーを啜り、ちょっと言い過ぎたかと思い直す。
「せめてもっと洒落てるやつにしろよ。しかもあれ防御力上げるやつだろ」
「! 知ってたんだ……」
「あたりめぇだろ」
「じゃあ今度はかっこいいやつ探してみる。今お金ないけど」
「お前ら金欠だったらしいな」
「稼ぎ手のシドがいなくなったからね!」
と、怒る。
シドは笑った。
「あとまだまだ訊きたいことあるんだけど」
「めんどくせぇなぁ……」
と、クッキーを口に放り込んだ。
「クッキー食べるんだ……」
「食っちゃわりぃのかよ」
「狙ってたのに……」
旅を再開すればゆっくり話をする時間もなくなるかもしれない。聞きたいことは今のうちに聞いておこうと思った。
「シドは、半信半疑だったんだよね? 私のこと」
「あぁ」
「組織の仲間になってたけど、私のこともしかしたらって思ってくれていた時もあったんだよね?」
「ダル……。なんだその質問」
「いいから答えてよ」
「だからお前に振り回されて苛立ってたんだろうが。何度見切りをつけたか」
「じゃあなんであんなこと言ったの? ずっと言葉の意味が気になってた。シド私に言ったよね?『お前もタケルと同じ道を歩めばいいと思う』って」
「…………」
「あれ、どういう意味……?」
あれは、アールがゼフィル城に戻されたときのこと。
ルイやカイが何度もアールに電話を掛けたが出ないと嘆いていたのを見兼ねてシドが電話を掛けてみたら何事かとやっと電話に出た日。アールがシドにタケルがグロリアだったらよかったのかと聞いたとき、暫く沈黙があって答えた。『お前もタケルと同じ道を歩めばいいと思うよ』と。
シドはそう言って電話を切ったのだ。
「あれって、私も死ねばいいのにってことなの……?」
「すげーぶっとんだ解釈すんだなぁ……」
「だってどう考えてもそうじゃん!」
「お前も偽者だったらってことだよ。そしたら丸く収まるのにってな」
「……嘘じゃん絶対」
「なんでだよ」
「無理あるもん。“同じ道を辿れ”って言い方、私の解釈の方がしっくりくる」
「まぁあん時は心底お前に苛立っていたし、やっぱ偽者なんじゃねぇかと思ってたからお前よりシュバルツを崇拝してた。タケルと同じように騙されてるだけならさっさと自分の世界に帰れって思っただけだ」
死ねばいいのに。余裕のない苛立ちからそんな感情が湧き出て発した言葉であったことに間違いはないけれど、今の自分はそれを否定したがるから仕方なく無理がある言い訳を並べている。
シドはちらりとアールを見遣ると、アールは怒っているような悲しんでいるような複雑な表情で視線を落としていた。納得していないのだろう。
「選ばれし者はタケルだったらよかったのになって言ったことなかった?」
と、アールは口を尖らせる。
「あったっけか? 覚えてねぇよ」
「覚えといてよ! 傷ついたんだから!」
「じゃあ忘れろ。そん時はそう思ってたんだろうよ」
「もう!」
と、泣きそうな顔でコーヒーを飲んだ。
「覚えてないんなら優しい嘘くらいついてくれてもいいのにっ」
「──あの時はタケルのがいいと思ったけどその後はお前のがいいと心から本気でずっと思っていました。」
と、棒読み。
「下手か。優しい嘘下手か!」
「お前が嘘をつけって言ったんだろーが。感謝しろ」
「下手くそな嘘に感謝できるか!」
「クッキー食うか? もういらね」
と、クッキーが乗っている小皿をアールの方へ指で弾いた。
「あ、うん。いただきます」
アールは残りのクッキーを貰った。
シドは視線を落とし、タケルのことを思い出す。
「まぁ、今考えても、選ばれし者がタケルだったらよかったとは思う。タケルと違ってお前は……しんどそうだしな」
「…………」
なにも言えない。
「それに、お前こそ偽物で城に帰したお前があのまま城から戻らずどっかに逃亡してくれれば、俺はお前を殺さずに済むのにって思ってた」
「…………」
「タケルの死は今でも悔やみきれない。けど、お前に残した動画を見る限り、あいつはあの日、自分の意思で外へ出て行ったんだろ? 少しでも力を身につけるために、危険を承知で。それなのに命を落とすことになって悔しかっただろうが、あいつの気持ちを考えてもあいつが選ばれし者だったらよかったのにって思うわ。お前が嫌だったわけじゃない。胸糞悪かったけどな」
「胸糞悪いならもうそれ嫌いじゃん……」
シドは笑ってコーヒーを飲み干した。
「ついでだから組織に入ったときのことも聞きたい」
「ついでってなんだよ……」
と、気だるそうに背もたれに寄りかかる。
「シドが組織に入ったのは、タケルが亡くなってからだよね?」
「俺が組織に入ったのは、タケルが死んだ後だ。タケルは偽物だと聞かされて、正直ゼンダといいギルトといい、何を考えているのかわからなくなった。短い間だったがタケルと共に生活をして、あいつの熱意やこの世界に対する思いだとか、自分の使命を受け入れる姿や必死さを見てきた俺からしてみれば、騙され続けてきたタケルが哀れで仕方なかった。それと同時に、ゼンダへの怒りを覚えた。世界を救う選ばれし者を召喚するのにお試しで召喚されて選ばれし者だと嘘で祭り上げられてその気になったタケルが決意を決めた途端に力を無くして死んでったんだぞ」
「うん……」
「そんな矢先に本物のグロリアを召喚するのにギルトの力が戻るのを数日間待つことになって、その間に俺は一度実家に戻った。そこで会ったんだよ。ベンと、ワードに。そのときはまだ俺がグロリアの付き人として選ばれたことは知らずに組織への入隊を促してきた。詳しく聞いてみりゃ、驚くことばっか口にしやがる」
「何を聞かされたの……?」
「歴史の真実だよ。シュバルツは元々ただの人間だ。魔導士で、力を備えていった。世間は自分の力に自惚れて暴走したシュバルツを悪とし、シュバルツを封じるために現れたアリアンを神として崇めた。そもそもその言い伝えが間違っていたと知らされた」
「…………」
「シュバルツも、未来を見る力を持っていたんだ。そして世界を滅ぼす邪悪な力がこの星に迫っていることを知り、それを阻止するために力を備えていった。その邪悪な力ってのが、アリアンだ」
「それを証明するものはないよね? 見せられた未来も偽物かもしれない」
「それはギルトが見た未来もそうだろ。その未来が本当に訪れる証拠はない。──俺は、ギルトとゼンダに不信感を抱いてた。そん時にそんな話を聞かされて腑に落ちた気がしたんだ」
「アリアン様は人々の声を聞いて、願いを叶えたんでしょ? その伝説はいくつも残ってるみたいだし、世界中に湧き出たアリアン様の力が含まれた聖なる泉も、旅人の疲れや怪我を癒してる。それに比べてシュバルツは世界に魔物を生んだ。戦いに巻き込まれた人々も多くいた。それだけでも十分彼女が世界を救った救世主であることの証明にはならないの?」
「だからそれを証明するものはねんだよ。当時生きてた人間もいねーんだし。あの塔にならあるのかもしれねぇけどな」
[しおりを挟む]
[top]
©Kamikawa
Thank you... |