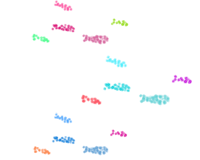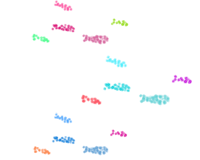
さゆる
空港内にあるカフェの一人席に二人で隣り合ってそれぞれ座っている。どこもかしこも人だらけでこの席しか空いてなかった。
「……」
「……」
それぞれ頼んだ飲み物のカップを握りしめて無言になる。なんなんだろう、これ。見送りに来てくれるなんて思ってなかったから、予想外すぎて頭がパンクしそうだ。
「…なんで今日の出発教えなかったんだよ」
「メールで言ったよ」
「おっせーんだよ!」
「ごめんね!!」
「……」
「……」
いきなり声が大きくなるから反射的に謝ってしまった。それからまた沈黙。なにか話題を探したいけど、賢二くんがなんだかいらいらしてるようで選択が難しいな…。教えるのが遅くなったこと、そんなにショックだったの?返事は頑張ってってシンプルだったのに。
「あとさ、なんでメールしてこないわけ?」
「………はい?」
「前みたく普通にしていいって言っただろうが」
賢二くんの言葉をきいて思わず瞬き。なんだ、あんなに悩んだのに。賢二くんが見栄を張って言ってくれたんじゃないかと、迷惑だったんじゃないかと考えていたのにね。どうやらわたしが勝手に一人でうだうだ考えていただけだったみたい。
「…うん。そうだね、ごめんなさい。していいって言われたし、するって言った」
「ああ、忘れてんじゃねーよ」
「……でもさあ、賢二くん」
「なんだよ」
「わたしたちの普通って何なんだろうね」
「それは、」
賢二くんが何かを言おうとしてから口を噤んだ。前を向いたりこっちに視線を寄越したり、視線をふよふよと彷徨わせている。それから、何かを決心したように小さくため息をついた。
「普通って言い方は悪かったと思ってる。普通にしろったって、できるわけなんかないんだよな」
だからさ、と言って賢二くんはわたしの方へ向き直った。思わずカフェオレの入った紙カップを握る手に力を入れてしまって、カップの蓋が外れて落ちて行く。何となく目が合わせられなくて視線をはずして、蓋を拾おうと伸ばした左手の手首を賢二くんに掴まれた。
「何度も同じやり取りするつもりなんてないから」
「なに、を」
「オレらの普通はとっくに変わってて、前と同じになんてできやしないんだ。だったら、お前が好きなようにしていい。メールも電話もしたいって、言ってただろ。」
その言葉に気付けば視界が曖昧で潤んでた。好きなようにしていいなんて勘違いしちゃうじゃん。わたし、これからアメリカいくのにさ。離れ離れになってしまって、たまたま顔を合わせるなんて機会もごっそり減って、本当ならこのまままたバラバラになれるのに。チャンスがあるのかもしれないって思っちゃうじゃん。そう思ったら、忘れられるわけないよ。
「また泣くのかよ…」
「うるさい!」
賢二くんはわたしが賢二くんのことをどれだけ好きかわかってないんだろう。だから、小さい頃に泣いてたわたしをあやすみたいに困ったように笑うんだ。それで、わたしが欲しいと言うものをあげようとしてくる。それでいて、本当のところは手に入らないなんて。夏目さんが言うように賢二くんは優しくないのかもしれない。きっぱり諦めさせてくれない、ひどい人なのかもしれない。だけど、それを望んでる自分もいて、馬鹿だなあとも思うよ。数日前に流しきったと思った涙はぼろぼろと零れてくるし、この前は泣いてるわたしに吃驚してた賢二くんだけど、今回はちょっぴり呆れた顔をしてハンカチを差し出してきた。
「またハンカチ持ってねーの?」
「も、持ってるよ!バッグの中にあるし!」
「いーから使えよ。汚くないし」
「でも、」
「泣かせたまんまだと目立つんだよ」
差し出していたハンカチをそのまま目元にぐいっと押し付けられる。ちょっとだけ乱暴に拭くから、思わず賢二くんの手から奪って自分で拭った。
「洗って返したいけど国際便になっちゃうね…」
「そんなのいつだっていいだろ。帰って来てからでも」
「まあ賢二くんならいっぱい持ってて困ってないんだろうけどさ」
日本に帰って来てから賢二くんに会う理由が一つできたことに喜んでしまっているわたしは本当に単純みたい。
「…そろそろ行くか」
「まだ時間大丈夫だよ?」
「あいつら来てんだろ。きっとお前探して歩き回ってるよ。向こう行ってからちゃんと会っとけばよかったって思っても遅いんだからな」
「たしかに」
借りたハンカチを握ったまま、二人でカフェを出た。やっぱり年末の空港は人だらけで、ロビーの方へ向かう人々でごった返してる。二人で横に並んで歩く。さっきまじまじと見つめていた大きな背中は見えない。
「紗希乃」
「なあに」
「向こうでも頑張れよ」
「それもうメールで聞いたよ」
「素直にありがとうって言っとけよバカ」
「泣くなとも言われたけどもう泣いちゃった」
「いいだろまだここは日本だし」
「いいのかな」
「いーんだよ。向こうでは泣くなよ。誰も慰めらんないんだから」
「泣くことあるのかな」
「無いとも限んないだろ」
「そうかな」
「そうだよ」
ふいに賢二くんがぴたりと歩くのをやめた。二歩くらい先に行ってしまって、不思議に思って振り向くと賢二くんが笑っていた。
「オレはここまでにするよ。あいつらと会うといいことがないんでね」
「水谷さんがいるから?」
「ちげーよ!」
わたしが先に行った二歩を賢二くんは軽々と一歩で距離を詰める。やっぱり大きい掌はわたしの頭をぽんぽんと撫でた。
「大丈夫。ちゃんとあいつらも他のやつらも日本で待ってるから」
「……賢二くんは?」
「当然だろ。ちゃんと待ってんだから、安心して行って来いよ」
馬鹿だなあ、なんて思われてるのかもしれない。けれど、笑ってそう言う賢二くんの言葉はとてもあったかい。半年ばかりでも留学することに不安を抱かなかったわけじゃない。けれど、どこか軽くなった。賢二くんの一言一言にこんなに気持ちを左右されるなんて何だか悔しい。最後になにか仕返しをしてやりたいくらい。
「うん。ちゃんと自分がやりたいこと勉強してくるよ。半年しかないけど成長できるだけいっぱいいっぱい成長してくる!だからね、賢二くん」
「おう」
「わたしを選んでおけばよかったって後悔させるくらい成長してやるんだから!」
「はあ?!」
あ、また泣きそう。苦し紛れにあっかんべえをして、走る。少し離れたところで振り返ると、賢二くんが吃驚したような顔で立ったままだった。
「来てくれてありがとう!バイバイ!またね!」
手を大きく振って、大きな声で言うと、賢二くんは恥ずかしそうにしながら小さく振り返してくれた。それに安心して、また走り出す。ああ、顔どうにかしないと嬉しいんだか寂しいんだかわかんない顔してるんだろうな。伊代ちゃんや夏目さんたちにつっこまれちゃう。一応、最後なんだからいいのかもしれないけど、ちょっぴり恥ずかしい。
「っはー、頑張んないとっ!」
顔を掌でたたいて、気合を入れた。本当に泣いてらんないぞ自分。朝よりも増えた人の合間をぬって、前に進んだ。