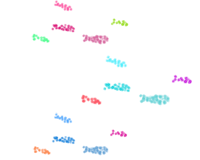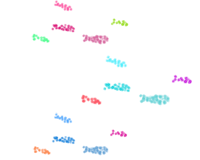
ゆきもよい
「パパとママは年が明けたら行くから、その時にでも学校を見学しに行きましょ。」
「正月に学校って空いてるの?」
「三が日なんてあるの日本とかアジアくらいでしょ。」
「そっか。確かに。」
空港へ向かう途中の車の中、後部座席にママと二人で乗っている。大きな荷物は向こうへ送ってしまったし、持って行く荷物はキャリーケースひとつだった。財布とパスポートやチケットが入ってるだけの小さなショルダーバッグだけでとっても身軽だ。ママもパパもお仕事が忙しくてわたしと同じタイミングで渡米できないのがちょっとだけ残念。まあ、向こうにはおばあちゃんが先に行っているんだけど、きっと仕事が忙しくて構ってもらえないとは思ってる。晩御飯くらいは一緒に食べたいけど、そうもいかないんだろうな。
「パスポートは?チケットは?お金は持ってる?」
「家出る時に確認したじゃん。大丈夫だって。」
「だって、一人でアメリカ行ったことないじゃない。」
「一人で帰って来た時はあったよ。」
「それは飛行機に乗るまでパパがいてくれたから、一人だったのは飛行機のなかだけだもの!」
「それはそうだけどさあ。」
パパの仕事の関係で、わたしだけ先に日本へ帰ってきたりだとかもあったけど、全部ひとりなのは本当に初めてだった。ちょっとだけ気を引き締めて行かなきゃとは思うんだけど、それにしても心配しすぎだよ。それを言ったら、用心するに越したことはないとキッパリ言い切られた。
「じゃあ、ママはもう行かなくちゃいけないからね、荷物は先に預けておくのよ。」
「うん。いつもみたくすればいいんだよね。」
「そうよ。わからなくなったら空港の人に聞きなさい。じゃあ後でね。」
「はーい。ばいばい。」
わたしとキャリーケースだけを降ろして車は行ってしまった。ママに言われたとおりにキャリーケースを預けて、時間になるまでぷらぷらすることにしようか。年末でごった返す空港の中を一人歩いていく。ここにいる人たちはお正月のバカンスで日本を出て行くんだろう。わたしみたいに半年も日本を離れる人はいるのかな。って言っても半年なんてあっという間だよね。今から半年前って言ったらそうだなあ……賢二くんと再会したのはそのあたりだった気がする。春から夏に変わるころ、お互いに一発じゃ気付けないくらいに変わっていたっけ。キャリーケースを預けて歩きながらぼけっと考える。この半年の中で本当に色んな事があった。ほとんど賢二くん絡みなのが何だか悔しいなあ。これからいくらでも一人で考えられる時間があるっているのに、忘れるどころか何でもかんでも賢二くんが出てくる。もう、出てこないでよ。なんて思っちゃうけど、どこか安心してしまうのも事実だったりする。ヘンな時に思い出すまでもなかったね夏目さん、日本を出てすらいないのにこのざまですよ。はあ、と溜息がこぼれてくる。日本への旅行者向けなのか、空港には和柄のグッズがたくさん売ってあるお店があった。そこでみつけた万華鏡をひとつ持ち上げて、覗き込む。痛いくらいに派手な黄色や赤やいろんな色が筒の中で形を変えていく。こんな風に人の気持ちも変わって行ってくれたら楽ちんなのにな。黄色が姿を見せなくなって、赤や緑に覆われたまるい円を覗き込むのはやめて万華鏡を降ろした。そうしたら、なぜか視界の隅でちかちかと黄色がはじける。
「賢二くん……?」
なんでいるの?喉からでてきそうな言葉を飲み込んで、万華鏡を棚に戻してさっき歩いてきた道を走る。なんでわたし、走ってるんだろう。なんでこんなに逃げたいんだろ。なんで賢二くんは……
「な、っんで!逃げんだよ!」
「ううっ、くび、しまってる!」
「あ、スマン。」
そもそもの手足の長さで賢二くんに勝てるわけがない。後ろからコートのフードを掴まれて首がしまる。ぐいっと引っ張っていたそれを賢二くんは一度パッと離したのに、もう一度つかんだ。もう首は締まってないけど、まるで子供がどこかへ走って悪さをしないように保護者が掴んでいるようだった。
「こーでもしないとお前逃げるだろ。」
「に、逃げないよ?」
「だったら今さっきお前のとった行動を思い返してみろ。」
「…ごめんなさい。」
フードを掴まれたまま賢二くんに向き直る。クリスマスぶりの賢二くんは何も変わってない。あたりまえだけどさ。
「なんで逃げたのかなんてわかりきってることだから聞かねーけど、できるならそういうことすんな。」
「うん、ごめん。元通りになろうって言ったのにね。」
「それだけど、」
「なに?」
「……おまえ、飛行機何時?」
「13時半。」
「はあ?」
「は、ってなに!」
「伊代が10時に車出すって言ったからもうちょい早いのかと思って。」
「わたしもそのくらいに家でてきたよ。っていうか、伊代ちゃんもいるの?また一人でふらふら動いてんじゃないの賢二くん?!」
「伊代がいなくなったんだ。オレは悪くないね。あいつがトイレ行くって言って戻ってこなかった。」
「この混雑具合だったらそりゃトイレも並ぶよ!動かないでねって言われなかった?」
「知らない。」
伊代ちゃんは絶対に動かないでって言ってたに違いない。そうだ、絶対そうだ。この状況で行方不明になれば下手したら放送で呼び出しされるレベルだもん。
「立ち話も何だしカフェでも入るか。」
「賢二くんそっちじゃないよ。」
「これはたまたまだ。久々だったら間違えもすんだろ。」
「そうだね、あんまり空港なんて来ないしね……。」
先に行こうとした賢二くんは、くるりと方向を変えてカフェのある方に歩いていく。その後ろをついていくと、何だかいつもより賢二くんと距離が近いことに気が付いた。歩くのが大変じゃない。ヒールの有る無しとかじゃなくて、距離的になんだか近い。一歩先を歩いているけれど、これまでの賢二くんの歩幅と比べたらいくらか小さい。急いで追いかける必要がないから、賢二くんの背中をまじまじと見つめた。大きいんだなあ。
「……おい。」
「ん?え?なになに?」
「だから、ここでいいかって聞いてんの。」
「あ、うん。ここでいいよ。下手に動いてもあれだし。」
「そうだな。」
店員さんを読んでいる賢二くんの後姿を見ながら、首を傾げる。あれ、もしかしてわたし普通に話せてる?前よりも上っ面になっているかもしれないと、確かにそう思ったんだけどなあ。
「紗希乃。」
「はいっ」
「あっちしか空いてないって。」
「了解〜。」