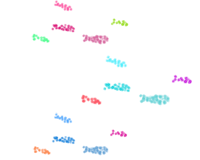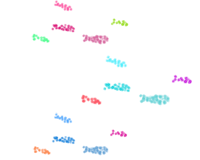
あきついり
文化祭。少し肌寒くなるこの時期に毎年行われるから服をどうしたものかいつも悩む。去年はわりと暖かかったけれど、今年は風が少し冷たい。
「よお!吉川じゃねーか何だそのカッコ、大正時代の女学生か」
「すごいね衣装テイストをここまではっきり当てたのあなただけだよ吉田くん」
出店が並んでいる通りを歩いていると、クレープ屋の屋台で楽しそうにクレープを焼いている吉田くんに遭遇した。わたしの衣装は、矢羽根模様の着物に袴、そして編み上げブーツ。吉田くんの言う通り大正の女学生風なんだけど、周りの子はイマイチ分からなかったみたいで大学の卒業式かと言われた。まあ、それもありっちゃありだけどね。
「お前が着ると古臭く見えないな!シズクが着たらきっともっさくなるぞ!」
「それってだいぶ水谷さんに失礼だと思う」
そーか?とけらけら笑う吉田くん。この前のマスコミの一件からわりと話すようになった。大体が水谷さんの話で、少しだけ山口兄妹の話をする。あの二人の内容といっても大抵ナルシストストーリーなわけだけど。
「これから友達のお迎えに行くの。後でクレープ買いに来るからね」
「おうさんきゅー!」
現在進行形で彼が焼いているクレープに明らかにクレープの材料じゃないものが投げ込まれているのは見ていない。わたしは断じて見ていない。(吉田くんがシフトじゃない時に来よう…)
*
昔からの友人を迎えに行き、一緒に伊代ちゃんのクラスの演劇を見た。伊代ちゃんが大好きな友人は嬉しそうにパシャパシャ写真を撮っていた。確かにあの天照の衣装は伊代ちゃんにとてもお似合いだった。わたしもデジカメで写真を数枚撮った。伊代ちゃんママに今度プレゼントすることにしよう。
これから合コンがあるという友人たちを見送って、自分のクラスに戻ろうと校舎に向かった。そうだ、夏目さんたちのクラスに少し顔を出してこようかな。お好み焼きを買ってクラスに戻ろう。夏目さんにメールでこれから行くことを伝えると、『今来たら例のあの人がいます!キケンです!』という意味不明な文が返ってきたけど、もう着いてしまった。
「夏目さーん、例のあの人って誰ー」
夏目さんの姿を見つけて声を掛けると、夏目さんの先にあるテーブルから、ばちこーん!いつぞやに貰ったウインクが飛んできた。
「これはこれは吉川のお嬢さんじゃないですかー、この前ぶりです」
「おい安藤他にも手出してたのかよ、やめろよ女子高生相手にー」
「え?え?吉川のお嬢さん?」
「だだだだめですよっ!吉川さんはお嬢様なんですからあなたみたいな野蛮な人に渡せませんっ!」
「野蛮も何も手すら出してないのにそう言われましてもねぇ」
「言動があぶねーんだろ」
「待って、安藤さんあの子と知り合いなんですか」
「そういう優山さんこそ知り合いなんですか」
バッティングセンターの店長に吉田くんのお父様の手先にメビウス様…。なんだコレ、吉田の一族が大集結してるのか。本人はいないけれど、何だか盛り上がっている。夏目さんの様子から推測するに、例のあの人は手先の人かしら。
「手先…いえ、安藤さんとは以前お会いしたことがあるだけですよ」
「いま手先って言いましたよね」
「いえいえそんな。ちなみに、メ…いや、吉田くんのお兄さんとはこの前病院で会いました」
「山口のお嬢さんもそうだけど、『メ』とか『メビ』って何なのかな」
「さ、さあ…」
危ない、心の中の呼び名があまりにも定着しすぎてそのまま呼んでしまうところだった。
「君、賢二くんの彼女さんなの?」
「ちが「えええええ!?吉川さん?!嘘ですよね!?どーして…どーして夏目には何も相談してくれないんですかぁぁ!!」
「夏目さん、話は最後まで聞いてほしいな。彼女じゃないですよ、あの日会ったのは偶然ですし」
「やっぱりーごめんねえ。あの時、僕けっこう不機嫌でさ。彼を煽るの楽しくて君を引き合いにだしちゃったんだよね…」
「確かに楽しんでましたねえ。で、もしかして、そのもじもじしてるのが本性なんですか」
「ブッハ!君おもしろいね!」
「はっはっはっ!優山さんは女性が苦手でしてねぇ!」
「こら笑うんじゃない!」
不機嫌だったと語るメビウス様は、またもじもじしていて何でそんなに顔を赤らめているのか疑問だったけど、手先さんの説明で納得した。なるほど。だからあの時、伊代ちゃんに迫られてあんなにテンパってたのね。
「いや〜、本当にごめんね。悪気はなかったんだよ」
「わたしは別にいいですけど、賢二くんには謝ってあげてください」
「え?なんで?」
「何でって……、わりと傷を抉るようなこと言ってたみたいじゃないですか。あの後、何だか変だったんですからね」
「まあ、それでもフラれることは人生に何度もあるでしょ」
「それには同感ですけど、あまりにもいつもと違いすぎたので酷いこと言われたのかと思って」
「まあ、自信家に見えるけど案外奥手だよねって言ったかな!」
「あの人のどこが奥手なんですかー!」
「まあまあ夏目ちゃん落ち着いて」
「きっと、本当に好かれたいから慎重になっただけでしょう?」
「……君は本当にそう思う?」
「思いますよ」
一体誰のことを言ってるのか。頭の中でもやもやする。思い出せ!そう言ってるようにぐるぐると回ってる。なんだこれ。何か忘れてる。大事なこと。大事だったから蓋をしたこと。なんだ、誰だ、忘れてる。いや、……本当に忘れてたの?
「だって好きになるのって簡単に忘れられることじゃないですもん」
忘れるわけない。
忘れられるわけない。
忘れた振りをしてただけだった。
都合のいいところだけ抜き出して、悪いところは蓋をする。君は何も覚えてないんだろうけど、わたしは覚えてるよ。きっと、今の君は別な人を見てるから振りむいてはくれないね。振り向いてくれないことだけは、昔も今も変わらないみたい。あぁ、わたし、賢二くんのこと好きだったんだなあ。今現在のわたしが賢二くんのことを好きかどうかはまだ曖昧だけど、昔のわたしは確かに賢二くんが大好きだった。何だってこのタイミングで蓋が開いちゃったんだか。全く…この後どうしてくれるの。
「はは、青いねぇ、」
店長さんのサングラスがキラリ。光ってわたしは我に返った。みんながわたしを凝視している。まずい、ちょっと物思いに耽りすぎたな。
「吉川さん!わたしが!この夏目が相談に乗りますよ!何てったって友達ですからね!」
「お嬢さんさえよければ私がお相手しますよー」
「安藤さんそれはダメでしょ!」