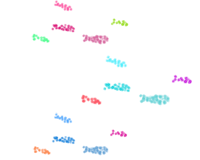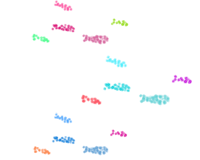
みじかよ
短い夏がもうすぐ終わってしまうなあ。今年の夏は去年と比べて結構遊べた気がする。避暑地では山口兄妹ご一行に遭遇して、なんやかんやと一緒に騒いで、パパの仕事についてアメリカに少し滞在した時は観光もできたし、帰国後は松陽の友達とたくさん遊んだ。今日のお祭りは音女に進んだ幼等部の頃からの友人たちとお祭りに来ている。
「でね〜ユカリがさ〜」
「それこないだ電話で聞いたしー」
「紗希乃は何かないの?」
「それが驚くほどなーんにもない」
「何もしてないだけでしょー」
「うちらの合コンおいでよ」
「やあね、どうせ三バカくんかヤマケンくんしかいないんでしょー」
「「可能性は高い」」
「だったらいいよ、ふたりの話でお腹いっぱいだもん」
世の高校生はこんなに合コンに命をかけているのか…。応えは否だろう。音女はお嬢様学校ってだけあって遊んでるイメージしかない。松陽でできた友達はみんな部活をしているし、今日だって部活があってお祭りに来れないと嘆いていた。
「好きな人、いないの?」
「いないんだよねえ。誰でもいいわけでもないハズなんだけども」
「理想がハッキリしてないやつね。わかるわかる。すぐにブレちゃうもの」
「あんたの場合男に全部あわせるからでしょー」
お祭りをひとしきり楽しんで、さて帰ろう。そうなった時、さすがお嬢様。それぞれ家の迎えを電話で呼び付けた。
「紗希乃も呼ぶでしょ?」
「うん。でも、すこしぶらっとしてからにしようかな」
「気を付けてよー?ひとりじゃあぶないんだから!」
「はーい!ふたりも気を付けてね?」
迎えを呼んだ二人から離れてカランコロン、下駄を鳴らして歩く。お祭りから少し離れた所に歩いていく。実は、下駄で足の指が擦れてとても痛かったの。すぐに迎えを呼んでもいいけど、とりあえず絆創膏を貼ってから呼ぼうと思った。その後、ママのお土産にたこ焼きを買って行ってあげようかな。
神社の脇に逸れて行った先に、人気のないベンチがぽつん、とあった。少々不気味だけど、絆創膏を貼るだけだし我慢しよう…、そう決めて余計な所に目線を送らないようにしてベンチに座った。
微妙に暗くてイマイチうまく剥がれない。うーん、ふたりがいるうちに貼っておけばよかったかなあ。
「……何してんの?」
「ひい!」
突然肩に誰かの手が降りてきた。驚いて、身を縮こませていると、「オレだよオレ」とオレオレ詐欺まがいにあった。ナンパにオレオレ詐欺はどうかと思うの。それでも、おばけとかそういった類のものじゃないことに安心して、顔を上げると見知った人がベンチの後ろに立っていた。
「賢二くん?」
「なんで疑問形なんだよ。他の誰に見えんの?」
「似てると言えば伊予ちゃんだけど」
「やめろ」
パシン、と軽く頭をはたかれる。そんなに伊予ちゃんが嫌いか。むすっとした表情の賢二くんは、わたしの隣りに腰かけて横目でちらりとこっちを見た。(その顔すっごい似てるよ)
「で、こんなとこで何してんの?」
「足に絆創膏を貼ろうと思って」
気付けば、ぐちゃぐちゃになった絆創膏しか手元に残ってなくて。ああ、こりゃ無駄なことしかしてないなあ、と思った。最後の一枚は、賢二くんに驚いた時によれよれになってしまった。
「ふーん……」
「そういう賢二くんは?迷子?」
「何で決定事項なんだよ」
「だって、ほら」
葉っぱまみれだよ。そう言って賢二くんの頭についた葉っぱを取ってあげたら、賢二くんが目をぱちくりと瞬かせて驚いた顔で固まっていた。
「な、」
「な?」
ぱちぱち瞬く。つられてわたしもぱちぱちぱちぱち。あ、そうか。
「迷うのなんて昔からじゃない、何てことないよ」
「は?」
な、とか、は、とかさっきから一文字しか発してないんだけど一体どうしたの賢二くんや。さっきの瞬きの時には緩んだ不機嫌顔も気づけば元通り。フォローの仕方間違えたかな。いや、でも事実だから仕方ない。
「落ち込んでるのかと思ったんだけど、ちがうの?」
「まずオレは迷ってないし、落ち込んでもない」
「ふうん。まあ、行方不明にはならなさそうだからそういうことにしといてあげるね」
「オイ」
迷ったと言っても不機嫌で迷ってないってことにしてあげても不満顔。山口兄妹はプライドが高いから好きなようにさせてあげようか。うんうん。そう決めたら黙っているのが得策だ。というわけで、お口にチャック!
「なあ」
「なに?」
「いつまでこうしてんの?」
不満顔はどこへやら。今度はそっぽを向いたまま賢二くんが話しかけてきた。そういえば、この前から面と向かって話したことあまりないかもしれない。
「痛くなくなったら歩く」
「どう見ても治んないと思うんだけど」
ちらり。視線だけわたしのつま先に向けてくる。普通に見ればいいのに。(流し目がかっこいいって音女の子が言ってたけど、それを真に受けてるんだろうか)
「さすがお医者の息子だね」
「普通に皮むけてりゃわかんだろーが」
また頭を軽くはたかれた。会わないうちに暴力キャラまで目覚めてしまったのかな。会う度に違うからどう対応していいかわからないよ。
「絆創膏は?」
「よれよれになっちゃって使い物になりません」
「…」
何だよ準備わりぃなコイツ。視線がそう言ってる。思ってることが顔に出やすいタイプだとは知ってたけどここまでハッキリわかったのは今が初めてかもしれない。
「迎えは?」
「神社の階段の下に呼ぶつもり。さすがに長い距離歩けないもん」
本当ならここまで来てほしいけどね。神社には階段があるからしょうがない。スマホの画面を覗き込んだ賢二くんは、またチラリとこちらを見た。
「オレも迎えソコだわ」
「あ、そうなの」
「じゃあ、脱げよ」
「は?」
「下駄、痛いだろ」
「いやいやいや下駄脱いだら歩けないからね?それとも何、裸足で歩けと、」
「貸す」
ぽいっと足元に投げ出されたのは、賢二くんの靴だった。
「はっ、え?なに?」
「下駄よこせ」
裸足になった賢二くんの足でぐいぐい下駄を引っ張られて、気づけばわたしの下駄が賢二くんの足元に移動してた。下駄の鼻緒をぐいぐい広げて無理やり履こうとしてるけど、中々うまくいかないらしく悪戦苦闘していた。そりゃそうだ、今の賢二くんはわたしよりも大きいんだから。
「……ちいせーな」
「そりゃーこれでも一応女の子だからね」
「……」
何か考えるようにぼうっとしたかと思えば、賢二くんはおもむろに立ち上がった。これで歩けるんだから、さっさと帰ろーぜ。そう言って、合わない下駄をカランカラン鳴らして歩いていく。踵が下駄からはみ出しているものだから、少し前かがみになりながら進んでいる。わたしは慌てて賢二くんの靴を履いて追いかけた。(うわ、ぶっかぶかだ)
「今日は帰り道わかるんだね」
「いつも分かってるっつーの」
カランカラン。ガッポガッポ。ふたつの音を鳴らしながら、静かな脇道を通って行く。