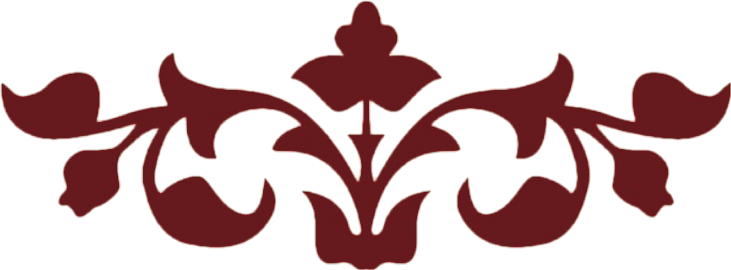
I am your…?
7月に入ってから急に茹だるような暑さが続くようになり、夏が到来したことを肌で感じられるようになった。基本的に暑すぎるのも寒すぎるのも苦手な私は、夏と冬が嫌いだ。だからこの暑さは正直辛い。普段なら暑いだけでテンションだだ下がりの私だけれど、今日は違った。7月最初の土曜日。私が新幹線の改札口でそわそわしているのは、久し振りに彼に会えるから。
私が送ったメールには、その日のうちに返事がきた。話って何?と尋ねられたので、その時に用件を済ませてしまおうかとも思ったのだけれど、いざ切り出すとなると何と確認したら良いのか分からなくて。
うだうだと返信内容を考えている内に彼から次のメッセージが届いて、今週末にこちらに来るということを告げられた。それが今日だ。
新幹線の到着時刻は過ぎているからそろそろ来るのではないかと改札口を凝視していると、見つけた。
背の高さだけでも目立つけれど、その整った顔立ちを見ればすれ違った人達は振り返る。しかも彼は、今やテレビでもよく見るプロのバレーボール選手。取り囲まれないだけマシというものだろう。
改札口を出たことを確認した直後すぐさま駆け寄った私を視界に入れてくれた彼は、半年前と変わらぬ笑顔を見せてくれた。相変わらず、絵になる男である。
「久し振り。元気にしてた?」
「うん。徹は?」
「特に変わりないかな」
遠距離恋愛をしていてやっとのことで恋人に会えたというのに、こんなに淡白なやり取りで良いのだろうか。私の心は随分と高揚しているのだけれど、彼からそういった様子は見受けられない。
再会するまでのドキドキはどこへやら。私は自分の中の陽の感情がみるみる内に萎んでいくのを感じていた。そんなことになど気付きもしていないであろう彼は、小さめのキャリーケースを転がしながら歩き始める。
「行かないの?」
「…行くよ」
彼の左手にはキャリーケース、右手はあいている。けれども手を繋ごうとする素振りがないどころか隣を歩くこともなく、彼は私の前をスタスタと進む。こういう時、私は途轍もない寂寥感に襲われるのだ。
彼の立場上、私みたいなごく普通の一般人と白昼堂々手繋ぎデートをしたら変に騒がれるかもしれないということは分かっている。だから、無理に手を繋いでほしいなんて強請ったりはしない。けれど、せめて隣を歩くぐらい許してはくれないだろうか。
許すとか許さないとか、そういう次元の話をしている時点で、私と彼の関係は恋人ではないんじゃないかと、またもやネガティブな思考に捉われる。ぼうっと大きな背中を眺めながら、いつの間にこんなに距離が開いてしまったのかなぁなどと考えていると、彼の足がピタリと止まった。
くるりと私の方に顔を向けて小首を傾げる様は、なんというか、あざとい。彼は自分の魅せ方をよく心得ているなぁと感心してしまう。
「どうしたの?元気ないね」
「あー…え、と…暑いから。そう、暑いから!」
「ああ、なるほど。暑いの苦手だもんね」
私の下手な誤魔化しなどお見通しの筈なのに、彼はそれ以上何も追求してくることなく踵を返す。私との会話を早く終わらせたいのだろうか。
会う前から燻っていたどろどろとした感情がむくむくと膨れ上がる。そのどす黒い感情に身を任せて、徹、と名前を呼べば、彼は再び歩き出そうとしていた足を止めてゆっくりとこちらを向いてくれた。
「何?」
「徹の方こそ…、久し振りに会えたのに嬉しくなさそうだよね」
妙な沈黙が流れる中、蝉の鳴き声だけがやけにうるさく脳内に響き渡る。少し驚いた顔の彼は、僅かに眉を顰めて。けれどすぐにいつもの表情に戻ると、困ったように眉尻を下げて苦笑した。
「そんな風に見える?」
「……うん」
「……そっか、」
否定も肯定もせず、ただそれだけ言って。彼は、私に背中を向けた。
そんなことないよ。お前と会えて嬉しいよ。
そう言ってほしかったし、言ってくれるんじゃないかと心のどこかで期待していた。馬鹿みたい。この距離を見て思い知ったばかりのくせに。彼がどこに向かっているのかも分からぬまま、私は後ろをとぼとぼと歩く。彼はずっと、振り返らぬままだ。
「ほら、着いたよ。ここだったよね?」
「…え」
漸く彼の足が止まって辿り着いたのは、駅からほど近い場所にある私の家。一人暮らしをし始めてから何度か彼も来たことがあるので場所を知っているのは当たり前のことなのだけれど、なぜ私の家に来るのだろう。
そんな疑問を抱いていることを表情から読みとったらしい彼は、ここまで歩いてくる間に噴き出た汗を腕で拭いながら、暑いからさ、と。言葉を紡いだ。
「どこにも行く用事ないし、名前は家に帰るだろうなと思って」
「徹は…?実家に帰るんじゃないの?」
「うん。今から帰るよ。名前はうちに来てもつまんないでしょ」
てっきり今日はずっと彼と一緒に過ごすものだとばかり思っていた私は愕然とした。つまり彼は、ご丁寧に私を家まで送り届けてくれただけだということになるのだろうか。
何度も言うが、私と彼はこれでも恋人同士の筈だ。ただでさえ一緒に過ごせる時間が少ないというのに、出会って1時間にも満たない、十数分程度の邂逅で彼は満足したというのか。私の胸中で、行き場のない感情だけが彷徨う。
「徹は、それでいいの?」
「うん?どういう意味?」
「…もう少し、一緒にいたいとか…思わないのかなって」
「ああ、そういうことか」
私の問いかけに、彼は少し間を置く。ここで間髪いれずに、一緒にいたい、と言われないあたり、潮時だなと思わずにはいられない。彼の考えていることがさっぱり分からない私は、ただ灼熱の太陽の下、じっと言葉を待つことしかできなかった。
「じゃあ夜ご飯は一緒に食べようか」
「疲れてるんでしょ。無理しなくても良いよ」
ここで素直に、嬉しい!と言えない私も大概可愛げがないなと思うけれど、彼の、じゃあ、という言葉にどこか引っかかりを覚えてしまったのだから仕方がない。まるで、お前がそんなに言うなら仕方ないから一緒に夜ご飯ぐらいは食べてあげようか?と言われているような気がして。勿論、そんな嫌味ったらしい口調ではなかったし、私の気持ちを汲んでくれた結果はじき出された言葉なのだろうとは思う。
暑さが苦手な私のことを考えて、駅から少し距離がある彼の家ではなく私の家に送るという選択をしてくれたのだろうということも。彼の実家に行ったら、私が気を遣って疲れてしまうんじゃないかと考えてくれているのだろうということも。きっと全て、彼なりの優しさだということは察しているし理解しているのだ。
けれども我儘なことに、私はその優しさが邪魔だと思ってしまっている。彼は付き合い始めてからずっと、きっと私のことばかりを優先してくれていて、そのことに気付いたのは社会人になってからだった。大学の時に私が幸せな毎日を送ることができていたのは、私の知らないところで彼が私を守ってくれていたからだと知ったのは、つい数日前のこと。
たまたま大学時代に仲が良かった友人と夜ご飯を食べていた時、まだ彼と付き合っているという話をしたら、昔から愛されてるよねぇ、と言われた。個人的にはそこまでべたべたした付き合いをしていたつもりはなかっただけに、そう?と返した私に、その友人は驚くべきことを教えてくれた。
本当は私に危害を加えようとする女子は沢山いたらしいが、その女子達をうまくなだめて私には手を出さないようにと根回しをしたのは彼だったということ。私の知らないところで何人もの女子に告白されていたにもかかわらず、その友人が知る限り全て断り続けてくれていたこと。
本当に知らなかったの?と言われたが、知らないものは知らない。そんな素振り、彼はちっとも見せなかったから。
私は大切にされている。きっと好きだと思ってもらえている。そんな気がしていたけれど、それは果たして愛なのだろうか。彼はいつも私のことばかりで、彼自身の想いを優先させたことは一度もなかったように思う。こんな関係は、私が求めていたものではない。
「ごめん…やっぱり、一緒に、食べたいな。夜ご飯」
「うん。分かった。また迎えに来るね」
彼はいつだって、何をしたって怒らない。今だってそうだ。こんなに可愛くない態度を取っている私に、柔らかな笑顔しか返してこない。その優しさが、どうしようもなく痛かった。もっと自分の感情をぶつけてほしいのに、彼は絶対にそんなことはしない。私がどうしたいか、私がどう思っているか、そればかりを優先する。
ねぇ徹。私は、あなたにとってどんな存在なのかな。どんな恋人なのかな。その感情は、本当に、好き、なのかな。それを確認するために送ったメールだったのに。会ったらすぐにでもそれをきこうと思っていたのに。臆病な私は、大切なことをいつも後回しにしまう。
相変わらずじりじりと照りつけてくる日差しを全身に浴びながら、去っていく彼の後ろ姿を見つめる私の目には、なぜかうっすらと水の膜が張っていた。