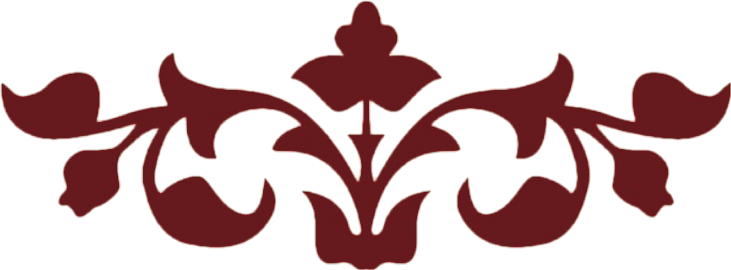
You are my…?
朝起きたら、真っ先にテレビをつける。別にニュースが見たくてたまらないわけではないし、それ以前にゆっくり見る時間があるわけでもないのだけれど、一人暮らしの静かな空間はいつまで経っても慣れないのだ。朝ご飯である焼き立てのトーストを齧りながら興味もないくせにぼんやりとテレビを眺めていると、私のよく知る人物が映って、思わず咀嚼している口までもが動きを止めた。テレビの向こう側で汗を拭いながら爽やかな笑顔でインタビューに答えているのは、全日本男子バレーの選手に選ばれた及川徹。私の大学時代の同級生。そして、たぶん、彼氏。たぶん、と言ったのは彼と私との関係が本当に恋人同士といえるそれなのか、自信がなかったからだ。
最後に会ったのは、確か半年ほど前のお正月の季節だったと思う。プロバレーボール選手として忙しい彼とは、初詣に行った帰りにラーメンを食べて、それっきり会っていない。今や季節は夏を迎えていて、もう1年が半分以上過ぎてしまったのかと今更のように驚いた。私はテレビに映る彼を見つめながら、出会った時のことを思い出す。
彼と出会ったのは大学生の頃。友達に誘われてバレーの練習試合を観に行った時のこと。さしてスポーツに興味のない私だったが、その試合で活躍する彼を見て心を奪われた。イケメンと名高い人物だったので元々がカッコいいのは分かっていたけれど、それ以上に、真剣な眼差しがとても印象的で。私はいとも簡単に恋に落ちてしまったのだ。
それからは秘かに試合の観戦に行ったり、バレーのルールを覚えたり。全く接点はなかったけれど、彼がモテることは知っていたし、付き合いたいなんておこがましいことは思っていなかった。ただ、遠くから見つめているだけで良い。そう思い続けて2年半が経過した頃に転機は訪れた。
その日、私は友達との飲み会で珍しく酔っ払っていて、ふらふらと家までの道のりを歩いていた。くだらない愚痴や恋話に花を咲かせているうちにお酒がすすんでしまっていたのだろう。生憎、迎えに来てくれるような彼氏がいなかった私は、幸いにも歩ける状態ではあったので家までの道のりを歩いていたのだ。そういえば季節は今と同じ夏だった。生温い風が肌に纏わりつく感じが少し不快だったのをなんとなく覚えている。
「大丈夫?」
「え?大丈夫…で……す?」
「こんな時間に、女の子が1人でふらふら歩いてるのは危ないと思うよ」
夢かと思った。背後から肩を叩かれたことにも驚いたけれど、その相手が想いを寄せる及川徹だったから。暗闇の中、頼りない街灯に照らされている彼の整った顔は苦笑を浮かべていて、後々考えてみれば第一印象は最悪だっただろうと思う。けれど、その時の私は酔っ払っていて頭が全く正常に機能していなかった。ましてや、ずっと恋愛対象として最高位に位置付けられている相手から声をかけられたのだ。冷静な判断などできるはずもなく。
「好きです」
私は、とんでもないことを口走ってしまったのだった。
勢いだけで感情を爆発させてしまい激しく後悔したけれど、気付いた時にはもう遅い。隣に佇む彼は目を数回瞬かせて。急に何を言い出すんだこの女は、と不審がっても良い所なのに、ふふっと笑った。
「初めて会話して、それ言う?」
「ご、ごめんなさい…!私、あの、酔ってて…」
「でも、その気持ちに嘘はないんだよね?」
「…はい……」
端正な顔に見つめられて、私は耐えられず俯いた。嘘はなかった。けれど、伝えるつもりはなかったし、伝えるとしてもこんなタイミングで伝えたくはなかった。何度振り返っても馬鹿なことをしたと思うけれど、その馬鹿な行動が思わぬ展開を生んだのだ。
「じゃあ付き合おっか」
「…は?」
「嫌?」
「いや!な!わけ…ないけど、」
「うん。それじゃあ宜しくね。名字さん?」
あまりの急展開に頭がついていかず、あの時の私は放心状態だった。初対面だった筈なのに私の名前をなぜ知っていたのか、よくよく考えてみたら不思議だったけれど、同学年だから何かしらで知る機会はあったのかもしれないと深く考えることはなく。そんな、世にも奇妙な恋の始まり方をした私達だったけれど、交際は信じられないほど順調だった。
浮気をされても仕方がないと思っていたのに、浮気をしているという噂は全く聞かなかった。女子に大人気の彼のことだから、他の女子に妬まれたり嫌がらせをされるかもしれないと身構えていたのに、そういったことも何ひとつなかった。浮気は私が知らなかっただけかもしれないし、嫌がらせに関してはそんなことをする価値もないほど平凡な女だと見做されたのかもしれない。それでも私は、とても幸せな大学生活を送ることができた。
大学を卒業し、私は東京を離れて地元である宮城の企業に就職した。これもまた偶然なのだけれど、彼の故郷も宮城ということで、大学時代には何度か一緒に帰省したこともある。東京で活躍する彼とは遠距離恋愛になってしまうけれど、その時は不思議と不安などなく、社会人1年目の年はお互いに仕事でいっぱいいっぱいながらも、わりと連絡を取り合ったり電話をしたりと上手くいっていたように思う。
それが、いつからだろう。少しずつ電話をする頻度が減って、ついには電話をすることはなくなった。連絡を取り合うこともほとんどなくなり、たまに会った時も以前ほどの高揚感は消失していた。私は彼のことがずっと好きなままで気持ちは変わっていない。何が変わったのか、自分でもよく分からないのだ。
「そういえば、私、好きって言われたことないや…」
ぽつり。テレビの音に混ざって呟きが漏れる。先ほどまで映っていた彼の姿はもうなく、いつの間にか見知らぬ政治家に切り替わっていた。
過去を振り返ってみて、初めて気付いた。彼に好きだと言われたことが一度もないということに。思えば、告白したのは私の方からだし、その時の返事も好きだから付き合おうとは言われなかった。付き合っていてもお互いに好きと言い合うような関係ではなかったし、どちらかというと淡白な付き合い方をしていると思う。付き合い始めてもう5年ほどになるだろうか。なぜ今まで気付かなかったのか、自分でも謎だ。
食べていたトーストの最後の一口を口の中に放り込む。安っぽいコーヒーを啜って口内の物を全て喉の奥に流し込むと、私は席を立った。くだらないことを考えているうちにいつの間にか時間が経っていて、このまま悠長にしていたら会社に遅刻してしまう。
テレビの向こうで笑う彼の姿を思い出して、考える。このままで良いのだろうか、と。私達は、これからどうするべきなのだろうか、と。今までも何度か、そんなことを考えることはあった。けれどもその話題を自分の口から彼に尋ねるのはなんとなく憚られて、今もずるずると燻った感情を抱き抱えている。そろそろ潮時ってやつなのかもしれない。
「今までが夢だったのかもなあ…」
誰もいない部屋で、またも零れる独白。シンデレラの魔法にしては長かった。けれど、そろそろ元の姿に戻る頃合いなのかもしれない。どうやって切り出すべきか迷うけれど、いつかは区切りをつけなければならないから。私は自分のスマホを取りだすと、久し振りに彼の連絡先を呼び出す。出勤前、時間がない中ではうまい言葉なんて見つからないけれど、思い立った時でなければまた先延ばしにしてしまいそうで怖い。
“久し振りだね。元気にしてる?忙しいと思うけど少し話したいことがあるから、時間のあるときに連絡ちょうだい。”
絵文字も顔文字もないシンプルな文面を送信する。彼の反応はほんの少し怖いけれど、なんとなくすっきりした気もして。壁にかかった時計を見て、私はテレビを消すと急ぎ足で玄関に向かった。ドアを開ければどんよりとした曇り空。そうえいば天気予報では午後から雨が降ると言っていたな、と思いながら折り畳み傘をカバンの中に放り込み鍵を閉める。
いつもと変わらない朝の筈なのに、私の胸中は穏やかではなく。どれだけ遠いところにいても、私はいつだって彼に揺さぶられてしまうのだなと思わずにはいられなかった。
prev next