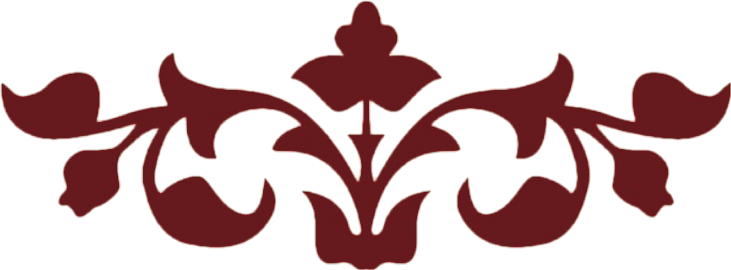
You love…?
夜になり、彼は別れ際に言った通り、私のことを迎えに来てくれた。2人で行くのは色気など微塵も感じられないけれどラーメン屋のことが多い。だから今日もそのコースかなと思っていたのに、今日はそんな気分じゃないから違うところでも良い?と言ってきた彼に、私は首を縦に振って了承の意を示す。相変わらず先を行く彼の後を追って着いたのはこじんまりとした居酒屋。お酒飲むの?と尋ねたら、飲まないよ、と笑われた。じゃあなんで居酒屋?という疑問を抱きつつも、私は案内された席へ足を進める。そして、椅子に座るのを躊躇った。
案内された席は所謂カップルシートになっていて、普通のカウンターに座る時よりも彼との距離が近くなるのは必然。付き合っているのだから躊躇う必要などない筈なのに、素直にこの状況を受け止めきれないのはなぜだろう。まるで彼に、私の心の中の不安やモヤモヤを読みとられていて、それを払拭させるためにこの場所へ連れて来られたんじゃないかと。そんな、打算的な考えが頭を過ってしまったからかもしれない。
「こういうのもたまには良いでしょ?」
「…そうだね」
心にもない返事をして、席に座る。食事は美味しかったしお店の雰囲気も好きだった。近況報告をし合って、普通に会話も弾んだ。けれども折角のカップルシートなのに私と彼の間に空いた微妙な距離は終ぞ埋められることはなく。その距離が私と彼との心の隙間を表しているような気がした。
帰り道、当たり前のように送ってくれた彼は、じゃあねと手を振って帰ろうとする。暑いから早く帰りたいだけなのかもしれないけれど、明日の夕方には東京に帰ってしまうというのに、こんなにもあっさりとしたさよならで良いのか。無意識のうちに握りしめた拳には、暑さのせいではない他の何かのせいで汗が滲む。
「徹、あの、話があって」
「ああ…そういえばメールでもそんなこと言ってたね。何?」
「暑いから…うち、寄って行かない?」
「名前が良いならお邪魔させてもらうけど」
彼はそこまで深刻な話だとは思っていないのだろうか。何の躊躇いもなく私の部屋に来てくれた。蒸し風呂状態の室内を冷やすべくすぐさまエアコンを稼働させて扇風機の電源を入れる。むわりとした生温い空気が狭い室内に充満する中、冷蔵庫から冷たいお茶を取りだしてグラスに注いだ私は、1つを彼に勧めて1つに口を付けて喉を潤す。
「こんな部屋だったっけ?」
「来るの久し振りだから…前とは違うところもあるかも」
「そっか…俺、お前のこと何も知らないね」
その言葉がどういう意味で落とされたものなのか、私には分からない。長い付き合いの中でお互いに変化を遂げて。そんなことを言うなら、私だって彼のことは何も知らない。否、最初から知っていたつもりでいて、何も知らなかっただけなのかもしれない。
「徹は、」
つい今しがたお茶を流し込んだ筈なのに喉はカラカラに乾いていて、うまく声が出なかった。彼がお茶を飲んだのを見て、私もそれに倣ってもう一度お茶を飲み干す。潤ってもすぐに枯渇するのは、この暑い部屋のせいだと思いたい。
「徹は、私の何なの?」
私の発言は、きちんと彼に聞こえたと思う。けれども眉ひとつ動かさず、いつかは尋ねられると思ってました、とでも言いたげな様子でお茶を啜る彼。
「彼氏だと思ってたつもりだけど。…違うの?」
「違わないよ」
「じゃあなんでそんなこときいてきたの?」
口調は穏やかなのに、言葉自体は鋭利。だから私の心臓は容易くぶすりと刺されてしまう。だって、よく考えてみてよ。私と貴方の距離を。再会を果たしてからまだ24時間も経過していないというのにこんなにも騒つく胸中は、そういうことじゃないの?
口籠る私に、すうっと息を吸い込んだ彼は、容赦なく確信を突く。
「話って、別れ話?」
「ちが、そういうつもりじゃ…なくて、」
「良いよ俺は」
時が、止まる。良いよ、とは。つまり。
「お前がしたいようにすれば良い」
「徹は、いつもそうだよね…、」
漸くひんやりとしてきた室内でぽつりと呟いた声音は、扇風機とエアコンの音で少し掻き消されてしまったかもしれない。それほどに弱々しい呟きだった。
別れ話をするつもりではなかったというのは本当のことだ。この関係をはっきりさせたいとは思っていたけれど、終わりにさせたいだなんて思っていなかった。けれど彼は、それをすんなり受け止めると言う。
たとえ別れるという道を辿ることになったとしても、好きならばせめて、どうして?とか、理由ぐらい確認してくれるものだと思っていた。あわよくば、別れたくないと引きとめてくれるんじゃないかと期待していた。本当に、私は夢を見過ぎている。そこまで愛されているならば、こんなことになりはしなかっただろうに。
それでも信じていたかったのだ。自分は愛されていると。心のどこかで、好きだよとか愛してるとか、そんな浮ついた薄っぺらいセリフを言ってくれる日が来るんじゃないかと。童話のお姫様とまではいかずとも、ただ幸せだなと思える日が来る筈だと。そんなの、やっぱり幻想だったと思い知らされる。
「じゃあ、別れようか」
殊の外すんなりと出てきたその言葉は本当に私が紡ぎ出したものだったかどうかすら分からない。彼はまた、お前がそうしたいならそうしよう、と。全てを私に委ねるようなことを言ってきた。
「今までありがとう」
ひとつも未練などないかのように、いつもと同じか、もしかしたらいつも以上かもしれない爽やかな笑顔を向けてきた彼は、今一体どんな心境なのだろう。本来なら私なんかがフっていいような人間じゃない。誰もが羨む完璧な彼氏だった。こんな平々凡々のどこにでもいるような女なんかにフられて、よく考えてみれば屈辱以外のなにものでもない気がする。
彼の言葉に何も返すことができず、自分から別れを切り出したくせにじわじわと視界が滲んでいく私はひどく滑稽だ。そんな私に追い打ちをかけるように、彼はふわりと柔らかく抱き締めてきて。涙腺はいとも簡単に決壊した。
「ごめんね」
「…っ、」
それは何に対する謝罪なのだろう。遠距離恋愛中、連絡を頻繁に取り合わなくなったこと?隣を歩いてくれなかったこと?引きとめてくれなかったこと?何にせよ、今更取り返しは付かない。謝られると余計惨めな気持ちになるからやめてほしいのに。どうしようもない私は、その体温を拒絶することができなかった。
暫くそのままの状態だった私達だけれど、先に動いたのは彼の方で、やんわりと身体を引き剥がす。そして、私の頬を伝う雫に気付いて手を伸ばしかけた彼は、そのまま動きを止めた。触れてほしい。けれど、これ以上乱されたくない。
今ならまだ間に合うのか。やっぱり別れたくないと縋りつけば、彼を繋ぎとめられるのか。きっと彼はまた、同じように言うのだろう。お前がしたいようにすれば良い、と。私は、そんな言葉を求めているわけじゃないのに。
一瞬の間にそんな思考を巡らせた私の頬に、彼の手が届くことはなかった。
「ばいばい」
私の部屋を出ていく彼の姿を、私はただ見つめることしかできなくて。ばたん、と玄関の扉が閉じたのを合図に、涙が溢れ出した。彼はずるい。最後になって身体に温度を染み込ませて去っていくところも、自分からは何も決めてくれないところも、全部。けれど一番ずるいのは、その優しさのせいにして全ての原因を彼に押し付けようとしている私なのだろう。
どうやったら別れずにすんだのか、なんて今更考えたって仕方ない。けれど、今はこの有り余る彼への想いを涙と一緒に流してしまわなければ先へは進めないような気がするから。私は冷たい部屋の中で、声を押し殺して泣き続けた。
凄く今更だ。そして遅すぎる。けれど、私も謝りたい。
ごめんね。大好きでした。