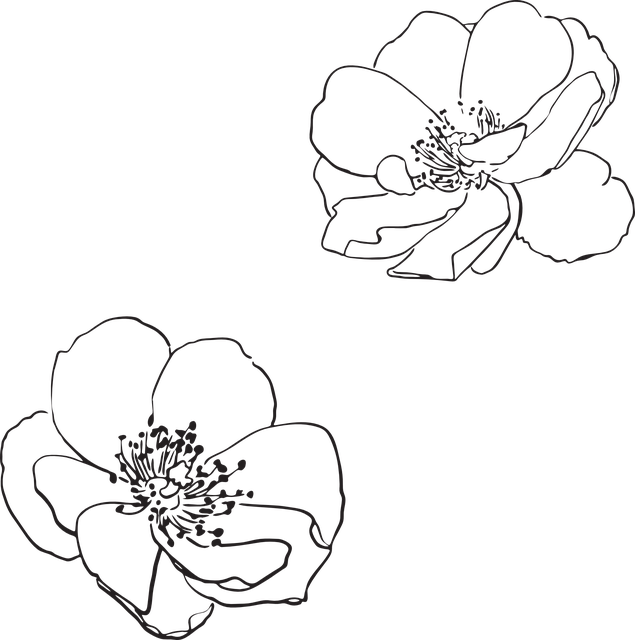
心の拠り所
北海道の夏は短い。爽やかな空気に包まれ、短い命を謳歌するように蝉が鳴く。夏の風物詩が月島の鼓膜に反響して少しだけ痛かった。
白石由竹の行方は依然と掴めない。旭川にいる追跡部隊からは、大雪山付近で見失ったと報告が上がった。鶴見は白石の追跡を一旦打ち切り、新たな刺青囚人の情報を収集することにした。二十四枚の刺青人皮を一枚でも多く手に入れ、優位に駒を進めなければならないからだ。
一週間前、小樽で銀行強盗を繰り返す義賊・稲妻夫妻の情報を得た。稲妻強盗こと坂本慶一郎は、刺青人皮持ちの網走監獄脱獄囚である。彼を誘き寄せるために、さっそく江渡貝が作った偽物の出番だ。
小樽市内のとある油問屋は表向き問屋であるが、裏の顔はヤクザが仕切る賭場である。月島に課せられた仕事は、わざと賭けに負けて偽の刺青人皮を借金のカタにすること。稲妻夫妻を誘き寄せる餌にするためだ。
「偽の刺青人皮を油問屋に流しました」
「よくやった、月島軍曹。しばらく周囲を張って、稲妻が釣れるのを待つだけだな」
鶴見は満足げにほくそ笑む。加えて有坂閣下から、真新しい武器を仕入れたので、鶴見は尚更上機嫌なのだ。切長な目を細めて笑う姿は、まるで獲物を狩る死神そのものだと月島は思った。この男の手にかかれば鬼だろうと蛇だろうと、間違いなく命を狩られるだろう。
月島が名前と再び会ったのは、油問屋で稲妻強盗を捕獲する数日前のことだった。名前は壮年の男と共に兵営内を歩いていたが、こちらに気が付いて小走りで駆け寄って来たのだ。
「月島様! お久しぶりです」
「あんたか。まさか兵営内で会うとは思わなかった」
「父の仕事の手伝いで来たのです」
最近、新しい兵服を作ると御達しがあった。各中隊の縫工卒達が忙しそうに、兵営内を駆け回る姿をよく見かける。彼らの姿を目にした月島は、大変そうだなと他人事のように眺めていたのだ。
名前は父と共に、試作品を持って来たのだと言う。
「仕事の邪魔をしてしまったな」
「大丈夫です。試作品をお渡しして、これから帰るところです」
軽く言葉を交わしていると名前の父がやって来て、あの夜に娘を助けてくれたことを何度も頭を下げで感謝された。月島は面映い気持ちになりながらも、頭を上げて下さいと言った。
市井の人々から北鎮部隊と畏怖の念を込められることはあるものの、面と向かって感謝されることは滅多にない。鶴見から命じられた汚れ仕事もこなしているから、余計に純粋な感謝を向けられると戸惑ってしまうのだ。素直に受け取って良いのか分からなかった。
「これからは、時々兵営に伺うことが増えますので、その際はよろしくお願いします」
「ああ。新しい兵服、楽しみにしている」
「精一杯尽力いたしますね」
名前はにこりと笑い、父親と共にお辞儀をした後、帰って行った。新しい隊服が出来るまでの間、月島は名前とささやかな交流をすることになる。
「子供は親を選べない。あの夫婦は凶悪だったが、愛があった」
油問屋での大捕物が終わった。稲妻強盗の刺青人皮を、手に入れることが出来た。しかし、それと共に思わぬ拾い物をした。
稲妻夫妻の赤子である。死んだ母親を求めるように泣き喚く赤ん坊は、まだ目が見えていない。生まれて数ヶ月だろう。両親を殺した当事者達に囲まれ、小さな手を一生懸命動かして、母親の存在を探している。これから先、一度も親の顔を目に映すことはないとも知らずに。
「あんな親が育てた子供は、どんな人間になるのか……興味があるところだったな」
月島には、父親から愛を受け取った記憶がない。もちろん母親の記憶すら曖昧だ。物心ついた頃から、既に謗られていたのだ。
「生粋の凶悪な殺人者でしょう」
人殺しの噂をまとった父親を、手にかけたからこそ口から出た言葉である。蛙の子はどう足掻いても蛙だ。それなのに月島には、赤ん坊が神聖なものに見えてしまう。
ぎゅうっと丸く握られた小さな手は、まだ人の血で染まっていない。母親を求めて泣く赤ん坊は、まだ真っ当な未来を選ぶことが可能なのだ。月島みたいに、人生が詰んでいるわけではない。
脳裏にちらつく、あったかもしれない未来。あの子と紡ぐはずだった家庭だ。彼女と一緒に駆け落ち出来ていれば、月島は道を踏み外すことはなかった。
悪童と謗られた月島でも、この両手に我が子を抱いていたかもしれない。柔らかくて温かい小さな命。少しでも力を入れれば、容易く潰れてしまいそうなほど儚い命。慣れない子守りに戸惑いながら、悪童でも真っ当な父親になれていたかもしれない。きっと今頃、あの子に似た子供達に囲まれて――。
鶴見の腕に抱かれた赤ん坊を見つめながら、月島は諦めた未来を何度も頭の中で描く。小樽運河に捨てたあの子が微笑む。脳内にこびりついて消えてくれない。とても虚しくて、心が疲弊しそうだったから蓋をした。鶴見の目指す未来に、月島の幸せは不要なのだ。
月島の毎日は目まぐるしい。部下達の教練。書類整理。鯉登への教育という名のお守り。そして刺青人皮の情報収集。休みなく兵営内を動き回る月島の姿は、働き蟻にそっくりである。
「月島、少し休憩しろ。近頃、働きすぎだぞ」
月島の前には淹れたての麦茶。机を挟んで目の前には、部下を労る上官の姿だ。
「いえ。そんなことはありません」
鶴見の言葉に月島が真面目に答えると、これ見よがしに大きな溜息が吐かれた。
「いざと言う時に、お前に倒れたら困るのだ」
「ですがこの後は、鯉登少尉の指導もありますし」
「鯉登のことは、私が面倒見ておくから気にするな」
月島の心配をよそに、鶴見がこともなげに言う。
月島は言葉に詰まった。鶴見にそう言われてしまえば、もう何も言うことがない。鶴見を信奉する鯉登は嬉しいはずだが、
鯉登を見ていると、かつての己を思い出してしまう。月島は鯉登のように猿叫したり奇行に走ることはなかったが、鶴見のことを信じて疑わない時期があった。いつの日か鯉登も、偽りの愛に気付く時が来るのだろうか。隣にいる
「私の優秀な右腕が、基本的な体調管理すら出来ないとは思っておらん。だが……私を失望させることだけはするなよ」
ふるふると首を横に振る鶴見の姿は、いっけん冗談めいて見えるが本気である。鶴見とは九年来の付き合いがある分、月島は良く分かっている。ここは大人しく、上官命令に従うのが賢明だ。
「……分かりました。鶴見中尉殿がそこまで仰るなら」
「うむ、なら良い。どうだ、今から気晴らしに街中を散歩して来い。ついでにお茶請けにみたらし団子を買って来てくれないか。急いではないから、ゆっくりで良いぞ」
「みたらし団子……ですか」
「花園公園のな」
鶴見は酒が苦手な割りに、和菓子が好きなのだ。
掌にはみたらし団子用のお駄賃。多くの人で賑わう小樽の街を歩きながら、月島は思った。名目上は休憩時間であるが、実は鶴見が団子を食べたいが故の口実にされた気がしなくもない。休憩時間とは、一体何をすれば良いか分からない。自分が何をしたいのかも――未だ見当つかない。
「まぁ、月島様も甘い物がお好きなんですか?」
みたらし団子屋に行くと、名字名前がいた。
「いや、まぁ、その……買い物に来ただけだ。上官命令で」
悪いことはしていないのに、しどろもどろになってしまう。月島は甘味が好きではない。このまま勘違いされるのも不本意だったから、慌てて上官命令と付け足した。
「そうなのですね! 月島様と兵営外でお会い出来るとは思いませんでした」
名前は月島の心境など知らず、屈託なく笑う。店先には出来立ての団子が綺麗に陳列されている。早く食べて、と客にねだっているように見えた。
「あの、この後少しだけお時間ありますか? もしよろしければ、先日助けていただいたお礼をさせて下さい」
「いや、あの夜の礼には及ばん」
「でも……、」
「本当にいいんだ」
あの場に居合わせたのも偶然だ。決して下心があったから助けたわけではない。疲労困憊で兵営に戻ろうと、一瞬思ったくらいだ。名前に対して、後ろめたい気持ちの方が大きい。月島がこのまま断り続けても、食い下がる彼女に効果はないに等しい。名前の親切心を無下にしないで、上手く断るにはどうすれば良いか。
名前は真面目で、悪く言えば頑固だと月島は思う。お礼をしたい名前でも、納得する理由でなければ意味がない。月島は腕組みして少しだけ思案するが、困ったことに妙案が浮かばない。
「茶を飲む時間は少しだけある。俺の暇潰しに付き合ってくれるか」
「暇潰し、ですか?」
「休憩時間なんだが……正直、何をすれば良いのか分からなくてな」
月島は肩を竦めて、本音を零した。
仕事漬けの人間から仕事を取り上げると、空いた時間に何をして良いか分からなくなってしまう。迷子の幼児のように、所在なさげに立ち止まってしまうのだ。だから鶴見は口実として、団子のお使いを頼んだのだが、月島は上官の真意に気付くことはない。
「私、和菓子が大好きなんです。ここのお団子は美味しいので、一緒に頂きましょう」
月島は真面目な男なので、急に降って来た休憩時間も、しっかり使わなければと思い直した。名前に誘われるように、月島は店の中に足を踏み入れる。いらっしゃいませ、と来店を歓迎されて席に通された。
しばらくして、注文した団子数本と麦茶が運ばれて来た。名前は、黄金色に輝くみたらしだれがたっぷりかかった串団子を、一口頬張る。
「美味しいです。月島様も食べて下さい」
「……いただきます」
月島も名前に倣って、串団子を口に運ぶ。
濃厚でとろみのある甘だれが、唾液腺を刺激して弾けた。団子はもっちりしており、噛みごたえある。疲れた身体に、糖分が深く沁みる。鶴見がこの店の団子を食べたがる理由が、何となく分かった気がした。
「ね、美味しいでしょう?」
「……そうだな」
向かいに座る名前は、甘味に舌鼓を打ち、幸せそうに頬を緩めている。その姿は年相応の娘だ。
月島は名前の様子を眺めながら、無言でもう一本の串団子を咀嚼する。こし餡の舌触りが滑らかだ。
名前は楽しそうに、近状報告をする。月島はその度に、相槌を打つだけだ。
「もう少しで、新しい兵服が完成するんです。だから父も私も忙しくて」
「そうか」
兵営内を縫工卒達が、忙しなく動き回っている姿を目にすることが多くなった。きっと大詰めなのだろうと、月島も何となく感じ取っていた。
「早く月島様にも見て頂きたいです。丁寧に藍染したので、楽しみにして下さいね」
「……あんたも染め物をするのか?」
「はい。父から教わっています」
名前は、自身の掌を月島に見せる。
女性特有の小さな手。よく見れば掌と爪先が、ほんのりと藍色に染まっている。そして肌は、乾燥しているようにも見えた。
まごうことなく職人の手だ。月島は今まで気が付かなかった。十年以上も女の手を握っていないから、疎くなっているのだ。
あの子の手は白魚のように真白で、藍色に染まっていなかった。
月島は無意識に、名前を通してあの子を見つめている。名前と話していると、どうしても過去の記憶がよぎって、無下に出来ないのだ。潮の匂い満ちる過去に、囚われたまま。
「染物は面白いのか」
「はい。とっても面白いんですよ」
全て手作業で染めたい布を揉んだり、泳がせたりする。余分な染料を絞り、空気に触れさせて乾かす。染め方の手順は一緒だという。
「だけど布の素材によっては、染料に漬け込む時間も、動かし方も変えます。同じ仕上がりになる物は一つもないんです。だから染め物は、楽しいんです」
名前は自身の掌を、愛おしそうに見つめている。月島は、その眼差しの正体を知っている。職人の目だ。丹精込めて、この世に唯一の作品を生み出す。江渡貝も似たような目をしていた。
肌にうっすら染まった藍色は、彼女が染め物と向き合って来た証拠。一枚一枚、布と過ごした年月が積み重なっている。何かを創り出す掌だ。戦争や汚れ仕事で人を殺し、真っ赤に染まった月島の掌は、さしずめ奪う掌と言えるだろう。
「……ご両親も、さぞ嬉しいだろう」
「そうだと良いんですけど」
「親父殿の顔を見れば分かる。あんたと一緒に仕事が出来て楽しいんだ」
たまに兵営内で、
「月島様のお父様は、どんな方なんですか?」
生温い血液。痺れてヒリヒリする拳。
この手で父親を殺したとは言えない。下手な嘘で取り繕い、墓穴を掘ることもしたくない。口が達者じゃない月島は、誤魔化すしかなかった。
「……だいぶ前に亡くなったから、あまり覚えていない」
「ご、ごめんなさい。私ったら――」
「いや、謝る必要はない」
名前は何度も、頭を下げた。
今の流れでは、家族の話を聞くのは自然だったし、名前に悪気がないことは月島も分かっている。ほんの僅かだが、自分が真っ当な人間でないことを失念する程、居心地が良かったのだ。
女将の元気な声。ぺちゃくちゃと会話を弾ませる客達で、店内は活気に満ちている。しかし二人を包む空気だけが重たい。麦茶が注がれた湯飲みは空になっていた。月島は鉛色の空気を、入れ替えようと別の話題を振る。
「上官にここの団子を包んで来いと言われたが、どれが良いか教えてくれないか」
「それなら……みたらし団子と、こし餡団子がおすすめです」
名前がそう言った。月島は女将に一声かけ、団子を数本包んでくれと注文した。
「月島様。ご馳走様でした」
「こっちこそ、暇潰しに付き合わせて悪かった」
「いえ、そんな。よろしければ、次も私とお話をしてくれませんか? 月島様がお忙しいのは重々承知しているのですが、とても楽しいのです」
本来であれば月島のような日陰者が、名前と言葉を交わすなんてあり得ない。頭では理解しているが、彼女と言葉を交わすのは嫌ではなかった。
「……また機会があればな」
純粋無垢な笑顔。出来れば悲しませたくないと、月島は思ってしまう。目の前にいる名前に対してなのか――はたまた記憶の中にいるあの子へ対してか。月島にも分からない。
「月島様。手を出して下さい」
言われた通り、月島は手を差し出す。無骨な掌にころんと転がるのは、藍色に染められた布の塊――手作りの小さな御守だ。
「月島様が怪我をすることがありませんように、と想いを込めて作りました。受け取って下さると嬉しいです」
「……あ、ああ」
月島はどうしても断ることが出来なかった。
いご草そっくりの癖っ毛。大きな瞳は、湖面のように穏やかだ。嬉しそうに頬を弛ませた名前が、あの子の姿と被るからだ。
幻影――白昼夢だと分かっていても、縋ってしまう。