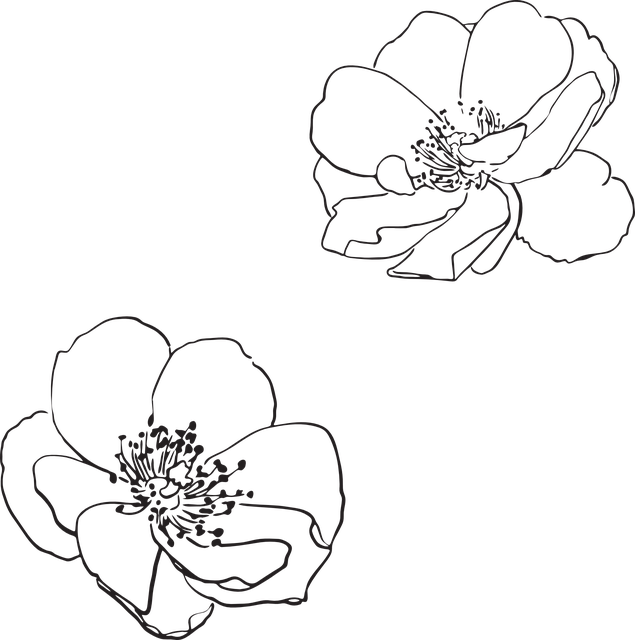
記憶の彼方
疲労が溜まった身体に鞭を打つ。重石を引き摺っているみたいに脚が重たい。雨水をたっぷり含んだ外套が、身体にまとわり付く。季節は夏なのに、今夜は冷たい雨が降っている。おかげで、あらかた煤や泥は洗い流されたが、早く兵営の風呂に浸かりたい。冷えた身体を温めなければ、風邪を引いてしまう。
土砂降りの音が、鼓膜に響いて痛い。不意に、どこかで男の喚く声が聞こえた。歩を進める度に、その声が大きくなる。雨粒が飛び散り、視界が悪い。月島は前方へ目を凝らすと、柄の悪い数人の男達が何やら喚いていた。何を言っているのかは、よく聞こえない。
こんな夜更けに近所迷惑だ。苦々しく思ったが、酷い雨音はそれすらも掻き消すだろう。面倒事は勘弁したい。月島は一瞥した後、そっと男達の後ろを通り過ぎる。もう少し歩けば兵営に着く。
誰か――。
「……女の声?」
激しい雨音に混じって、よく聞こえなかった。空耳かもしれない。月島はそう思い直し、足早に歩を進める。
誰か、助けて。
紛れもない女の叫び声が届いた。切羽詰まった金切り声に、尋常じゃない予感がした。背中に厭な汗が噴き出して、雨で濡れた身体に混じる。
身体は冷え切っている。屈強な北鎮部隊の一員といえども、休む間もなく働き詰めだったから疲労も限界を超えていた。爪先は兵営の方角を向いている。今すぐ風呂に入ってゆっくりしたい。寝心地良くないが、慣れ親しんだ煎餅布団で眠りたい。女の叫び声を聞かなかったことにすれば、月島のやりたいことは全部叶うのだ。ざぁざぁと、雨が止む気配はない。
月島は急いで元来た道を戻った。バシャバシャと、泥水が跳ねる。ぬかるむ地面に、足裏を叩き付けながら走る。耳に入ってしまったからには、無視するわけにはいかなかった。
月島は勢いを殺さぬまま、女に覆い被さる男めがけて拳を振り上げた。肉と肉がぶつかる鈍い音と衝撃を感じながら、月島の拳は止まらない。小柄な月島よりも、幾分大きい体躯の男が泥水に沈む。
突然の乱入者にお愉しみを邪魔された男達は、怒声を上げながら月島に襲いかかる。動きに隙がある。動作が鈍い。腑抜けた拳だ。月島は男達の動きを完全に見切った。
佐渡の悪童。十年以上経っても、月島の身体奥深くまで染み付いた汚れは色褪せていなかった。寧ろ、二つの戦争に従軍した経験が加わり、更に磨きがかかったと言える。加えて彼は今、虫の居所が悪い。月島がひと睨みしただけで、男達は気圧された。月島が第七師団の軍人だと分かったのだろう。死線を潜った歴戦の猛者に、叶わないと悟ったのだ。無様に腫れ上がった顔を曝しながら、悪態を吐いてさっさと逃げて行った。
「……大丈夫か」
女の顔を見て、月島の心臓が大きく脈打つ。身体が寒さとは別の理由で強張る。
九年前、東京へ嫁いだあの子の幸せを想って獄中で身を引いた。死刑囚である月島が、今更あの子に対して何か出来ることなどなかったからだ。あの子の髪の毛だと思っていたものが、月島の脳裏に蘇る。ようやく膿んだ傷口が
『基ちゃん――』
色白の
「北鎮部隊の兵隊様、ですか?」
月島があの子に想いを馳せていると、女が声をかけてきた。固まったままの月島を、不思議なものを眺めるように見つめている。月島は慌てて、過去から今に意識を引き戻した。
「助けていただき、ありがとうございました」
よろよろと覚束ない動作で、女は立ち上がる。せっかくの着物も、泥水で汚れてしまっていた。
雨でびっしょり濡れた着物が肌にぴったり張り付いており、女性特有の曲線が浮かび上がっている。おまけに裾から、生白い脚が覗いていた。雨に打たれて冷えたそれは、体温を失っている。まるで、精巧な作り物のようだが目には毒だ。見てはいけない物を見てしまった背徳感。月島にとって、女の有り様は目の遣り場に困った。
「これでも羽織っておけ」
月島は濡れた外套を女に羽織らせる。小柄な月島の外套でも、女が羽織るとやはり大きい。おかげで彼女の身体の曲線を、隠すことが出来た。
「こんな夜に、女性が一人で出歩くのは感心しない」
「お使いの帰り道でした」
彼女は染物屋の娘だと言った。お得意先に注文の品を届けた帰り道に、大雨に遭って雨宿りをしていたところ、先程の男達に絡まれたと言う。あの叫び声を無視して兵営に戻っていたら、女はどうなっていたのだろう。もしかしたら、殺されていたかもしれない。最悪の事態を想像した月島の背筋に、ぞくりと悪寒が走った。
助けた以上、最後まで面倒を見る責任がある。
「自宅まで送る。場所はどこだ」
「いえ、大丈夫です。兵隊さんに手間を取らせるわけには――」
「手間ではない。せっかく助けたのに、また襲われたら目覚めが悪いだけだ」
暴漢に襲われたばかりなのに、何故そんなことが言えるのか。月島は女に苛立ちを覚えた。だがたった今、怖い思いをした彼女を叱り付けて、更に追い詰めてしまうのは得策ではないと思った。月島は苛立つ己を鎮めて、再び彼女に自宅の場所を聞く。すると、今度はこちらですと大人しく従ってくれた。気が付けば、あれだけ降り注いだ雨は上がっていた。
「お名前を教えてください」
「……月島だ」
寝静まったような静かな町中を、月島と女は歩く。彼女はおもむろに口を開き、月島に名前を教えてくれと乞うた。名乗る程のものではないと思ったものの、答えない理由もなかった。だから月島は簡潔に答えたが、新たな会話の糸口が生まれることはなかった。
彼女は知らない男達に襲われかけ、怖い思いをしたばかりだ。きっと今だって、怖くて仕方ないはずだ。月島と二人でいるのも、我慢しているかもしれない。こんな時、彼はどう声をかけて良いか分からなかった。口下手というより、元から口数は多くない。こういうのは、鶴見の得意分野だ。彼の甘い嘘にまんまと誑し込まれた月島だからこそ、自信を持って断言出来る。きっと淀みなく、彼女の不安を取り除いてくれる都合の良い言葉をかけるのだろう。
「ここです」
結局二人は、会話らしい会話をすることもなく、目的地に到着した。
目の前に聳えるのは、二階建てのどっしりした家屋。小樽の町でも、比較的大きな
「本当にありがとうございました」
丁寧にお辞儀をする彼女に、軽く会釈した月島は兵営に戻ろうと踵を返す。すると、慌てたような声が背中に投げかけられた。
「あの……! 助けていただいた御礼に、うちのお風呂に入って身体を温めて下さい。風邪を引いてしまいます。それに、軍服も汚れておりますので、こちらで洗います」
言われてみれば軍服のあちこちに、煤なのか泥なのか分からない汚れが着いている。夕張炭鉱の爆発事故に巻き込まれ、ほつれてしまった箇所も多々あった。
「いや、結構だ。俺は大したことはしていない。あんたこそ風呂に入るべきだ」
月島は女の申し出をきっぱり断った。
偶然通りすがっただけで、感謝される程のことはしていない。彼女を自宅まで送ったのも、助けた責任を途中で放棄するのは違うと思ったからだ。そして何よりも早く、兵営に戻って横になりたい。さすがに疲れてしまったので、風呂は明日の朝に入れば良い。
尚も食い下がる彼女に、月島はもう一度結構だと言って――振り切るようにその場から足早に去った。
あの冷たい雨が降った夜から数日経った。月島は刺青人皮の情報を探りながら、日々の定例業務をこなしている。変わったことと言えば――。
「月島! 月島! どこ行った? 月島ァ?」
「……何ですか、鯉登少尉殿」
いつでもどこでも雛鳥のように啼く、新任少尉の教育係という職務が増えた。新任少尉は現場叩き上げの軍曹に付いて、様々なことを学ぶのがしきたりになっている。鶴見を信奉するこの薩摩隼人は、幾らか手を焼くので月島も困っているところだ。
先日旭川本部から、網走脱獄囚の一人である白石由竹が杉元佐一と共に逃走した。追跡部隊を放っているが、未だに行方は掴めていない。おまけに鶴見陣営から造反した、尾形百之助も一緒だったらしい。反乱分子である鶴見達を旭川本部に差し出し、出世を目論んでいるのか。定かではないが、厄介である。
鶴見は白石達の捜索と並行して、他の脱獄囚人達の所在を探っている。幕末の亡霊・土方歳三。不死身の杉元。今後刺青人皮争奪戦は、鶴見を加えた三つの陣営で熾烈を極めるだろう。それを見越した鶴見は戦力を強化するために、鯉登の参戦を許可したのだ。おかげで月島の仕事は増えた。
「どこにいたんだ、探したぞ。兵営の門に月島宛の客人が来ている」
「……私に客人ですか?」
「ああ、しかも女性だ」
月島を訪ねる女など、今まで一人もいない。師団内では、遊郭に遊びに行く輩もいるので、時々女が訪ねて来ることもある。月島も仕事の延長線で、遊郭へ行くことはあるが女遊びはしない。仕事の付き合いだと割り切っている。
月島は鶴見のおかげで一度助かり、一度死んだようなものなのだ。今更、女に現を抜かすことはない。睦言を交わすような親しい女を作るつもりは毛頭ない。だから客人が誰なのか見当もつかない。とは言っても、鯉登が嘘を言う男ではないので、尚更気になる。不思議に思いながら、兵営の門へ行くと一人の女が立っていた。
「こんにちは、月島様」
「あんたは、あの夜の……」
どきりと、心臓が大きく音をたてた。
客人は数日前の夜に出会った女だった。大きな風呂敷包みを両腕に抱えている。女は月島の姿に気が付き、ぺこりと頭を下げた。
「申し遅れました。私は名字名前と申します」
あの子にそっくりな女が、あの子と違う名前を告げた。当たり前だ。あの子は――。頭では分かっていたが、月島の心がちくりと痛む。まるでささくれが剥けたみたいにちくちくと痛む。とっくに小樽運河へ放り棄てた感情なのに未練がましいと心の中で罵る。
「あの夜は、ありがとうございました。本当に感謝しても仕切れません」
「いや……俺は大したことしていない。もう出歩いても平気なのか」
「さすがに夜間外出は怖くて出来ませんが、日中なら何とか大丈夫です」
「……そうか」
いっけん元気そうな名前の姿に、月島がホッと胸を撫で下ろしたのは事実だ。だけど、ぎこちなく笑う女の姿に、月島は容易に察した。名前に問うた言葉は、配慮が欠けていたかもしれない。考えてみれば当たり前だ。
まだ傷は癒えていないが、命の恩人に心配させまいと心を奮い立たせているのだろう。だから月島はそれ以上何も言わずに、神妙な表情をすることしか出来なかった。密かに自己嫌悪に陥る月島をよそに、名前は傷付いたり不愉快に感じた素振りはしなかった。
しかし傷も癒えぬ内に、どうして無理をして兵営まで来たのか。その答えは彼女の両腕に抱えられている風呂敷包みだ。
「今日はこれをお返しに参りました。お名前が“月島様”以外存じ上げなかったので、門まで呼び付ける形になり、失礼いたしました」
差し出された風呂敷包みを開けると、着古した外套だった。
雨が轟音のような音をたてながら降りしきる夜、震えていた彼女に羽織らせたものだ。彼女を自宅に送り届け、振り切るようにその場を去った。兵営に戻ってから外套を置いてきたことに気付いた月島だったが、あまり困らなかった。外套は支給品なので、また支給された時に貰えば良いと思っていたからだ。
「煤や泥で汚れていたので、綺麗に洗濯しました。それと勝手ながら、ほつれた箇所もあったので直しておきました」
綺麗に洗濯された外套を受け取る。綻びかけていた箇所は跡形もなく、しっかりと修繕されていた。
「手間をかけさせて悪かった」
「いいえ、
「……参ったな」
名前の言葉に、月島は思わず苦笑してしまう。くすくすと小さく笑う名前に、月島の心が久しぶりに凪いた。彼女が笑う姿を見て安心したのだ。血みどろの日露戦争を経て、阿鼻叫喚の刺青人皮争奪戦に身を投じてから、初めてのことだった。