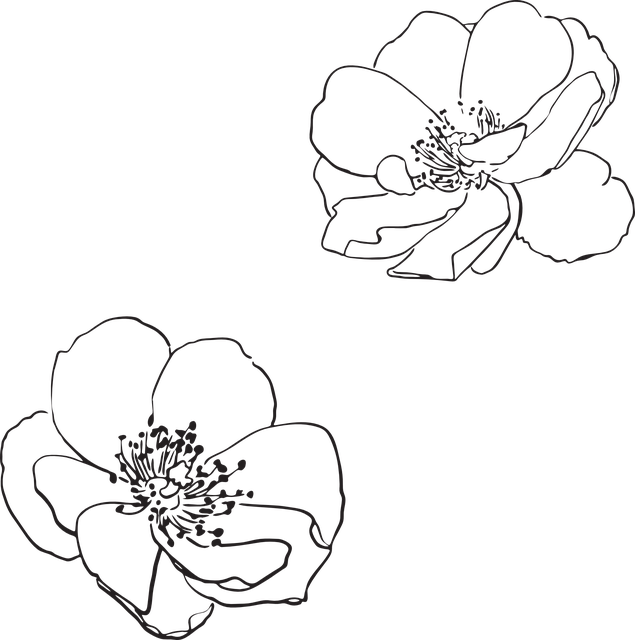
愛の聖域
まだ覚悟が足りないのだろうか。帰る場所を失い、大事だった者を全て手放したというのに。あと何回、何を諦めれば良いのか。月島は、掌の上に転がる御守を眺めながら、柄にもなく感傷に浸った。
貰った御守を捨てることも、返すことも出来ない月島を嘲笑うように――夏の盛りが過ぎ去る。瑞々しく爽やかな空気の中に、物悲しい湿った匂いが混じる季節を迎えようとしていた。
新しい兵服が完成した後も、月島は空いた時間を縫って名前と交流を続けている。知人と表現するのは味気なく、かと言って友人と呼べるほど親しい間柄でもない。月島に恋慕の情はないが、彼女との関係に名前を付けられないでいる。
率直に言えば、名前と交流を続けるつもりは全くなかった。あの日、共に串団子を食べて終わりにするはずだったのに、どこで狂ってしまったか。「これで最後にしよう」と、伝える決心が持てないままだ。部下から鬼軍曹と言われているのに、このザマでは聞いて呆れる。
「何かあったのか」
小樽の町を一望出来る、見晴らし良い場所で二人は久しぶりに会った。
数週間ぶりに会う名前は、明らかに空元気だった。本人は至っていつも通りに振る舞っているが、声の端々に覇気はないし表情も少しだけ暗い。ひと目で心ここに在らずだと月島は見抜いた。
「何か、とは?」
「いや……いつもより元気がないと思っただけだ」
寝不足だから。朝食に苦手な食べ物が出て来た。もしくは、思うように藍染が出来なかったから――など、月島の勘違いであれば良い。
「……月島様には、隠し事が出来ませんね」
名前から、只ならぬ雰囲気を感じた月島は、無意識に生唾を飲み込む。名前は頭の中に散らかった言葉を、上手く組み立てている様子だ。
「実は数週間前、両親が縁談を持って来ました。私の家は男児がいないから、婿を取らないと家業を継ぐ者がいないんです」
「縁談か、良かったな。婿に入ってくれるなら、ご両親も安心するだろう」
名前は年頃の女性だ。縁談の一つや二つあってもおかしくない。器量も良いから、良妻賢母になるだろう。日向で暮らす彼女が、自分みたいな男といるのは良くない。だから月島は、その話を聞いて安堵する。なのに隣にいる名前の顔は暗いまま。
「見合いは、したくないのか」
秋の匂いを運ぶ風が二人の間を抜ける。隣にいる名前から、ぼそぼそと何か聞こえたが風の音で掻き消されてしまう。肌寒いのは、風だけのせいではないだろう。
「……私は月島様と、一緒にいたいのです」
蚊の鳴くような声だった。まだ会ったことも、話したことすらない男と添い遂げるのは嫌だ――名前はそう口にするが、月島にはよく聞こえなかった。
小樽の町並みが、ぐんにゃりと歪む。天と地が混ざり合う。冷たい液体が胃の腑に流れ落ちる。心臓が痛いくらい鼓動した。
「月島様。お慕い申しております」
真っ当な人生を歩む名前が――。
あの子と瓜二つの容姿で恋慕を伝えられると、月島軍曹の決意が呆気なく揺さぶられてしまう。月島基は故郷の佐渡島に、未練を捨てて来ることが出来なかった。身を焦がした恋の結末に納得出来ないまま、ずっと蓋をし続けたに過ぎない。
「もし月島様も私と同じ気持ちなら……私は実家を飛び出す覚悟は出来ております」
いご草そっくりの癖っ毛。頬を赤く染め、今にも泣き出しそうな名前は、記憶の中にいるあの子と違うのに、何故か目が離せない。
月島は、ふと思った。もしかしたら、人生をやり直す最後の機会ではないだろうか。首を縦に振るだけで、名前と共に人並みの幸せを掴むことが出来るかもしれない。
もう良いじゃないか。十分、苦しんだ。楽になっても良い頃合いだろう。蓋をした感情が堰を切って、諾々と溢れ出てしまいそうなのに、月島は頷くことが出来なかった。今まで犯した業が重い鎖となって、月島の身体を締め上げるのだ。
「……好きな相手と一緒にいたい君の気持ちも分かるが、親の気持ちも痛いほど分かる」
娘と仕事が出来て、父親は嬉しそうだった。手塩にかけて育てた娘を、駆け落ち紛いな行為で奪うなんて月島には出来ない。もう勢いだけで生きていけると思うほど、青臭い子供のままではいられなかったのだ。
「あんたの幸せを願っているだけなのに、どうして、そんな残酷なことが言えるんだ!」
大事な人が生死不明の辛さを、月島は身を以て知っている。確かめたくても、確かめる術がない。どれほど辛いことか、年若い名前には分からない。五臓六腑が擦り潰されそうな苦しみを、彼女の両親にさせたくない。
月島が柄にもなく強い口調で言うと、名前は言葉を詰まらせながらも気持ちを伝える。
「私の幸せは、月島様のお側にいることなんです」
「俺は君が思っているほどの男ではない。今まで、汚れ仕事も……たくさんした。人を殺したことだってある。ご両親が選んだ人間の方が、俺なんかよりよっぽど良い男だ」
今まで手にかけた人間の顔が浮かんでは消える。この両手は血に塗れているのに、人並みの幸せを掴もうとは片腹痛い。もう遅いのだ。
「月島様が今まで多くの人を、殺めて来たことも承知してます。国を守る兵士の勤めですから、軽蔑していません。それに月島様は、あの夜見ず知らずの私を助けてくれて親切にも自宅まで送ってくださいました。忙しい中、私とお話しする時間を作ってくれるし、私の両親のことも考えてくださる。あなたは、とても優しい方です」
湿った秋の風に曝された月島の両手に、じんわりと温かさが宿る。微かに藍色に染まった指先が、冷えた月島の指を包み込む。
十年以上ぶりに向けられた恋慕に、月島は言葉が出て来ない。不要なものだと決めていたからだ。
「手が冷たい方は、心が温かいと聞いたことがあります。私は月島様と過ごす時間が、何よりも大事です。あなたといられるなら、藍染を……辞める覚悟も出来てます」
「何を言って――!」
「巻き込んでしまってごめんなさい。でも私は自分の気持ちに、嘘は吐きたくないんです。明日の子の刻に、ここで待っております」
名前は月島にお辞儀をして、その場から小走りで去った。小さい背中が小樽の町並みへ吸い込まれて行く。月島はその光景を、黙って眺めることしか出来なかった。
爪が分厚い皮膚に食い込む程、月島は力任せに拳を握った。遣る瀬なさと悔しさが綯い交ぜられて、思わず唇の端を噛む。名前の乾燥気味な掌。薄い藍色が移った爪先には、布と向き合って来た証拠だ。死に物狂いで習得した技術を手放すなんて、あってはならない。
掌に残った人肌の温もりは、冷えた空気に呑まれて次第に消えた。いつの間にか、太陽が地平線の向こう側へ沈もうとしていた。
あの後どうやって兵営に戻ったのか。月島の記憶は曖昧だ。頭の中はとっ散らかっているのに、身体が勝手に淡々と通常業務をこなしている。
「鯉登少尉殿。書類の承認を早くしてくれないと困ります」
「分かっている。今やっているだろう」
ああ言えばこう言う。まるで言うことを聞かない幼児だ。むくれながら承認印を押す鯉登の前に、月島は圧力をかけるように控える。
「月島軍曹。鶴見中尉がお呼びです」
「……分かった。今行く」
脱獄囚人の新たな情報を掴んだのか。鶴見の一室へ続く階段を登る。ノックをして一声かけて部屋に入ると、鶴見は窓辺に佇んでいた。じわっと滲んだ洋燈の灯りが、夜の帳を押し留める。灯りが届かない部屋の四隅や執務机の真下には、ぽっかりと濃い影が浮き彫りになっていた。小さな紙切れを眺めていた鶴見は、静かに入室した月島へ呼び出した理由を述べる。
「網走監獄に潜入している宇佐美上等兵からだ」
紙切れは電報だった。手渡されたそれには、細筆で網走監獄の状況が簡潔に記されている。のっぺらぼうは毎日、独房を移動させられているらしい。もうしばらく様子を見れば、移動の規則性が見出せるとのことだ。金塊を狙う者同士、監獄側も
「後は谷垣の動向次第だな」
「出発準備は、滞りなく進めています」
「頼んだぞ」
折目正しく敬礼して部屋を出ようとすると、後ろから呼び止められる。世間話の続きみたいな口調の鶴見に、月島は扉の前で控えた。
「ところで、月島軍曹。新しく支給された兵服の着心地はどうだね」
「兵服……ですか?」
藪から棒に、一体何だろう。会話の意図が見えない。
コツコツコツ。長靴の踵が硬い床板を叩く音。洋燈の灯りが小さく震え、月島の目の前に影が広がる。人型の陰影から伸びる、橙色の薄い光。輪の形をした筋が、放射線状に外側へ細く輝く。まるで聖母像の如く、鶴見に眩しい後光が差す。
「とても着心地が良い。染め方も丁寧で、藍色も美しい! 職人のこだわりを感じる。この服を作った親子へ、御礼に差し入れをしたいと思ってな。月島軍曹……」
見知った上官の眉間から溢れる、どろりとした液体。何らかの感情を、昂らせた時に見せるものだ。聖母とは程遠い容貌の鶴見は、死神と形容した方がしっくりする。
「彼女が好きなものを――知っているか?」
ドクンと心臓が厭な音で軋む。
情報将校。月島は上官の異名を忘れていた。頭の中で警鐘が鳴り止まない。カンカンカンと脳髄に響く、けたたましい音。月島は生唾を呑み込み、努めて冷静に答えた。
「……鶴見中尉殿。“彼女”とは一体誰のことでしょうか」
月島は鶴見の仄暗い瞳から、目を逸らさない――いや、逸らしてはいけない。無関係な名前を、危険に曝してしまう。月島は無遠慮に探る視線を一身に浴びた。
ポン、と肩を叩かれて月島は我に返る。鶴見の目は、既にこちらを見ていなかった。
「……そうか。鯉登も知らんと言うから、てっきり月島なら知っているかと思ったのだが。後で縫工兵に聞くとしよう」
「申し訳ございません」
「気にするな。もう下がって良い。網走への準備を進めておけ」
「はい。失礼いたします」
人の気配がない廊下は、夜の闇が支配していた。一歩ずつ足を進める度に、カチャカチャと鋲を打った軍靴の音が響いて煩わしい。呼吸の仕方を思い出したかのように、肺の奥底に溜まった空気を吐き出す。土砂降りの雨に濡れたみたいに、全身から冷汗が滝の如く吹き出す。
名前との関係は、いずれ終わらせないと取り返しがつかない事態を招くかもしれない。嫌な胸騒ぎを感じていたのも事実だ。
鶴見の口ぶりは、確実に名前のことを知っていた。彼女は一定期間、兵営に出入りしていたから、月島と言葉を交わした場面を鶴見が見かけていても、何ら不思議ではない。にも拘らず月島に聞いた理由は、考えるまでもない。
他人の弱くて柔らかい部分を逆手に取り、愛を試す行為は鶴見の常套手段である。月島もその手法で駒へ堕ちたし、時に相手を嵌める側になったこともある。だけど無関係な名前を、鶴見劇場の演者にしてはならない。大事なあの子と同様、月島は二度も同じ思いをしたくないのだ。
懐から御守を取り出す。丁寧に縫われたそれは、月島と名前を繋ぎ止める物。純朴な幸福への道標は、やっぱり不要だ。
『それでこそ、私の戦友だ』
ぞくりと首筋が粟立つ。蠱惑的な囁きと共に、後ろから鶴見の両手が伸びて来て――月島の暗い世界に差す一縷の光を、包み込むように遮断する。もう何も見えない。暗くて冷たい海底から、いご草に似たあの子の髪の毛が伸び、月島の首や胴体、手首と足首に絡まる。ぐん、と底に向かって引っ張られ、冷たい慣れ親しんだ闇の底へ向かって、堕ちて行く。
翌日アイヌの女から、谷垣の動向について電報が届いた。杉元佐一と合流したので、網走へ向かうとのことだ。
「月島。出立の準備は、どのくらいで終わる?」
「武器弾薬を積み終われば、いつでも出発出来ます」
「でかした。では夜が深い内に、出発しよう。網走は遠いからな」
深夜間近の小樽は肌寒い。日増しに秋の気配が色濃くなる。橋の欄干に手を添えると、ひんやりした。月島は小さな御守を手に、約束の数刻前にやって来た。名前の姿はまだ見当たらない。辺り一面に広がる宵闇の中に、淡い灯りがぽつぽつと点在している。
月島は掌に転がる御守を転がす。たった数ヶ月間の交流が、走馬灯のように押し寄せて――消えた。
『月島様』
名前との交流は、月島にとって束の間の休息だったのだ。橋の欄干に結んだ御守は、どこか物悲しい。あの子の髪の毛が、小樽運河の底に沈む様子を、眺めた時の心情とそっくりだった。
網走へ出発する時間が迫っている。
煮え切らない思いは、断ち切らなければならない。月島が下した決断に、名前は悲しむだろう。泣いてしまうかもしれない。だけど彼女の幸せを想うなら、これしかない。鶴見の手が彼女へ伸びる前に。この地でこれからも、彼女が生きていけるなら――。
さようなら。別れの言葉を伝えることすら、また出来なかった。
月島は本格的に、金塊争奪戦に身を投じる。満州を日本の国土に。冷たい土の下で眠る戦友達のために戦い続ける。鶴見は口を大にして述べるが、誰も本当の目的を知らない。もしかしたら、そんなものはないかもしれないが、鶴見が嘯く目的の先が見れるなら操り人形で構わない。
大事なものを諦めて、自分を捨てて生きて来た。身軽なはずなのに、背負い込む業は重くのしかかる。
『さあ、月島軍曹。行くぞ』
「はい。鶴見中尉」
瞼の裏に映る鶴見が手を差し出す。月島よりも、すらりとした長い指。しっかり角ばったそれは男性的だ。月島は鶴見の掌を掴む。自分の人生に、大した価値はない。月島は鶴見の駒として、死ぬまで踊り続ける。
軍靴の音は、もう煩わしくなかった。
(了)