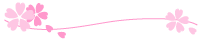
【拾】
男の手が、舌が、身体を這いずり回る。
私の身体は間違いなく喜んでいた。
心からは血が流れそうなほど嫌がっているというのに。
「どれ、そろそろ味見と行くかな」
気持ちが悪い。
身体の自由が効くなら、男に好き勝手される前に自害するというのに忌々しい……!
悔しい悔しい。
さくらという狡猾な女を憎んだ。
そして、こんなとこまでノコノコやってきて罠に落とされた自分の抜け目を恨んだ。
…穢れた私をあの人は軽蔑するであろうか……穢されてしまった私は、平然と彼の前に姿を現せるだろうか。
想像すらできない。
彼に失望されるくらいなら死んだほうがマシだ。
ドタドタドタ、と勢いよく階段を駆け上がるような音が聞こえたのは、その時だった。
──スパーンッ!!
「亜希ちゃん!」
「ちょっ、あんたら何なんだ! 困るよ!」
悪夢から覚めたようだった。
彼は私の散々たる惨状を見てサァッと顔面蒼白にさせた。
「お、にぃ…さ」
「貴様…っ何してる…!!」
彼は止めようとする茶屋の主人の腕を乱暴に振り払うと、私の体の上に乗っか
る男の首根っこを掴んで投げ飛ばした。
力の加減ができなかったのか、おじさんは勢いよく吹っ飛んで襖を破り、隣の部屋まで吹っ飛んでいった。
「亜希ちゃん! しっかりするんだ!」
「にぃ、さま…あつい、あついの…」
舌まで痺れて声が出しにくい。
私は自身の体の異変を彼になんとか伝えようと訴えた。
私が着せられていた着物は乱れ、中の襦袢までも乱れてるが、忠お兄様が助けてくれたお陰で最悪の事態は免れた。
だけど、目の前の忠お兄様は怖い顔をして、穴が空きそうなほど私を睨みつけている。
「にい、さま…いや、嫌わないで…」
そんな目で見ないで。
あなたに軽蔑されるなんて耐えきれない。
そう訴えたいのに、私の口は動かない。
熱い。とにかく熱くて、全身が疼いて苦しいのだ。
「亜希ちゃん…」
「あぁっ…!」
忠お兄様に助け起こされた私ははしたなく喘いでしまった。
薬と香の影響で、全身という全身が性感帯になってしまったかのように甘く痺れるのだ。ただ抱き起こされただけで私は感じてしまっていた。
「ん…あつい、あついの…」
私はハフハフと息を荒げて訴える。
そんな私を見下ろした忠お兄様はギリッと歯を食いしばっていた。
「おーい、早乙女さーん。長居しねぇほうがいいんでない?」
聞き覚えのある声がもう一つ。
開かれた襖の向こうからひょこっと現れた吹雪さんだ。なぜ彼までここにいるのだろう。
「あんた! なんてことしてくれんだ!」
「俺は高い金を払ってんだぞ! その娘の水揚げは俺がするんだ! 早く引き渡さんか!」
茶屋の主人と、水揚げ大好きおじさんが忠お兄様に文句をつけてきた。私は熱に浮かされながら、忠お兄様の胸元にすがりつく。
いやだ、あんな男に抱かれるくらいなら死んだほうがマシだ。
「……この娘は、女郎ではない。ふざけたことを言うのも大概にしろっ!」
その怒鳴り声に部屋がビリビリ反響した。彼がこんなに声を荒げる姿を見たことのない私はぼんやりながらもびっくりしていた。
殺気を込められたそれに茶屋の主人も水揚げ大好きおじさんも固まってしまっている。
彼は羽織っていた海軍の上着を脱ぐと、それで私を包み込んだ。横抱きに抱き上げられた私は「んっ…」と熱い吐息を漏らしてしまったが、忠お兄様は何もおっしゃらなかった。
「…吹雪君、これ、渡してくれるか」
「えー? 払わなくて良くないっすかー?」
「あとが面倒だ。襖の弁償代として渡しておいてくれ」
忠お兄様は片手いっぱいのお金を吹雪さんに手渡していた。それは決して少なくない金額になるだろう。吹雪さんはあまり乗り気ではなさそうだったが、茶屋の主人にそれを渡してなにか話していた。
私は忠お兄様に抱っこされたまま、茶屋の一階に降り、店を出た。
時間はもう夜に差し掛かっていたらしい。男性客が賑わっているではないか。視線が一斉にこちらに集中したのがわかった。
「…亜希ちゃん、いい子だから顔を伏せているんだ」
私は彼の言う通り、身を縮こめて彼の胸元に顔を埋めた。
そのまま吉原の大門を通過し、外に戻り、家まで送り届けられた。その間ずっとお兄様は無言。私はそれが怖くて堪らなかった。
「亜希ちゃん、今湯を沸かしてもらってるから、風呂に入るといい。それと飲まされた薬がどんなものかわからないから、水分をとって排出してしまったほうがいい」
自室まで運んでくださった忠お兄様の声は優しかった。
いや、優しい声を出そうと努めているように思えた。私を気遣い、傷に触れないようにしてくれているのがわかった。
だけどそれが彼との距離が生まれてしまったかのように思えて、私は悲しくなった。自分が情けなくて涙が止まらなかった。
「や、いや…」
このままでは忠お兄様は帰ってしまう。私を軽蔑したまま。
「亜希ちゃん」
「熱くてつらかったの。私怖かったの。ごめんなさい。迷惑かけて、ごめんなさい」
もっとちゃんと単語を並べて説明したかったのに、薬の影響が色濃く残っている私は幼児みたいな話し方になってしまっていた。
忠お兄様が困惑している雰囲気がしたが、私は彼の背中に腕を回して離さなかった。
はしたないと眉をしかめられるかもしれないが、このまま彼と離れ離れになりたくなかった。
「大丈夫、もう怖い人はいないからね」
「やだ、ひとりやだ。怖いの…熱いの。助けてお兄様……」
私はまるで駄々っ子のようだ。
いつまでも彼に甘えて、これではいつまでも子供扱いをされるに違いない。
だけど私が彼にすがりつくのは、あのおじさんの感触がまだ残っていてそれがおぞましく、気持ち悪かったからだ。
「……亜希ちゃん、頼むから」
「ひとりにしないで、お兄様……身体が熱いの…」
べそべそと泣く私の頭を撫でてなだめようとする忠お兄様。だけど私は離さない。手足の力はまだあまり入らないけど、絶対に離すものかと気合でしがみついていた。
「…亜希ちゃん…っ」
「んむっ」
耐えきれないとばかりに、忠お兄様は私の唇に噛み付いた。私はぼんやりしたまま、彼の口づけを受け入れていた。
……なぜキスをされているのかしら? という疑問が浮かんだのは一瞬のことだった。
私は彼の唇に自分から吸い付いた。それに驚いた様子の忠お兄様の身体がビクリと震えたが、私は彼の首に抱きついて、そのまま彼の唇を吸い続けた。
「う、ん…んん…」
彼の舌が唇をこじ開けるようにして侵入してきた。熱い舌が私の口の中をうごめいた。
あぁ、私忠お兄様とキスをしてる。
学友に借りたロマンス小説のようだわ。
だけどそれよりももっと官能的な……
チュク…と濡れた音を立てて離された唇。私は物足りなくて自分からキスを求めた。
「もっと、もっとほしい」
「…どこでこんな事を習ったんだい?」
「ん…」
私は畳の上に押し倒され、先程よりも激しく唇を貪られた。
「はぁ…あ…お兄…さま……」
彼の手が私の襦袢の上から体を撫でた。その手の上から自分の手を乗せ、私は笑った。
こんなに幸せなことって、ある?
夢心地のように感じた。
胸の奥底で封印していた恋心。
お慕いしていた方にお情けをいただけるのだと夢のようだった。
夢は所詮夢。
それでも、こんな幸せな夢を見られるなら、それだけでも私は──…
次に目が覚めると、私は自室で眠っていた。
寝間着に着替えており、身体もなんともなかった。
──あれは悪夢といい夢を同時に見せられたのかしら? と私は首を傾げてしまったのである。
■□■
「亜希子お嬢さん、お転婆はいいですけど、考えなしの行動はやめてくださいよね」
吹雪さんからの指摘に私は首を傾げてしまった。
「マサさんが異変を感じて俺に声を掛けてくれたから間に合いましたけど、それがなければお嬢様は大変なことになっていたんですからね」
吹雪さんが言うには、昨日私が手紙を見て飛び出したという話を下働きのマサさんから聞かされて、胸騒ぎした吹雪さんが吉原に駆けつけようとした際に偶然遭遇した忠お兄様を連れて来たという話であった。
「間に合ったから良かったですけど…ほんと、ご自分の立場を理解なさってくださいね」
吹雪さんににチクリと言われた。
「お嬢さん、あのまま寝ちゃったみたいですけど、今度会ったら早乙女さんにお礼を言うんですよ。あの人がいたからあなたを探し出せたものなんですから」
その話を聞かされた私の身体は体温の急上昇が著しかった。
あれ、夢じゃなかったの?
全部、現実…!?
私は頭を抱えた。
とんでもなくはしたない姿を彼にお見せしてしまったのだと知った私は、このまま自害してしまいたい衝動に駆られたが、私の様子を見に来たという忠お兄様は平然としていらっしゃって、むしろ拍子抜けしてしまった。
「いいかい、亜希ちゃん。知らない人の呼び出しにのこのこ出向かないように。君はもう子どもじゃないだろう? わかるね?」
言い方が子どもに言い聞かせるみたいな言い方だったけど、私はぐうの根も出なかった。
…いつもどおりすぎない?
私は上目遣いで忠お兄様を見上げた。
すると彼は苦笑いして、私の頭を撫でてくれた。
「あれは全部悪い夢だ。早い所忘れてしまいなさい」
……そんな事出来るはずがない。
忠お兄様の唇や舌の感触をおぼろげながらに覚えている。
彼にとっては慰めの一つに過ぎないのかもしれないが、私にとってはそうじゃない。
「…お兄様は忘れてしまわれるの?」
私は問いかけた。
一瞬だけ目を見張った彼は、はにかんだ笑顔を浮かべると「いい子だからいうことを聞くんだ」と子ども扱いをしてきた。
「…私は、子どもじゃないわ……」
昔は嬉しかった扱いが今では全く嬉しくない。私はどうしても、彼にだけは子ども扱いされたくないのだ。
「…そうだね、俺も子どもに手を出す趣味はないよ」
「え…」
私はパッと顔を上げた。すると私の視界を遮るかのように彼の大きな手が私の目元を隠した。
「とにかく、知らない人の呼び出しに行かないこと。わかったね?」
彼はそう言うと「じゃあね」と言って踵を返してしまった。
……私の目の錯覚かしら。
彼の顔が赤らんで見えた気がするのだけど。
|